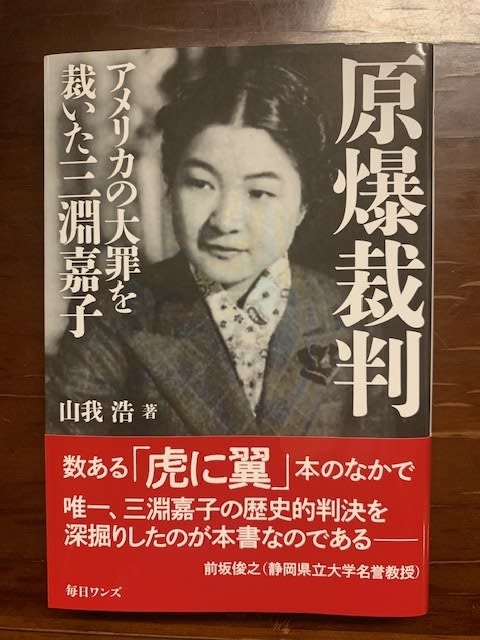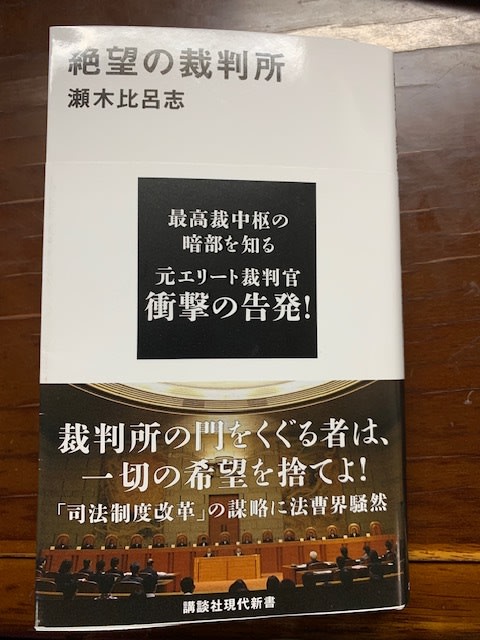良い教師は、生徒の名前を覚えるのが早いとか。その意味では私はよい教師ではありませんでした。年を取るにしたがって、覚えるのが遅くなってきて、挙句の果てには、覚えなくてもいいかなと、開き直る始末でした。目立つ生徒は自然と覚えるのですが、そうではない生徒は覚えきれてなかったです。名簿は持っていたので、指名することはできましたが。尤も、大学1,2年では名前を憶えていて、授業をされた記憶はほとんどありませんが。
教育論議では、例えば部活指導で教員が大変だという話題では、主に中学の話であり、モンスターペアレンツの話では、対象が小学校であるのに、対象を明確にしないで、小学校から高校までを十羽一絡げにした議論になりがちです。高校生を教えていて、小中学校からの議論の延長線上での議論の立て付けが多く、その結果、例えば高校3年生を教える中では、教育議論が当てはまらなく、却って大学1,2年生に視点での議論が参考になった記憶が強くあります。
文科省の組織では、小中高(初等中等教育局)と大学(高等教育局)は別組織である点が情報や議論の対象も影響を受けていると考えられます。
いずれにせよ、いい授業をすることが大切で、ややもすると、小中学校では、今流行りの形式の授業をすることに重きを置かれ、授業内容に関する議論が薄められる傾向にあるように思われます。高校では、授業内容が問われることが多く、それが大学ではもっと顕著になると思われます。
しかし、どの段階であっても、児童生徒や学生が教師の話に興味をもち、注目するための話術や話の展開に関して、もっと教員として意識を持つべきであると今更ながら感じます。もちろん作られた噺ではなく、リアルタイムの対話に近い側面も授業にはありますが。それら二つをミックスしながら作り上げられる授業は出来上がりの旨さが味わえれば最高ですね。
私も時々、授業の導入や話の掴みなど、噺家を参考にできればと思っていましたが、残念ながら、その実践までには到達できませんでした。
そんな思いもあってか、最近、新聞の書評欄に書いてあった本で、噺家の書いた

を読んでみましたが、なるほど、いたるところにその噺を彷彿させる文言に成程と思わせられる箇所も多く、一気に読んでしまいました。作者は私より少し年上ですが、ほぼ同世代であり、時代感覚も近いことから惹きつけられました。噺家の徒弟社会と学校という組織での指導教育という点でリンクできるところもありかなと感じます、部活動の指導なども含めて。
興味深く読めて、しかも読後の印象もよかったので、更に著者の初期の作品

も一気に読んでしまいました。社会を風刺しながらも根底には意外と冷静な目が話術にも反映されているのかと、はままた、実社会の何気ない日常の一人の生き方を噺の様に語られる中に、我を思い出させてくれる、それを楽しみながら読めます。教育においても大いに参考になる視点かな、一人の教師として。