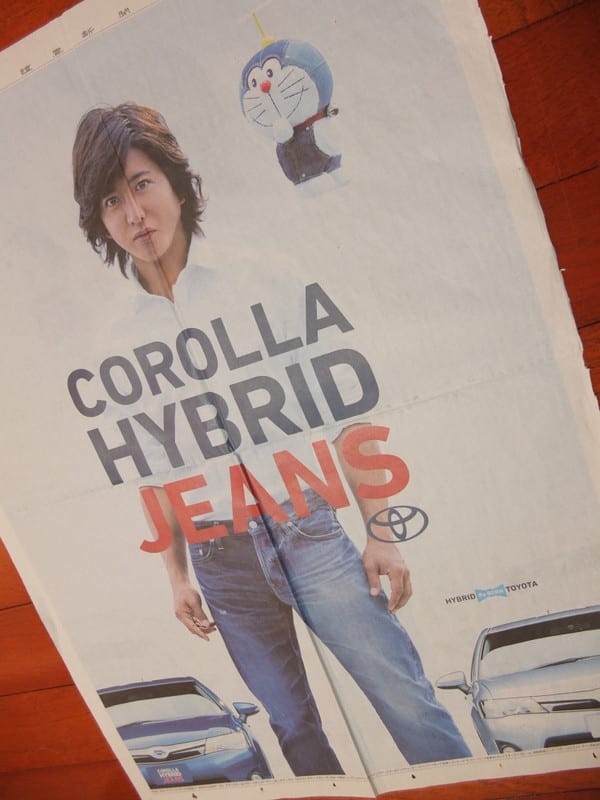財務省が打ち出した消費税の10%への引き上げに当たっての負担緩和策に対し、(予想されたことではありますが)9月7日の読売新聞の紙面では、まさに社を挙げて実現阻止に向けたキャンペーンが展開されています。
そもそも、政治に大きな影響力を持つとされる渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長が、2013年の暑中見舞いにおいて有力政治家たちに新聞への軽減税率の適用を迫ったというニュースは、当時から一部のメディアでは有名な話でした。
そして、これと歩調を合わせるかのように、同年9月に日本新聞協会(読売新聞グループ本社代表取締役社長白石興二郎会長)の諮問を受けて発足した「新聞の公共性に関する研究会」が、消費税率引き上げに際しては新聞に軽減税率が適用するべきだとする意見書を発表。(社)日本新聞販売協会もこれに追随し、政府に対し「新聞の軽減税率はこの国の明日へのともしび」と題するアピールを行ってきたところです。
一方、今回、麻生財務大臣は一連のコメントの中で、軽減税率に関する政府の制度案では「酒を除く全ての飲食料品」を対象品目にすることを明言(日本経済新聞9/5)したとされています。つまり、今回の財務省案が具体化すれば、新聞協会などの2年越しの目論見が外れ、これまでの努力が無になることは必至の状況です。
財務省が示す原案では、再来年4月に予定されている消費税の10%引き上げに際しては、全品目に10%の税率を課したうえで、飲食料品などの購入で消費者が払った税率2%に相当する額を後から給付することとしています。また、これら飲食料品の購入額の把握に当たっては、将来的にマイナンバーの活用を検討するとの方針も示されているようです。
ここしばらくの間静かであった軽減税率を巡る議論が急展開を見せる中、「複数税率(軽減税率)を導入することは面倒くさい。それを面倒くさくしないようにすることが手口だ。」とする麻生財務大臣の説明を、9月7日の読売新聞の社説は、「あまりに無責任」な発言と断じています。自民・公明両党は、2013年12月に生活必需品などへの軽減税率の導入で合意し、2014年の衆院選の公約にも掲げている。与党が政治的に積み上げてきたこうした議論を「面倒くさい」といった理由で投げ出すことなど到底許されるものではないというのが、その論旨ということになります。
一方、軽減税率の導入を目指す与党・公明党からも、「(財務省案は)党の考え方とはかけ離れたもので、軽減税率とは言えない」という指摘や、「買い物をするときの税率が10%であれば、『痛税感』は緩和されず、国民はメリットを感じない」などの反発の声が上がっている(←NHK報道)ということであり、この財務省案に関しては今後の政局において厳しい議論にさらされることになりそうです。
さらに言えば、支払った消費税額をマイナンバーにより把握するとういう財務省案にも、解決すべき課題はまだまだ多いと言わざるを得ないでしょう。全国の商品小売店の全てにカード情報読み取りのための機器を設置したり、新たな手続きを導入することが事業者への負担に繋がることは明らかなうえ、予期せぬトラブルや煩雑さのコストをどのように考えるのかという問題も整理されなければなりません。
加えて、マイナンバーの利用により政府が国民一人一人の買い物の履歴を管理することが、プライバシーの点から国民の間に大きな議論を呼ぶことは論を待ちません。
読売新聞を中心とした新聞各社も、この機を逃さず、軽減税率の導入と適用範囲の拡大に向けて連携して世論を動かし、財務省に対する圧力を一層強めてくることが予想されます。
軽減税率の導入については、制度の一定の複雑化が排除できないだけに、メリットとコストの十分な比較が欠かせません。そして麻生大臣の言うように、世論が後押しするこの「面倒くさい」制度の導入を、いずれにしても何らかの「手口」で整理(料理)していくことが政府には求められています。
大手メディアを敵に回し、国民の「納得感」をどれだけ得ることができるのか。この先の議論の中で日本の政治と行政の手腕が試されることになると、私も改めて感じたところです。