国際ジェンダー学会2013年度大会の新しい企画ラウンドテーブル<アジアにおける性比問題>で、「中国の性比問題をめぐって」という話題提供をしました。一緒に話題提供をした佐野麻由子さん・幅崎麻紀子さんはそれぞれネパールをフィールドとする社会学者・人類学者です。
私は、以下のような話をしました。
中国では「一人っ子政策」によって、非常にたくさんの「失われた女性」(性別鑑定による選択的な中絶や育児放棄などで生まれなかった、育たなかった女性の命)がある、といわれています。たしかにそれは間違っていませんが、ただ、そのような矛盾が激しく噴出していたのは、1980年代から90年代半ば頃まででした。現在の中国では、農村でも「子供はたくさんいらない、女の子だけでもよい」という人が増えて、生育意識に変化が起き、出生率も下がって、むしろ少子高齢化が問題になっています。その背景には、育児費用の高騰や、農村での年金制度の開始、農業の機械化によって重労働の必要が減ったこと、などがあります。「失われた女性」が起きた原因は、「一人っ子政策」による子供の数の制限以上に男児偏重の家父長制の存在を問題視する必要もある(例えば、やはり出生率が低い韓国では、中国以上の性比のアンバランスが観られるが、日本では見られない)と思われますが、それには近年変化が見られます。
また、中国の計画出産は、これによって広大な中国農村の女性たちがバース・コントロールにアクセスできるようになったことを考えると、女性のリプロダクティブ・ヘルス&ライツという点で、マイナスだけでなくプラスの面でも大きなものがあったといえます。
日本でも、「一人っ子政策」については、リプロダクティブ・ヘルス&ライツの点からも問題点ばかりが強調されているので、ちょっとそれとは異なった視点を意識的に紹介してみました。たしかに問題は大きなものがありましたが、現在はもう問題のピークを超えていることもあり、複眼的・歴史的な視点での議論も必要でしょう。
今日の議論で気がついたこととして、(日本以外の)東アジア地域では、特に性比のアンバランスの問題が大きいことがあります(インドでも問題ですが)。東アジアは現在、とりわけ少子化が進んでいることと併せて考えてゆく必要がありそうな気がします。
私は、以下のような話をしました。
中国では「一人っ子政策」によって、非常にたくさんの「失われた女性」(性別鑑定による選択的な中絶や育児放棄などで生まれなかった、育たなかった女性の命)がある、といわれています。たしかにそれは間違っていませんが、ただ、そのような矛盾が激しく噴出していたのは、1980年代から90年代半ば頃まででした。現在の中国では、農村でも「子供はたくさんいらない、女の子だけでもよい」という人が増えて、生育意識に変化が起き、出生率も下がって、むしろ少子高齢化が問題になっています。その背景には、育児費用の高騰や、農村での年金制度の開始、農業の機械化によって重労働の必要が減ったこと、などがあります。「失われた女性」が起きた原因は、「一人っ子政策」による子供の数の制限以上に男児偏重の家父長制の存在を問題視する必要もある(例えば、やはり出生率が低い韓国では、中国以上の性比のアンバランスが観られるが、日本では見られない)と思われますが、それには近年変化が見られます。
また、中国の計画出産は、これによって広大な中国農村の女性たちがバース・コントロールにアクセスできるようになったことを考えると、女性のリプロダクティブ・ヘルス&ライツという点で、マイナスだけでなくプラスの面でも大きなものがあったといえます。
日本でも、「一人っ子政策」については、リプロダクティブ・ヘルス&ライツの点からも問題点ばかりが強調されているので、ちょっとそれとは異なった視点を意識的に紹介してみました。たしかに問題は大きなものがありましたが、現在はもう問題のピークを超えていることもあり、複眼的・歴史的な視点での議論も必要でしょう。
今日の議論で気がついたこととして、(日本以外の)東アジア地域では、特に性比のアンバランスの問題が大きいことがあります(インドでも問題ですが)。東アジアは現在、とりわけ少子化が進んでいることと併せて考えてゆく必要がありそうな気がします。














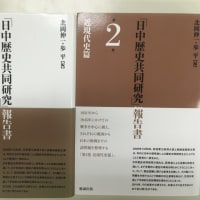



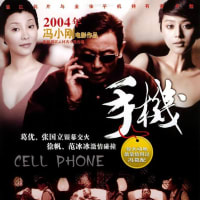
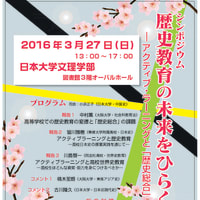
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます