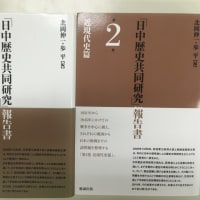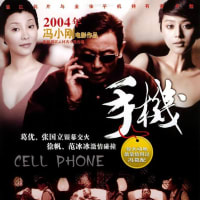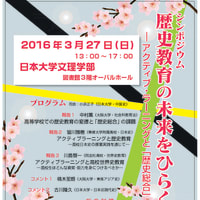慌ただしく前期の仕事を一段落させて、イギリスはマンチェスター大学に、国際科学医療技術史学会(International Congress of History of Science, Technorogy and Medicice)に参加するため、ほとんど初めてのイギリスにやって来た。
マンチェスターは、産業革命発祥の地のイメージを裏切らない、赤レンガの建物が重厚な街だ。19世紀に綿棒職業で勃興し、20世紀に入って衰えたが、近年テクノロジーと文化の街として再生しているという。マンチェスター大学は、16世紀だかに始まったイギリスでも有数の伝統ある大学である。
私は今回、冷戦期アジアの家族計画に関するパネルで、中国の計画出産について報告した。他に日本・台湾・インドに関する報告を、アメリカ・イギリス・日本で研究している台湾・日本・インドの出身の研究者が行い、コメンテーターは韓国の研究をしてシンガポールで教えているイタリア系アメリカ人というインターナショナルなパネルだった。
私の報告以外は冷戦期のアメリカの人口政策がアジア各国の家族計画に如何に影響したかが共通の視点であり、社会主義の中国との対比が面白かった。アメリカ人の家族計画関係者と各国の専門家との間のやりとりの中で、それぞれの地域の政策が方向付けられてゆく話に、冷戦期のアメリカの影響力の大きさが国際的によくわかった。
こちらで印象的だったのは、学問とはもともと文系・理系などの境界のない全面的に問題を考えるものであり、現在そういう態度が非常に必要だということだ。大学の中にマンチェスター博物館があり、覗いてみたが、恐竜の骨格から世界中のランプなどさまざまな道具まで、自然のものも人の作ったものも、一緒に展示してあるのが面白かった。大英帝国の「博物学」の精神を観た思いだ。
計画出産(いわゆる「一人っ子政策」)に関する研究を始めてから、広い領域に関わる出産研究者と一緒に仕事をするようになって、文系学者の私はそれまで縁のなかった人類学会や助産学会などでも発表の機会を得た。今回は科学史分野では最大の国際学会に迷い込んで、隣の部屋では天文学史のパネルをやっていたりして、中学生の理科のワクワク感を思い出した。
そもそも学問とは境界のない知的好奇心から始まったもののはずで、現代社会の課題を解決するためにも研究領域の垣根を越えた英知の結集が求められている。この学会-ICHSTMには、そういう意味で最先端の文理融合の研究をしている人も、日本からも含めてたくさん参加していた。ダーウィンの国は、現在の文理融合の研究の方向を考えるのにふさわしい場所に思えた。
マンチェスターは、産業革命発祥の地のイメージを裏切らない、赤レンガの建物が重厚な街だ。19世紀に綿棒職業で勃興し、20世紀に入って衰えたが、近年テクノロジーと文化の街として再生しているという。マンチェスター大学は、16世紀だかに始まったイギリスでも有数の伝統ある大学である。
私は今回、冷戦期アジアの家族計画に関するパネルで、中国の計画出産について報告した。他に日本・台湾・インドに関する報告を、アメリカ・イギリス・日本で研究している台湾・日本・インドの出身の研究者が行い、コメンテーターは韓国の研究をしてシンガポールで教えているイタリア系アメリカ人というインターナショナルなパネルだった。
私の報告以外は冷戦期のアメリカの人口政策がアジア各国の家族計画に如何に影響したかが共通の視点であり、社会主義の中国との対比が面白かった。アメリカ人の家族計画関係者と各国の専門家との間のやりとりの中で、それぞれの地域の政策が方向付けられてゆく話に、冷戦期のアメリカの影響力の大きさが国際的によくわかった。
こちらで印象的だったのは、学問とはもともと文系・理系などの境界のない全面的に問題を考えるものであり、現在そういう態度が非常に必要だということだ。大学の中にマンチェスター博物館があり、覗いてみたが、恐竜の骨格から世界中のランプなどさまざまな道具まで、自然のものも人の作ったものも、一緒に展示してあるのが面白かった。大英帝国の「博物学」の精神を観た思いだ。
計画出産(いわゆる「一人っ子政策」)に関する研究を始めてから、広い領域に関わる出産研究者と一緒に仕事をするようになって、文系学者の私はそれまで縁のなかった人類学会や助産学会などでも発表の機会を得た。今回は科学史分野では最大の国際学会に迷い込んで、隣の部屋では天文学史のパネルをやっていたりして、中学生の理科のワクワク感を思い出した。
そもそも学問とは境界のない知的好奇心から始まったもののはずで、現代社会の課題を解決するためにも研究領域の垣根を越えた英知の結集が求められている。この学会-ICHSTMには、そういう意味で最先端の文理融合の研究をしている人も、日本からも含めてたくさん参加していた。ダーウィンの国は、現在の文理融合の研究の方向を考えるのにふさわしい場所に思えた。