


(三回の講演通知。一緒に写っているのは、金一虹先生)
陽春というにはやや早いが、江南の上海・南京、そして長江を渡って淮安へ出かけた。
上海で少し史料を見たのち、昨秋に招聘した中国のジェンダー研究の中心の一人、南京師範大学の金一虹先生との「今度上海へ来た時には南京へ足を延ばして講演してほしい」という約束を果たすべく南京へ。
諸般の調整の結果、2日間に3回の講演を行うというハードスケジュールになったが、三回とも大変面白いものになった。
まず南京師範大学で、同大学の前身の金陵女子大学建学100周年記念講座の一つとして「比較史の視野から見た中国ジェンダー史」。この間の共同研究の中でわかってきた古代から現代までの中国家族史の変化を、日本や西洋と比較しながら一時間ほど話した。図書館のホールで立ち見が出るくらいの盛況で、聴衆には学生もジェンダー関係の研究者もいたが、さまざまな質問が出た。中国の社会も急速に変化しているが、その中でどのようなジェンダー構造や家族のあり方が求められるのか、皆が関心を持っていることがよくわかった。
続いて、夜には南京大学人文社会科学高級研究院で同じ話をする。こちらは市民にも公開された講座で、南京大学の院生・研究者・南京市民が部屋にぎっしり。やはり質問も活発に出た。日本と中国の家族構造の違いや、現在の日本での同性パートナーの状況など、多様な関心が伺える。「近代家族」の概念などは、中国ではあまり知られていないようだ(まあ現象として一般化してないから当然か)。
それにしても二回とも大入り満員で、南京の人々の知的好奇心の高さを見せつけられる思いだった。講演の通知を見て、旧知の南京大学の先生が連絡をくれたり、別の友人は終了後、近刊の著書を持ってやってきてくれたりしたのもうれしいことだった。
翌日は南京大学社会学系で、「中国農村における計画出産の普及―生殖をめぐる技術と権力」のテーマで話す。これは基本的に社会学系の教員と院生だけで、事前にペーパーも配られた少数精鋭の議論の場だった。「一人っ子政策」にかかわる「敏感」なテーマなだけに、最初は発言をためらっていた先生方も、やがて活発にそれぞれに自分のフィールドでの事例などを紹介してくださった。終了後、社会学系の日本留学経験者の先生方を中心に食事をして、いろいろ話した。「敏感」な話題についても、日中の政治関係がよくなくても、かなり議論ができるようになっていると実感した。














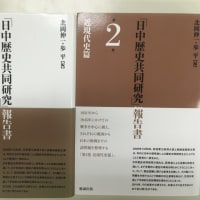



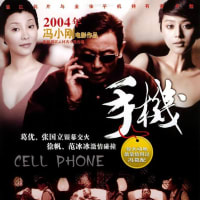
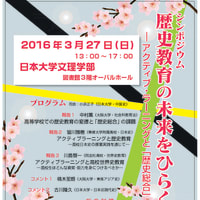
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます