
昨夜予定通りナデジダ・グラチョーワがシルフィードを演じるバレエを見てきました。ジェームズ役は先日の黄金時代の初日に好演したキエフバレエ出身のコデニス・マトビエンコ。
先ず劇場に入る前にチケット売り場の周りに人だかりがあるという最近余り見なかった風景で何とか劇場に入ろうという人、高く売りつけようというダフ屋の攻防が見られました。これも一重にグラチョーワの人気、それとマトビエンコも女性陣に人気上昇中の様です。
なお 2004年のモスクワ日本人会誌にグラチョーワの解説を見つけましたたので下記引用させて頂きます。
Quote
グラショーワはボリショイ劇場で働く女性陣が「今日の公演は最高よ」と言えばナデジダ・グラチョーワが主演の日であり「ナージャ(ハデジダの愛称)、ナーシャ バレリーナ(私達のバレリーナ)」と愛されているプリマです。。(中略)。1987年ボリショイ・バレエ学校卒業と共にボリショイ・バレエ団に入団しますが、何と最初からソリストとしての出発です。1991年グリゴロービッチ振付の「バヤデルカ」において主演ニキヤを好演、そして彼女はプリマバレリーナに昇格します。ニキヤはグラチョーワの代名詞ともいえる当り役で本人もテレビインタビューで「一番好きな役。私はニキヤを生きているのよ。」と話しています。。(中略)。。彼女の踊りを言葉で表すとすれば「古典的な美しさ」「やまとなでしこ」「品性」。ゆったりとおおらか穏やかに、それでいて華やかに。これ見よがしな高いジャンプや速い回転はせず、すべての動きは役の自然の流れに溶け込み、彼女の踊りを通して役の持つ感情が私達観客の心に深く浸み込んでいきます。グラチョーワのジゼルやニキヤや白鳥を観た後、感動で動けなくなった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。情感に溢れ、テクニックさえも芸術と感じさせる本物のバレリーナ、ナデジダ・グラチョーワ。彼女と同時代にモスクワに暮らす幸福を味わいに、ぜひボリショイ劇場へ足を運びましょう。
Unquote
さて昨夜の踊りですが グラチョーワの踊りは軸がしっかりしていて感情表現が豊かで例えば窓から現れジェームズが結婚するというので涙を流すマイムがあるのですが今までの2回のバレリーナは目から指で涙が流れるしぐさがあっさりしていたのですがグラチョーワはゆっくりと指を頬に伝わせるしぐさで本当に涙を流しているように見えました。今までの2回を演じたバレリーナとは格が違いますから比較するのがおかしいのでしょうが上記の日本人会誌の解説の通り 踊りに余裕があり決して急がずゆったりと只ジェームズと森で再開して楽しげに踊るところは可愛らしく愛らしく魔法のスカーフとは知らず綺麗なスカーフを欲しがる場面ではまるで少女のように喜んで、又スカーフの魔法にやられるところは苦しげにそして指輪にキスをしてジェームズに渡して息絶えるところは悲劇を感じさせる見事な踊り、表情でした。
マトビエンコも先日の黄金時代の初日を任されただけだけあって先日のAndrey Bolotinと比較するとぴたっと止まるべきところは止まりアントルシャ(飛び上がって足を打ち合わせる)は非常に俊敏で見事した。
カーテンコールは何時までも何時までも続きました。写真と動画をご覧ください。
因みにこの3回ともジェームズのフィアンセはAnna Antropova(写真右端)でした。確かにフィアンセにふさわしい綺麗なバレリーナですのでこの役が当り役なのでしょう。
マッジは悪役と言えばのGennadiy Yanin。先日の女性のマッジと比較するとやはり迫力、怖さで勝っていましたが飽くまで舞台では控え目でした。











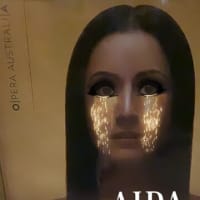
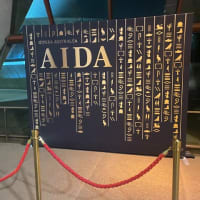



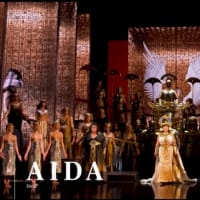



ちょっとどうなるか気になってた舞台、キャスト通り上演され、無事ご覧になれて良かったです。開演前の様子、カーテンコールのことも入って、へえ~でした。
モスクワ日本人会誌、品のある文ですね。今でこそ日本でグラチョーワ論といったら赤尾氏ですが、出た当時は独自の視点(オトコ目線!my lover グラチョーワ論、みたいな?)で実は斬新だったのだと、この会誌を見ると思います。割と昔のグラチョーワについてのオーソドックスな見方が、ここにはあるな、と。
ちょっとデニス・マトヴィエンコのことを書くと。
日本のボリショイファンは、野球は巨人、みたいな感じで「ボリショイ最高」「男性舞踊手はボリショイ」等思ってるので、ボリショイのアカデミズムとは外れた教育を受けた地方バレエ団の雄マトヴィエンコへの評価はあまり高くないような。ただ、劇場の改修関係で今のボリショイは激変し、このマトヴィエンコ、男性ダンサー不足の現実の中で使いでのあるダンサーとして、いい助っ人になると考えます。
グラチョーワの相手役が不足してる気がしていたのでとりあえずほっとしました。恋多きグラチョーワに新しい男いや、新パートナー、とどんな風になるか興味あったんですが。互いが順当に技量を振るったようで化学変化まではまだみたい。女王グラチョーワ、高い山、という感じかと。
ブルノンヴィルの「ラ・シル」についてはブルノンヴィルスタイルを踊れているかとかの話もありますが。
それがまあまあのペアでも、二人がラブラブで見てて楽しかった舞台など、色々見ました。
20代のグラチョーワ、フィーリンの「ラ・シル」もよかったですが、この二人はラブラブというよりジェームズがシルフを追う、シルフがはぐらかす。みたいな様子で、シルフが本気なのか、何も考えていないのか、よく判らずいかにも妖精。男性をからかってるようなグラチョーワの若い頃のコケットリーが際立った「グラチョーワ味」のシルフィードでした。フィーリンはこのソロに定評あり。申し分ないですが個人的には昔ラトマンスキー(今の芸監)が踊った踊り方が好みでした。(単なるマニアで定番評価はフィーリンかと)
マトヴィエンコは地方バレエ団の雄らしく万能型で、どの演目もそれなりに踊るというタイプなのかな?。日本のファン層もあります。初めてバレエ見る人が見たら、フィーリンとこの人とでは、どっちがいいっていうかわからない。好みの差だろう、と。ボリショイのファンはフィーリンだろうけど。自分はどっちでも楽しめるので(いいかげん)グラチョーワの表現が相手変わってどう変わるかの方が興味ありました。そんな意味も含めレポ楽しく読ませて頂きました。
アニュータもよかったみたいですね。
このところコメント無かったのでどうされたのかと思っておりました。何時もながら詳細なコメントどうもありがとうございます。なるほど、マトビエンコは中々の評価なのですね。声援も可也ありましたから現在のボリショイでは人気なのだと思います。
>今でこそ日本でグラチョーワ論といった>ら赤尾氏ですが、
そうなんですか?
本人喜んじゃいますよ。
>出た当時は独自の視点(オトコ目線!>my lover グラチョーワ論、みたい
>な?)で実は斬新だったのだと、
斬新というか、奇を衒ったというか。 でも愛していることは確かなようで。
>恋多きグラチョーワに新しい男や、新パ>ートナー、とどんな風になるか興味あっ>たんですが。互いが順当に技量を振るっ>たようで化学変化まではまだみたい。女>王グラチョーワ、高い山、という感じか>と。
仰る通りでしょう。彼女はパートナーによって変わるのではありません、役柄によって変わる、役に完全に入っているので、当然ながら高みへ昇ってしまいます。
>ブルノンヴィルの「ラ・シル」について>はブルノンヴィルスタイルを踊れている>かとかの話もありますが
はい?踊れてますよ、完璧に。男性の方が意外と難しいのです。
>20代のグラチョーワ、フィーリンの
>「ラ・シル」もよかったですが、この二>人はラブラブというよりジェームズがシ>ルフを追う、シルフがはぐらかす。みた>いな様子で、シルフが本気なのか、何も>考えていないのか、よく判らずいかにも>妖精。男性をからかってるようなグラチ>ョーワの若い頃のコケットリーが際立っ>た「グラチョーワ味」のシルフィードで>した。
だってグラチョーワの良さは小悪魔的キャラだもん。
>フィーリンとこの人とでは、どっちがい>いっていうかわからない。好みの差だろ>う、と。ボリショイのファンはフィーリ>ンだろうけど。自分はどっちでも楽しめ>るので(いいかげん)
今だったらマトヴィエンコの方が良いと思いますよ(直近の舞台を見ないで断言して申し訳ありませんが、ズバリ、彼の方が資質は上です)。
では、また。
ボリショイ来日公演公式ブログの方もよろしく。
って、今更遅いか。
宇治かなよ様、再度のお出まし恐縮です。公式ブログは、文の完成度が高く、はあ~なるほど~プロの文とはこういう風に書くもんなのか-と、勉強になります。でもそのあとに書くのはちょっとハズかしいもんですね。
さて。
>今、日本でグラチョーワ論といったら赤尾氏
だと思うんだけど・・。素人の、雑誌とかパラパラ見てて思ったことを書いたので、専門家的にはわかりません。昔は薄井憲二氏等ありましたが。
しょぼい根拠:一方でグラチョーワ礼賛書いた村山久美子さんは、モスクワのレドフスカヤとマリインスキーのプリマに浮気してるもんっ(後者はほめなきゃいけない人なのかもしれんが)
赤尾氏はグラチョーワ一筋ですから。(別にいんですけど他の人書いても思い入れても)
あ、グラチョーワ論の話はマジでどっかで書けたら書かせていただくかもです。ぼーっと見ていて気ずかないことってあって、批評とか言葉化するって意識化って作用があって、氏のグラチョ^-ワ論も、今まできずかなかったことを、あっ、そうなのかな~と自分的には思ったってのがあって。
「オトコ目線」は電車の隣人の読んでた雑誌のサブタイトルを気分で盗んだだけ。今の東京の空気を感じてください(?)
>ブルノンヴィルスタイル
えっと、この日の主役二人がこれを踊れているかどうか、というのではなくて、この振付家が出てきたので本当はそういう話もあるけど割愛します、の意味です。ちょっとマトヴィエンコの話を先にしないと、と思ったので。ボリショイファンと思われる宇治様だけでもマトヴィエンコの素質を見抜いていらして、ほっとしました。(とーぜん?)
<マトヴィエンコのブルノンヴィル>
宇治様のフォローがあって助かりました。
自分は彼の「ラ・シル」をテレビ放映で見て、遜色なかった曖昧な記憶はあるのですが、ながら族で見てそんなにきっちり見てなかったし、相手が日本のバレリーナの中でも実力はともかくテレビ写りのいい方ではなく、まわりも普通に日本のコールド(もっと水準高いとこもあるし、ここもマトヴィ共演したりして水準上がったときもあるけど)ヴィジュアル的にうっ、そりゃ-、相対的に体型にも恵まれお顔もテレビ栄えするマトヴィが良く見えて当たり前!!だった。主役二人の容姿の差に強い印象をもってしまい、自分が踊りを細部までちゃんと見てたか自信がないので、完璧に踊れてたなら、ほっ。
ついでにマトヴィ、そのプリマを「非常に忍耐強いんだ」と(たぶん本気で)ほめてました。日本人女性のプリマはロシアより忍耐強いのか・・・?。
>直近の舞台を見ないで断言して申し訳ありませんが
その通りですよね。私も、たぶん、と思って書いちゃいました。フィーリン、以前より主役オーラを増し、ラ・シルなら踊りも磨きかかって、「やっぱこっちが流石」って日もありかもですが。
あと、どっちかっていうと、バレエ初めて見る系の人がより感動できるのはどっちか(踊りだけじゃなく全幕ものを盛り上げる力など)、とか、踊りより、どっちが女の子に好まれるか、っていう観点も含め
「好みの差」と書きました。
私は、フィーリンだったら爽やかな青春譜、マトヴィはもっと甘い感じかなと想像してます。どっちも楽しめるけど。
>今だったら、・・(略)・ズバリ資質は彼の方が上です。
ハイ、私もそう思います。てか、根拠は彼がコンクールのメダル取るの得意だから、位のことしかわかってませんが。
マトヴィエンコは、キエフ時代を見てなくて、日本の新国立劇場に常連主役で出るようになったころ、つまりおそらく教師が変わり一番質を落としていた時代しか全幕はみてないので。そこでもっとも評判になったのは「マノン」の瑞々しい演技。こっちをみてなくて、そこまでではなかったといわれてる次の舞台とかを見てるので、あまりわかる方ではないですが。
メダリストで資質に恵まれた彼がボリショイの最強コーチ陣で上のせが期待できるのかな、と。
バレエは資質だけではないし、ボリショイという環境やプリマたちとうまくやってけるか、彼の要求と条件が折り合うかってのもあるし、今後誰がメインのプリマになるかとも多いに関係あるでしょうけど。(メインプリマの身長とか)
どっちが上とかより、守備範囲が広く使いでのあるダンサーとして今切実にボリショイに必要な人材だと認識してます。
グラチョーワのパートナー、ウヴァーロフとばかり踊ってる(少なくとも大事なとこでは)のが気になっていて、それで、単純に取って代われる人がいたら、というのが、実は私の最大の関心でした。
ザハロワは引き抜きのための契約条件が非常によく、このところ何でもザハロワ優位できてましたから、ザハロワお気にいりのパートナーのウヴァーロフをいつまでもグラチョーワがあてにしてると損するんじゃないかと。(バッティングするとザハロワ優先になりそうで。)
ま、結果はまあまあのパートナーかな、と。グラチョーワ相手役に要求高いし、一朝一夕で芸術ってしあがるもんじゃないとわかりました。もちろん、いつまでも続いたカーテンコールなので大成功ですが。
今、ウヴァーロフがケガで修理中なので、逆に彼とのパートナーシップで名声をさらに上乗せしたザハロワが、どうなるのか逆の心配が出てきましたけど。いつまでもザハロワ時代じゃないかも??
長いわりにグラチョーワの話ができんかった-。ではー。
私がラトマンスキーのラ・シルが好みだったというのは、音の取り方が好きだったんだと思います。管理人様が書いてらっしゃるジェムーズの着地の止めについてはラトマンスキーは止れてなく、ラトと同じ私好みの踊り方をしたボリショイの昔のダンサーは止れてました。どうもボリショイには着地を決めるノウハウや調整を教えられるとこがあるのでは?と。でも、マトヴィエンコはここでコーチ受けなくても止れてたんでしょうが。逆に日本の新国立劇場で彼が踊った「マノン」は、恋で破滅していく劇の部分で等身大の表現が生き生きしていて共感されたんであって、恐らくマクミランの振付を完全には踊れてなかったのでは、と思ってます。本家がみたらあそこがちょっと違うとか、あるかも。そこらへんが舞台芸術のびみょーなとこで、振付がきっちり踊れてても舞台の人が生き生きしてなければバレエオタクはわかっても一般の人には伝わらない。振りが完璧に踊れてかつ楽しい表現ができるというのが理想なんでしょうけど。
マトヴィエンコやヴォルチコフってまだわりと若くて実人生の恋愛の気分を役に投影しやすい、なんてこともあるのかな、等と想像しております。マトヴィエンコはラトマンスキーの昔の相手役でもあったかわいい系美人のフィリピエワというプリマと一時期公私共にパートナーでしたが今は分かれて、美人でスタイルも良く、でも踊りがややおおざっぱな奥さんと再婚してまだそんなにたってない時期。この二人の踊りをみてますが。パートナーの問題って誰にも悩ましいもんだけど。コンビ組んで踊りたいんでしょうけど奥さんが格落ち。グラチョーワは前夫とは組んで踊ってたけど今の人とは組まないようですが。役が違うようで。では。
例の有名な彼女のゆっくりフォンデュを見せる技。あそこを確か氏の評論では、プリマが観客に体を見せている、というような理解でした。それが官能的であると。ここで、なるほどと思ったんですね。グラチョーワのような女性は本質にそういうものを持ってるし、表現の受け手がその部分をキャッチしていると。ところが、私はそういわれるまであんましそういうことは意識したことはなかった。氏の見方だと、彼女のソロに色気を感じているわけですが、私は、(評論読むまで意識してなかったけど)どちらかといえば舞台の上に男性がいるときのグラチョーワを色っぽいと感じていた。彼女の官能性がマックスで発揮されたエギナだと、彼女の謀略のセクシーダンス、それをみて興奮していく牧夫さん、その、牧夫の興奮を感じ取ってた、と思う。つまり赤尾氏の場合、舞台の表現の送り手と受け手の見る、見られる、の関係性がダイレクトなんですね。私のは、セクシーな自分を見せるグラチョーワ扮するヒロインがいて、それに色気を感じる男の人が舞台にいて、観客の私がそれをみている、というような関係性になってるんです。
これは、女性が全て必ずしも私と一緒とは限らないかと。他の人にも聞いてみないとわからないですね。ま、女の自分がダイレクトにグラチョーワをみて色っぽいな~ってのもちょっとあれだが・・。
それと、何割方かのプリマは二重性を持っていて、色っぽいグラチョーワの本質が一方であり、もう一方にウラーノワが望んだ清純なヒロインのイメージがあると思うんです。
私の場合、あのグラチョーワのゆっくりと脚を美的に上げていく技術に、その、ソロ部分には別のものを感じてまして。色気よりは、陶酔的ではあるんだけどなにか神秘的で侵しがたいものも感じていて、祈り、みたいなのとか。何か時をとめるような感じって言うのは共通して見る人がもってるんじゃないかと思うんだけど。その、止まった時に何をみるかがひとにより3種くらいにわかれるのかもしれませんね。
技術てきにはあれはバレエの美そのものだし。脚の筋肉各箇所に均等に力が加わってる美しさ、とか、瞬間瞬間の造形美とか。どっちかっていうと脚中心に見ていて、後、顔の表情とかで、体を見せている、という理解でみてはなかったです。私は、ウラーノワの見せたかったニキヤをグラチョーワの身体からみていたのかもしれません。そして赤尾氏が看破されたものはにじみ出るグラチョーワ自身の本質であり、表現者としての彼女が、後にウラーノワを越えて自分の独創的な芸術表現としてエギナ役で爆発させたものの萌芽がそこにはあったのかもしれません。
以上、赤尾氏の「発見」についての私見です。
>>今、日本でグラチョーワ論といったら赤尾氏
>だと思うんだけど・・。
繰り返しになりますが、本人喜んでいます。
>昔は薄井憲二氏等ありましたが。
う~ん、薄井さんは取り立ててグラチョーワについて論じていないと思いますが。グリゴロ版「バヤデルカ」初演のときの批評の中で、ちょろっと触れてはいましたが。
>しょぼい根拠:一方でグラチョーワ礼賛書いた村山
>久美子さんは、モスクワのレドフスカヤとマリイン
>スキーのプリマに浮気してるもんっ(後者はほめな
>きゃいけない人なのかもしれんが)
>赤尾氏はグラチョーワ一筋ですから。(別にいんで
>すけど他の人書いても思い入れても)
あ、その根拠、ほんとにしょぼいです(失礼!)。
彼、リドフスカヤ(私はリドフスカヤと発音する)にも惚れています。でも、良いものだから惚れているだけで、誉めなきゃいけないから惚れているとなんてことは決してありません。だからザハーロワもロパートキナも特に好きではない。
>「オトコ目線」
目線あるいは視線という観点はエロティシズムにとって非常に重要です。でもそれはオトコ特有のものでは決してありません。
>グラチョーワと視線 (Nana)
このタイトル、とても良いですね!視線が大事。
さあ、これからコメントが長くなります。
>例の有名な彼女のゆっくりフォンデュを見せる技。
重箱の隅をほじくるようで申し訳ありません(ジューバコフと呼んで)が、フォンデュではなくてデヴロッペですね。
>あそこを確か氏の評論では、プリマが観客に体を見
>せている、というような理解でした。それが官能的
>であると。
ええっと、それで間違いはないのですが、もう少しくどくど言うと、身体の隅々にまで視線が注がれるように踊る、別に言い方をすればそのように見せるテクニックを持っている、という感じでしょうか。
>ここで、なるほどと思ったんですね。グ
>ラチョーワのような女性は本質にそういうものを持
>ってるし、
ここは少し違うようなのです。氏がここでエロスを感じたのは、「女性が持つ本質的なもの」にではなく、(性別を超えた)一個の踊り手がテクニックによって、自分の身体の隅々まで観客の視線を惹きつける、そのことによってなのです。
もちろん、グラチョーワはとても美人ではありますが、だからと言ってスーパー美人ではない。鈴木晶氏は自身のウェブサイトで彼女を「ちんころ姐ちゃん」と形容したくらいです(でも私はこの表現は、一個の女性としてのグラチョーワが漂わせる一種のいかがわしさ=小悪魔的性格を考えたとき、ひどく適切なように思いました)。ザハーロワなんかはスーパー美人と言えるかも知れませんが。
でも私は、スーパーでない普通の美人が、このようなデヴロッペによって多くの人々の視線を惹きつける、その非日常的現象に言い知れぬエロスを感じるのです(あ、私じゃないですね、赤尾氏です。でも私も感じるのです)。
>氏の見方
>だと、彼女のソロに色気を感じているわけですが、
これはバレリーナのエロスではなく、バレエという芸術において稀に見るエロスと言ったほうが良いのかも知れません。
>私は、(評論読むまで意識してなかったけど)どち
>らかといえば舞台の上に男性がいるときのグラチョ
>ーワを色っぽいと感じていた。彼女の官能性がマッ
>クスで発揮されたエギナだと、彼女の謀略のセクシ
>ーダンス、それをみて興奮していく牧夫さん、そ
>の、牧夫の興奮を感じ取ってた、と思う。
小悪魔=グラチョーワには誰もが誑かされそうですが、「スパルタクス」では、グラチョーワでないバレリーナがエギナを演じた場合でも、牧夫がエギナを見る視線が彼女の官能性を表現することが演劇的に可能になります。あ、でもやっぱグラチョーワは特別かなあ・・・。
>つまり赤尾氏の場合、舞台の表現の送り手と受け手
>の見る、見られる、の関係性がダイレクトなんです
>ね。私のは、セクシーな自分を見せるグラチョーワ
>扮するヒロインがいて、それに色気を感じる男の人
>が舞台にいて、観客の私がそれをみている、という
>ような関係性になってるんです。
所謂、メタシアター的構造ってやつですね。Nanaさんの見方は正しいと思いますよ。ちゅうか、氏もそのように見ているはずです。見る・見られるの関係を対称的に捉えているように思われたのは、紙数の関係で脇役まで言及できなかったからです。別の論考(ゴルスキーの「ドン・キホーテ」)では、そういう主張をしています。皆がキトリを見ている、そのことによって彼女が主役の位置を確固たるものにしている、と。
>これは、女性が全て必ずしも私と一緒とは限らない
>かと。他の人にも聞いてみないとわからないです
>ね。ま、女の自分がダイレクトにグラチョーワをみ
>て色っぽいな~ってのもちょっとあれだが・・。
た、確かにビミョウ・・・。
>それと、何割方かのプリマは二重性を持っていて、
>色っぽいグラチョーワの本質が一方であり、もう一
>方にウラーノワが望んだ清純なヒロインのイメージ
>があると思うんです。
う~ん、ウラーノワはともかく、グラチョーワの本質って、色っぽいvs.清純のどちらか一方では割り切れないと思います。この辺りはマクシーモワに匹敵する玉虫色の表情を持っています(芸幅の広さはプリセツカヤに匹敵する)。
>私の場合、あのグラチョーワのゆっくりと脚を美的
>に上げていく技術に、
>色気よりは、陶酔的ではあるんだ
>けどなにか神秘的で侵しがたいものも感じていて、
>祈り、みたいなのとか。何か時をとめるような感じ
>って言うのは共通して見る人がもってるんじゃない
>かと思うんだけど。
時を止める、というのも正鵠を射ていますね。止める(かのように見せる)ことによって何を表現するか。「ジゼル」「海賊」「バヤデルカ」のような作品では確かに祈りのようなものかも知れません。もちろん、氏はこの祈りや敬虔さに対してエロスを感じたわけではありません、念のため。
>技術てきにはあれはバレエの美そのものだし。脚の
>筋肉各箇所に均等に力が加わってる美しさ、とか、
>瞬間瞬間の造形美とか。
私的には、脚の筋肉各所に均等に力が加わっているからあのデヴロッペが可能になる、というようなことはどうでも良いことだと思っています(踊り手はそう考えるかも知れないが、私は見るだけの人なので)。ただ、あのデヴロッペによって観客の視線は踊り手に惹きつけられ、ある種、時間が止まるような印象を得、そこに敬虔さとか無垢さとか、あるいは誘惑とかが立ち現れてくるのだと思います。つまりバレエのテクニックはあくまで表現の「器」でしかありません。でもその「器」がしっかりしていないと、表現が成り立たないのです。私がテクニックという「器量」にこだわる理由はひとえにこの点にあるのです。
>どっちかっていうと脚中心
>に見ていて、後、顔の表情とかで、体を見せてい
>る、という理解でみてはなかったです。
これも紙数の関係で脚中心に記述したのですが、もちろん顔の表情や上体の所作も、演技に多大な影響を及ぼします。
>私は、ウラ
>ーノワの見せたかったニキヤをグラチョーワの身体
>からみていたのかもしれません。そして赤尾氏が看
>破されたものはにじみ出るグラチョーワ自身の本質
>であり、表現者としての彼女が、後にウラーノワを
>越えて自分の独創的な芸術表現としてエギナ役で爆
>発させたものの萌芽がそこにはあったのかもしれま
>せん。
ううう、こりゃ参りました。あれ(「バレエ・テクニックのすべて」)を書いていたころ、実は氏はまだグラチョーワのエギナをナマで見たことがなかったのですね(その後、3回くらい見ていますが)。ですから、氏が「エギナ役で爆発させたものの萌芽」を看破していたというのは買いかぶりです。Nanaさんこそ、凄いですよ。参りました。
では、また。いや~長かった・・・。
いや~、いやいや、堪能させていただきました。とても丁寧なご指摘ありがとうございます。「ジューバコフ」な所がかえってよかったです。このごろヌルく生きてる脳に心地よい刺激の数々。ビミョーなようで大事な差。流し読みや走りぬけるように読んでる文の誤読って結構あるのかも。
ところで「ゴルスキーの”ドンキ”の論考」とは、今でも簡単に入手できる所に記載があるでしょうか?公演パンフにはこの作品について少しだけ言及したものがありましたが、書き手が誰だったかも??
今日本にはいらっしゃらないようなので分からなかったらスルーして下さい。
私は書き込んで得しちゃいましたが、これもひとえに管理人様の広い度量のおかげ。長くなってしまったのでここらで切ります。自分の文って、「エロス」「官能性」等の言葉の使い方が平板でステレオタイプだなとは思いましたわ。
黄金時代3のあとに以前のコメントの続きを少々書き込ませて頂きましたが、今更あまり役に立たないかも。では。
ながながと返信して失礼しました(管理人さま、ブログを私物化してしまったみたいで、申し訳ありません)。
ゴルスキー云々については、だいぶ前(97-8年頃)にダンス・マガジンでヒロイン特集を組んだときに「ドン・キ」のキトリを取り上げて書いたものです。今手元に無いので、お送りできないのが残念です。
では、また。