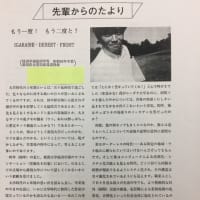●新潟暮らしセミナー@回帰センター(その2)
「新潟暮らしセミナー」と銘打った、UIターン促進に向けた都内在住者向けの新潟での生活の魅力の説明や移住のための相談の会合を、私の着任する前の年に企画調整された既定路線に沿って何回か視察してみた。殆どが有楽町駅前の交通会館の中にあるふるさと回帰支援センター内にあるセミナールームを借用して開催するのであるが、隣接する別のセミナールームにおいて、他の自治体が同様のセミナーを開催していたりして、私はそれらも移住検討者よろしく忍び込んで、他自治体の説明ぶりなどをるだけ見聞きしてみた。地方創生が叫ばれて以来数年。こうしたセミナーは多くの自治体が行うようになっていて、それぞれの特長やウリを宣伝するどれも似たような情報発信合戦は、ある種の飽和状態に達しているように思えた。
全国各地からの魅力的な情報発信が氾濫するなかで移住検討者から新潟を選んでもらうためには、差別化が必要となる。これまでの数年間においても新潟暮らしの独自性や魅力を掘り下げてセミナーやホームページなどで情報発信してきたのであるが、突き詰めればどれも新潟が唯一とは言い切れないし、また、何か一つが魅力的でも現実的な生活を考えれば、それをもって新潟に居を移すに至らしめるものではないだろう。冬のスキーや夏のマリンレジャーはもとより、農業や田舎暮らしの楽しさなどを新潟暮らしの醍醐味の一部として移住実践者などを通じて詳しく発信しているのであるが、それらでさえも、季節に一定期間訪れて楽しめればそれで十分とされないこともない。誘い込み方について何か新たな展開が必要な段階に来ているのではないだろうか。
そういえば、春先の着任早々に開催された、移住促進に関連する県内各界の関係実務者による新潟暮らし推進ネットワーク会議を終えた後で、パネラーとして参加して頂いた移住実践者の方が、「移住促進のための現地視察会に来訪する移住検討者の中には、既定の視察ルートに飽き足らずに、視察の前後や隙間時間などに自分が個人的に関心を持つ視点でタクシーを利用するなどして地域を見て回る人がいる」といったような話をしていた。子育てを重要視している人は視察地の周辺の小中学校や住宅地の小さな公園や雰囲気などを、趣味を持っているひとはその活動に関連した場所をという具合に。そうした個別のニーズは千差万別なので、幅広く生活に共通する視察地にしにくいのであるが、逆に万人共通性と地元自治体としての目線で"ウリにしたい気持ち"の高さから、観光ツアーのようになってしまっている視察も散見されるようだ。
移住への動機付けには現地を見て体感してもらうことが必須と言って良い。一度現地に来て地元と関わったりすると親近の情も湧いて移住先の選択肢としてのステータスが大きく動くようだ。その重要な機会に、移住を考える一人ひとりが各々で重要視している課題について十分に見ることができて、良い心証を得て頂けるようにできる仕組みを講じるべきではないか。
そうして私は、来期のセミナーの企画として、新潟暮らしセミナーにおいては、これまでの説明型中心ではなく、移住検討者が移住実践者と地域を良く知る市町村役場の担当者などが、ワークショップ形式でわいわいガヤガヤと話ししながら、オーダーメイドで視察内容を組み立てて行く催しを組み込むことを考えて予算化に漕ぎ着けた。セミナーの設営そのものを他の自治体と差別化を図り、新潟を氾濫する移住関連の情報から浮かび上がらせたいのだ。
これまでように地域のウリを宣伝するばかりではなく、「移住を考える一人ひとりの関心や悩み事を聞いて、その答えは新潟にありますよと提案する」。プッシュ型からプル型への転換。新潟暮らし推進課長を務めるにあたり"私ならでは"としての方向性を固めた。
全国各地からの魅力的な情報発信が氾濫するなかで移住検討者から新潟を選んでもらうためには、差別化が必要となる。これまでの数年間においても新潟暮らしの独自性や魅力を掘り下げてセミナーやホームページなどで情報発信してきたのであるが、突き詰めればどれも新潟が唯一とは言い切れないし、また、何か一つが魅力的でも現実的な生活を考えれば、それをもって新潟に居を移すに至らしめるものではないだろう。冬のスキーや夏のマリンレジャーはもとより、農業や田舎暮らしの楽しさなどを新潟暮らしの醍醐味の一部として移住実践者などを通じて詳しく発信しているのであるが、それらでさえも、季節に一定期間訪れて楽しめればそれで十分とされないこともない。誘い込み方について何か新たな展開が必要な段階に来ているのではないだろうか。
そういえば、春先の着任早々に開催された、移住促進に関連する県内各界の関係実務者による新潟暮らし推進ネットワーク会議を終えた後で、パネラーとして参加して頂いた移住実践者の方が、「移住促進のための現地視察会に来訪する移住検討者の中には、既定の視察ルートに飽き足らずに、視察の前後や隙間時間などに自分が個人的に関心を持つ視点でタクシーを利用するなどして地域を見て回る人がいる」といったような話をしていた。子育てを重要視している人は視察地の周辺の小中学校や住宅地の小さな公園や雰囲気などを、趣味を持っているひとはその活動に関連した場所をという具合に。そうした個別のニーズは千差万別なので、幅広く生活に共通する視察地にしにくいのであるが、逆に万人共通性と地元自治体としての目線で"ウリにしたい気持ち"の高さから、観光ツアーのようになってしまっている視察も散見されるようだ。
移住への動機付けには現地を見て体感してもらうことが必須と言って良い。一度現地に来て地元と関わったりすると親近の情も湧いて移住先の選択肢としてのステータスが大きく動くようだ。その重要な機会に、移住を考える一人ひとりが各々で重要視している課題について十分に見ることができて、良い心証を得て頂けるようにできる仕組みを講じるべきではないか。
そうして私は、来期のセミナーの企画として、新潟暮らしセミナーにおいては、これまでの説明型中心ではなく、移住検討者が移住実践者と地域を良く知る市町村役場の担当者などが、ワークショップ形式でわいわいガヤガヤと話ししながら、オーダーメイドで視察内容を組み立てて行く催しを組み込むことを考えて予算化に漕ぎ着けた。セミナーの設営そのものを他の自治体と差別化を図り、新潟を氾濫する移住関連の情報から浮かび上がらせたいのだ。
これまでように地域のウリを宣伝するばかりではなく、「移住を考える一人ひとりの関心や悩み事を聞いて、その答えは新潟にありますよと提案する」。プッシュ型からプル型への転換。新潟暮らし推進課長を務めるにあたり"私ならでは"としての方向性を固めた。
(「新潟暮らし推進課8「新潟暮らしセミナー@回帰センター(その2)」編」終わり。県職員として11箇所目の職場となる新潟暮らし推進課の回顧録「新潟暮らし推進課9「潟コン@六本木」編」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea