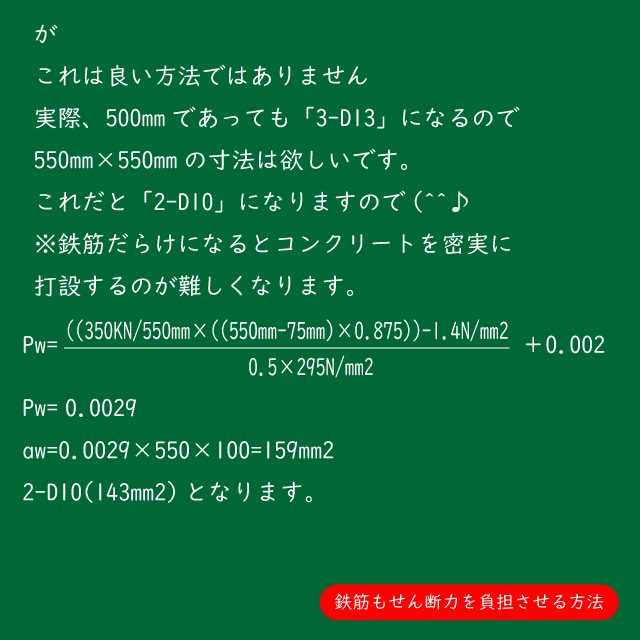施工管理技士に合格できないのは
難しいのは基本を学んでいないからだと思う。
実務では「工期や予算管理」を求められるので、肝心の「施工の品質管理」が疎かになる。
これが、試験に受からない原因だと思っています。
試験に求められるのは「施工管理技術者」としての品質管理です。
品質管理の基本が解らないから、受かる道理が無い訳です。
不合格の理由を
仕事が多忙で、休日が無いからと嘆いている方が居られますが、それは、違います。
そういう状況下でも合格する方がおられるので、言わない方が良いです。
どうしても合格したいのなら「工期と予算管理」と「施工の品質管理」を紐づけて考えるようにしたら良いと思う。
事実、物事を単独で捉え覚えると「忘れてしまう」と終わりです。
加えて、覚えてしまっている事実を復習しないこと
時間が勿体ないし、覚えたという自己満足しか残りません
具体的な例
一日で「96立法メートル」のコンクリートを「8時間で打設」しなければならないと仮定します。
一時間で12立法メートルを打設し、一台(10トン車)当たり20分で打設しなければなりません。
また、気温25度以下では120分(練り混ぜから打設完了まで)という制限が加わります。
今回は「勉強の方法」が主題なので、詳細は割愛しますが、
チェックすべき事項は
・コンクリートの運搬時間
・打設計画(打設部位の順番・配管計画・人員配置)
等になります。
これを「グループ」として覚えるのが良いと考えています。
「コンクリート」というお題が出れば
・配合(設計強度の確認)
・打設計画(打設数量と見積もり数量の確認)
・気温(補正強度の有無や打設完了時間)
というように覚えてしまえば「スイスイ」と「情報」が頭から出てくるはずです。
私が導き出した情報には「工期と予算管理」と「施工の品質管理」が含まれています。
これらを、分けて覚え、関連性を考えなければ、忘れたら終わりです。
私は、このようにして覚えて理解するようにしています。
これが、施工管理試験の勉強方法だと思いますが、どのように感じますか?
合格点に至らない原因は、解らなかった問題があるからですよね
解らなかった問題を処置していないから、翌年も不合格になるのです。
勉強をする場所を間違えているのです。
覚えたことの復習なんて要らない
不得手な分野と、覚えたことと他の関連性を考えた方が、効率が上がります。
沢山の知識を求められる試験ですが、満点を求めてはいません
しかし、必ず実務の経験を記述しなければならない問題が出題(二次試験)され、これが解けない書けないと不合格と一般的に解釈されています。
おそらく、実務において「幅広い知識の関連性を考えて実践している」のかを問うているのでしょう。
これが、施工管理試験の主題ではないでしょうか?
合格出来ないのは、点数が足らないからですよ!は常識です。
でも「必須の記述問題」が「幅広い知識の関連性を考えて実践している」を求めている限り、その「関連性と応用力」が無いと、合格できないと考える方が正しいと思っています。
私は、覚えた知識を実務で用い正しく運用すること、また、「監理技術者の講習義務」を定め、継続的に正しい知識を学び続けることを、施工監理技術者に求めているものだと解釈しています。