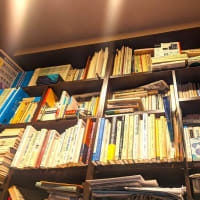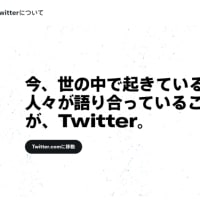考えさせられる記事があったので、以下、その記事を引用します。
「助けて」1日2万件、死にたい・食べてない…
読売新聞 5月31日(木)14時44分配信
東日本大震災後の社会不安の高まりを受けて、国の補助金で3月にスタートした無料相談ダイヤルに電話が殺到し、開設2か月あまりでパンク寸前となっている。
「死にたい」「5日間何も食べていない」など深刻な悩みも多く、厳しい世相を反映している。
一般社団法人「社会的包摂サポートセンター」(本部・東京)が行う24時間対応の「よりそいホットライン」。貧困、失業、いじめなどあらゆる悩みを1か所で受け止めるワンストップ型の支援が好評で、1日約2万件の電話に対し、つながるのは1200件程度だ。
全国38か所の支援拠点で、午前10時~午後10時は計30回線、深夜・早朝も計10回線を用意。1回線に2人の相談員がつき、計約1200人が交代で対応する。活動に協力する各地の弁護士などが必要に応じて助言。命に関わる場合には、福祉団体などの支援員が相談者のもとへ駆けつける。
インターネット上の口コミなどで存在が周知され、今では平均20回かけてやっと通じる状態だ。
相談の7割は生活上の悩みで、30~50歳代からの電話が多い。「失業して家を失った」「生きていてもしょうがない」「誰かと話がしたかった」など、貧困や孤独を訴える声が目立つ。
失業して生活保護を申請中という30歳代の男性は、「所持金が底をつき、何日も食べていない」と助けを求めてきた。衰弱した様子で、「命に関わる」と判断した相談員は、支援員に連絡して食料を届けた。「どこに相談しても、誰も助けてくれなかった」と、男性から感謝された。
引用元
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120531-00000681-yom-soci
ふと、不思議に思う。
これだけインターネットが広まり、いろんな人といつでもコミュニケートできるのに、その一方で、これほどまでに相談サービスに需要があることに。SNSなんかもあり、他者との交流は手軽に、いつでも、無理なくできるようになった…はずだった。
が、その一方で、孤独に、誰にも相談できないで生きている人が多い、ということも明らかになりつつある。
僕は「勝ち負け」を主張する立場にはない人間だけど、それでも、思わざるを得ない。「いつから、人間ってこんなにも脆弱になったのだろう?」、と。ものすごく弱くなってきているように思う。
インターネットの世界に住み込んでいる僕だけど、インターネットの世界って、実は「本音」が全然出せない場所である、ということには最近まで気付かなかった(鈍感なもんで、、、)
インターネットの世界って、一般の社会よりも、実は許容範囲がすごく狭い。一般の社会よりも、多様に見えて、実は多様性のない世界だったりもする。シンプルにいえば、ネットの世界には、赤ちゃんや子ども、高齢者等の声はほとんどない。多様性という点では、現実社会の方が多様であり、ネットの世界は極めて制限された世界なのだ。ゆえに、許容度も狭く、寛容さも乏しい。
けれど、今の人たちはますますネットに依存しつつある。また、それにもかかわらず、孤独感や社会的不安感も増大している、というのだ。
この現象をどう考えたらいい?!
僕が考えるのは、やはりネットはサブ空間であるということ。メインの現実の世界がしっかりとまわっている人だけが、ネットの世界をエンターテイメントとして楽しむことができる。インターネットの世界は、やはり根本的にはバーチャルリアリティーなのだ。それを間違えると、現実世界という足場がないまま、浮遊することになる。足場が脆い人間は、その存在自体が危うくなる。
それから、やはり本音を言える場所がどうしても必要なのだ、ということ。信じられる人、頼れる人、話を聞いてくれる人、そういう人がいるかいないかで、人生はかなり大きく変わってくると思う。友達も大事だとは思うけど、それ以上に大切なのは、斜め上から心配してくれる存在だと思う。僕はそういう斜め上からの存在を、「フィリアの愛」という風に言語化して、学生たちに伝えている。
僕らに必要なのは、対等な愛以前に、斜め上からの愛情なのではないか? 最近はそう強く思うようになっている。信頼できて、信用できて、頼れて、安心できる存在。そういう存在が、今、ますます求められているように思う。
この部分は、もっともっと考えていきたい。でも、当面はできないかな。ライフワークとして考えていきたいかな。