浮世絵の研究が始まる明治半ばから、研究が盛んになる大正時代を経て、昭和10年代の研究の集大成期に至るまで、写楽に関しては、「浮世絵類考」の補記の内容から一歩も踏み出せなかったと言っても良いでしょう。
そして、「写楽は、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛といい、江戸八丁堀に住んでいた」ということは専門家から一般人までほとんどの人がずっと信じて疑わないことでした。したがって、その研究(というより探索)は、この斎藤十郎兵衛という人物の実在を突き止め、この人物の生年没年、出自や経歴を明らかにすることに集中しました。
なかでも、いちばん熱心だったのは著名な人類学者の鳥居龍蔵(1870~1953)で、同じ阿波(徳島)出身ということもあって、大正の末頃から斎藤十郎兵衛の探索に乗り出しました。地元の資料や墓石などを調査して、何度かの誤認にも挫けず、ようやく斎藤十郎兵衛が実在していたことを突き止めます。昭和6年12月号の雑誌「武蔵野」に掲載された論文「写楽は絵を捨てた後どうしたか」の中で、鳥居博士は、文政8年以前でない能番組(江戸蜂須賀邸で催された)に斎藤十郎兵衛が喜多流の能楽「巴」のワキ役およびその他の役を勤めているという記述があることを発表しました。ほぼ同時期に徳島の森敬介という学者が斎藤十郎兵衛の出演している能番組があったという報告をします。これで、斎藤十郎兵衛が実在する能役者だったことが確かめられたのでした。
一方、唯一の文献である「浮世絵類考」の検証も進んでいきました。この本は、原本が出来てからずっと刊行されたことがなく、手書きの写本によって普及していきました。明治22年になって初めて、増補された時期が最も新しい写本が単行本(「戯作者略伝」との合本)になり、畏三堂から出版されます。「新増補浮世絵類考」と題され、慶應4年に龍田舎秋錦が斎藤月岑編「増補浮世絵類考」を再編集したものです。
その後、違った写本が幾度か刊行されましたが、ようやく底本に近い「浮世絵類考」が出版されたのは昭和16年のことでした。その時、2種類の「浮世絵類考」が出版されます。
一つは、大曲駒村編の限定版「浮世絵類考」で、もう一つは仲田勝之助編の岩波文庫版「浮世絵類考」です。
前者は、文政4年に大田南畝が編纂を終えた時の原本(三部作)に最も近い形のもので、後者は、原本とそれに書き加えられた重要な補記をすべて掲載し、活字の級数と頭注でその区別が分かるようにした総合版といったものでした。前者は、発行部数が300部だったので、あまり普及しなかったようです。後者は、岩波文庫なので大変普及し、戦後になっても再版されました。(40年ほど絶版になっていたようですが、1991年に復刊しています)
大曲駒村編の「浮世絵類考」は、国立国会図書館のデジタルライブラリーにあるので、私は全ページをプリントアウトし、熟読しました。岩波文庫の「浮世絵類考」は復刊本を買って、ざっと読んでみました。
それぞれの本で、写楽の項目に書かれていることを以下に記しておきましょう。(新字体にしておきます)

大曲駒村編「浮世絵類考」
写 楽
是また歌舞伎役者の似顔を写せしが、あまりに真を画んとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず、一両年にして止む
三馬按、写楽号東周斎、江戸八丁堀ニ住ス。僅ニ半年余行ハルゝノミ

岩波文庫「浮世絵類考」
写 楽 斎 【曳】東洲斎写楽
【新】俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿波侯の能役者也。
これは歌舞伎役者の似顔をうつせしが、あまりに真を画んとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず、一両年にして止ム。
【曳】しかしながら筆力雅趣ありて賞すべし。
【三】三馬按、写楽号東周斎、江戸八丁堀に住す、はつか半年余行はるゝ而已。
【無】五代目白猿 幸四郎(後京十郎と改) 半四郎 菊之丞 富十郎 広次 助五郎 鬼治 仲蔵の類を半身に画たるを出せし也。
【新】回り雲母を摺たるもの多し、俗に雲母絵と云。
*【曳】=加藤曳尾庵による写本。通称「曳尾庵本」
【三】=式亭三馬による補記
【無】=渓斎英泉による「無名庵随筆」。通称「続浮世絵類考」
【新】=龍田舎錦秋編「新増補浮世絵類考」
そして、「写楽は、阿波藩お抱えの能役者・斎藤十郎兵衛といい、江戸八丁堀に住んでいた」ということは専門家から一般人までほとんどの人がずっと信じて疑わないことでした。したがって、その研究(というより探索)は、この斎藤十郎兵衛という人物の実在を突き止め、この人物の生年没年、出自や経歴を明らかにすることに集中しました。
なかでも、いちばん熱心だったのは著名な人類学者の鳥居龍蔵(1870~1953)で、同じ阿波(徳島)出身ということもあって、大正の末頃から斎藤十郎兵衛の探索に乗り出しました。地元の資料や墓石などを調査して、何度かの誤認にも挫けず、ようやく斎藤十郎兵衛が実在していたことを突き止めます。昭和6年12月号の雑誌「武蔵野」に掲載された論文「写楽は絵を捨てた後どうしたか」の中で、鳥居博士は、文政8年以前でない能番組(江戸蜂須賀邸で催された)に斎藤十郎兵衛が喜多流の能楽「巴」のワキ役およびその他の役を勤めているという記述があることを発表しました。ほぼ同時期に徳島の森敬介という学者が斎藤十郎兵衛の出演している能番組があったという報告をします。これで、斎藤十郎兵衛が実在する能役者だったことが確かめられたのでした。
一方、唯一の文献である「浮世絵類考」の検証も進んでいきました。この本は、原本が出来てからずっと刊行されたことがなく、手書きの写本によって普及していきました。明治22年になって初めて、増補された時期が最も新しい写本が単行本(「戯作者略伝」との合本)になり、畏三堂から出版されます。「新増補浮世絵類考」と題され、慶應4年に龍田舎秋錦が斎藤月岑編「増補浮世絵類考」を再編集したものです。
その後、違った写本が幾度か刊行されましたが、ようやく底本に近い「浮世絵類考」が出版されたのは昭和16年のことでした。その時、2種類の「浮世絵類考」が出版されます。
一つは、大曲駒村編の限定版「浮世絵類考」で、もう一つは仲田勝之助編の岩波文庫版「浮世絵類考」です。
前者は、文政4年に大田南畝が編纂を終えた時の原本(三部作)に最も近い形のもので、後者は、原本とそれに書き加えられた重要な補記をすべて掲載し、活字の級数と頭注でその区別が分かるようにした総合版といったものでした。前者は、発行部数が300部だったので、あまり普及しなかったようです。後者は、岩波文庫なので大変普及し、戦後になっても再版されました。(40年ほど絶版になっていたようですが、1991年に復刊しています)
大曲駒村編の「浮世絵類考」は、国立国会図書館のデジタルライブラリーにあるので、私は全ページをプリントアウトし、熟読しました。岩波文庫の「浮世絵類考」は復刊本を買って、ざっと読んでみました。
それぞれの本で、写楽の項目に書かれていることを以下に記しておきましょう。(新字体にしておきます)

大曲駒村編「浮世絵類考」
写 楽
是また歌舞伎役者の似顔を写せしが、あまりに真を画んとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず、一両年にして止む
三馬按、写楽号東周斎、江戸八丁堀ニ住ス。僅ニ半年余行ハルゝノミ

岩波文庫「浮世絵類考」
写 楽 斎 【曳】東洲斎写楽
【新】俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿波侯の能役者也。
これは歌舞伎役者の似顔をうつせしが、あまりに真を画んとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず、一両年にして止ム。
【曳】しかしながら筆力雅趣ありて賞すべし。
【三】三馬按、写楽号東周斎、江戸八丁堀に住す、はつか半年余行はるゝ而已。
【無】五代目白猿 幸四郎(後京十郎と改) 半四郎 菊之丞 富十郎 広次 助五郎 鬼治 仲蔵の類を半身に画たるを出せし也。
【新】回り雲母を摺たるもの多し、俗に雲母絵と云。
*【曳】=加藤曳尾庵による写本。通称「曳尾庵本」
【三】=式亭三馬による補記
【無】=渓斎英泉による「無名庵随筆」。通称「続浮世絵類考」
【新】=龍田舎錦秋編「新増補浮世絵類考」










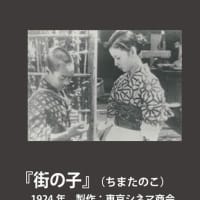



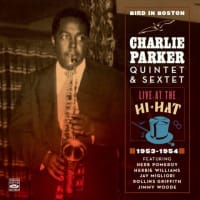
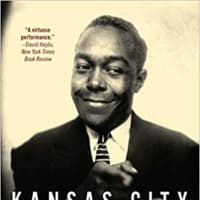

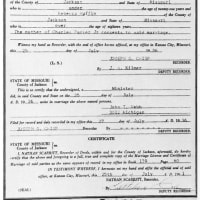



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます