三州街道(R153) 道の駅信州平谷 ・・・ひまわりの里
併設されている「信州平谷温泉ひまわりの湯」「しょうかん亭」「ほっとパークひらや郷(Go!!)」、標高920m
県境、平谷に設営されたこの道の駅は、思いのほか人気者らしい・・・・・
人気の秘密を探って見ると、まず、田舎の風景、自然の豊かさ・・赤石山系の端の山の中だから当たり前・・三河の母なる大河、矢作川の源流付近・・ここがポイントかも知れない・・そして、温泉設備・たぶん鉱泉の沸かし湯だろうが、ことのほか、すこぶる評判がいい・・そして清潔な付随設備・トイレなど、と比較的経済的な食事処など・・・
もとより、貶すつもりもないが、かなり欠点の少ない道の駅といえようか、と思う。・・こんなに褒めると、道の駅平谷のポチか回し者と思われかも知れないが、それはない・・・・・。
周辺のひまわり畑・・・

ここが、温泉施設・・ひまわりの湯、と言うらしい。

写真では、スペースに余裕がありそうだが、かなり広い駐車場はほぼ満車状態・・・・・。車の8割が、三河ナンバーです。
R153線は、昔三州街道と言われた。つまり、信州と三河を結ぶ道路なのです。県境の平谷の隣は、もう豊田市なのです。愛知県豊田市なのだから、愛知県です。
ですが、塩の道三州街道を、歴史として読み込んできた自分には、どうもすっきり来ません。飯田から豊田まで、表示では約80Kmぐらいになっています。平谷から県境を越える豊田まで20分ぐらいでいけそうです。平成の大合併で、足助や稲武あたりが豊田になっていると言うことでしょうか。
どうも、この車の三河ナンバーの数の多さを見ますと、ドライブ一時間半以内の三河の人達の、田舎的オアシスに、平谷が認定されている様子です・・・冬は、数カ所、スキー場もできたそうですし・・・
 ・・平谷の隣村の根羽村は、もとは三河だったみたいですよ。
・・平谷の隣村の根羽村は、もとは三河だったみたいですよ。
------------------------------------------------
五平餅・・
せっかくだからと、近辺の旧跡を見て見ると、平谷には意外と少ない。三州街道を、飯田から辿ると、まず駒場、そして浪合、続いて平谷、そして根羽と連なる。根羽を過ぎると、そこはもう、三河、通称は奥三河と呼ばれる地区となる。奥三河を含めてこの一帯を、勝手に名付ければ、”五平餅食文化圏”となる。五平餅が、発祥を、三河とするのか、信濃とするのか、それは各(オノオノ)が主張しているので、どちらかに組みするつもりはない。五平が作ったのか、御幣に似ていたからなのか、は御幣に似ていたからの名の由来に賛成する。御幣とは・・神社などで、注連縄にぶら下がる、あの菱形状の白い紙の連なりを指し、外界の邪気から聖なる領域を”バリヤー”するものである。・・神社は、御幣により護られた神域・・・・・菓子など無かった時代、五平餅は、”はれ”の時に食する貴重な食べ物だったらしい。
四つの集落・・
駒場(コマンバ)、浪合、平谷、根羽の集落を見ると、駒場と浪合は比較的大きな集落をなし、旧跡も多い。・・・駒場は古代に東山道の古道の分岐点で、木曽を通る東山道の脇往還として栄え、塩の道の宿場としても有名で、現代で言う”トラックターミナル”の昔版の”馬のターミナル”=駒場であったみたいだ。古くは、小笠原守護家の、そして武田信玄の東方の守り、駒場城もあった。駒場は武田信玄の終焉(しゆうえん)の地(長岳寺)もここにある。・・・浪合は、駒場から分岐して足助、岡崎方面に向かう三州街道の宿場である。ここにも信玄は”浪合関”を設けて、織田・徳川の脅威を防いでいたらしい。更に昔の南北朝時代、南朝の将軍、宗良親王が死んだ後、息子の尹良親王は、ここ浪合で、新田軍とともに、幕府軍と戦い、ここで討ち死にしたらしい。尹良親王の墓もあるという。・・この尹良親王伝承はかなり疑わしい点もあるが、南朝軍が幕府軍と戦った痕跡は確からしい。・・・平谷と根羽は、三州街道、塩の道にあり、関の外に存在し、垣外(ガイト)であった。とくに根羽は、信玄によって信濃に属したが、住民は三河を向いているという。

















 ・・小渋ダム 日本一美しいダム?ともいわれる
・・小渋ダム 日本一美しいダム?ともいわれる 
 ・・転記 4月始め頃?
・・転記 4月始め頃?



 ・・塩見岳 ・・・ 拝
・・塩見岳 ・・・ 拝



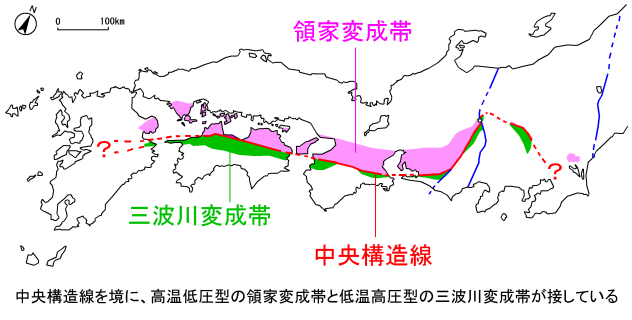 転記
転記
 S36災害の時、この北川地区に大洪水と土砂崩れが襲いました。
S36災害の時、この北川地区に大洪水と土砂崩れが襲いました。







 転記1
転記1 転記2
転記2 転記3
転記3 転記4
転記4
 ・・護国観音とか、白衣観音とか。
・・護国観音とか、白衣観音とか。






 ・転記 曰く、名品・・
・転記 曰く、名品・・




















 古くは、この水上に弁天堂がまつられ参詣したというが、今は池の対岸にある久昌寺の境内に移されている。
古くは、この水上に弁天堂がまつられ参詣したというが、今は池の対岸にある久昌寺の境内に移されている。



















