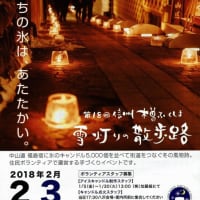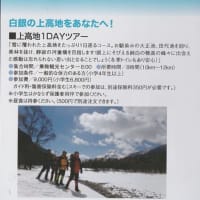どこの地域でも昔から、三九郎という行事があるのではないでしょうか?
もちろん田舎である、ここ沢渡でも伝統的に旧来から続けられています。
地域の男性諸兄達が、山から木の枝を切り出し、やぐらに組みあげて作り上げるというものです。
その大きさが半端ではないのです。

完成したものが、こちら↑↑。その高さ約6m。
昨今、人手も少なくなり年齢がみな高くなってきたので思うように作業が進まない。
そこで、ここはお客さんにも「体験」と称して一緒にお手伝いしてもらおう・・・・という企画。
参加者を募集します。
作業の日:平成25年12月22日(日) 朝8時30分頃からです。
日帰りでも泊まりでも結構です。昼食付きですので是非どうぞ!。
男性に限らず、応援してくれる女性の方も大歓迎です。
地域の人たちと一緒に作業をすることで、もっともっと沢渡が好きになり、地域の伝統文
化の一端を知ることが出来ることと思います・・・・よ。
ざっと、流れを・・・・・。
まず、材料となる木の枝の切り出しと運び込みです。
枝払いには、安全を確保しながら木登りをして、細い枝ばかりを集めます。
沢山の材料が集まって運び込みました。↓↓
もうこの写真では、芯になる棒を立て始めています。

中心の芯棒にどんどん集めた木の枝を押し付けて(巻いて)いきます。


どんどん大きくなってきます。こうなるともう梯子を使っての作業となります。
こうして枝を押し付けては、荒縄で締め出来上がったのが冒頭の写真。
実はこの「三九郎」。これだけで終わりではないんです。
各家庭で一年、見守っていてくれた「ダルマ」を持ち寄ったり、角松、しめ飾りなどを持ち寄ってさ
らににぎやかになるのです。
(松飾りを外せるのは、新年松の内が過ぎてからとなるのでおおよそ1月7日頃でしょう。)
先ほどの三九郎がこんな風になります。
さぁ、これに「無病息災」 「家内安全」などの祈願をし、点火するのはいつか?
1月14日(火)夜です。
この日もみなさん、ご参加いただきたいですね。
この三九郎は地域では伝統的に 「厄除け」 という意味合いが大きくあり、男性・女性の厄年
の人が、大きなふるまいをします。 (これがとてもお楽しみ・・・)
少しでも盛り上げようと、今まではこんな飾り付けも行いました。

今年も多くのみなさんに来てほしいですし、地域の行事に参加してもらいたいと願っています。
どうぞ、参加をお待ちしてます。
関連する ブログはこちら。