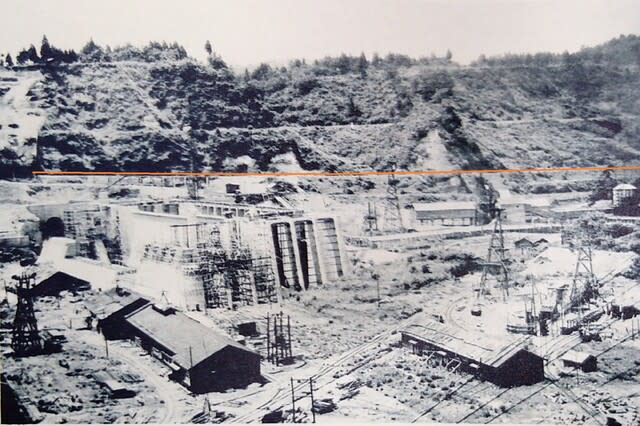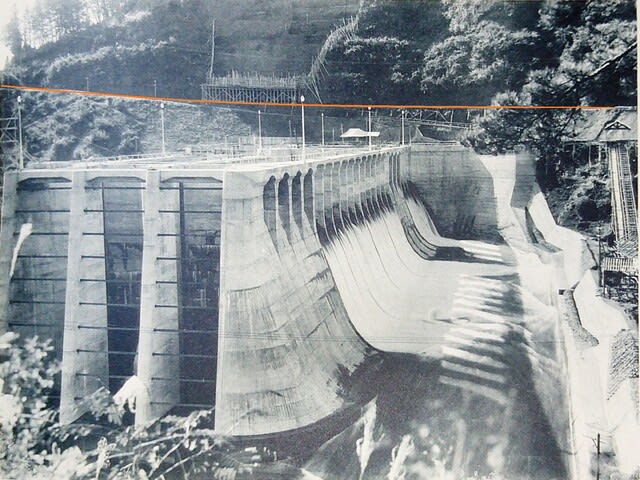「信濃川水力設備要覧 鐡道省東京電気事務所 昭和十五年三月二十日発行」より、更に写真を紹介する。なお、必要に応じて私がトリミングを行っている。

材料運搬線の除雪も、人夫を使っての人海戦術である。キャプションには、”材料運搬線除雪”程度にしか書かれていない。
豪雪地域故、軽便線の沿線は冬になれば数メートルは雪が積もる。なお、軽便線は積雪期は運休となっていたようで、4月下旬に運転を再開していたようである。というのも、十日町新聞でも冬期は軽便線が運休で十日町からの通勤もバスによることを伝える記事や、毎年四月二十日前後に軽便線客車列車の運転時刻が掲載されていたからだ。圧倒的な降積雪を前に、軽便線による冬期輸送は考慮されていなかったようだ。軽便線が冬期は運休というのは、戦後の工事でもそうであったようで、そのために各現場には冬期の工事で使用する分のセメント等を貯蓄しておくための倉庫を建築したとされる。
さて、上の写真も運転再開時期を反映するかのように、春の気温が緩んできた頃の様子であろうことが分かる。こんなに雪が積もっていても、これは冬の景色ではないことは雪の質感などから分かっていただけると思う。四月、新たに雪も積もらなくなり、軽便線の運転再開に向けて人夫を使って除雪作業を行っていたのだろう。
そして何より、この写真がどこで撮られたのかが気になる。見た限り線路の右手が山側であるから、左手に信濃川が流れているはずだ。つまり、信濃川上流方を見ている景色と言える。かなり深い切取りの底を、そこそこの勾配で線路は登ってきている。更に、右側斜面の上辺を前方の左カーブの先まで追っていくと、途中で途切れていることが分かる。掲載した写真だと分かりにくいが、途切れた先で中腹から生えているだろう杉の木が頭を覗かせている。連続した地形なら、杉がそんな風に生えるわけがない。つまり、カーブの先で崖に落ち込んでいる地形なのである。
写真から観察される条件から、私が考えた撮影地点は「鉢沢橋梁の高島方(千手方)」である。


国土地理院地図・空中写真閲覧サービスよりUSA-R1338-79である。ここから、写真で撮影された区間を赤塗する。

おおよそここだろうと。空中写真からも鉢沢橋梁を渡ってすぐに切取りをカーブしながら川側に進路を向け、しばし直線で登っていく様子が確認できる。そして、想定される鉢沢川橋梁の高さと高島方の河岸段丘上とはかなりの高度差があるため、このような切取りで克服していたと推測していることは再三述べている通りだ。その大規模な切取りこそ、今回紹介した写真に写っている光景なのではないか。なお、この切取りは現在、土砂で埋め戻されている。なんとなくの痕跡は残っているものの、この光景は今は見られない。ましてや、当時の路盤は地中にあって辿ることはできない。こうして、当時の写真を見付けては、往時の様子を知ることが出来るのみである。


最後に、現在の現地の写真を見てみよう。左の写真は、当時(右)の写真の線路の直線上の右側の斜面の上から撮影したと言えそうだ。
特定への判断基準となるだろう背景の山が写ってないので比較することが出来なかったため、次に現地を訪れる際には山の形と睨めっこしながら、確認したいと考えている。

材料運搬線の除雪も、人夫を使っての人海戦術である。キャプションには、”材料運搬線除雪”程度にしか書かれていない。
豪雪地域故、軽便線の沿線は冬になれば数メートルは雪が積もる。なお、軽便線は積雪期は運休となっていたようで、4月下旬に運転を再開していたようである。というのも、十日町新聞でも冬期は軽便線が運休で十日町からの通勤もバスによることを伝える記事や、毎年四月二十日前後に軽便線客車列車の運転時刻が掲載されていたからだ。圧倒的な降積雪を前に、軽便線による冬期輸送は考慮されていなかったようだ。軽便線が冬期は運休というのは、戦後の工事でもそうであったようで、そのために各現場には冬期の工事で使用する分のセメント等を貯蓄しておくための倉庫を建築したとされる。
さて、上の写真も運転再開時期を反映するかのように、春の気温が緩んできた頃の様子であろうことが分かる。こんなに雪が積もっていても、これは冬の景色ではないことは雪の質感などから分かっていただけると思う。四月、新たに雪も積もらなくなり、軽便線の運転再開に向けて人夫を使って除雪作業を行っていたのだろう。
そして何より、この写真がどこで撮られたのかが気になる。見た限り線路の右手が山側であるから、左手に信濃川が流れているはずだ。つまり、信濃川上流方を見ている景色と言える。かなり深い切取りの底を、そこそこの勾配で線路は登ってきている。更に、右側斜面の上辺を前方の左カーブの先まで追っていくと、途中で途切れていることが分かる。掲載した写真だと分かりにくいが、途切れた先で中腹から生えているだろう杉の木が頭を覗かせている。連続した地形なら、杉がそんな風に生えるわけがない。つまり、カーブの先で崖に落ち込んでいる地形なのである。
写真から観察される条件から、私が考えた撮影地点は「鉢沢橋梁の高島方(千手方)」である。


国土地理院地図・空中写真閲覧サービスよりUSA-R1338-79である。ここから、写真で撮影された区間を赤塗する。

おおよそここだろうと。空中写真からも鉢沢橋梁を渡ってすぐに切取りをカーブしながら川側に進路を向け、しばし直線で登っていく様子が確認できる。そして、想定される鉢沢川橋梁の高さと高島方の河岸段丘上とはかなりの高度差があるため、このような切取りで克服していたと推測していることは再三述べている通りだ。その大規模な切取りこそ、今回紹介した写真に写っている光景なのではないか。なお、この切取りは現在、土砂で埋め戻されている。なんとなくの痕跡は残っているものの、この光景は今は見られない。ましてや、当時の路盤は地中にあって辿ることはできない。こうして、当時の写真を見付けては、往時の様子を知ることが出来るのみである。


最後に、現在の現地の写真を見てみよう。左の写真は、当時(右)の写真の線路の直線上の右側の斜面の上から撮影したと言えそうだ。
特定への判断基準となるだろう背景の山が写ってないので比較することが出来なかったため、次に現地を訪れる際には山の形と睨めっこしながら、確認したいと考えている。