一週間をおかずして、私は現地を再訪していた。前回発見した橋台跡を改めて観察するためだ。興奮醒め止まぬままではあるが、今回は橋台に注力するつもりで来ている。
またしても夜明け前から現地入りをして、観察を行う。この時、気まぐれに橋台の側に生えていた笹を引っこ抜いたら、根が張り巡らされているはずの地面があっさりと剥がれた。地面が剥がれたと言うのは、文字通り笹を引っ張ったら根と地面ごとベロッと剥がれたのである。その感触には覚えがあって、その下にコンクリートか岩盤か、何かしら土も無く根が張れないものが存在しているという感触である。


そこら辺に散乱している枝を一本手に取り、私はそれで地面が剥がれた跡の土を払って行く。下にはコンクリートが顔を覗かせている。



ボルトが飛び出ている。そして、一部欠損しているものの、コンクリートには何か形成された痕跡がある。明らかにここにガーター橋として主桁が載っていただろう形状だろう、このディテールは。
主桁と橋座はここに飛び出ているボルトで接続されていたはずだ。これほどの痕跡は初めて見た。にしても、数十年は湿った地面の下に埋もれていたにもかかわらず、むしろ埋もれていたからか、エッジが効いたディテールが綺麗だ。

前回、ガーター橋が載っていたと言った部分も必要な構造物だと思われるが、こちらにはそれらしき造形は一切無い。ただ、中心に線路方向の溝が掘られているのみである。これを書いている時点で、私は溝の用途については分からない。類似例を調べている。また、こちらの構造物は川石が表面に浮いているのが特徴だ。橋台と比べると明らかにセメントと川石の配合率が違うように見える。用途によって変えていたのかも知れないが、それを示す資料については見付けられていない。もっとも、私は素人なのでコンクリートに詳しくない。単に風雨による劣化具合の差なだけかもしれない。



ガーター橋であるなら橋座も対になっているはずだから、山側も同じような形状をしていると推測される。しかし、いくら笹を引っこ抜けば地面ごと剥がれるとは言っても、これだけの土を除けるのに躊躇した。いや、同じような構造が土の下にあるとは思う。しかし、正直なところ、発掘するのが面倒くさくなった。我こそはと言う方、是非、発掘して欲しい。私はその後でまじまじと観察させていただければ良い。
とは言え、対岸(高城澤方)にも橋台跡はあるしということで、ある程度観察して、さっさと対岸へと移動した。
以下の写真の中ほどにある沢の右手が先ほどまで私がいた斜面だ。これから、沢の左手になる正面の段丘崖を登る。つい先日登ったばかりの斜面なので、何処をどう登って橋台跡へアプローチすれば良いかを知っているだけ、今回は気楽なもんだ。


途中、中腹で橋台下のコンクリートを改めて観察する。全容は全く掴めない。ただ、ガーダー橋なら、特にこの位置に橋脚なりを設ける必要も無かったろうし、単なる土留めなのかもしれない。位置的にもコンクリートの劣化具合的にも軽便線関係の構造物だとは思うのだけども。



なお、このコンクリートの塊は以下の写真のような場所にある。右手が発電所方で、沢へと落ち込んでいる谷の縁である。谷底の沢まで3m以上はあるため、落ちたら痛そうだ。足で上に載った土を少しばかり落としたものの、殆どの部分を木の根が覆っており、何も見付けることは出来なかった。

そして、少し登って橋台跡に辿り着く。こちらの橋台も同様の構造だと想像し、橋台そばの植物を引き抜こうとすると、またしても地面ごとベリッと剥がれた。
そこから何だかんだで1時間くらい発掘作業を行い、以下の写真のような状態まで露わになった。



木々の成長具合に時代を感じる。正面に立つ。本当によくぞ残っててくれたと感動した。「ここに鉄道ありき」と言うのに十分な光景だ。それにしてもコンクリートが綺麗な表面を保っている。



橋座はしっかりと一対の構造物として残っている。こちら側も桁と接続されていただろうボルトが残っている。あぁ、ここにガーダー橋を載せてみたい。なお、橋座の構造物の幅は20cm程度で、橋座間の距離は100cm程度だった。
こちら側もエッジが効いていて、ディテールは大きく損なわれていない。先ほどまで見てきた千手河原方のそれと同じ造形が残されている。








また、橋台の上部には切り欠きのような跡がある。これは明らかに後になってコンクリートで埋められた様子が見て取れる。丁度、軽便のレール幅程度の位置にあるものだから気になったものの、よく分からない。改めて、各種ガーダー橋を観察して類例を探していきたい。





軌道上の位置、真上から見下ろすとこのような感じだ。ここに軽便のガーター橋の桁が載ってた。


改めて盛土を眺めると、往時の様子が偲ばれる。現役時代に積まれただろう石積みの盛土が非常にそそられる。段丘崖の中腹から盛土の向こうに信濃川を眺める。これぞ信濃川電氣事務所の材料運搬線といった景色だ。これらの積まれた石たちも、目の前の信濃川の河原から持って来られたものかもしれない。ここに積まれて約90年、よくぞ持ち応えてくれた。



ここにいたのは何時間だろうか。気が付けば太陽が高く登り、頭の上にあった。去り際に、最後に一枚と。

興奮醒め止んで、ガーダー橋の構造について勉強して、また訪れたい。
またしても夜明け前から現地入りをして、観察を行う。この時、気まぐれに橋台の側に生えていた笹を引っこ抜いたら、根が張り巡らされているはずの地面があっさりと剥がれた。地面が剥がれたと言うのは、文字通り笹を引っ張ったら根と地面ごとベロッと剥がれたのである。その感触には覚えがあって、その下にコンクリートか岩盤か、何かしら土も無く根が張れないものが存在しているという感触である。


そこら辺に散乱している枝を一本手に取り、私はそれで地面が剥がれた跡の土を払って行く。下にはコンクリートが顔を覗かせている。



ボルトが飛び出ている。そして、一部欠損しているものの、コンクリートには何か形成された痕跡がある。明らかにここにガーター橋として主桁が載っていただろう形状だろう、このディテールは。
主桁と橋座はここに飛び出ているボルトで接続されていたはずだ。これほどの痕跡は初めて見た。にしても、数十年は湿った地面の下に埋もれていたにもかかわらず、むしろ埋もれていたからか、エッジが効いたディテールが綺麗だ。

前回、ガーター橋が載っていたと言った部分も必要な構造物だと思われるが、こちらにはそれらしき造形は一切無い。ただ、中心に線路方向の溝が掘られているのみである。これを書いている時点で、私は溝の用途については分からない。類似例を調べている。また、こちらの構造物は川石が表面に浮いているのが特徴だ。橋台と比べると明らかにセメントと川石の配合率が違うように見える。用途によって変えていたのかも知れないが、それを示す資料については見付けられていない。もっとも、私は素人なのでコンクリートに詳しくない。単に風雨による劣化具合の差なだけかもしれない。



ガーター橋であるなら橋座も対になっているはずだから、山側も同じような形状をしていると推測される。しかし、いくら笹を引っこ抜けば地面ごと剥がれるとは言っても、これだけの土を除けるのに躊躇した。いや、同じような構造が土の下にあるとは思う。しかし、正直なところ、発掘するのが面倒くさくなった。我こそはと言う方、是非、発掘して欲しい。私はその後でまじまじと観察させていただければ良い。
とは言え、対岸(高城澤方)にも橋台跡はあるしということで、ある程度観察して、さっさと対岸へと移動した。
以下の写真の中ほどにある沢の右手が先ほどまで私がいた斜面だ。これから、沢の左手になる正面の段丘崖を登る。つい先日登ったばかりの斜面なので、何処をどう登って橋台跡へアプローチすれば良いかを知っているだけ、今回は気楽なもんだ。


途中、中腹で橋台下のコンクリートを改めて観察する。全容は全く掴めない。ただ、ガーダー橋なら、特にこの位置に橋脚なりを設ける必要も無かったろうし、単なる土留めなのかもしれない。位置的にもコンクリートの劣化具合的にも軽便線関係の構造物だとは思うのだけども。



なお、このコンクリートの塊は以下の写真のような場所にある。右手が発電所方で、沢へと落ち込んでいる谷の縁である。谷底の沢まで3m以上はあるため、落ちたら痛そうだ。足で上に載った土を少しばかり落としたものの、殆どの部分を木の根が覆っており、何も見付けることは出来なかった。

そして、少し登って橋台跡に辿り着く。こちらの橋台も同様の構造だと想像し、橋台そばの植物を引き抜こうとすると、またしても地面ごとベリッと剥がれた。
そこから何だかんだで1時間くらい発掘作業を行い、以下の写真のような状態まで露わになった。



木々の成長具合に時代を感じる。正面に立つ。本当によくぞ残っててくれたと感動した。「ここに鉄道ありき」と言うのに十分な光景だ。それにしてもコンクリートが綺麗な表面を保っている。



橋座はしっかりと一対の構造物として残っている。こちら側も桁と接続されていただろうボルトが残っている。あぁ、ここにガーダー橋を載せてみたい。なお、橋座の構造物の幅は20cm程度で、橋座間の距離は100cm程度だった。
こちら側もエッジが効いていて、ディテールは大きく損なわれていない。先ほどまで見てきた千手河原方のそれと同じ造形が残されている。








また、橋台の上部には切り欠きのような跡がある。これは明らかに後になってコンクリートで埋められた様子が見て取れる。丁度、軽便のレール幅程度の位置にあるものだから気になったものの、よく分からない。改めて、各種ガーダー橋を観察して類例を探していきたい。





軌道上の位置、真上から見下ろすとこのような感じだ。ここに軽便のガーター橋の桁が載ってた。


改めて盛土を眺めると、往時の様子が偲ばれる。現役時代に積まれただろう石積みの盛土が非常にそそられる。段丘崖の中腹から盛土の向こうに信濃川を眺める。これぞ信濃川電氣事務所の材料運搬線といった景色だ。これらの積まれた石たちも、目の前の信濃川の河原から持って来られたものかもしれない。ここに積まれて約90年、よくぞ持ち応えてくれた。



ここにいたのは何時間だろうか。気が付けば太陽が高く登り、頭の上にあった。去り際に、最後に一枚と。

興奮醒め止んで、ガーダー橋の構造について勉強して、また訪れたい。













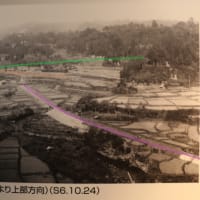

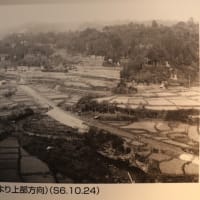




今年は雪が少ないせいもあって雑木が結構生い茂っていて難儀しました…
貴殿のようなキレイな写真は無理でしたが、橋台跡はしっかりと残っており感動しています。
余談ですが、信濃川第一発電所の姿横坑・真人横坑立坑(現役施設あり)と他にも色々と収穫がありました。
材料運搬線の橋台跡が残っている感動を共感していただけたのは私も嬉しいです。
姿や真人における現地調査の結果もご教示いただければ幸いです。