そう思っていたら、あに図らんやで、外国でも事情は変わらず言葉遊びがいろいろあるようで、これは世界共通のものらしい。
新約聖書には「はじめに言葉ありき 言葉は神と共にありき 言葉は神なりき」(ヨハネ福音書一章一節)というのがある。
西洋の「言葉遊び」として
まずはパングラムpangramという技法。
パングラムとは、アルファベット二六文字を重複させずに使って文章を作る言葉遊びで、その中でもすべての文字を使いきる「完全パングラム」を作るのは至難の業だという。
「完全パングラム」で「いろは歌」のように特別の深い意味を持たせるまで作り上げることは不可能のようである。
パングラムでよく知られているのは次の文章。
The quick brown fox jumped over the lazy dogs.
この文意はたわいないものだが、うまく出来ている。これですべてのキーが叩けるので、昔のタイプライターの試し打ちに使われたそうだ。
アナグラム anagrms というのもある。
これは単語の文字をバラバラにして組み替え別の単語に作り替える言葉遊びである。例えば
Statue of Liberty → built to stay free
数年前に世界的なベストセラーになったダン・ブラウンの小説「ダ・ビンチ コード」ではアナグラムで暗号文の謎解きする筋書になっている。
更に、アナグラムからパリンドローム palindromes に連想が飛ぶ。
日本語ではこれを「回文」という。
前から読んでも「山本山」、後ろから読んでも「山本山」という海苔店のテレビのコマーシャルがあったが、あの類いだ。
英語のパリンドロームとして最も有名なのは、エデンの園で男女初対面の会話
Madam, I’m Adam
というのがあり、エルバ島に流されたナポレオンの嘆きというのもなかなかの出来だ。
Able was I ere I saw Elba
(エルバ島を見るまでは私には力があった。)
中国には古代から「回文詩」という詩形式があるが、これは初めから順に読んでも、逆から読んでも詩になるというもので、パリンドロームや日本の「回文」とはちょっと違う。
「回文詩」は数多く作られているが、代表するものとしては五世紀南斉の王融の作「春遊廻文詩」を掲げておこう。
しかし、これは中国語ができないとちょっと理解できない。
枝分柳塞北 葉暗榆關東 垂條逐絮轉 落蕊散花叢
池蓮照曉月 幔錦拂朝風 低吹雜綸羽 薄粉豔粧紅
離情隔遠道 歎結深閨中
日本の回文と同じ形式では梁の簡文帝が作ったというのがある。
塩飛乱蝶舞、花落飄粉匳、匳粉飄落花、舞蝶乱飛塩
「詠雪」と題して降る雪を詠った漢詩だが、なんとなく分かりはするが、これもさっぱり。
日本語の回文は作り易いようで、今でも趣味として盛んに作られているようだ。





















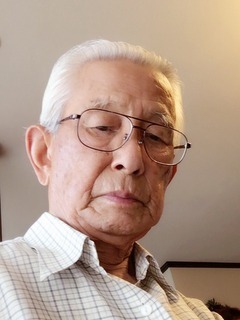





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます