こんなふうに「いろは歌」にすっかり嵌まり込んでしまったら、今度は「いろは歌」と同じように四七文字(「ん」を加えれば四八文字)を読み込んだ歌がほかにもあるかどうか知りたくなった。
調べてみたらいろいろとある。
江戸時代における国学の大家本居宣長が作った「雨降り歌」は「いろは歌」には到底及ばぬものの、なかなかの出来である。
「雨降れば 井堰(いせき)を越ゆる 水(みつ)分けて 安く諸(もろ)人 降(お)り立ち植えし 群(むら)苗(なえ)
その稲よ 真(ま)穂(ほ)に栄(さかえ)ぬ」
あめふれは いせきをこゆる みつわけて やすくもろひと おりたちうゑし むらなへ そのいねよ まほにさかえぬ
同じ国学者の堀田恒山が作ったのもある。
「春ごろ植ゑし 相生(あいおゐ)の 根松行く方(へ) にほふなり 齢(よわひ)を末や 重(かさ)ぬらむ 君も千歳(ちとせ)ぞ
めでたけれ」
はるころうゑし あいおゐの ねまつゆくえ にほふなり よわひをすへや かさぬらむ きみもちとせそ めてたけれ
近代に入って作られたものとして著名なのが「鳥啼き歌」である。
明治三八年に「いろは歌」に代わる新しい同音の歌が募集され、これに応じた坂本百次郎という教師が作ったもので、なかなかよく出来ている。しかも、この歌は「ん」を入れて四八文字すべてが使われている。
「鳥啼く声す 夢さませ 見よ明け渡る東(ひんがし)を 空色映えて 沖(おきつ)へに 帆舟群れゐぬ 靄のうち」
とりなくこえす ゆめさませ みよあけわたる ひんかしを そらいろはえて おきつへに ほふねむれゐぬ もやのうち
推測するに、明治政府が暗い響きをもった「いろは歌」が近代日本にふさわしくないと考え、これに代わる新しい歌を求めたのではあるまいか。
しかし、この歌は結局のところ「いろは歌」に代わって国中にひろまることはなかった。
戦後になって作られたものとしては、こんなものもあるようだ。これも四八文字である。
「乙女花摘む 野辺見えて 我待ち居たる 夕風よ 鴬来けん 大空に 音色も優し 声ありぬ」
をとめはなつむ のへみえて われまちゐたる ゆふかせよ うくひすきけん おほそらに ねいろもやさし こゑありぬ
このようにあれこれ見てくると、日本語は言葉を自在に操ることができ、歌の巧者も多いように思う。
まさしく「敷島の 大和の国は 言霊(ことだま)のたすくる国ぞ まさきくありこそ(万葉集・柿本人麻呂)」である。





















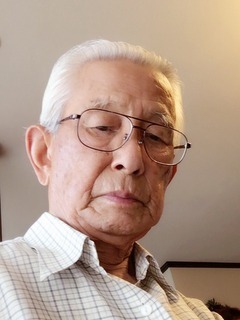





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます