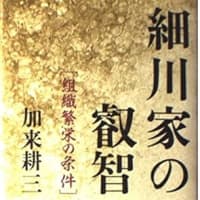本書では大国主命(大名持命、大物主命)に着目して、出雲系の神々を求めて各地に出かけて、各地に伝わる神話と記紀の記述とを読み解くことから、神話に秘められ歴史的事実に思いをはせた結果、古代史に秘められた歴史の仮説を検証してみたという一冊である。その仮説とは出雲系の勢力こそが大和地方に邪馬台国を形成した一族であり、それを九州から東征してきた勢力が制圧した、それが大和政権だったというもの。出雲ゆかりの土地を歩きながら、記紀、出雲国風土記、魏志倭人伝などを読み解いて古代史における出雲系勢力の存在と役割にせまる古代史仮説である。
仮説の根拠の一つが山そのものが御神体とされる三輪山の存在である。その祭神は大物主神であり出雲系。8世紀の初めに出雲国造が朝廷に出かけて奏上した神賀詞(かみよごと)の中で貢置を申し出た「皇孫の命の近き守り神」が三輪山の大神神社、葛城の高鴨神社などいずれも出雲系。それは出雲系の神々が守り神としてヤマト政権以前から大和盆地に存在してきたから。そして魏志倭人伝で知られる卑弥呼の名は、記紀に全く出てこないことから、記紀編纂者は強くそのことを意識していたはずだと指摘。

記紀編集者たちが魏志倭人伝の内容を熟知していたことは、女王国の存在と記紀の内容に矛盾を来さないように工夫しているから。日本書紀には倭の女王、倭王、倭国の主として三度登場する。それは神功皇后紀39年「魏志によれば明帝景初3年倭の女王、大夫難升米などを遣わし、、」、40年「魏志によれば建忠校尉らを遣わし詔書を奉りて倭国に詣らしめず」、43年「正始4年、倭王生口を含む献上品を上献ず」。日本書紀編集者が年号を修正したり皇帝名を手直しするなど、魏志倭人伝と書紀内容を精査していたことが伺われる。書紀では編集作業を通して魏志倭人伝での記述の内容を知り、その知識を持って神功皇后紀のなかに先のとおり記事を引用しているのである。 書紀では神功皇后を卑弥呼になぞらえているのは不思議ではない。卑弥呼の名を出さないのは記紀記述の魏志倭人伝との矛盾が露呈してしまうため。神功皇后は斉明天皇の白村江の戦への同行を神功皇后の逸話と映し、倭の女王が「親魏倭王」称号を得たことと重ねたと考えられる。このこと自体が卑弥呼は大和政権とは無縁の存在であったことの証左である。
魏志倭人伝よれば邪馬台国には卑弥呼の下に他の国とは違い四つの「官」が存在する。伊支馬(いしま→生駒)、弥馬升(みます)、弥馬獲支(みまき)、奴佳「革編に是」(なかと)と考えられ、概念図としてあらわすと以下の通り。

邪馬台国は領域を4つに分けられ、「イコマ(生駒)」「ミマス(葛城)」「ミマキ(三輪)」に取り囲まれて周囲を固め、「ナカト」が中央部を担う。これが奈良盆地の中央部に位置していたと考えられる。邪馬台国当時、北には物部氏、西南は鴨氏、東に大神氏が盤踞、いずれも出雲系で、邪馬台国は出雲系氏族連合で擁立されていた、という仮説である。「近き守り神」は三輪の大神神社、葛城の高鴨神社、飛鳥のカヤナルミ神社、宇那手の川俣神社と同定できる。神武東征神話は、神武勢力に抵抗する登美のナガスネヒコが神武勢力に抵抗し、一度は打ち破るが、熊野に再上陸した神武勢力が八咫烏の登場があり勝利する。この戦いの中で、抵抗勢力として立ちはだかったのが、三輪、鴨、栢森の出雲系の軍勢で卑弥呼なき後の邪馬台国を守っていた。神武勢力は戦いには勝利したものの、出雲勢にはその後も配慮、神話には国譲りを登場させ、出雲国造には郡司と兼務を全国で唯一認めることで、出雲勢に大いに配慮した。
具体的な年表と突合すると、神武東征は西暦248年の卑弥呼没直後であり、ナガスネヒコ反撃、饒速日命はその後神武に帰順し、神武(崇神)が橿原宮に即位、その後四道将軍を派遣、出雲、備中、越後、尾張を配下に治める。雄略朝にはようやく西は中国地方から近畿、越前、越後、尾張、信濃、毛の国あたりまでを統一できたとする。
筆者は上記仮説検証のため、出雲、伯耆、備前、備中などに点在する神社などを訪れ、大国主命や出雲神話など上記仮説の痕跡を訪ね歩いた。歴史学者として定説や常識を外れ神話の検証を行うことは常道ではないかもしれないが、大国主命に関連する出雲世界の世界を垣間見ることができたという。本仮説を捨て石として今後の議論を期待する。本書内容は以上。
筆者は上記仮説検証のため、出雲、伯耆、備前、備中などに点在する神社などを訪れ、大国主命や出雲神話など上記仮説の痕跡を訪ね歩いた。歴史学者として定説や常識を外れ神話の検証を行うことは常道ではないかもしれないが、大国主命に関連する出雲世界の世界を垣間見ることができたという。本仮説を捨て石として今後の議論を期待する。本書内容は以上。