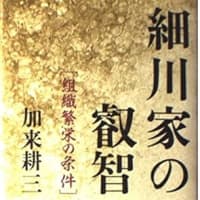まずは有名なガダルカナル島、別名餓島である。1942年8月から43年1月の戦いから撤退を指揮したのは今村均大将、回顧録によると「大本営直轄部隊3万の将兵中敵兵火に倒れたのは5千、餓死したもの1万5千、1万が救出された。制空権も補給もできない島に陸軍を送り込んだ軍部中央部の過誤である。」この時の参謀本部作戦課長は服部卓四郎、全く兵隊たちの命に重きを置かない作戦であったという。まずは先遣隊に千名の一木支隊をあて7日分の糧食をもたせ、白兵戦で突撃を命じた。戦車や重火器を持つ米軍に全滅させられた後も、川口支隊に続けて第17軍を今村均大将のもとに送り込んだのである。南太平洋の日本軍戦略基地ラバウルから離れること1100Km、制空権、制海権がない中での攻撃であり、重火器や食料を持てない鼠輸送という駆逐艦による輸送で兵隊を送り込んだのである。降伏を許されず死ぬまで戦うことを義務付けられた日本の兵隊たちは食料がなくなって敵に追われて森林をさまよい次々と餓死していった。次のように言われたという。
立つことができる人間は寿命30日。
身体を起こして座れる人間は寿命3週間。
寝たきり起きられない人間は1週間。
寝たまま小便をするのは3日間。
ものを言わなくなった人間は2日間。
またたきをしなくなれば明日死ぬ。
ガダルカナル以降も餓島の教訓を活かせず、補給困難な島々に兵力を送り込んで飢餓の悲劇を繰り返した。
ポートモレスビー攻略戦では大本営参謀の辻政信が作戦を指揮した。4000mを超える山を徒歩で越えて図上距離220Kmの島の反対側にあるポートモレスビーを攻略するという作戦である。実際の徒歩距離は360Kmあったのだが、兵員一人が運べる食糧は25Kg、1日平均担送距離は20Kmとすると、一日の必要食料600gを補給すためには32000人の補給要因が必要となる、実現不可能な作戦であった。しかし辻は大本営には問い合わせることもなくこの作戦遂行を命令、その後これが辻の独断であったことを知った大本営の服部卓四郎までが辻の独断専行を追認した。この作戦にはじめから参加していた南海支隊の人員は5586名、補充人員1797名、消耗人員5432名、残人員1951名であった。戦死者は3割、餓死者が7割というのが死者の内訳であった。辻は作戦指示をした後に日本に戻っている。
インパール作戦を構想し指揮したのは牟田口廉也司令官、危険で無茶な作戦だとする意見が多い中で、南方軍総司令官寺内寿一はこれを認可した。そして杉山参謀長までもが同調したために作戦は実行されることになった。盧溝橋事件を指揮したのもこの牟田口廉也、強硬論、積極論が常に慎重論に勝ったのが日本軍の論理であった。携行食料2週間分をもって進軍を開始した日本軍に補給はなく、すぐに立ち往生したが、補給を求める司令官を次々に消極的だとして罷免、「米一粒も補給がない」として独断退却をした佐藤幸徳中将は軍法会議にかけられた。インパール作戦だけでの死者は不明、ビルマ戦線での総兵力は30万3501名、戦没者は18万5149名、帰還者は11万8352名であった。参加した中隊の病死者率が78%程度だったことから推測すると、ビルマ戦線での病死者は14500名程度であったことになる。
太平洋の離島には置き去りにされた兵隊たちも沢山いた。マリアナ諸島を島伝いにサイパン、グアム、テニアンと上陸を果たした米軍は無駄に戦死者を出さないために、後方にいる日本軍を放置した。放置された島の多くは珊瑚礁の島、農耕には適さず食料生産ができない上に補給もないという状況になった。ウォッゼ、ミレ、ヤルート、ナウル、メレヨン、大鳥島、南鳥島などに12万名以上の兵隊が残され食料補給が絶たれたのである。最も悲惨だったメレヨン島では戦死者307名、病死者4493名、生還者1626名であった。将校の生還率は67%、下士官は36%、兵隊の生還率は18%であった。しかしこうした状況でも降伏は出来ず、食料統制のために食料盗難には制裁も行われたという。
戦場別で最も多くの戦没者を出したのがフィリピン、50万人の戦没者のうち40万人が餓死者だったと推測できるという。中国本土では戦没者数が45万、このうち22万7800名が栄養失調による病死者だった。その他の地域では沖縄89400名、小笠原諸島15700名は玉砕したのでほとんど戦死、ソ連、満州などでは死因の2割が餓死と見て21000人が餓死・病死とみる。これらを合計して、集計すると栄養不足、餓死、病死者は127万人、全体の戦没者212万の約6割が餓死・病死であると考えられるという。
馬も犠牲になった。帰還した馬は一匹もいないという。中国とその南方大陸で50万頭、日中戦争以来を合計すると100万頭が犠牲になったと推測できるという。
南部仏印進駐時点で大本営参謀本部で責任が重いのは田中新一第一部長と武藤章軍務局長、服部卓四郎作戦課長、真田穣一郎軍事課長、その後作戦課にはいるのが辻政信であった。特に服部、辻のコンビは兵員への食料補給を考慮せず、飢餓を承知で作戦を遂行した。玉砕の放置は参謀本部の人間の命の軽視の表れであると指摘する。また火力軽視で白兵主義は旅順やノモンハンでの反省を活かせず、精神主義をかざしたままで米軍への突撃を命じたのはこうした陸軍のエリートである参謀たちであった。
こうした精神主義は陸軍幼年学校、士官学校、陸軍大学校でのエリート教育で培われた。そこでは輜重兵や砲兵、軍医兵などが差別される現実もあり、歩兵が第一とされる教育であった。筆者は幼年学校の問題点を次のように整理している。
1. 12歳で入学する幼年学校での軍人教育は偏狭な軍国主義者を育てた。
2. 全寮生活でエリート意識を植えつけられその他中学卒業生を排他した。
3. 軍隊に不向きな生徒もエリートとして育成された。
4. 外国語が仏露独の3ヶ国語であり、英語が排除され、米英国力を見誤る原因となった。
降伏の禁止と玉砕の強要は日本の捕虜政策が日露戦争後転換したことと関連する。日露戦争後の捕虜は国際法に基づいて厚遇されたことは有名であるが、第一次世界大戦での捕虜扱いに関し、軍内部から厚遇すぎるという批判が起きた。明治には世界の一流国と評価されたいという期待から文明国並みの扱いを捕虜に対しても行うことが行われたが、第一次大戦で、日本はすでに一流国となり、文明国から学ぶべきことはもうない、と慢心することになったことが原因である、と筆者は分析する。捕虜の扱いを決めた1929年のジュネーブ条約に批准しなかったのがその現れであったという。中国人への差別的心理が中国人捕虜への取り扱いでも現れ、1933年に陸軍歩兵学校が頒布した「対支那軍戦闘法の研究」では、中国人捕虜は戸籍を持たないので死んでもよくわからないのであるから殺害や他の地方に連れていっても問題はない」と記述していたという。南京大虐殺はこうした中国人蔑視が根底にあった、という指摘である。
第二次大戦の日本軍にあった問題を抉り出したような著作である。軍人勅諭、戦陣訓、降伏の禁止、捕虜の扱いなどについても調べてみようと思う。