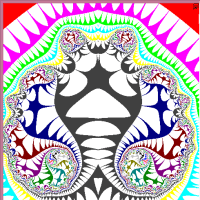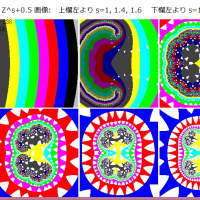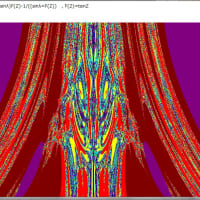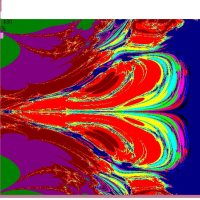芥川龍之介の『藪の中』を再読したのだが、掲題の映画が私に刷り込まれていて、芥川の短編を読みながらも、映画の映像を頭の中で再現せざるを得なかった。
確か此の短編小説は私は小学生の頃読んでいて、映画は其の後、だいぶ経ってから観ているのだが、今や私には此の短編を読むことは掲題の映画の映像を反芻することになってしまった。
しかし、勿論、芥川のあの文体があってこその映像ではあるのだが、要するに、掲題の映画と芥川の文体・・・というより美意識・・・は私には表裏一体となっている。
タルコフスキーを「水と火」の映像作家とするならば、黒澤明は「雨と風」の映像作家であることは誰も異論はないだろう。
実際、掲題の映画の冒頭の羅生門での豪雨の場面の強烈さは、短編『羅生門』には見いだせない迫力がある。
しかし、此の映画と、芥川の短編『藪の中』『羅生門』に共通しているものは、其の美学・美意識にあるのであって、これらの作品から人生云々を見つけるのは全く見当外れに私には思える。 例え作者達が其れを幾分なりとも意図していたとしてもだ。
芥川龍之介という作家の魅力は私には其の特異な美学・美意識にあるのであって、人生云々にあるのでは全くない。
同様に掲題の映画の最大の魅力は、其の映像の美学・美意識 (撮影:宮川一夫) 即ち光と翳の映像の鋭敏さにあるのであって、これまた人生云々にあるのでは全くない。
***
掲題の映画の映像での圧巻は、巫女(本間文子)が死霊を呼び出し、巫女が死霊の声で事の次第を喋る場面であった。
この場面は、短編での芥川のあの妖しい噺「巫女の口を借りたる死霊の物語」の映像的再現であった。
***
ネットでの掲載によると、
『当初、黒澤は真砂役に原節子を起用しようと考えていたが、京がこの役を熱望して眉毛を剃ってオーディションに臨んだため、京の熱意を黒澤が買い、京に決まった。』とある。
もし原節子だったら、おそらく全く違った印象の映画になっていただろう。
京マチ子のほうが適役であったのは、この映画のその後の評価が断定している。
原よりも京のほうが、はるかに妖しいのだから、この評価は妥当だと言える。
確か此の短編小説は私は小学生の頃読んでいて、映画は其の後、だいぶ経ってから観ているのだが、今や私には此の短編を読むことは掲題の映画の映像を反芻することになってしまった。
しかし、勿論、芥川のあの文体があってこその映像ではあるのだが、要するに、掲題の映画と芥川の文体・・・というより美意識・・・は私には表裏一体となっている。
タルコフスキーを「水と火」の映像作家とするならば、黒澤明は「雨と風」の映像作家であることは誰も異論はないだろう。
実際、掲題の映画の冒頭の羅生門での豪雨の場面の強烈さは、短編『羅生門』には見いだせない迫力がある。
しかし、此の映画と、芥川の短編『藪の中』『羅生門』に共通しているものは、其の美学・美意識にあるのであって、これらの作品から人生云々を見つけるのは全く見当外れに私には思える。 例え作者達が其れを幾分なりとも意図していたとしてもだ。
芥川龍之介という作家の魅力は私には其の特異な美学・美意識にあるのであって、人生云々にあるのでは全くない。
同様に掲題の映画の最大の魅力は、其の映像の美学・美意識 (撮影:宮川一夫) 即ち光と翳の映像の鋭敏さにあるのであって、これまた人生云々にあるのでは全くない。
***
掲題の映画の映像での圧巻は、巫女(本間文子)が死霊を呼び出し、巫女が死霊の声で事の次第を喋る場面であった。
この場面は、短編での芥川のあの妖しい噺「巫女の口を借りたる死霊の物語」の映像的再現であった。
***
ネットでの掲載によると、
『当初、黒澤は真砂役に原節子を起用しようと考えていたが、京がこの役を熱望して眉毛を剃ってオーディションに臨んだため、京の熱意を黒澤が買い、京に決まった。』とある。
もし原節子だったら、おそらく全く違った印象の映画になっていただろう。
京マチ子のほうが適役であったのは、この映画のその後の評価が断定している。
原よりも京のほうが、はるかに妖しいのだから、この評価は妥当だと言える。