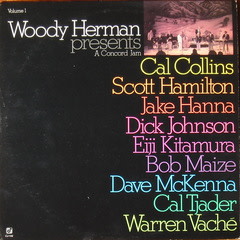Profiles / Gary McFarland
1966年といえば日本ではビートルズが初来日した年。その年の2月6日、日曜日の夜、翌7日月曜日にサドメルオーケストラの初ライブを控えた、ボブブルックマイヤーやジェロームリチャードソン、ジェリーダジオン、そしてスヌーキーヤング、ダニームーア、さらにはベースのリチャードデイビスなどなど・・各セクションの主要メンバー達が、続々とマンハッタンのブロードウェイに面したリンカーンセンターのフィルハーモニックホールに集結していた。ここは言わずと知れたニューヨークフィルの本拠地、クラッシク音楽のホームグラウンド。エヴリフィッシャーになってからも音響の悪さで昔からすったもんだしていた所だが、ジャズクラブに較べると桁違いの観客が入れる大ホールだ。
ところが、この日のイベントはクラッシクではなく、アレンジャー、ゲーリーマクファーランドのコンサートだった。当時新人アレンジャー達の中で、オリバーネルソンやラロシフリンなどと並んでクローズアップされていた新進気鋭のマクファーランドの作品のお披露目コンサートだった。よくある過去のアルバムで演奏された曲のライブでのお披露目でもなく、定期的に開かれているジャズコンサートにマクファーランドが出演したわけでもない。その日は一夜限りの彼の新作の発表の場であった。その日のために、ニューヨークのトップレベルのミュージシャンに声が掛かった。というわけで、サドメルオーケストラのメンバーの多くにも声がかかった次第だ。特に、木管系の楽器を多用するので各種の持ち替えが効くミュージシャンとなると、人選にも苦労したと思われる。ジェロームリチャードソンなどは、このコンサートのために9種類の楽器を持ち込んだとか。これだけ肝いりで開かれたコンサートなので、リハーサルにも4日もかけたそうで、忙しいメンバー達を拘束するのはさぞかし大変だったであろう。
8時に、VOAのジャズアワーのアナウンサー、Willis Conoverの司会で幕を開ける。
彼のMCの中でも「プランされたものと自然発生的なものに乞うご期待」との一言が入る。
確かに、全編彼らしいアンサンブルが聴き所だがその間のソロもとって付けた様なソロではない。反対にソロを生かす事を思い描いたオーケストレーションとも言える。
彼の作品には自然の風物を題名にした曲が多い。最初の曲も”Winter Colors”と命名された組曲風の曲だ。作編曲もこの題名を十分に意識して書かれたものだろ。他のアレンジャーとは曲作りの取り組み方も違うのかもしれない。次の“Willie”は前の年の夏交通事故で亡くなってまもない友人のトロンボニストのウィリーデニスに捧げた曲。次の“Sage Hands”はサックスセクションのプレーヤーをクローズアップした曲。ピターガンのイントロに似た感じで始まる”Bygones & Boogie“は彼が子供の頃聞いてお気に入りであったブギウギをイメージしたとか。最後の”Milo's other Samba”はボサノバジャズの世界ではひとつの世界を作ったマクファーランドの世界をアピールしている。とにかく多彩な曲想、そして色々な木管を組み合わせた響き、それに合わせた一流どころのソロと、あっという間に終わってしまうが残りの録音が無いのか気になるところだ。
‘ボサノバブームに乗って一躍有名になったが、彼の原点は幅広く色々な音楽を取り入れ、色々な表現をするということに尽きる。初期のアルバムにはアニタオデイのバックもあったが、その後どちらというと軽いノリのアルバム作りに参加することが多かった。このアルバムのように真正面から取り組んだ作品は聴き応えがある。
このコンサートを企画したのはNorman Schwartz。後に、Sky, Gryphonでマクファーランドとはタッグを組む。また、コルトレーンの全盛期にこのようなライブをアルバムにしてラインナップに加えたBob Thieleの度量には感嘆する。
独自の世界を展開させ将来を嘱望されたマクファーランドだが、このアルバムを録音してから5年後、1971年にニューヨークのバーで毒を飲んで(飲まされて?)亡くなってしまう。詳しい状況は発表されていないようだが、これからという時に何とも残念。もし生きていればというのは、早く逝ってしまったジャズの巨人の残された作品を聴くといつも思うことである。
Gary McFarland Conductor, Marimba, Vibraphone
Bill Berry Brass
Clark Terry Brass
Bob Brookmeyer Brass
Joe Newman Brass
Bob Northern Brass
Jimmy Cleveland Brass
Jay McAllister Brass
Phil Woods Reeds
John Frosk Brass
Bernie Glow Brass
Richie Kamuca Reeds
Jerome Richardson Reeds
Zoot Sims Reeds
Richard Davis Bass
Gabor Szabo Gutar
Sammy K. Brown Gutar
Joe Cocuzzo Percussion
Tommy Lopez Percussion
All Songs Composed By Gary Mcfarland
Willis Conover Narrator
Produced by Bob Thiele
Engineer : Rudu Van Gelder
Recorded live at Lincolin Center's Philharmonic Hall on Feb.6, 1966
1966年といえば日本ではビートルズが初来日した年。その年の2月6日、日曜日の夜、翌7日月曜日にサドメルオーケストラの初ライブを控えた、ボブブルックマイヤーやジェロームリチャードソン、ジェリーダジオン、そしてスヌーキーヤング、ダニームーア、さらにはベースのリチャードデイビスなどなど・・各セクションの主要メンバー達が、続々とマンハッタンのブロードウェイに面したリンカーンセンターのフィルハーモニックホールに集結していた。ここは言わずと知れたニューヨークフィルの本拠地、クラッシク音楽のホームグラウンド。エヴリフィッシャーになってからも音響の悪さで昔からすったもんだしていた所だが、ジャズクラブに較べると桁違いの観客が入れる大ホールだ。
ところが、この日のイベントはクラッシクではなく、アレンジャー、ゲーリーマクファーランドのコンサートだった。当時新人アレンジャー達の中で、オリバーネルソンやラロシフリンなどと並んでクローズアップされていた新進気鋭のマクファーランドの作品のお披露目コンサートだった。よくある過去のアルバムで演奏された曲のライブでのお披露目でもなく、定期的に開かれているジャズコンサートにマクファーランドが出演したわけでもない。その日は一夜限りの彼の新作の発表の場であった。その日のために、ニューヨークのトップレベルのミュージシャンに声が掛かった。というわけで、サドメルオーケストラのメンバーの多くにも声がかかった次第だ。特に、木管系の楽器を多用するので各種の持ち替えが効くミュージシャンとなると、人選にも苦労したと思われる。ジェロームリチャードソンなどは、このコンサートのために9種類の楽器を持ち込んだとか。これだけ肝いりで開かれたコンサートなので、リハーサルにも4日もかけたそうで、忙しいメンバー達を拘束するのはさぞかし大変だったであろう。
8時に、VOAのジャズアワーのアナウンサー、Willis Conoverの司会で幕を開ける。
彼のMCの中でも「プランされたものと自然発生的なものに乞うご期待」との一言が入る。
確かに、全編彼らしいアンサンブルが聴き所だがその間のソロもとって付けた様なソロではない。反対にソロを生かす事を思い描いたオーケストレーションとも言える。
彼の作品には自然の風物を題名にした曲が多い。最初の曲も”Winter Colors”と命名された組曲風の曲だ。作編曲もこの題名を十分に意識して書かれたものだろ。他のアレンジャーとは曲作りの取り組み方も違うのかもしれない。次の“Willie”は前の年の夏交通事故で亡くなってまもない友人のトロンボニストのウィリーデニスに捧げた曲。次の“Sage Hands”はサックスセクションのプレーヤーをクローズアップした曲。ピターガンのイントロに似た感じで始まる”Bygones & Boogie“は彼が子供の頃聞いてお気に入りであったブギウギをイメージしたとか。最後の”Milo's other Samba”はボサノバジャズの世界ではひとつの世界を作ったマクファーランドの世界をアピールしている。とにかく多彩な曲想、そして色々な木管を組み合わせた響き、それに合わせた一流どころのソロと、あっという間に終わってしまうが残りの録音が無いのか気になるところだ。
‘ボサノバブームに乗って一躍有名になったが、彼の原点は幅広く色々な音楽を取り入れ、色々な表現をするということに尽きる。初期のアルバムにはアニタオデイのバックもあったが、その後どちらというと軽いノリのアルバム作りに参加することが多かった。このアルバムのように真正面から取り組んだ作品は聴き応えがある。
このコンサートを企画したのはNorman Schwartz。後に、Sky, Gryphonでマクファーランドとはタッグを組む。また、コルトレーンの全盛期にこのようなライブをアルバムにしてラインナップに加えたBob Thieleの度量には感嘆する。
独自の世界を展開させ将来を嘱望されたマクファーランドだが、このアルバムを録音してから5年後、1971年にニューヨークのバーで毒を飲んで(飲まされて?)亡くなってしまう。詳しい状況は発表されていないようだが、これからという時に何とも残念。もし生きていればというのは、早く逝ってしまったジャズの巨人の残された作品を聴くといつも思うことである。
Gary McFarland Conductor, Marimba, Vibraphone
Bill Berry Brass
Clark Terry Brass
Bob Brookmeyer Brass
Joe Newman Brass
Bob Northern Brass
Jimmy Cleveland Brass
Jay McAllister Brass
Phil Woods Reeds
John Frosk Brass
Bernie Glow Brass
Richie Kamuca Reeds
Jerome Richardson Reeds
Zoot Sims Reeds
Richard Davis Bass
Gabor Szabo Gutar
Sammy K. Brown Gutar
Joe Cocuzzo Percussion
Tommy Lopez Percussion
All Songs Composed By Gary Mcfarland
Willis Conover Narrator
Produced by Bob Thiele
Engineer : Rudu Van Gelder
Recorded live at Lincolin Center's Philharmonic Hall on Feb.6, 1966