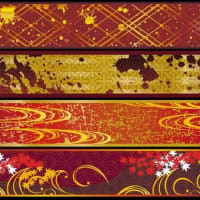世之主が奥方と長男の3人で自害した時に、徳之島に乳母と一緒に逃げていた長女と二男が騒動が収まったあとに帰島し、居を構えたところが直城(なおしぐすく)と呼ばれる地です。かつてはそこは小高い丘になっていて、城を新たに直したという意味でそう呼ばれているのだそうです。
この地は城があった丘より北側で、城があった丘よりは少し低く、下の二段目の平場と同じくらいの高さがあったそうです。
今となっては、その丘も客土の採取のために取り崩されてしまい、あたりは平らな畑になってしまっており、当時の面影は全くないといいます。
昭和50年頃にちょうど造成中の直城のあった場所が黄色の枠内です。

現在の付近は綺麗に区画整理された畑です。

大正14年の地図で見ると、黄色い箇所が直城の丘だったようです。

この直城の丘が削り取られる前は、段々畑になっていたといいます。
昭和22年頃の航空写真で場所を確認してみました。緑色の箇所が直城に該当します。周りに確かに段々畑がありますね。
客土の採取中には陶磁器などの遺物が発掘されたようですが、その当時はこの場所が歴史的に重要な場所であるという認識があまりなされていなかったようです。いまこの地が昔のままの形で残されていれば、当家のご先祖様調査において何らかの発見ができたかもしれないと思うと、非常に残念な気がしております。それに昔の景観を見てみたかったです。

写真は立体的に見えればもう少し当時の様子を思い描くことができるのですが、そこは残念。しかし、丘があった場所がわかり、上部は平場になっていることが見えます。しかもその平場に建物らしきものが見えるような気がします。まさか世之主の二男が住んだ居住跡ではないでしょうが、後世の人が住んだ家があったのかもしれません。これは別途調査してみようと思います。
古地図から直城の場所が明確になり、実は更にもう1つ直城から分かったことがあります。直城は当家のご先祖様を紐解く上でも重要な場所です。それは次回に書きたいと思います。