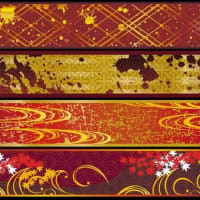野間氏の本には、島の人から聞き取ったという世之主の母方の情報が書かれていました。
口碑によれば、沖永良部島がまだ琉球の支配にあった頃、村ごとに琉球王のもとに貢物を届けていた。その時にはノロの他に生娘が伴われて行くのが慣例であり、ちょうどその時も同行していた。その娘は美しかったので、国王の目にとまり、王の子供を宿した。琉球から島に帰るときは臨月で船中でお産の傾向があったから、初め屋子母に船を着けて大津勘付近で分娩しようとしたが、ちょうどその時はシニグ祭りの時で、そんな汚れたことはお断りだと断られ、やむなく次の島尻に上陸しようとしたら、また同様に断られたので、自分の生まれ故郷の下城の下の沖泊に上陸し、下城の入間というところまで来た時、ここでも家々を追われ、路傍に付近から雨蓑を集めて産屋を作り分娩した。
産後は体調がすぐれず、かろうじて賃仕事に出たりして苦労して何とかその子供だけは育てたが、子供が成長するにつれて他人から父親がいないことで色々言われるので、ある夜に母親に問うてみた。初めは母親は口を堅く閉ざしていたが、我が子の不憫さに、ついに父親が琉球の王であることを話した。
その子は後日に王の前に出ることができたが、王は最初は我が子とは認めてくれなかった。その後しばらくして、自分の子供だとわかり、沖永良部島の統治を賜った。彼はすぐさま渡海の上、内城に城を作り本拠を構えた。
これが後の世之主その人であった。
一説にはそのノロはウキヌルといって沖野の姓での家である。その家の婆さんが世之主の御霊を見ていると聞いている。また、その生娘というのはノロの姪であったとかいうことである。ノロは神に仕える身であったため、夫を持つことはできなかったので、こうして姪を養女にするのが常であったという。
ここまでが野間氏が昭和12年当時に島で聞いた世之主出生に関する話です。
内容は分かりやすい言葉で書き換えております。
ノロの姪が王に気に入られて、、、という点は、世之主の出生についての口碑の中に必ずでてくるところです。
しかしそのノロや姪が現在の沖野家であること、ここが別で伝わる世之主の母方とされる要家とは違う点です。
わたしがこれまで世之主の出自について探していた中では、一番古い記録に残るものだと思います。沖野家には口碑伝承でずっと語り継がれていたのでしょうが、こうして研究者が記録として残している中では最古になるのかもしれません。
いっぽうの要家の方は、私が知る限りでは記録として登場するのは昭和43(1968)年発行の沖永良部島郷土史資料です。
大正時代から奄美群島の歴史研究が盛んになり、研究者がその調査記録などを書籍で残しておられますが、世之主やその出自についての記録は見当たりません。上記のように沖野家や要家の話が表舞台に登場するのは昭和の時代になってからのこと。
恐らくですが、それは沖野家が関係するノロを祭神とした花沖神社の建立が昭和3年。世之主誕生の際に産湯を沸かした「かまど石」をご神体として祀っている下城地区になる世之主神社が建立されたのが昭和2年。
これら神社が建立されたことによって、世之主の母親の話やその出生の話が昭和期以降に広く知られるようになったのだと思います。
不思議なことに、当家のお爺さまの記録には世之主の母方についての話が全く記録されていないのです。母方どころか出生の話さえありません。そして親族一覧に要家は記録されていますが、沖野家の記録はありません。
ここは何か重要なポイントのような気がします。
考えられる点を記述してみます。
・そもそも沖野家と要家は同族であった。お爺さまの記録に要家のみが書かれているところから見て、要家の方が本家であった。(ノロや世之主の話は両家のご先祖のこと)
・沖野家も要家もノロの家で、琉球王との間に子供が出来てその子が島の世之主になる点は同じであるが、実は両家は時代が違うノロや世之主の話である。
上記の2つはあくまで考察です。
沖野家のことはまだ詳しく分からないのですが、要家の方は琉球時代はノロ家であったことは間違いありません。そして我が宗家とも婚姻や養子縁組などで繋がっている家ですので、世之主とは深く繋がりがあったと思われます。
世之主の出生の話は一度整理してみることで、沖野家と要家にその話がある理由や時代などが少し見えてくるかもしれません。当家のご先祖である世之主の母のことですから貴重な情報です。
花沖神社や世之主神社については、別で紹介予定です。