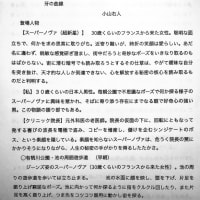追悼:スタン・アンダーソン氏
初夏の頃、軽井沢駅に現れたのは、紺のTシャツとジーンズ姿の大柄なアメリカ人だった。アメリカ人としては普通なのだろうが、私には大柄で寡黙な人と映った。
私は、なぜか彼の姿に、ソマセット・モームの「月と六ペンス」の主人公、ストリックランドの人物描写を重ね、思い描き始めていた。彼は、自身が翻訳したルーベンスや、その他の画集を、紙袋いっぱいに手土産として持っていた。
軽井沢駅前のホテルのレストランに入っても、寡黙な彼とは最初、打ち解けなかった。日本語で話し始めると、ようやく会話が弾み、それからだいぶ寛いだ。
ロビーに移り、さらに話しが進んだ。彼がアメリカのユタ州出身で、ソルトレイクのことなどを話してくれた。「アメリカと日本のどっちが好きか」と、私が気軽に訊いたのに、「どちらも好きだ」と、彼がとても気を遣って答えたのが印象に残っている。全般に、馴れ初めの会話だったのだと思う。
2回目に彼に会ったのは、群馬県の中之条町で開催されているトリエンナーレ美術展に企画出品しているので、見にこないかと誘いを受けたときだった。私の小説「孵化」の英訳が済み、まもなく出版されるという心ときめく時期にも当たっていた。
彼は、美術関係の翻訳者として既に有名で、画集や美術館のカタログについての業績をご存知の方も多いと思う。その実績、文体を見て、私の芸術、文学の協力者のフランス人、Marie Parra Aledo氏によって、私の小説の英訳の適任者として紹介されたのだった。彼は、まさしく素晴らしい翻訳を成し遂げてくれたところだった。お互いの満足感もあり、彼の誘いは非常に嬉しかった。彼はまた、山の自然や大地を素材にした自然の彫刻家としても知られていた。
彼は、私の宿泊するホテルへわざわざ車で迎えにきてくれた。初回とはまるで違う親しみと敬意に溢れていた。小説「孵化」を英訳し終え、表わしてくれた気持ちだっただけに、私は大いに喜びを感じた。彼自身でさえ見尽くしていない山の中のトリエンナーレ全体を、一日かけて案内してくれるという。破格の接待だった。
トリエンナーレの会場巡りの車中で、様々な芸術のことについて話し合った。 まず同じく中之条の山中にこもっている陶芸作家のことが話題にのぼった。真っ黒で不思議な宇宙を包み込んだような陶器を作っているという。それは、曜変天目茶碗ではないかと、私はピンと来た。ファンでもある京都の貴和皓山(きわこうざん)という陶芸作家について紹介した。かつてその陶器に浮かんだ壮大な宇宙図に惹かれ、満天の星空のシリーズの絵を描いたことがあったのだ。
車はさらに奥へ進み、やがて私は彼の山の彫刻作品を目の当たりにして驚嘆した。それは山から切ってきたばかりの二本の葡萄の幹を、ちょうど弧を描く象牙のように山道の入り口に屹立させ、門か鳥居を想わせるふうに構えさせていた。そしてその二本の柱の間に、蔓植物で人が潜れるほどの輪をいくつか作っていた。まさに山の幽暗の世界へ入る門を表していた。
その象牙様の幹の形が、まさに私の小説家としてのデビュー作「マンモスの牙」の中心的主題を髣髴させると、私があまりにも興奮して語って聞かせるのに、彼はくだんの冷静さで、戸惑いすら見せ佇んでいるばかりだったのが印象的だった。マンモスの牙は、ここに至り博物館を飛び出し、山の中に聳え、広大な天を指し示していた。
その他、山の中に作った彼自身の木橋などの作品や、トリエンナーレの様々な作品会場めぐった。中之条町は元々養蚕の盛んな土地柄だったので、伝統的な施設の中での作品が多かった。仕事の後、毎日地元の温泉に通うというアンダーソン氏の体は柔軟で、立体作品の中で子供のように戯れてみせる彼の姿は、健康そのものだった。
そして、夕暮れた頃、なぜアンダーソン氏は都会の華やかな生活ではなく、山に引きこもる生活を選んでいるのかという話になった。「ある人が、私はナチズムに通じる愛国心のようなものの持ち主じゃないか、って言うんですよ」と彼は唐突に言って苦笑いを浮かべた。その話を聞いたとき、かつてジャック・デリダと中上健二が対談で似たようなことを言っていたのを私は思い出した。地域にこもり、やがて地域愛が国家的宇宙の構造を持ち始めるとき、一気に排他的でマニアックな愛国心と相似の様相を帯び始めることを言ったものだろうか。しかし、アンダーソン氏の場合、それは全く当たらないと思った。
それから彼が、率直な言葉で、私はソローの「ウォールデン 森の生活」が好きなんですよ、と言った。それを聞いたとき、私は全てが納得いったような気がした。
そして、宿にたどり着いたとき、日はとっぷり暮れていた。しかし、その充実した美術トリエンナーレを巡る旅が、彼との最後の一日になるとは想像だにしなかった。彼は、そのまま、あの山道への入り口に聳える門を潜り、幽暗の彼方へ去ってしまった。
2016年7月19日
初夏の頃、軽井沢駅に現れたのは、紺のTシャツとジーンズ姿の大柄なアメリカ人だった。アメリカ人としては普通なのだろうが、私には大柄で寡黙な人と映った。
私は、なぜか彼の姿に、ソマセット・モームの「月と六ペンス」の主人公、ストリックランドの人物描写を重ね、思い描き始めていた。彼は、自身が翻訳したルーベンスや、その他の画集を、紙袋いっぱいに手土産として持っていた。
軽井沢駅前のホテルのレストランに入っても、寡黙な彼とは最初、打ち解けなかった。日本語で話し始めると、ようやく会話が弾み、それからだいぶ寛いだ。
ロビーに移り、さらに話しが進んだ。彼がアメリカのユタ州出身で、ソルトレイクのことなどを話してくれた。「アメリカと日本のどっちが好きか」と、私が気軽に訊いたのに、「どちらも好きだ」と、彼がとても気を遣って答えたのが印象に残っている。全般に、馴れ初めの会話だったのだと思う。
2回目に彼に会ったのは、群馬県の中之条町で開催されているトリエンナーレ美術展に企画出品しているので、見にこないかと誘いを受けたときだった。私の小説「孵化」の英訳が済み、まもなく出版されるという心ときめく時期にも当たっていた。
彼は、美術関係の翻訳者として既に有名で、画集や美術館のカタログについての業績をご存知の方も多いと思う。その実績、文体を見て、私の芸術、文学の協力者のフランス人、Marie Parra Aledo氏によって、私の小説の英訳の適任者として紹介されたのだった。彼は、まさしく素晴らしい翻訳を成し遂げてくれたところだった。お互いの満足感もあり、彼の誘いは非常に嬉しかった。彼はまた、山の自然や大地を素材にした自然の彫刻家としても知られていた。
彼は、私の宿泊するホテルへわざわざ車で迎えにきてくれた。初回とはまるで違う親しみと敬意に溢れていた。小説「孵化」を英訳し終え、表わしてくれた気持ちだっただけに、私は大いに喜びを感じた。彼自身でさえ見尽くしていない山の中のトリエンナーレ全体を、一日かけて案内してくれるという。破格の接待だった。
トリエンナーレの会場巡りの車中で、様々な芸術のことについて話し合った。 まず同じく中之条の山中にこもっている陶芸作家のことが話題にのぼった。真っ黒で不思議な宇宙を包み込んだような陶器を作っているという。それは、曜変天目茶碗ではないかと、私はピンと来た。ファンでもある京都の貴和皓山(きわこうざん)という陶芸作家について紹介した。かつてその陶器に浮かんだ壮大な宇宙図に惹かれ、満天の星空のシリーズの絵を描いたことがあったのだ。
車はさらに奥へ進み、やがて私は彼の山の彫刻作品を目の当たりにして驚嘆した。それは山から切ってきたばかりの二本の葡萄の幹を、ちょうど弧を描く象牙のように山道の入り口に屹立させ、門か鳥居を想わせるふうに構えさせていた。そしてその二本の柱の間に、蔓植物で人が潜れるほどの輪をいくつか作っていた。まさに山の幽暗の世界へ入る門を表していた。
その象牙様の幹の形が、まさに私の小説家としてのデビュー作「マンモスの牙」の中心的主題を髣髴させると、私があまりにも興奮して語って聞かせるのに、彼はくだんの冷静さで、戸惑いすら見せ佇んでいるばかりだったのが印象的だった。マンモスの牙は、ここに至り博物館を飛び出し、山の中に聳え、広大な天を指し示していた。
その他、山の中に作った彼自身の木橋などの作品や、トリエンナーレの様々な作品会場めぐった。中之条町は元々養蚕の盛んな土地柄だったので、伝統的な施設の中での作品が多かった。仕事の後、毎日地元の温泉に通うというアンダーソン氏の体は柔軟で、立体作品の中で子供のように戯れてみせる彼の姿は、健康そのものだった。
そして、夕暮れた頃、なぜアンダーソン氏は都会の華やかな生活ではなく、山に引きこもる生活を選んでいるのかという話になった。「ある人が、私はナチズムに通じる愛国心のようなものの持ち主じゃないか、って言うんですよ」と彼は唐突に言って苦笑いを浮かべた。その話を聞いたとき、かつてジャック・デリダと中上健二が対談で似たようなことを言っていたのを私は思い出した。地域にこもり、やがて地域愛が国家的宇宙の構造を持ち始めるとき、一気に排他的でマニアックな愛国心と相似の様相を帯び始めることを言ったものだろうか。しかし、アンダーソン氏の場合、それは全く当たらないと思った。
それから彼が、率直な言葉で、私はソローの「ウォールデン 森の生活」が好きなんですよ、と言った。それを聞いたとき、私は全てが納得いったような気がした。
そして、宿にたどり着いたとき、日はとっぷり暮れていた。しかし、その充実した美術トリエンナーレを巡る旅が、彼との最後の一日になるとは想像だにしなかった。彼は、そのまま、あの山道への入り口に聳える門を潜り、幽暗の彼方へ去ってしまった。
2016年7月19日