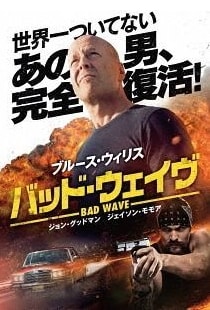阪元裕吾監督・脚本、2023年、101分、日本。アクション監督、園村健介。
伊澤彩織、高石あかり、水石亜飛夢(あとむ)、中井友望、丞威(岩永ジョーイ)、濱田龍臣。
前作で高校を卒業した主人公二人による、「最強殺し屋稼業」と「ゆるゆる同居生活」。相変わらずな二人を引き続き描く、シリーズ2作目。
「シリーズ」と言ってしまったけど、実際まだまだ続きそうな感じ。
メイン・キャラクターも揃った(揃えた)感じがあるし、今作は、今後のシリーズ化に向けての橋渡し的作品か?
監督は、フェイクドキュメンタリー『最強殺し屋伝説国岡』(2019年)の阪元裕吾さん。今作から登場の『少女は卒業しない』の中井友望さんは最初気づかなかった。今後メインキャラの一人として定着するのかな。
前作『ベイビーわるきゅーれ』(2021年)の設定を引き継いでいるが、ストーリーは特に繋がっていないので、前作未見でも大丈夫。見ておいた方が、しょっぱなから共鳴、同調しやすいかもしれないけれど。
さて主人公、「まひろ」と「ちさと」。この映画のヒットの核は、やっぱりこの二人なんだろう。
この二人、実に良いコンビで、ストーリー上も、戦闘パフォーマンスから日常生活まで「阿吽の呼吸」の親友同士。小ネタで挟まれる二人の喧嘩は、殺し屋だけあってレベルが違う。
一歩引いた観客目線で見ても、口下手でマイペースな努力家まひると、口が立ち向こう見ずな開拓者ちさとのやり取りは、コミカルで楽しく、二人でなくてはならない気持ちにさせてくれる。
か弱そうな女の子が実は凄腕の殺し屋という、ありがちな設定ではあるが、スタントパフォーマー・伊澤彩織のリアルアクションはお腹にずしんと来るし、高石あかりのガン・アクション、七変化演技もパワーアップして心臓にずきゅん。(言い方が古い…)見所はやっぱり真剣シーンだ。
実際はまひろ役の伊澤さんが6歳年上だそう。そうは感じさせず、うまくキャラクターの雰囲気にマッチして、個性となってるのも良いところ。
今後作品のファンがもっともっと増えて、B級枠を一息に飛び越え、隅田川の橋を次々に爆破するサイコパス殺し屋集団(何ソレ)に立ち向かう二人。なんて大掛かりなアクション・シーンも是非見たい。
よっしゃ、どかんと花火を上げてくれ!楽しみにしてる!
いかにもな二人の同居部屋↓ところどころに女子っぽくないトレーニンググッズも。

伊澤さんの肉弾戦はかっこよくてキレッキレ!↓前作よりさらにアクションが楽しい。

「殺し屋協会」に所属している二人↓武器は協会を通して買うのかな?どうでも良いか!