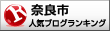こんばんは‥(^_-)

今の奈良は昨夜から寒く、今は4℃となってまた寒いですね?・・(^_-)-☆
二度寝せずに今日は眠くなれば早めに眠りますね。
マリア猫も朝は枕元で寝ていましたが、今朝は先に起きて触りに行くと手を噛まれて引っ掻かれました。
なぜか私が起きると、2mほど離れて開いた窓際に?・・
一階ではエアコンを入れてもやっと15~16℃なので一階で生活しますね。
今日の問題は奈良まほろばソムリエ15回の奈良通2級の検定問題からです‥(^_-)-☆
10 東大寺に関する事柄について、最も適当なものを選びなさい
(97)大仏開眼の年から毎年欠かさず行われ、「不退の行法」といわれる二月堂の修二会は令和6年(2024)で何回目に当たるか
ア 1263回目 イ 1273回目 ウ 1283回目 エ 1293回目
(98)二月堂修二会において、法会に参加する練行衆は現在何名か
ア 11名 イ 21名 ウ 31名 エ 41名
(99)法華堂の本尊である不空羂索観音立像の造像法は、次のうちどれか
ア 脱活乾漆造 イ 塑造 ウ 銅造 エ 木造
(100)国の天然記念物に指定されたナラノヤエザクラが咲く東大寺の塔頭はどれか
ア 観音院 イ 真言院 ウ 地蔵院 エ 知足院
(97)東大寺二月堂の修二会は、天平勝宝4年(752)、東大寺開山良弁僧正の高弟、実忠和尚が創始された。
以来、令和6年(2024)には途絶えることなく続いてきました。
開始から途絶えないともう始まった歳が分かればわかりますよね。
(98)12月16日(良弁僧正の命日)の朝、翌年の修二会を勤める練行衆と呼ばれる僧侶が発表され、明けて2月20日より別火(べっか)と呼ばれる前行が始まり、3月1日からの本行に備える。
そして3月1日から14日まで、二七ヶ日夜(二週間)の間、二月堂において修二会の本行が勤められる。
昔は今の練行衆より多いときもあったようですが現在は今の人数です。
最後の14日には、練行衆を案内する松明が舞台に全部並びます。
全部並べる数といえばもう分かりますよね。
(99)像高は362センチメートル、頭髪は群青彩、全面は漆箔仕上げで金色を帯び、三目八臂、頭上には銀製の宝冠(高さ88センチメートル)を戴いている。
眉間には白毫として水晶がはめ込まれ、額にある3番目の眼は縦に開く。
目鼻立ちは均整がとれていて、威厳ある表情を造り上げている。
漆を使う手法だとこれしかありませんね。
(100)東大寺境内の最北端に位置する知られざる塔頭寺院。
この寺は、広い東大寺境内の中でも、大仏殿や二月堂とは離れ、正倉院などよりも更に北側に位置する東大寺の塔頭寺院です。
境内地は「奈良奥山ドライブウェイ」に接する山林の中にひっそりと佇んでおり、丁寧な案内表示もありません。
私の人生の目標である少欲知足と関係する寺院です。
今日はお水取りについて紹介します。
東大寺の大仏の開眼供養は数回行われているが、その最初は752年(天平勝宝4)4月9日に孝謙天皇、聖武太上天皇、光明皇太后らが臨席して、インド僧のぼだいせんなによって行われた。
その年から始まったのがお水取りなんですね。
「お水取り」とは、 東大寺二月堂で行われる「修二会」という法会のなかの一行事 です。
儀式の主な内容としては、 心身を清めた「練行衆」が、一般の拝観者は見ることが出来ない二月堂の本尊「十一面観音菩薩」に向かい宝号を唱え、荒行によって過去の罪過を懺悔し、併せて天下安穏などを祈願するもの です。
練行衆は選び抜かれた11名の精鋭ともいえる僧侶で、彼らが2月下旬から3月中旬にかけておこなう一連の行法を修二会と呼びます。
修二会は752年から始まり、大火事で伽藍が焼け落ちても続けられてきた不退の行法で、 2024年で1273回目となります 。
「お水取り」は、この修二会の行法のひとつで、3月12日の深夜から3月13日の未明にかけておこなわれる儀式。
二月堂前の若狭井という井戸から観音菩薩にお供えする「お香水」を汲み上げるという内容 になっています。
こちらは深夜におこなわれるにもかかわらず、多くの人がその儀式を一目見ようと訪れています。
だからお水取りは修二会の一部なんですね。
だから私も含めてですが、みんなは修二会の一部分だけを見て、お水取りと修二会が同じと思っていると思います。
この行事が終えれば奈良に春が来ると言われています。
だから早く終えてほしいですね。
もうだいぶ奈良まほろばソムリエ15回の奈良通2級の検定問題慣れてきましたか?・・
今回で、2年前の試験問題をすべて終えました。
振り返って何問正解しましたか?・・
70点以上なら合格です。
明日もお楽しみに‥(^_-)-☆
答え
(97) イ (98) ア (99) ア (100) エ