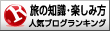富貴寺(ふきじ)は、大分県の瀬戸内海に突き出た国東(くにさき)半島にある古刹です。コンパクトで凛とした印象の、平安時代後期の建築・大堂(おおどう)は国宝です。
平安時代に国東半島に栄えた寺院群とその仏教文化を指す六郷満山(ろくごうまんざん)の形跡を今に伝える貴重な遺産でもあります。京都から遠く離れた国東半島に平安時代の美しいお堂が遺されているのは驚きです。六郷満山の成り立ちを紐解きながら、富貴寺の魅力を探ってみたいと思います。

六郷満山は、国東半島の南側にある宇佐神宮(うさじんぐう)抜きには語れません。
宇佐神宮は全国の八幡社の総本宮で、日本を代表する神社の一つです。奈良の大仏の造立に協力していたように、古くから神仏習合が進んでいました。奈良の朝廷は宇佐神宮を仏教の守護神としたため、八幡社が全国に広がり、日本で最も多い祭神の神社になっていきます。
国東半島は古来より山岳信仰が盛んでもあり、奈良時代から山岳信仰の場が寺として成立するようになります。平安時代には宇佐神宮の神宮寺・弥勒寺の傘下に入るようになり、天台宗系の修験道場になっていきます。六郷満山は、これら修験道と宇佐神宮の八幡信仰が神仏習合して栄えました。
六郷とは近辺の6つの集落群を指し、満山とは付近にあった3つの寺院群の総称です。平安時代には国東半島に65ヶ寺があったと言われています。富貴寺は六郷満山を統括していた寺の末寺でした。
豊後高田市の熊野磨崖仏に代表される石造物に六郷満山の特徴が表れていますが、木製の阿弥陀如来や不動明王の美仏も数多くのこされています。現在も旧正月に豊後高田市の天念寺で行われる火祭りの修正鬼会(しゅじょうおにえ)も、六郷満山文化を幻想的に今に伝えています。
富貴寺大堂の本尊は重文・阿弥陀如来です。頬がぽっちゃりして伏し目がちな平安時代半ばの特徴が見いだせる美仏です。内陣の壁画は傷みが目立ちますが、建物と同じく平安時代の作品です。雨天でない限り、堂内で拝観できます。
【大分県立歴史博物館公式サイトの画像】 富貴寺大堂(実物大模型)
宇佐神宮の近く、富貴寺から車で40分ほどの距離にある大分県立歴史博物館には、大堂内陣の創建時の再現レプリカが実物大で展示されています。極楽浄土壁画が特に目を見張ります。国東半島の仏教文化はかなり高度なレベルであったことが推測されます。

階段下から見える大堂の屋根が実に美しい
大堂は、山のすそ野のわずかな平地の面積に合わせるが如くコンパクトに建てられています。大堂から少し離れた、参道から続く階段から鑑賞するとより美しく見えます。宝形造りの屋根の棟(稜線)のラインが優美です。稜線の先端に板瓦を重ねてわずかに反らせており、屋根のラインの印象を引き締めています。
平安時代の和風建築をよくぞ残してくれたと、感謝したくなるほどの逸品です。いわき市の白水阿弥陀堂と共に、平安時代を代表する阿弥陀堂でることは間違いありません。必見です。

富貴寺を訪れたのは夏でしたが、はちきれるようでな木々の緑がとても新鮮でした。国東半島には豊かな自然が残っていることがわかります。四季折々の美しい風景をきっと楽しませてくれることでしょう。
また今年2018年は六郷満山が開かれて1300年にあたり各地でイベントが目白押しです。国東半島がとても賑やかになります。
【公式サイト】 六郷満山開山1300年
こんなところがあるのです。
ここにしかない「美」があるのです。
国東で千年の時を経た仏の里に伝わる説話には心が洗われる
富貴寺
【豊後高田市観光公式サイト】
原則休館日:なし
※雨天の場合、大堂内には入れません(本尊を拝観できません)
おすすめ交通機関:
JR日豊線宇佐駅から車で30分、豊後高田市「昭和の街」から車で15分
※この施設には無料駐車場があります。
※公共交通機関は地域住民向けの本数の限られたコミュニティバスのみです、公共交通機関での訪問は非現実的です。
※現地付近のタクシー利用は事前予約を強くおすすめします。
◆このブログ「美の五色」について
◆「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal
「お寺・神社・特別公開」カテゴリの最新記事
 あの本能寺は今どうなっているか?_光秀と信長の夢の跡
あの本能寺は今どうなっているか?_光秀と信長の夢の跡 黄不動の彫像、世界最古のビザ_大津 三井寺の至宝が特別公開
黄不動の彫像、世界最古のビザ_大津 三井寺の至宝が特別公開 世界最高峰の天平彫刻と静かに向き合える_東大寺 戒壇堂 四天王
世界最高峰の天平彫刻と静かに向き合える_東大寺 戒壇堂 四天王 里山風景の中に美少年のような十一面観音_京田辺 観音寺
里山風景の中に美少年のような十一面観音_京田辺 観音寺 南山城に不思議な魅力の白鳳仏_カニがいっぱい蟹満寺
南山城に不思議な魅力の白鳳仏_カニがいっぱい蟹満寺 福岡 宗像大社_大陸との交流が封印された沖ノ島は素晴らしい世界遺産
福岡 宗像大社_大陸との交流が封印された沖ノ島は素晴らしい世界遺産 今しか見れない仁和寺の魅力_観音堂&御殿 特別公開 7/15まで
今しか見れない仁和寺の魅力_観音堂&御殿 特別公開 7/15まで 京都の”端っこ”はやはり素晴らしい_嵯峨野 愛宕念仏寺 ほのぼの石仏
京都の”端っこ”はやはり素晴らしい_嵯峨野 愛宕念仏寺 ほのぼの石仏 琵琶湖疎水の脇にたたずむ安祥寺、驚きの国宝美仏が伝わる
琵琶湖疎水の脇にたたずむ安祥寺、驚きの国宝美仏が伝わる 京都 大覚寺 王朝文化を伝える美仏と書_「天皇と大覚寺」展 5/13まで
京都 大覚寺 王朝文化を伝える美仏と書_「天皇と大覚寺」展 5/13まで