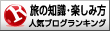やや高台にあって風格を感じさせる長屋門
青蓮院(しょうれんいん)は、京都・東山にたたずむ静寂で上質な空間を体験できる寺である。皇室や摂関家の子弟が門主(住職)を務める門跡寺院の中でも、京都の三千院・妙法院と並んで「天台三門跡」として格式を誇ってきた。江戸時代には仮御所になったことがあり、王朝趣味を感じさせる上質な設えがとても魅力的だ。
天台三門跡はいずれも、比叡山頂に僧侶が住む坊を起源としている。青蓮院は平安時代末期に、鳥羽上皇の帰依を受けて現在地のやや北側に寺域を設けたのが門跡寺院としての始まりだ。鎌倉時代に現在地に移転した後も高い格式を保ち、今の知恩院のほぼ全域を含む広大な寺域を有していた。
また青蓮院は浄土真宗にとっても聖地である。開祖・親鸞が青蓮院で得度(とくど)し、僧侶としての道を歩み始めたことが由縁になったのだろうか、室町時代に本願寺の寺勢が風前の灯火だったころに中興の祖・蓮如も青蓮院で得度している。異なる宗派でも救いの手を差し伸べる懐の深い寺であった。
室町時代には後に6代将軍となる足利義教が門主を務めたこともあった。江戸時代後期には天明の大火で内裏が焼失した際に後桜町上皇の仮御所となり、「粟田御所」と呼ばれた。1893(明治26)年の火災で大半の建物を失い、長らく保ってきた上流階級とのパイプにより作り上げた上質な空間も一旦は失われている。しかしながらその後の努力で建物の復興は進み、上質な空間も見事に復活させている。
祇園・円山公園から知恩院前を通って神宮道を北へ向かうと青蓮院がある。道沿いに並ぶ巨大なクスノキの太い枝の迫力が、この中が特別なエリアであることを感じさせる。入口を入ると華頂殿(かちょうでん)で、木村英輝によるカッコいい蓮の襖絵に囲まれた部屋からは、目前の山裾と池が見事に調和する庭とじっくり向き合うことができる。

東山を借景にした庭園、アカマツが見事
足利将軍家に仕えた芸能プロデューサー・相阿弥(そうあみ)の作と伝わる庭で、コンパクトな空間の中に幽玄な趣を表現している。半円形の反りの美しい小さな石橋とその横の堂々たるアカマツは、空間の中で存在感を感じさせ、幽玄さを上手に演出している。
華頂殿に面するのは小御所(こごしょ)だ。明治の焼失後に仮御所の設えを復興したものだが、隣の宸殿(しんでん)と並んで、門跡寺院らしい気品を感じさせる。宸殿の障壁画・濱松図は重要文化財で、建物に調和してとても美しい。徳川秀忠の息女が後水尾天皇の女御として入内した際に造営した御殿にあったもので、畳に座る際には背筋を伸ばして正座するのがふさわしいことを暗に伝える雅な気品がある空間だ。
青蓮院は毎年、春と秋にライトアップも行っている。四季を通じて表情は素晴らしく、夜に木々や建物に下から光が当たる光景も見応えがある。都心の近くで静かに庭を楽しむことができるスポットとしておすすめだ。

縁側でのんびり、京都らしいひと時
こんなところがあったのか。
日本の世界の、唯一無二の「美」に会いに行こう。
青蓮院門主による解説が秀逸
青蓮院門跡
原則休館日:なし
※仏像や建物は、公開期間が限られている場合があります。