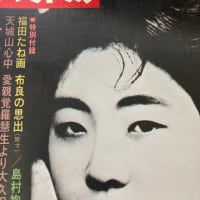今日から、弥生三月。
季節は冬から春に移ります。
これを機会に初心に戻って、蔵書を読み直そうと思いました。


まず、思い浮かんだのが藤沢周平の『三屋清左衛門残日録』です。
これは江戸時代、要人(今でいう会社の重役)の要職に就いた清左衛門が、家督を息子に譲り隠居してからの日記の形をとっています。
平均寿命の短い江戸時代は、暮らしに困らない階層の男性は、早や45歳を過ぎると仕事を離れ悠々自適の生活(隠居生活)に入るのが普通でした。
時に清左衛門52歳、三年前妻に先立たれてから隠居を考えるようになったのです。
家族に恵まれ、いかにも落ち着いた様子の彼ですが、隠居生活に入って初めて「自分」が何者であるかを迷い、暗中模索の中に入ります。
彼は「ぼんやりしておっても仕方がないからの。日記でも書こうと思った」
と嫁に告げるのです。
それでも50代初めで「残日録」とは。
「もう少しおにぎやかなお名前でもよかったのでは、と思いますが」と息子の嫁は彼の身を案じます。
実は「残日録」とは
清左衛門にとって、「日残りて昏るるに未だ遠し」の意味だそうで、決して人生の終わりを意味したものではなかったのです。
仕事のない日々の、圧倒的な空白の時間をどう過ごすか、清左衛門は今までのしがらみから自由になって自分らしく生きたいのだと私には思えます。
この日記の中に描かれた出来事は、時代を超え仕事から離れた人間にとって共感できます。
青春のやり直しなんてチャチな言葉で括れるものでなく、本当の自分らしく生きるために清左衛門の、言わば「悪戦苦闘の日々」が綴られていくのです。
再度読み直して実感として伝わってくるものがありました。
これから、日記の中の挿話を二三紹介出来たら良いなと思いました。