前回は「無知な愛情と残酷性」について考えてみましたが、今回は「食生活と残酷性」のお話から始めたいと思います。
大分前の事ですので、はっきりとは覚えていないのですが、確かアメリカの有名な女性シンガーが「日本人はクジラを食べるから、日本では公演をしない」と言っているのを聞いた事があります。
人から聞いた話では、アメリカでもクジラは獲っていたようなのですが、それは食用ではなく油を取る為だったと言う事です。
という事は、アメリカではクジラの油を取った後の肉は全部捨てていたという事になりますが、日本ではクジラの体全体を無駄なく利用していたという事ですから、どちらが残酷なのかは判断出来ません。
日本ではクジラだけではなく、賢くて可愛いイルカも食べていましたが、そういう地方でも今では「イルカ漁」よりも「イルカ・ウォッチング」に切り替えて観光用としているようです。
「イルカ療法」や「イルカの癒し効果」などのイルカ・ブームの影響でしょう。
また日本人はイカやタコを食べますが、西洋人はこの2つをデビル・フィッシュと呼ぶくらいですから食べません。
西洋人から見れば日本人の食生活を不思議に思う人も多いと思いますが、江戸時代の日本人は、四足を食べる西洋人の事を「南蛮人」と呼んで野蛮な人種だと本当に考えていたようですから、どっちもどっちのようです。
アジアの一部の国では猿や犬を食べるようですが、これなども日本人の感覚からみたら残酷に感じるのではないでしょうか・・・。
「食」というのは、その国の昔からの習慣や宗教などの違いによって随分と違って来るものだと思いますし、そういう食生活の違和感から人間同士の誤解も生じているのではないかと思います。
ところで、人間は「雑食」という事もあって、「動物」を食べない宗教家や菜食主義の人たちも多い訳ですが、そういう人たちでも生きて行く為には「生き物」を食べなければなりません。
つまり「植物」の事ですが・・・
では何故植物を殺して食べる事に対しては残酷とは感じないのでしょうか?
多分これは植物には心(感情)がないと考えているからではないでしょうか・・・。
或る研究では植物に対して話しかけると、それが植物に伝わって、明らかに何らかの反応や変化が現れるのだそうです。
また植物に電流計?を繋いで、包丁で野菜を切っている時の音を聞かせたり、その野菜を切った人間が植物の傍に近づくと、針が大きく振れて反応を示すのだそうです。
つまり動物と同じ様に、「植物にも感情があって、喜んだり悲しんだりしている」という事を真剣に考えて、実験を繰り返している人たちがいるという事です。
以前公園を散歩している時に、花壇が荒らされて、沢山の綺麗な花々が無惨にも踏み倒されているのを見かけた事があります。
これを植物を可愛がっている人たちが見たら、当然残酷と感じるのではないかと思います。
理屈は抜きにして、「心ある人たち」にとっては「植物にも感情がある」という事は、感覚的には納得のいく事だと思えるのですが・・・。
私が以前住んでいた近くに、或る施設のビルがあったのですが、そのビルの周りに2メートルくらいの細長い綺麗な花壇がいくつも置かれるようになったのです。
理由は分かりませんが・・・。
ところが、それから一年経つか経たない内にビルの一部が改修され、その花壇は全部なくなってしまったのです。
後になって分かりましたが、そのビルの裏側の誰も目に付かないところに、その花壇は放置されていました。
本当のところは良くは分かりませんが、その施設の性質上それらは世話をする人もなく「邪魔者」として一箇所に置き去りにされているように感じられました。
私なども部屋のインテリアを考えて観葉植物を置いたりしていましたが、初めの内はうっかりすると「生き物」という事を忘れて、水をやるのもいい加減にしてしまい、ほとんど「造花」や単なる「飾り物」と同じ様に扱っていたものです。
ですから人を批判出来るような立場ではないのですが、世の中を見ていますとやはり同じ様な間違いをしている人たちが多いような気が致します。
食生活の話から、いつの間にか「植物には心があるのか?」という話になって来てしまいましたが、事のついでに・・・生物だけではなく、「単なる物質にも心があるのか?」いう事にも少し触れてみたいと思います。
ある漫画家のエッセイの中にこんな話が載っていました。
古くから使っている机や家具などには、魂が宿っているので粗末にしてはいけない。
そういう机で仕事をしていると、精神状態も良くなり仕事も良くはかどり、良い影響があるというのです。
或る時、その大切にしていた机を「心無い人」がノコギリで足を切ってしまったそうなのですが、その為かどうか後になって、その足を切った男はその業界から消えてしまった、つまり「失脚」してしまったと言うのです。
一般の人にとってはタダの「物質」のように思えても、それを大切にしている人にとっては「心がある」と感じているのです。
そういう人にとっては、机の足をノコギリで切られた時には、単なる物質である筈の机が悲痛の叫び声をあげているように感じられるのではないでしょうか。
この間テレビを見ていたら、西洋人が何人か集まって自分の手を顔に近づけて、幸せそうに指輪に話しかけているのです。
その指輪に付いているダイヤは自然の宝石ではなく、家族の遺骨の一部を加工して作ったダイヤなのだそうです。
その人たちにとっても、宝石は単なる石ではなく「感情のある石」なのです。
「心ある人たち」というのは・・・動物も、植物も、単なる物質も、皆「心あるものたち」のように感じ、接して、日常生活を送られているように思われます。
大分前の事ですので、はっきりとは覚えていないのですが、確かアメリカの有名な女性シンガーが「日本人はクジラを食べるから、日本では公演をしない」と言っているのを聞いた事があります。
人から聞いた話では、アメリカでもクジラは獲っていたようなのですが、それは食用ではなく油を取る為だったと言う事です。
という事は、アメリカではクジラの油を取った後の肉は全部捨てていたという事になりますが、日本ではクジラの体全体を無駄なく利用していたという事ですから、どちらが残酷なのかは判断出来ません。
日本ではクジラだけではなく、賢くて可愛いイルカも食べていましたが、そういう地方でも今では「イルカ漁」よりも「イルカ・ウォッチング」に切り替えて観光用としているようです。
「イルカ療法」や「イルカの癒し効果」などのイルカ・ブームの影響でしょう。
また日本人はイカやタコを食べますが、西洋人はこの2つをデビル・フィッシュと呼ぶくらいですから食べません。
西洋人から見れば日本人の食生活を不思議に思う人も多いと思いますが、江戸時代の日本人は、四足を食べる西洋人の事を「南蛮人」と呼んで野蛮な人種だと本当に考えていたようですから、どっちもどっちのようです。
アジアの一部の国では猿や犬を食べるようですが、これなども日本人の感覚からみたら残酷に感じるのではないでしょうか・・・。
「食」というのは、その国の昔からの習慣や宗教などの違いによって随分と違って来るものだと思いますし、そういう食生活の違和感から人間同士の誤解も生じているのではないかと思います。
ところで、人間は「雑食」という事もあって、「動物」を食べない宗教家や菜食主義の人たちも多い訳ですが、そういう人たちでも生きて行く為には「生き物」を食べなければなりません。
つまり「植物」の事ですが・・・
では何故植物を殺して食べる事に対しては残酷とは感じないのでしょうか?
多分これは植物には心(感情)がないと考えているからではないでしょうか・・・。
或る研究では植物に対して話しかけると、それが植物に伝わって、明らかに何らかの反応や変化が現れるのだそうです。
また植物に電流計?を繋いで、包丁で野菜を切っている時の音を聞かせたり、その野菜を切った人間が植物の傍に近づくと、針が大きく振れて反応を示すのだそうです。
つまり動物と同じ様に、「植物にも感情があって、喜んだり悲しんだりしている」という事を真剣に考えて、実験を繰り返している人たちがいるという事です。
以前公園を散歩している時に、花壇が荒らされて、沢山の綺麗な花々が無惨にも踏み倒されているのを見かけた事があります。
これを植物を可愛がっている人たちが見たら、当然残酷と感じるのではないかと思います。
理屈は抜きにして、「心ある人たち」にとっては「植物にも感情がある」という事は、感覚的には納得のいく事だと思えるのですが・・・。
私が以前住んでいた近くに、或る施設のビルがあったのですが、そのビルの周りに2メートルくらいの細長い綺麗な花壇がいくつも置かれるようになったのです。
理由は分かりませんが・・・。
ところが、それから一年経つか経たない内にビルの一部が改修され、その花壇は全部なくなってしまったのです。
後になって分かりましたが、そのビルの裏側の誰も目に付かないところに、その花壇は放置されていました。
本当のところは良くは分かりませんが、その施設の性質上それらは世話をする人もなく「邪魔者」として一箇所に置き去りにされているように感じられました。
私なども部屋のインテリアを考えて観葉植物を置いたりしていましたが、初めの内はうっかりすると「生き物」という事を忘れて、水をやるのもいい加減にしてしまい、ほとんど「造花」や単なる「飾り物」と同じ様に扱っていたものです。
ですから人を批判出来るような立場ではないのですが、世の中を見ていますとやはり同じ様な間違いをしている人たちが多いような気が致します。
食生活の話から、いつの間にか「植物には心があるのか?」という話になって来てしまいましたが、事のついでに・・・生物だけではなく、「単なる物質にも心があるのか?」いう事にも少し触れてみたいと思います。
ある漫画家のエッセイの中にこんな話が載っていました。
古くから使っている机や家具などには、魂が宿っているので粗末にしてはいけない。
そういう机で仕事をしていると、精神状態も良くなり仕事も良くはかどり、良い影響があるというのです。
或る時、その大切にしていた机を「心無い人」がノコギリで足を切ってしまったそうなのですが、その為かどうか後になって、その足を切った男はその業界から消えてしまった、つまり「失脚」してしまったと言うのです。
一般の人にとってはタダの「物質」のように思えても、それを大切にしている人にとっては「心がある」と感じているのです。
そういう人にとっては、机の足をノコギリで切られた時には、単なる物質である筈の机が悲痛の叫び声をあげているように感じられるのではないでしょうか。
この間テレビを見ていたら、西洋人が何人か集まって自分の手を顔に近づけて、幸せそうに指輪に話しかけているのです。
その指輪に付いているダイヤは自然の宝石ではなく、家族の遺骨の一部を加工して作ったダイヤなのだそうです。
その人たちにとっても、宝石は単なる石ではなく「感情のある石」なのです。
「心ある人たち」というのは・・・動物も、植物も、単なる物質も、皆「心あるものたち」のように感じ、接して、日常生活を送られているように思われます。













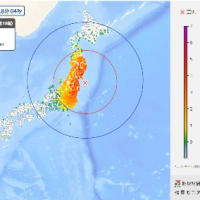
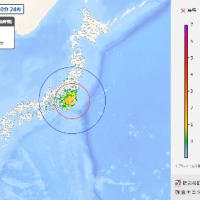
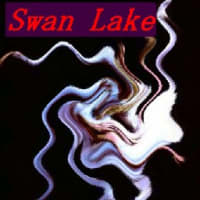










と感じ(信じ)脈々と命を繋いで参りました。
(あ、私、別に宗教のお話をするつもりではないんです)
空と大地と木々と海とまた全ての命宿る物に
神が居られる…と「畏れ」を持って
「慎ましく」「敬虔」に生きて来た
と申しても過言ではないかと
思うわけです。
そして、自然淘汰の摂理にて
そのように生きる者が生き残り現在に至って
いる
(筈なのだけど…どうもそうではない者が
目につき悲しいですが)
とも想えます。
当時は、全ての事象に意味がある…と捉え
日々過ごしていたと予想されます。
(例えば、午後から急に雨が降って来たのは
「何か良くないことのお告げだ!」
などと捉える)
ソルジェニーツインの「デルス・ウザーラ」
の中にもこのアミニズムは出て参りましたね。
原始的でごくシンプルは「畏れ」の一歩は
自分以外の万物事象に対するこの「畏れ」から
発生するようです。
宇宙の理を解明しようと挑戦する現代でも
この「畏れ」は要です。
どうも世の中、妙ちきりんになってしまった
一つの根本的な理由にこの点が言えるんじゃないかな?
と私は思います。
何もかも征服し理解できていると傲慢にも
思い上がってしまった「人の浅薄さ」
なのではないか…と。
物事を深く洞察し捉える時間を軽視する風潮と傾向。
欲望第一の商業主義が大きな顔して歩き回って
いるんです((-_-;…。
あらたさんの仰りたいこと…
伝えたいこと…って
その辺にございませんか?
つらつらと想うまま書いてしまいました。
たはは(;^_^A アセアセ・・・
長々と失礼いたしました<(_ _*)>
アミニズム ×
アニミズム ○
訂正致します<(_ _*)>
では、一つだけ付け加えておきましょう。
アニミズムの場合は、社会全体が先祖から伝えられた知恵を、幼い頃から教育されて出来たものではないでしょうか?
ですからこれと違う考え方をすれば、異端視され、村八分にされますよね。
このエッセイで私が「心ある人」と表現したのは、それとは逆で、社会がどんな教育をしようとも、それに関係なく全く個人的な自己発見によって得た心境の事です。
ですから社会の教育や流行によっては、「心ある人」の方が異端視されて孤独を感じる事になるのです。
綺麗な空を見て感じる心はその人の感性で
感じる物ではない?
深い森の中にいると、荘厳な畏れを持って
自然と静かな気持ちになる事など自然な
心の動きだと私は想うけれど…。
心ある人そのものだと思う。
木を切るのは生活に必要な為、
感謝し手を合わせながら樵は木を切る。
猟をするのも命を繋ぐため…。
必要最低限な分だけ祈りながら猟師は
獣を屠った。
村八分とか排他主義?となると
統治し易くする為、後から出てきた強欲な人の
厭らしい面じゃないでしょうか?
私がお伝えしたかったのは
おおらかな人の柔らかな感性のこと。
純粋で先入観がない素のままの心のこと。
教育以前のお話し…です。
これを考えますと、幼い頃からアニミズム教育を受けた社会に於いても、その本質を理解出来る人は少数だと思います。
何時の時代でも「心ある人」というのは少数派ではないかと思います。
この事を考えて、もう一度読み返してみて下さい。
このエッセイのテーマ
「食生活と残酷性」について
あと…余談ですが、私は感想を述べているのです。
あらたさんと対峙して議論するつもりはございませんので(苦笑)
「論語読みの論語知らず」などとバッサリ
斬られてしまうのは悲しいものです。
(確かに私は論語を理解しておりませんがね…)
「食生活・・・」の話から始めてみましたが・・。
「教育以前・・・」と言われますが・・・
どんな社会であっても、人間は誰でも教育を受けています。
それが良い教育であっても悪い教育であっても、後々個人が自己発見をしなければなりません。
問題なのは教育を受けている事に気が付かない事です。
それが「うぐいすは何となく鳴く?」というエッセイのテーマだったのです。
日本人なら「ホー・ホケキョー」と鳴くと言うでしょう。
でもこれは教育によってそう思い込んでいるだけなのです。
自分の感受性に目覚めた人にはこうは聞こえなくなるのです。
外国の人には「ホー・ホケキョー」とは聞こえません。
何故なら「ホー・ホケキョー」というのは「法華経」という仏教用語から来ているとひらめいたからです。
「心ある人」というのは、「教育以前の心」というよりは、「教育後」の自己発見や経験や才能によって得る事の出来る心境と考えた方が分かりやすいと思います。
Arataさんとえるぜさんは難しい議論を・・
私は簡単すぎて相手にしてもらえないかな・・
わたしはね
無機質な物質にも心はあるとおもうの。
それはなんでかというと感じるから。
でも心があるといっても
あくまでもそれに対峙する人間の心が
反映し共鳴した結果だとも思うのですが。
私が手を合わせてみても、どうしても「形式的」にやっているだけで、心が入らないのです。
お年寄りにとっては、遺体は単なる物質ではないのです。
お墓にしても単なる石ではないのです。
お葬式にしても単なる「形式」ではない訳です。
お恥ずかしい事に、私がお墓参りをした時に、亡くなった人と生きている時と同じ様に会話をするようになったのは、40代になってからの事なのです。