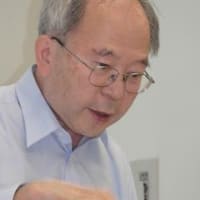北方四島問題
わが国固有の領土である北方四島を不法占拠しているロシアは、これらの島々の沿岸12海里を自国の領海と主張しています。北方四島周辺海域は、水産資源の豊かなことで世界的にも有名な海域であり、納沙布岬から貝殻島まで3.7km、一番遠い択捉島まで144kmしか離れていないことから、小型漁船が容易に出漁できる距離にあります。ソ連時代から現在に至るまで、ソ連・ロシアが主張する領海において無許可で操業したなどとして、拿捕される日本漁船が後を絶たず、平成14年から18年までの間に21隻245人が拿捕されています。18年8月には発砲を受け昭和38年以来となる死亡者が出ています。このため、海上保安庁は、ロシア連邦保安庁国境警備局との間で、累次に亘る協議をし、18年12月、同種事案の再発防止のため、両機関間の連携強化について合意しました。海上保安庁は拿捕などの発生が予想される根室海峡周辺海域に常時巡視船艇を配備し、出漁船に対し直接、または漁業協同組合を通じて、被拿捕の防止の指導と漁業関係法令の遵守指導を行っています。
竹島問題
竹島は、島根県隠岐諸島の北西約160kmに位置し、2つの島と周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.2平方Kmで日比谷公園とほぼ同じ広さです。政府は歴史的事実に照らしても、国際法上もわが国の領土であるという立場を堅持する一方、竹島問題は平和的に解決されるべきであり、外交ルートを通じて粘り強く解決を図る方針を示しています。海上保安庁は、政府方針に従い、竹島周辺海域に常時巡視船を配備して監視を続けるとともに、わが国漁業者の安全確保の見地から、被拿捕の防止指導を行っています。
東シナ海における資源開発
豊富な地下資源が埋蔵されているといわれる東シナ海では、日中両国の間で排他的経済水域および大陸棚について、境界を画定するには至っていません。我が国は地理的中間線により、境界を画定すべきとしているのに対し、中国は、中国大陸から自然延長の終点である沖縄トラフが日中間の大陸棚の境界であると主張しています。
中国は、既に東シナ海の日中地理的中間腺付近に存在する油ガス田に、採掘用の海洋構築物を設置し、一部では生産を開始させています。資源エネルギー庁によると、これら油ガス田の一部は、地下構造上、地理的中間線の日本側にも連続しており、このまま中国が開発を続ければ日本側の資源が吸い取られてしまうことになります。
我が国は、資源開発問題について話し合う日中協議等において中止を求めています。19年4月の日中首脳会談の際には、双方が受け入れ可能な比較的広い海域において共同開発を行い、19年秋に具体的方策を首脳に報告することを目指すこととされています。
海上保安庁は、東シナ海で航空機による哨戒を行い中国の開発状況を把握し、情報提供しています。
外国海洋調査船
中国は、近年、東シナ海などの我が国の排他的経済水域において、調査活動を活発に行っています。平成11年には、33隻の中国海洋調査船を確認しました。この中には、我が国の領海内に進入して調査活動を行う事案もありました。こうした東シナ海における無秩序な状況を解決するため、13年、中国との間で、東シナ海における相手国の近海で海洋の科学的調査を行う場合は、調査開始予定日の2ヶ月前までに、外交ルートを通じ通報することを内容とする「海洋調査活動の相互事前通報の枠組み」について合意し、同年2月から運用が開始されました。その結果、近年は東シナ海において我が国の同意の無い調査活動は減少し続け、17年には確認されませんでしたが、再び18年には7件の我が国の同意の無い調査活動が確認されました。
19年2月は、我が国に事前通報した海域の外である尖閣諸島魚釣島周辺の我が国EEZにおいて、航行・漂白を繰り返しつつ、科学的調査と思われる調査を断続的に行うという事案が発生しています。
海上保安庁は、これら海域において、巡視船、航空機による監視を行い、我が国の同意が無い調査活動を行う外国海洋調査船を確認した場合には、外務省が外交ルートで中止要求、厳重抗議を行うとともに、現場においても、巡視船艇・航空機により無線等を通じた中止要求を行い、海洋権益の保全に努めています。

外国漁船による不法操業の取締り
九州に基地を置くある1,000トン型巡視船は、日本海から対馬海峡、五島列島沖の東シナ海の領海・経済水域の監視取締りを主任務としておりました。対象となる外国漁船や不審船は、夜間、しかも深夜から早朝に掛けて侵入してきます。夕刻、数百隻に上る対馬周辺の日本漁船群・外国漁船団が煌々と集魚灯、航海灯を点灯して活動を始めると、海上保安官は巡視船の舷窓を閉じて、航海灯を消し全ての灯火が外に漏れないようにし、肉眼では巡視船が全く闇の中に溶けるようにして、全速力で対馬の北から、五島列島の沖までレーダーと肉眼の見張りを厳重にして、衝突事故は絶対に起こさない、しかし少しの異常な動きも見落とさないという態勢で、一晩で領海線の内外を哨戒します。覆面の1,000トンの船が、19ノットで対馬海峡の通航船と漁船集団群の中を、相手に気づかれないように旋回航走し密漁船・不審船を確認するということが、いかに緊張と覚悟のいる哨戒か、夜の対馬海峡を航行した経験のある方なら判ると思います。何も不審なことが無く緊張の一夜が過ぎると海上保安官達は「今夜の対馬海峡一帯は治安が保たれたか」と自問自答し、次の当直に引き継ぎます。
この様な哨戒の結果、多くの完全無灯火で操業する外国漁船の領海侵犯操業を発見し、暗闇の中で激しい公務執行妨害を受けながら強行接舷して停船させ、まさに身の危険を犯して拿捕し、また国際海峡でしばしば起こる外国船が絡む不審事象を確認し、海上治安機関として蓄積しているのです。
ある夜の哨戒は、対馬海峡が200-300mの視界の深い霧でした。夜明け前、上空が少し白み、海上はまだ暗く深い霧の中で、レーダー監視員が「2~3海里先の船影が、中型トロールの動きをしている。」と報告。船長は直ちに総員立入検査・検挙体制を発令。
この海域でこのような動きをするのは外国の密漁底引船以外は無いからです。巡視船の船首先端部、船橋等に見張り監視・ビデオ採証担当保安官を配置し、巡視船に積んでいる高速ボートに立ち入り検査班8名が乗り組みいつでも発進できる準備をし、レーダーで相手の動きを見ながら静かに接近しました。200mくらいの距離で濃い霧の中に、ぼんやりと船の形が見えましたが、相手船の明かりは一切見えません。真っ暗闇の中で明かりの無い2つの船影が次第に近づいていく状態です。突然、船首の監視員から「火花2箇所。グラインダーの切断音。エンジンの加速音。前方船影のもの。」と報告。船橋で指揮していた船長にも火花とチャリン、チャリンというグラインダーでワイヤーロープを切断する音が聞こえてきました。引いている網を漁船の上に引き上げていたのでは巡視船に捕まるので、一瞬のうちに2本のワイヤーロープを切断して網を捨て、身軽になって逃げるためで、密漁のプロの手口です。
直ちに拿捕体制に入り、高速ボートを発進させ、2隻での挟み撃ちに入りました。相手は、200トン位の中型底引きトロール漁船。国籍を示すものはありませんが一目瞭然、韓国船による領海内侵犯底引き密漁です。相手も必死で、最大速力でジグザグに逃げ回ります。巡視船は1、000トン、長さ70m、速力35km時。巡視船の甲板上には完全装備の立ち入り検査班が一瞬でも接舷したら、密漁船の甲板に飛び込もうと身構えています。しかし、大型巡視船と小回りの効く漁船では、逃げ回るほうが断然有利です。高速ボートの立ち入り検査班は、ジュラルミンの大盾を構えて身を守りながら接舷した瞬間飛び移ろうと機会を窺っていますが、密漁船から高速ボートに向けて乾電池、ビン、ビス、ナット、などあらゆるものが投擲されて、大盾がカンカン音を発てているのが聞こえ、なかなか挟み撃ちができません。其の内韓国の領海が近くなりました。此の時、応援のため、高速で小回りが利く対馬海上保安部の巡視艇が夜明けの海面をすべるように接近して来ました。これに気づいた密漁船は、このままでは拿捕されると思い最後の逃走方法と思ったのか、突然、平行して走っていた巡視船の直前に直角に突進し、反対側に逃げ出そうとしました。巡視船の船長は、瞬間、避けきれないと判断し「後進全速」を令しました。時速35キロで走っている1,000トンの船体が直に停止することはできません。船体が壊れるほどの急激な振動と同時に船橋の不安定なものは全て落下し、乗組員は皆前のめりになり、急激にスピードが落ちましたが、密漁船は、なお前を潜り抜けようと全速で突っ込んできました。密漁船の船橋のすぐ後ろの船体が少し低くなった所に、巡視船の船首が当たり、そのまま食い込んで、ゆっくりと密漁船を横に押しながら急激に速力が落ち、停止しました。現場にいた海上保安官は皆、一瞬、密漁船は巡視船に直角に圧し掛かられて、横倒しになり、転覆すると思ったそうです。密漁船の乗組員全員が甲板上で呆然と巡視船のへさきを見上げていました。幸い、韓国船は、フレームが少し曲がっただけで、怪我人も、損傷も無く、拿捕しました。
誰も意図して、このような状況を作り出したものではありません。深夜から早朝に掛けた領海侵犯で、他国の資源を密漁しようとする者は必死です。韓国の領海に逃げ込んでしまえば絶対安全となるわけですから、逃げ方も操船の常識の範囲外にあります。捕まえる側の巡視船の保安官も全員その覚悟で、それでも人身事故は双方に絶対出さない、という決意と、経験からくる自信と、何よりも海保が行動することによってのみ、両国間の紛争の原因が減り、この海域の治安が保たれるという使命感が無くては、この任務は果たせないのです。
この頃、対馬海峡の領海侵犯密漁取締りでは、石、出刃包丁を投げつけられるだけではなく、立ち入り検査のため飛び乗った海上保安官が海上に突き落とされる事件も起きており、極めて困難で危険を伴う外国密漁船の取締りが、厳格に行われていました。
公海上外国船内暴動
韓国からオーストラリアに向かう8万トンのパナマ籍鉱石運搬船「EBキャリア」において発生した、フィリピン人乗組員が英国人幹部船員に対し待遇改善を求めた船内暴動事件では、船長からの切迫した救助要請無線が、直接海上保安庁に入りました。公海上の事件であり、出港地、仕向地、船舶所有者、乗組員の国籍等全て我が国との関係は無かったのですが、現場が那覇の南100海里で、付近に暴動を鎮圧できる関係国の実力部隊が存在せず、台風の発生も懸念され、英国人の生命に危険が切迫している状況下、関係国から日本政府に救助要請が出され、巡視船隊と大阪の特殊部隊が派遣されました。救助要請は、「刃物を突きつけられ、幹部数名が船長室に逃げ込み、入り口にバリゲートを作っているが、斧でドアを破壊している。銃の有無はわからない。」と言うものです。
現場では、暴動者に対する母国語と英語の無線による説得。武器による抵抗に備えて、ヘリコプターから海面上18メートルの高さの「EBキャリア」の甲板へ完全装備の特殊部隊を降下させ、多数の完全装備の保安官を送り込み、その周囲では巡視船隊による威圧を行い、説得を受け入れれば両者の仲裁を行なうが暴動を続ければ実力で制圧する旨通告し、硬軟両方の交渉を行いながら、海上保安官の部隊が船内の暴動区域に入り込んで両者を隔離し、暴動の原因を調査し、痕跡を証拠化し、那覇港での両国の関係者による話し合いを確約させ、保安官の警備の下那覇港に回航させ、死傷者を出すことなく解決しました。これは国際的視点での治安確保が求められた顕著な事例ですが、実際に海上保安官が鎮圧のため実力を行使せざるを得なかった場合の法的問題や、複数国間の問題を包含した「今ここにある人命の危機」に対して、海上保安庁が蓄積した現場の経験を下に様々な難問を乗り越えながら、人命の救助を行なった一つの例です。
日本はどの点からも当事国では無かったが、海上という特殊性から発生した、緊急かつ人命に係る重大な国際協力事案として、当事国の要請を受け対応しました。
海に国民生活を委ねている我が国は、今後もこの様な事態が発生した場合には、海上保安庁の蓄積した経験を活かして、的確に対応する必要があります。
海賊対策
マラッカ海峡における海賊は以前から在りましたが、我が国において大きな関心を呼んだのは、平成10年日本の会社が所有する便宜置籍船「テンユー号」海賊事件と同じく11年、便宜置籍線「アランドラ・レインボー号」海賊事件です.国際商業会議所国際海事局に報告された、平成18年の東南アジアにおける海賊の発生件数は、17年の122件から88件と減少しており、マラッカ・シンガポール海峡における発生件数は、19件から16件と減少しています。けれども、17年3月マラッカ海峡を航行中の日本籍タグボートが、武装集団に襲撃され、日本人2人を含む乗組員3人が誘拐されるという事件が発生した外、19年4月インドネシアベネット湾で、外国貨物船が10隻の高速ボートの武装集団から発砲を受けるなど、依然として凶悪な事件が発生しています。
東南アジアにおける海賊の発生件数は、引き続き減少傾向で、これは、海上保安庁と沿岸国海上保安機関の連携協力体制の強化と沿岸国海上保安機関自らの積極的な取り組みの成果によるものと思います。
海上保安庁では、巡視船の東南アジア派遣、現地での人材育成、わが国と複数国間での連携訓練、「アジア海賊対策地域協力協定」に基づく情報ネットワークの構築、「東南アジアにおける海上セキュリテイ・海賊セミナー」、海保大への留学生の受け入れなどを実施しています。
協定に基づきシンガポールに設置された情報共有センターには、海上保安大学での留学を経験したフィリピン沿岸警備隊員が勤務しているなど、海上保安庁の人材育成は確実に成果を挙げてきています。海上保安庁では、今後も積極的に東南アジア各国海上保安機関の人材育成支援を行っていきます。