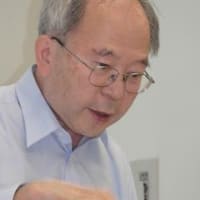7月20日に行われた戦略情報研究所講演の原稿を紹介します。
後藤光征(みつゆき)・元海上保安庁警備救難監 による「わが国における海上警備の現状と問題点」 と題した講演でした。
※講師は昭和17年生まれ、秋田県のご出身で巡視船くにさきの船長、第3管区海上保安本部警備救難部長、本庁警備救難部警備第二課長、第4管区海上保安本部長などを歴任された方で、わが国の海を身をもって守ってきた経験に基づき貴重なお話です。
几帳面に原稿を用意され、静かで丁寧な語り口で、日本の海の現状をお話になりました。
落ち着いた話し方でしたが、現場の生の臨場感も伝わってきました。
無駄な言葉が一つもない、充実したお話でした。
調査会荒木代表に申し入れ、後藤光征氏の了解を頂き、当日の原稿をそのままご紹介させていただくことになりましたので海上保安庁の仕事、日本の海上警備について関心のある方は、ぜひ、お読みいただければと思います。
戦略情報研究所講演会
平成19年7月20日
わが国における海上警備の現状と問題点

海上保安庁は、昭和23年に創設されて以来、多様かつ複雑化する日本の海の情勢に対応するために、様々な対策を採ってきました。
昨今の日本の海は、排他的経済水域や尖閣諸島周辺海域における海洋権益の保全、テロの脅威、不審船の徘徊等様々な問題が散在しています。
四海を海で囲まれたわが国は、古くから様々な海の恩恵を受けて繁栄を続け、近年、海洋に対する国民の関心が高まる中で、このような問題は極めて憂慮すべきことであり、今や皆さんが海洋国家日本を考える上で、身近な問題として捉えられていると思っております。
海からの多くの恩恵の主なものには、経済活動として漁業、海底資源、海上輸送、マリンレジャーなどがあります。
輸送活動を見れば、
わが国の海上貿易量 約9億4999万トンは世界の約14パーセント
国際貨物の約71パーセント(金額ベース)
約99パーセント(重量ベース)が海上を利用
食料の約60パーセントを輸入に依存
エネルギーの約90パーセントを輸入に依存など
日本の海が国民生活に密着していることがわかります。
豊かな恵みを受ける海も、一方では世界でも屈指の厳しい海洋気象の海でもあります。皆様は、春一番、夏から秋の台風、冬の大陸からの季節風によって起きる海難のニュースに頻繁に接しております。
恩恵を受ける海と、国民が生活する領土との関係については、わが国の
領土の面積 約38万平方km 世界第61位
領海の面積 約43万平方km
領海・排他的経済水域の面積 約447万平方km(領土の12倍) 世界第6位
体積 約1,580万立方km 世界第4位
海岸線の延長 約3.5万km 世界第6位
国の面積当たりの海岸線延長 約92m/平方km 世界第1位
国の人口当たりの海岸線延長 約27m/百人 世界第1位
となっております。
つまり、わが国は、世界でも有数の広くて深くて海岸線の長い海に取り囲まれている訳です。
この海の利用については、国連海洋法条約によって、領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通行に関する様々の取り決めがなされています。
国連海洋法条約は、H6年発効、平成16年に145カ国が批准しました。
我が国は、領海12海里を採用。(領海及び接続水域に関する法律第1条)
・領海の地位は
沿岸国の主権が上空(領空)、海底、海底の下まで及び生物・鉱物資源の採取に独占権。完全な主権が及ぶ内水とは異なり、沿岸国の平和、秩序、安全を害さない限り無害通航権あり。
・排他的経済水域200海里(限定的、機能的な管轄権)
天然資源の探査・開発等に関する主権的権利。科学的調査に関する管轄権。海洋環
境の保護・保全。
などについて取り決められています。
このような環境の下、わが国周辺の海洋を巡る諸問題として、
尖閣諸島、北方領土、竹島の周辺海域警備
排他的経済水域内の外国海洋調査船監視
外国漁船不法操業取締り
東シナ海エネルギー資源開発
東南アジア航路の海賊対策
不審船・工作船警備等があります。
これらの諸問題について、海上保安庁がどのような業務を行っているか、事例を加えながら紹介します。
尖閣諸島領海警備
尖閣諸島は、沖縄群島西南西の東シナ海に位置し、魚釣島、南小島、北小島など5つの島と3つの岩礁からなり、魚釣島からは、石垣島まで170km、沖縄本島まで410km、台湾まで170km、中国大陸まで330kmの距離があります。この帰属については、日本はわが国の領土であるとして、問題としていませんが、昭和46年以降、中国、台湾が領有権を公式に主張し始めました。それは、昭和43年日本、韓国、台湾の海洋専門家が国連アジア極東経済委員会の協力を得て、東シナ海海底の学術調査を行った結果、東シナ海の大陸棚には、豊富な石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘されたためです。さらに、平成8年7月に国連海洋法条約がわが国について発効し、排他的経済水域が設定されたことに伴い、台湾・香港等で漁業活動への影響が生じたことに対する不満や、北小島に日本の政治団体が灯台としての構築物を設置したことを背景に、「保釣活動」と呼ばれる領有権主張活動が活発となり、尖閣諸島周辺の領海に侵入するなどの大規模な活動が行われる様になりました。近年では、中国において新たな活動団体が台頭し、急激に勢力を拡大し、領有権主張活動を展開しています。平成16年には、巡視船の間隙を縫って中国人活動家7名が魚釣島に不法上陸する事案が発生しました。18年には、台湾と香港から活動家の乗った船が出港し領海内へ不法侵入しました。
海上保安庁は巡視船等の部隊を派遣し、関係省庁とも協力して警備し、島への上陸を阻止しています。
尖閣諸島は、遠隔地の上、台風の常襲海域という地理的条件にあり、かつ付近に巡視船艇の避難港、補給港が無いため、大規模な警備を行うには、全管区から巡視船艇・航空機を長期に亘り派遣する体制をとらざるを得ないこと、巡視船隊が活動家の船舶を規制・退去させる際に、荒れる海上で巡視船と活動家船舶が衝突・接触した場合には、小さな活動家船舶が大きなダメージを受ける可能性が大きいため、双方に人身事故が起きないように慎重な規制をする必要があることなどから、尖閣諸島領海警備は、極めて大規模、かつ慎重な体制で行うことになります。海上保安庁は、政府方針に基づき常時周辺海域に巡視船を配備し、航空機による哨戒を行っていますが更に警備体制を磐石とするため、新しい巡視船の整備などを進めています。
後藤光征(みつゆき)・元海上保安庁警備救難監 による「わが国における海上警備の現状と問題点」 と題した講演でした。
※講師は昭和17年生まれ、秋田県のご出身で巡視船くにさきの船長、第3管区海上保安本部警備救難部長、本庁警備救難部警備第二課長、第4管区海上保安本部長などを歴任された方で、わが国の海を身をもって守ってきた経験に基づき貴重なお話です。
几帳面に原稿を用意され、静かで丁寧な語り口で、日本の海の現状をお話になりました。
落ち着いた話し方でしたが、現場の生の臨場感も伝わってきました。
無駄な言葉が一つもない、充実したお話でした。
調査会荒木代表に申し入れ、後藤光征氏の了解を頂き、当日の原稿をそのままご紹介させていただくことになりましたので海上保安庁の仕事、日本の海上警備について関心のある方は、ぜひ、お読みいただければと思います。
戦略情報研究所講演会
平成19年7月20日
わが国における海上警備の現状と問題点

海上保安庁は、昭和23年に創設されて以来、多様かつ複雑化する日本の海の情勢に対応するために、様々な対策を採ってきました。
昨今の日本の海は、排他的経済水域や尖閣諸島周辺海域における海洋権益の保全、テロの脅威、不審船の徘徊等様々な問題が散在しています。
四海を海で囲まれたわが国は、古くから様々な海の恩恵を受けて繁栄を続け、近年、海洋に対する国民の関心が高まる中で、このような問題は極めて憂慮すべきことであり、今や皆さんが海洋国家日本を考える上で、身近な問題として捉えられていると思っております。
海からの多くの恩恵の主なものには、経済活動として漁業、海底資源、海上輸送、マリンレジャーなどがあります。
輸送活動を見れば、
わが国の海上貿易量 約9億4999万トンは世界の約14パーセント
国際貨物の約71パーセント(金額ベース)
約99パーセント(重量ベース)が海上を利用
食料の約60パーセントを輸入に依存
エネルギーの約90パーセントを輸入に依存など
日本の海が国民生活に密着していることがわかります。
豊かな恵みを受ける海も、一方では世界でも屈指の厳しい海洋気象の海でもあります。皆様は、春一番、夏から秋の台風、冬の大陸からの季節風によって起きる海難のニュースに頻繁に接しております。
恩恵を受ける海と、国民が生活する領土との関係については、わが国の
領土の面積 約38万平方km 世界第61位
領海の面積 約43万平方km
領海・排他的経済水域の面積 約447万平方km(領土の12倍) 世界第6位
体積 約1,580万立方km 世界第4位
海岸線の延長 約3.5万km 世界第6位
国の面積当たりの海岸線延長 約92m/平方km 世界第1位
国の人口当たりの海岸線延長 約27m/百人 世界第1位
となっております。
つまり、わが国は、世界でも有数の広くて深くて海岸線の長い海に取り囲まれている訳です。
この海の利用については、国連海洋法条約によって、領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通行に関する様々の取り決めがなされています。
国連海洋法条約は、H6年発効、平成16年に145カ国が批准しました。
我が国は、領海12海里を採用。(領海及び接続水域に関する法律第1条)
・領海の地位は
沿岸国の主権が上空(領空)、海底、海底の下まで及び生物・鉱物資源の採取に独占権。完全な主権が及ぶ内水とは異なり、沿岸国の平和、秩序、安全を害さない限り無害通航権あり。
・排他的経済水域200海里(限定的、機能的な管轄権)
天然資源の探査・開発等に関する主権的権利。科学的調査に関する管轄権。海洋環
境の保護・保全。
などについて取り決められています。
このような環境の下、わが国周辺の海洋を巡る諸問題として、
尖閣諸島、北方領土、竹島の周辺海域警備
排他的経済水域内の外国海洋調査船監視
外国漁船不法操業取締り
東シナ海エネルギー資源開発
東南アジア航路の海賊対策
不審船・工作船警備等があります。
これらの諸問題について、海上保安庁がどのような業務を行っているか、事例を加えながら紹介します。
尖閣諸島領海警備
尖閣諸島は、沖縄群島西南西の東シナ海に位置し、魚釣島、南小島、北小島など5つの島と3つの岩礁からなり、魚釣島からは、石垣島まで170km、沖縄本島まで410km、台湾まで170km、中国大陸まで330kmの距離があります。この帰属については、日本はわが国の領土であるとして、問題としていませんが、昭和46年以降、中国、台湾が領有権を公式に主張し始めました。それは、昭和43年日本、韓国、台湾の海洋専門家が国連アジア極東経済委員会の協力を得て、東シナ海海底の学術調査を行った結果、東シナ海の大陸棚には、豊富な石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘されたためです。さらに、平成8年7月に国連海洋法条約がわが国について発効し、排他的経済水域が設定されたことに伴い、台湾・香港等で漁業活動への影響が生じたことに対する不満や、北小島に日本の政治団体が灯台としての構築物を設置したことを背景に、「保釣活動」と呼ばれる領有権主張活動が活発となり、尖閣諸島周辺の領海に侵入するなどの大規模な活動が行われる様になりました。近年では、中国において新たな活動団体が台頭し、急激に勢力を拡大し、領有権主張活動を展開しています。平成16年には、巡視船の間隙を縫って中国人活動家7名が魚釣島に不法上陸する事案が発生しました。18年には、台湾と香港から活動家の乗った船が出港し領海内へ不法侵入しました。
海上保安庁は巡視船等の部隊を派遣し、関係省庁とも協力して警備し、島への上陸を阻止しています。
尖閣諸島は、遠隔地の上、台風の常襲海域という地理的条件にあり、かつ付近に巡視船艇の避難港、補給港が無いため、大規模な警備を行うには、全管区から巡視船艇・航空機を長期に亘り派遣する体制をとらざるを得ないこと、巡視船隊が活動家の船舶を規制・退去させる際に、荒れる海上で巡視船と活動家船舶が衝突・接触した場合には、小さな活動家船舶が大きなダメージを受ける可能性が大きいため、双方に人身事故が起きないように慎重な規制をする必要があることなどから、尖閣諸島領海警備は、極めて大規模、かつ慎重な体制で行うことになります。海上保安庁は、政府方針に基づき常時周辺海域に巡視船を配備し、航空機による哨戒を行っていますが更に警備体制を磐石とするため、新しい巡視船の整備などを進めています。