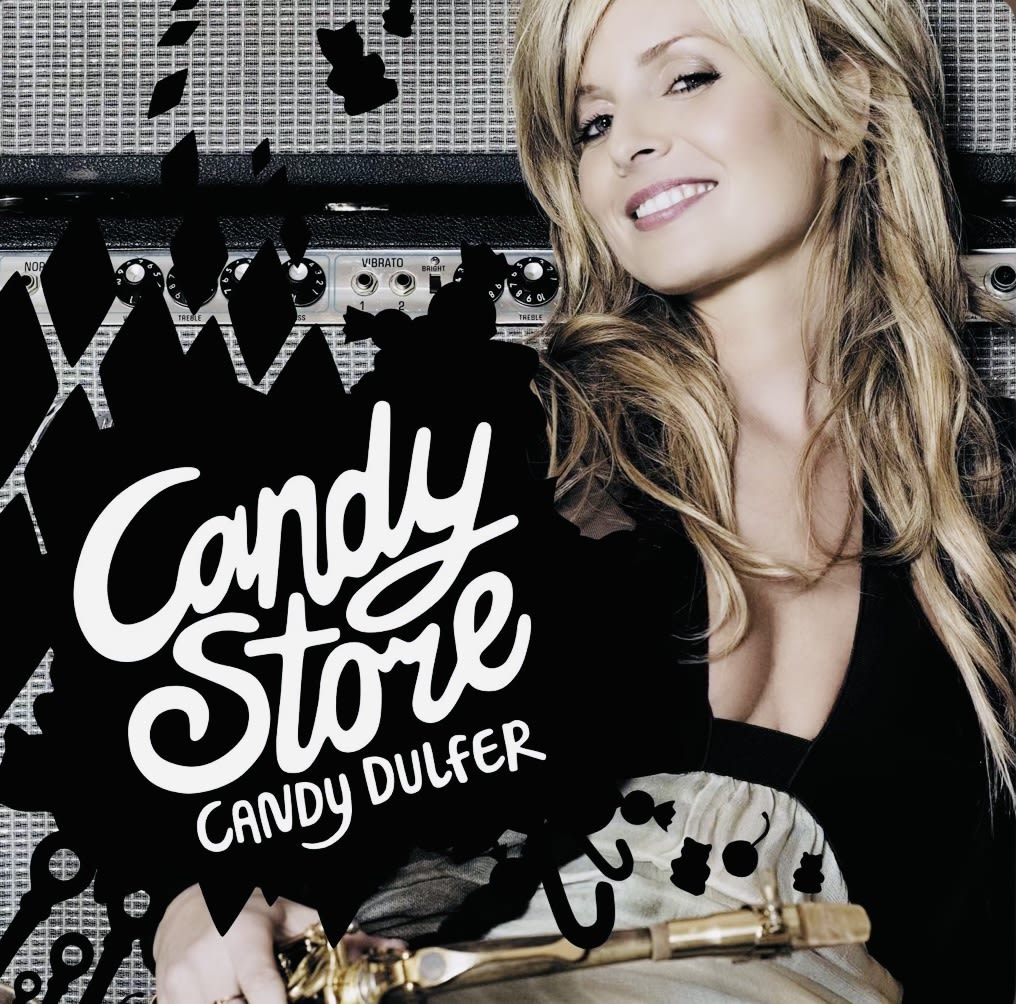最果タヒ・著「十代に共感する奴はみんな嘘つき」
書籍『最果タヒ・著「十代に共感する奴はみんな嘘つき」』について
(2019年5月10日第1刷・文春文庫より発行。)
<著者について(本書より)>
最果タヒ(さいはて・たひ)
1986年、兵庫県神戸市生まれ。2006年、現代詩手帳賞を受賞。07年、詩集『グッドモーニング』を刊行。同作で08年に中原中也賞を受賞。15年、『死んでしまう系のぼくらに』で現代詩花椿賞を受賞。著作に、詩集『空が分裂する』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』、小説『星が獣になる季節』『少女ABCDEFGHIJKLMN』、エッセイ集『きみの言い訳は最高の芸術』『百人一首という感情』などがある。清川あさみとの共著『千年後の百人一首』では百首を現代語に訳した。
<本書について(本書より)>
女子高生の唐坂和葉は17歳。隣のクラスの沢くんへの告白の返事は「まあいいよ。」いつもヘッドフォンをつけていて「ハブられている」クラスメイトの初岡と、沢の会話を聞きながら、いろいろ考える。いじめのこと、恋愛のこと、家族のこと。十代のめまぐるしく変化する日常と感情と思考を、圧倒的な文体で語る新感覚の小説。
◯心地よいスピード感に触れる
詩人、最果タヒのこの一風変わった小説のタイトルに惹かれつい読んでしまったが、女子高生の日常を覗き見るような大人感覚ではやはり太刀打ちできない。それは著者の詩人としての感性(こんなことを書くこと自体不自然)から生まれた当然の帰結だ。脳が柔らかく力んだ結果、スラスラとこのような作品を誕生させるのだろう。読後感は誠に素直である。もっと読んでいたかったという気にさせられる。
話の主題は“いじめ”。彼女・主人公の考えは淡々と展開しながら進んでいく。共感してたまるかと心に決めて読み進めるが、共感することばかりなので失速することなく話につられて脳のどこかが追随していく。それにしてもこの終わりのない詩のような文章のスピード感が心地よく、頭の中でくるくると他人ごとのような思い出までもが息を吹き返してくることに待ったをかけることができない。待ったをかけたが最後、したり顔で共感する嘘つきになってしまうだろうから。
◯素直な言葉の応酬
まずは冒頭に主人公による自分の分析がある。主人公の珠玉のような言葉の数々の一例でしかないが、たとえば「(引用)かわいそうな人のためにしか芸術がないから、かわいそうな人がかわいそうぶっている世界が嫌いです。音楽に救われたって言っている子に永遠に勝てない。」「(引用)かわいそうだったり、モテたかったり、世界への違和感をいだいていたりすると、アーティスティックだからうらやましい。」「(引用)私は私の感性を守りたいとかそんなことは思わないけど、とにかく私の感情は私だけのもので、そして私はそれを守らず捨てていく。」
◯“いじめ”について
続いてこの小説のテーマでもあるいじめについて、異論はあるだろうが油断すると共感してしまいそうになる。「(引用)ヘッドフォンの彼女は最後の机を並べ直して、自分が掃いたゴミを自分で回収し、ゴミ箱に捨てた。いじめなんていうのはくだらないからこの学校では起こらないっていうのが保護者の認識で、生徒の認識で、っていうか生徒は多分彼女をハブろうなんて思ってなくてただ掃除をさぼったら、彼女だけがさぼらなかったっていうだけなんだろうけれど、彼女はいじめられていると思っても私にもろくに話しかけずにヘッドフォンをつけて、音楽だけが友達と思っていて、私と同じミュージシャンのファンだったとしたらきっと彼女はそのミュージシャンに救われたと言って、この人がいなくなったら生きていけないとか簡単に言えて、私はいや生きるしって思う。」主人公のハブられることに対する認識はそれほど深刻ではない。が、周りと感じていることの違いにうんざりしてしまう。たとえば特に仲が良いわけではないが、学校帰りの駅のホームでいっしょに食べる「(引用)団子が美味しいから私は彼女たちと一緒にいるのが楽しかった。共感だとかそういうものは知ったこっちゃないけど、おいしいものはおいしいし、それだけで場はもつ。」いじめられていることを弱みとして体現するか否かが問題だと提起する。ストーリー的にはここから山場だが、これ以上、内容について深く触れるとあらすじを追うようになってしまうので端折る。
◯“かわいそう”であること
主人公の兄の友人・三井と、“かわいそう”と他人から思われていることを自覚している可能性がある同じクラスの女子高生・初岡の会話に苛立つ主人公。三井は主人公を救うため一緒にいたはずなのに、初めて会った初岡がバンドをやっているという話を聞いて興味を示す。果たして主人公は“いじめ”と“かわいそう”の関係について次のようにさらりと考える。「(引用)三井がもてなしているのが遠い世界の出来事みたいだ。なんでみんなそんなふうに、あっさり他人と仲良くなれるんですか。そいつが最低な人間である可能性とか、自分を殺したいと思っている可能性とかどうして考えないんですか。平和主義ですか。私は今全員大嫌いです。全員殺したい。誰も気づいていないことにいらつきますよ。死ねよ。」なんのためにいじめられたのか、苛立つ主人公の気持ちを示している表現が大変良くて読者として共感を示したくなる。兄の友人・三井に奢ってもらったイチゴパフェを食べながら「(引用)いちごをパフェの底まで沈めて、かき混ぜてどんどんまずくしていくんだ。何にも言えない。家出も、パフェ食べてるだけじゃん。かわいそうぶってるってみんなに言われておしまいだ。初岡だってもう私に興味ないし、三井の不幸に興味津々。」結局、主人公は何も変わっていないしかわいそうという自覚もないのに、周りの勝手な思いや言葉の波に揺れる。
◯話はこうして終わっていくのだが
著者のあとがきには十代の頃の自分について本人の考えが示されている。タイトルの〝みんな嘘つき〟の一人にならないためにこの内容をヒントとして記載しておく。「(引用)過去のきみは、きみの所有物ではない。当たり前のそんなことを忘れてしまう。10代の私のことを私は、一つも理解できていない。そう思っていなければあの頃の私があまりにもかわいそうだ。懐かしさという言葉ですべてをあいまいにして、そしてわかったつもりになるなら、それは自分への冒涜だって、気付かなければならない。」
この本、時間の流れや表現の気持ちよさ面白さに翻弄される本だ。詩だと思って読んでも良い。現代詩手帖の詩にも選ばれた最果タヒはいけてるのでそのまま味わうことができる。たとえば2019年に発行された詩集「恋人たちはせーので光る」はかっこよくて、「十代に共感する奴はみんな嘘つき」の延長にあり、いまという時が駆け足で通り過ぎようとするので待ってくれと何度でも読み返したくなる。

(おわり)