瓦火桶と云物、京都に多し。
桐火桶の製に似て大なり。
瓦にて作る。
高さ五寸四分、足は此外也。
縦のわたり八寸三分、横のわたり七寸、縦横少(し)長短あるべし。
或(は)形まるくして、縦横なきもよし。
上の形まるき事、桐火桶のごとし。
めぐりにすかしまどありて、火気をもらすべし。
上に口あり、ふたあり。
ふたの広さ、よこ三寸、たて三寸余なるべし。
まるきもよし。
ふたに取手あり。
ふた二三の内、一は取手なきがよし。
やはらかなる灰を入置(いれおき)、用ゐんとする時、宵より小なる炭火を二三入て臥さむとする前より、早く衾(ふすま)の下に置、ふして後、足をのべてあたゝむべし。
上気する人は、早く遠ざくべし。
足あたゝまらば火桶を足にてふみ退け、足を引てかゞめふすべし。
翌朝おきんとする時、又足をのべてあたたむべし。
又、ふたの熱きを木綿袋に入て、腹と腰をあたゝむ。
ふた二三こしらへ置、とりかへて腹、腰をあたゝむべし。
取手なきふたを以ては、こしをあたゝむ。こしの下にしくべし。
温石(おんじゃく)より速(すみやか)に熱くなりて自由なり。
急用に備ふべし。
腹中の食滞気滞をめぐらして、消化しやすき事、温石并(ならびに)薬力よりはやし。
甚(はなはだ)要用の物なり。
此事しれる人すくなし。
・瓦火桶という、粘土を焼いて作った物が京都ではよく使われる。
・柔らかな灰を入れておき、使う時は日暮れから小さな炭火を2、3個入れ、寝るとき布団の中に入れて足を温める。
・のぼせやすい人は、早く布団から出すと良い。
・足が温まったら、火桶は足で布団の隅に押しやっておく。
・翌朝、起きる前に再び足を伸ばして火桶で温めると快適。
・また、熱くなった蓋を木綿袋にいれて腹と腰を温めるのも効果がある。
・消化不良や気の滞りを解消するのは薬より早い。
・これを知っている人は少ない。
火桶は流石に現代で使う人はあまりいないと思われます。
湯たんぽ、に置き換えると今でもできそうですね。
・赤ちゃんの手足が温かいと「もう眠たいんだなぁ〜」
と子育てをしたことがある方は、経験があると思います。
大人になっても、
・副交感神経が優位
になると、手先足先の毛細血管が拡張し、血液が流れるため手足が温かくなる。
逆に、手足が冷たく、毛細血管がキュ〜っと収縮した状態は
・交感神経優位
で戦闘モード、リラックス状態ではないので眠りにつきにくい。
・手足が温まり、熱が放出
・体幹の温度が下がると、眠りにつける
だから、ある程度足が温まったら、湯たんぽは遠ざけないと熱が放出されないため体感温度は下がらない。よって、
・足が温まったら、火桶(湯たんぽ)は足で布団の隅に押しやっておく
私は、寝る前のストレッチが習慣になっていますが、ストレッチをしているとだんだん手足が温まってきます(リラックス〜)
・温まった手をお腹に置いて深呼吸を繰り返す
と、とっても気持ちがいいです。
・眠くなり
・胃腸も動く感じ
寒くなってきたこの時期は
・腹巻
も良さそうですね。
・良質な睡眠
・腹腰を温める(腸内細菌もぬくぬくと育ちそう〜)
ことで免疫力が上がりそうな感じがします。
最後まで読んで頂いて有難うございます。
よろしければ下の応援クリックお願いします。















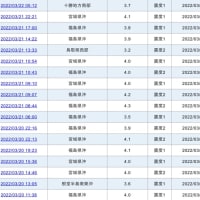



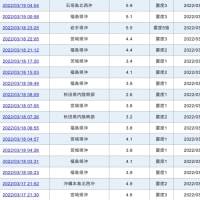
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます