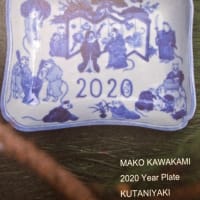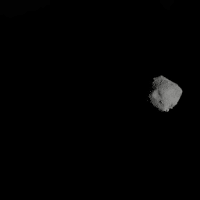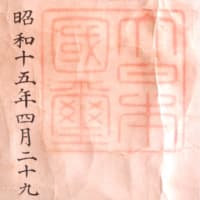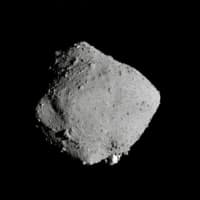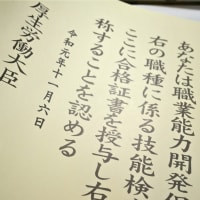TVではじめて放映されるとき。すべてが唐突にはじまるので、世界観を知るための準備なんて誰にもできなかったはず。画面に出てくること以上の情報はないわけだから、「エヴァ」にしたって視聴者はいきなり「エヴァ」の世界にポンッと投げ込まれる。現在に至るまでにいろんな話が飛び交って、時代が進んで、また復活して。。。という具合に、すでにたくさんの情報が積み重なっているけれど、情報なしでいきなり目に焼き付いてしまった衝撃からはずいぶん遠く離れてしまったようにも思います。売れすぎてしまった作品のゆえですよね。
でも、作っている側には放映前に相当周到な準備があったであろうと。観ていくに従って、情報が説明なしに絡み合っていくので、目の前のストーリーを追いかけるのに手一杯。だけど、ある一定の話までは予定調和的にどんどん話が展開していくわけで。。。僕なんかは10年乗り遅れているくせにやっぱり「うまいことはめられた」。
あとから見返してみれば、ハッと気付くこともある。そもそも、環境設定にはぬかりないプログラム。主題歌にはこの作品の目的がたからかに歌い上げられていたりする。「少年よ神話になれ♪」だものね。そのうちに一種の宣言にも聞こえてきたりする。つまりは最初から「神話」を目指していた、っていう風に考えられるのです。
難解な設定に、一度聞いただけでは意味不明な用語など、ひたすら繰り返し観られることに耐えられる環境設定も「うまくはめられた」っていうことの要素になっていて、謎解きのおもしろさもある。人によって違う見方っていうのを可能にしているのは、「説明不足」の部分というよりは意図的な「説明放棄」の部分。ごろっと無造作に目の前に転がしておいて「ほうら、見えているでしょ」っていうような。それは例えば登場人物の「名前」だったりするのかも?
ネーミング、名付けることの意味がこれほど物語の世界観に貢献し、成功している例は、アニメには他にないように思うのです。同時に、それは引用先や参照元を隠すことができないっていう意味にもなるはず。引用、借用のタグがあからさまにぶら下がっている。今回はちょっとそいつを追いかけてみようかと。
執拗なまでに「がんじがらめ」な世界観は、役割を持って名付けられた登場人物の設定がうまく行き過ぎたからと言っても差し支えないように思います。神話的な「必然性」を導入するためには、環境設定にも周到な準備がなされた、と見た方がおもしろい。「気分で決めた」とか?「好きだから」とか?そういうのはないと、完全に否定することはできないかもしれないけれど、「気分」と「好み」だけであれだけの世界観を構築できるって考える方にムリがある。「好き」「嫌い」で出来上がった程度の設定では、世界観はおろか、第三新東京市だって、ネルフだって、肝心なエヴァだって起動しないんじゃないか?
この際、シンクロ率ではなくて、「どの必然性とシンクロしているのか?」っていうことがエヴァに設定された環境(=世界観)を開く鍵になるのではないかと。
たとえば「碇」司令。
「碇」を名乗る前は「六分儀」という姓だったというエピソードがあるけれど、このことは示唆的です。うまいネーミングだなぁって。外洋を「航海」するには欠かせない計測器が彼の元々の姓であったことになりますが、「碇ユイ」という女性と結婚してその姓を戴くことになったのは、即ち、すでに目的地にたどり着いているということを示してはいないか?ということが言えるからです。必然的に彼にはもう「六分儀」は必要ないことになります。すでに「航海」を終えてしまっているのだから。

「帝国海軍」や「宇宙戦艦ヤマト」、「ふしぎの海のナディア」のパロディとして、何かを象徴するために彼が「司令」として登場するなら、その頭には艦長にふさわしい帽子が与えられていても良さそうなものです。「ナディア」では「ノーチラス号」の「ネモ船長」は帽子を冠っていた。ちょうどあんな感じで「碇」司令が帽子をかぶっていたら。。。その帽子には「船長」「艦長」を象徴する「錨」のエンブレムがくっついているはずだから、見た目はそんなに問題にはならいようにも思える。でも、碇司令は髭をたくわえてはいても、帽子はかぶっていない。もし「ジオフロント」や「ネルフ」が飛び立つことができる「宇宙船」かなにかだったら、「帽子をかぶる」っていうことがひとつのシーンになっていたかもしれないけど。冠ってしまうとちょっと具合がよくない、と考えられたからかもしれません。「碇」の表記は「錨」であっても「𨦈」「イカリ」であっても、どれでもよかったはず。そうはならず「碇」。なぜ?
航海を終えてしまった「碇」には、なにか別の、もっと外の概念世界に連結しうる論理素子として機能する必要があったからじゃないのか?神話的世界を再構築するため、それに十分足りる「記号」=「名前」として。
艦船の「錨」のようにではなく、もっと古い時代の方法、あるいはもっと原始的な方法で碇泊させる。「石」で位置を「定める」類いの舟に用意されていた「碇」。それは言い換えれば、アンカーAnchorの意味か?シンカーSinkerの意味であるか?の違いでもある。この違いは与えられた性格や役割に影響するはずなので、注意深く選択されている、と考えた方がおもしろい。
Sinkerには主に「錘り(おもり)」としての意味があるけれど、Sinkする人という意味にあてはめれば、さらに象徴性を増します。彼は「六分儀」に象徴される水平線を捨てて、「碇」に象徴される深さを目指すことになるからです。Sinkする、あるいはSinkさせるという役割。
「新世紀エヴァンゲリオン」=「新世紀福音書」ということであるなら、オリジナルの福音書に触れないわけにはいかないのですが、ここではどこまでも表層的に人の名前にこだわってみるつもり。
福音書で人を漁(すなど)る者としてイエスに指名された男、シモン・ペテロがいます。
「マタイによる福音書」
4:18さて、イエスがガリラヤの海べを歩いておられると、ふたりの兄弟、
すなわち、ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが、
海に網を打っているのをごらんになった。彼らは漁師であった。
4:19イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。
あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。
4:20すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。
4:21そこから進んで行かれると、ほかのふたりの兄弟、
すなわち、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、
父ゼベダイと一緒に、舟の中で網を繕っているのをごらんになった。
そこで彼らをお招きになると、
4:22すぐ舟と父とをおいて、イエスに従って行った。
マルコによる福音書
1:16さて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、
シモンとシモンの兄弟アンデレとが、海で網を打っているのを
ごらんになった。彼らは漁師であった。
1:17イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。
あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。
1:18すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。
1:19また少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、
舟の中で網を繕っているのをごらんになった。
1:20そこで、すぐ彼らをお招きになると、父ゼベダイを雇人たちと
一緒に舟において、イエスのあとについて行った。
同じ出来事を複数の福音書が別の角度から書いているというのは、共観福音書のあり方の大きな特徴。ここではまったく同じような文章で描写されています。「エヴァンゲリオン」の「風景」をフィルターにして福音書をのぞいてみると、ちょっと気になる「風景」が現れてきます。
シモン・ペテロがイエスにいわば指名を受けて従うのは「ガラリヤの海」「海べ」とあります。
パレスチナにあるガラリヤの海。ここは淡水の湖で、シモン・ペテロは舟で漕ぎだしていって魚を網でとる漁師さんだったことが書かれています。「舟」は、このblogでは重大な関心事。そこに「碇」があったか?なかったか?はいまのところ福音書には現れてきません。ですが、そこが淡水の「湖」であり「水辺」であることは、「エヴァ」の風景を通してみれば見逃すことはできません。それから、「舟」をおいていくところも。
このシモン・ペテロが新約聖書における第一使徒。つまりはイエス最初のお弟子さんということになります。
「碇」の文字を念頭に置いて、もう少し福音書をのぞいてみましょう。
マタイによる福音書
16:18そこで、わたしもあなたに言う。
あなたはペテロ(ケファ=岩=石)である。
そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。
黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。
16:19わたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。
そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、
あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう」。
シモン・ペテロが「岩」「石」を意味するアラム語の「ケファ」という名前で呼ばれていたことは、新約聖書におおく見いだすことができます。この「ペテロ=岩=石」を、ローマ・カトリックでは初代教皇と見なしていますが、イエスが「この岩(ペテロ)の上に教会を建てよう」と言ったことの成就として、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂の存在があるからです。歴代教皇が眠る地下墓所の更に下、最も深いところで初代教皇ペテロの遺骨が発見されたという話があります。
「エヴァ」に即して「碇」の姓に見いだせる表層的な記号だけをみると、ペテロにゆだねられた「天国のかぎ」と、「ペテロの上に教会を建てよう」という言葉には注意が必要な雰囲気です。
「石」に「定」められた場所=ペテロの上に建つ教会。
「新世紀福音書」でなにが成就されるのか?僕には実のところよくわからないのですが、「碇」を「ペテロ」にだぶらせることにはムリがないように思えます。ダブルドイメージに耐えうる。「碇」に複数の意味をあずけることができるということを「エヴァ」で発見した人がいる。複数の神話、宗教を繋ぎうる象徴的な名前の発見があったんじゃないか?
まぁ、全部推測なんだけどね。。。乱暴に書けるって楽しい。
作った本人に「いいえ、違います」って言われれば、それで一発撃沈なんだけど、これくらいのことはサラッとやってるんだと思うんですよ。
最大の決め手は、「碇」が「記紀」の記述される「井光」「井氷鹿」(いひか)につながることだと僕は思っています。意識的に使用したとするなら(。。。僕にはそうとしか考えられないのですけど)、古事記につながる回路、神武天皇東征の物語やヤマトタケルの物語へと繋がる意味の抜け穴をちゃんと用意していた、という証拠にもなりそう。「記紀」にもあたっていたというウルトラマンやゴジラからの影響の指摘もありますが、それにしたって古事記そのものにあたらないとそうはならないんじゃないか?っていうことが山ほどあるものですから。ですが、これをまともに追いかけると本居宣長、平田篤胤、矢野玄道に続く国学者の系譜にも言及もしなくちゃいけない。
うわぁ、それってホントかなぁ?
上っ面だけなめるにしても長くなりそうなので、それはまた次回に。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(2)
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(2)
でも、作っている側には放映前に相当周到な準備があったであろうと。観ていくに従って、情報が説明なしに絡み合っていくので、目の前のストーリーを追いかけるのに手一杯。だけど、ある一定の話までは予定調和的にどんどん話が展開していくわけで。。。僕なんかは10年乗り遅れているくせにやっぱり「うまいことはめられた」。
あとから見返してみれば、ハッと気付くこともある。そもそも、環境設定にはぬかりないプログラム。主題歌にはこの作品の目的がたからかに歌い上げられていたりする。「少年よ神話になれ♪」だものね。そのうちに一種の宣言にも聞こえてきたりする。つまりは最初から「神話」を目指していた、っていう風に考えられるのです。
難解な設定に、一度聞いただけでは意味不明な用語など、ひたすら繰り返し観られることに耐えられる環境設定も「うまくはめられた」っていうことの要素になっていて、謎解きのおもしろさもある。人によって違う見方っていうのを可能にしているのは、「説明不足」の部分というよりは意図的な「説明放棄」の部分。ごろっと無造作に目の前に転がしておいて「ほうら、見えているでしょ」っていうような。それは例えば登場人物の「名前」だったりするのかも?
ネーミング、名付けることの意味がこれほど物語の世界観に貢献し、成功している例は、アニメには他にないように思うのです。同時に、それは引用先や参照元を隠すことができないっていう意味にもなるはず。引用、借用のタグがあからさまにぶら下がっている。今回はちょっとそいつを追いかけてみようかと。
執拗なまでに「がんじがらめ」な世界観は、役割を持って名付けられた登場人物の設定がうまく行き過ぎたからと言っても差し支えないように思います。神話的な「必然性」を導入するためには、環境設定にも周到な準備がなされた、と見た方がおもしろい。「気分で決めた」とか?「好きだから」とか?そういうのはないと、完全に否定することはできないかもしれないけれど、「気分」と「好み」だけであれだけの世界観を構築できるって考える方にムリがある。「好き」「嫌い」で出来上がった程度の設定では、世界観はおろか、第三新東京市だって、ネルフだって、肝心なエヴァだって起動しないんじゃないか?
この際、シンクロ率ではなくて、「どの必然性とシンクロしているのか?」っていうことがエヴァに設定された環境(=世界観)を開く鍵になるのではないかと。
たとえば「碇」司令。
「碇」を名乗る前は「六分儀」という姓だったというエピソードがあるけれど、このことは示唆的です。うまいネーミングだなぁって。外洋を「航海」するには欠かせない計測器が彼の元々の姓であったことになりますが、「碇ユイ」という女性と結婚してその姓を戴くことになったのは、即ち、すでに目的地にたどり着いているということを示してはいないか?ということが言えるからです。必然的に彼にはもう「六分儀」は必要ないことになります。すでに「航海」を終えてしまっているのだから。

「帝国海軍」や「宇宙戦艦ヤマト」、「ふしぎの海のナディア」のパロディとして、何かを象徴するために彼が「司令」として登場するなら、その頭には艦長にふさわしい帽子が与えられていても良さそうなものです。「ナディア」では「ノーチラス号」の「ネモ船長」は帽子を冠っていた。ちょうどあんな感じで「碇」司令が帽子をかぶっていたら。。。その帽子には「船長」「艦長」を象徴する「錨」のエンブレムがくっついているはずだから、見た目はそんなに問題にはならいようにも思える。でも、碇司令は髭をたくわえてはいても、帽子はかぶっていない。もし「ジオフロント」や「ネルフ」が飛び立つことができる「宇宙船」かなにかだったら、「帽子をかぶる」っていうことがひとつのシーンになっていたかもしれないけど。冠ってしまうとちょっと具合がよくない、と考えられたからかもしれません。「碇」の表記は「錨」であっても「𨦈」「イカリ」であっても、どれでもよかったはず。そうはならず「碇」。なぜ?
航海を終えてしまった「碇」には、なにか別の、もっと外の概念世界に連結しうる論理素子として機能する必要があったからじゃないのか?神話的世界を再構築するため、それに十分足りる「記号」=「名前」として。
艦船の「錨」のようにではなく、もっと古い時代の方法、あるいはもっと原始的な方法で碇泊させる。「石」で位置を「定める」類いの舟に用意されていた「碇」。それは言い換えれば、アンカーAnchorの意味か?シンカーSinkerの意味であるか?の違いでもある。この違いは与えられた性格や役割に影響するはずなので、注意深く選択されている、と考えた方がおもしろい。
Sinkerには主に「錘り(おもり)」としての意味があるけれど、Sinkする人という意味にあてはめれば、さらに象徴性を増します。彼は「六分儀」に象徴される水平線を捨てて、「碇」に象徴される深さを目指すことになるからです。Sinkする、あるいはSinkさせるという役割。
「新世紀エヴァンゲリオン」=「新世紀福音書」ということであるなら、オリジナルの福音書に触れないわけにはいかないのですが、ここではどこまでも表層的に人の名前にこだわってみるつもり。
福音書で人を漁(すなど)る者としてイエスに指名された男、シモン・ペテロがいます。
「マタイによる福音書」
4:18さて、イエスがガリラヤの海べを歩いておられると、ふたりの兄弟、
すなわち、ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが、
海に網を打っているのをごらんになった。彼らは漁師であった。
4:19イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。
あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。
4:20すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。
4:21そこから進んで行かれると、ほかのふたりの兄弟、
すなわち、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、
父ゼベダイと一緒に、舟の中で網を繕っているのをごらんになった。
そこで彼らをお招きになると、
4:22すぐ舟と父とをおいて、イエスに従って行った。
マルコによる福音書
1:16さて、イエスはガリラヤの海べを歩いて行かれ、
シモンとシモンの兄弟アンデレとが、海で網を打っているのを
ごらんになった。彼らは漁師であった。
1:17イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。
あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。
1:18すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。
1:19また少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、
舟の中で網を繕っているのをごらんになった。
1:20そこで、すぐ彼らをお招きになると、父ゼベダイを雇人たちと
一緒に舟において、イエスのあとについて行った。
同じ出来事を複数の福音書が別の角度から書いているというのは、共観福音書のあり方の大きな特徴。ここではまったく同じような文章で描写されています。「エヴァンゲリオン」の「風景」をフィルターにして福音書をのぞいてみると、ちょっと気になる「風景」が現れてきます。
シモン・ペテロがイエスにいわば指名を受けて従うのは「ガラリヤの海」「海べ」とあります。
パレスチナにあるガラリヤの海。ここは淡水の湖で、シモン・ペテロは舟で漕ぎだしていって魚を網でとる漁師さんだったことが書かれています。「舟」は、このblogでは重大な関心事。そこに「碇」があったか?なかったか?はいまのところ福音書には現れてきません。ですが、そこが淡水の「湖」であり「水辺」であることは、「エヴァ」の風景を通してみれば見逃すことはできません。それから、「舟」をおいていくところも。
このシモン・ペテロが新約聖書における第一使徒。つまりはイエス最初のお弟子さんということになります。
「碇」の文字を念頭に置いて、もう少し福音書をのぞいてみましょう。
マタイによる福音書
16:18そこで、わたしもあなたに言う。
あなたはペテロ(ケファ=岩=石)である。
そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。
黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。
16:19わたしは、あなたに天国のかぎを授けよう。
そして、あなたが地上でつなぐことは、天でもつながれ、
あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう」。
シモン・ペテロが「岩」「石」を意味するアラム語の「ケファ」という名前で呼ばれていたことは、新約聖書におおく見いだすことができます。この「ペテロ=岩=石」を、ローマ・カトリックでは初代教皇と見なしていますが、イエスが「この岩(ペテロ)の上に教会を建てよう」と言ったことの成就として、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂の存在があるからです。歴代教皇が眠る地下墓所の更に下、最も深いところで初代教皇ペテロの遺骨が発見されたという話があります。
「エヴァ」に即して「碇」の姓に見いだせる表層的な記号だけをみると、ペテロにゆだねられた「天国のかぎ」と、「ペテロの上に教会を建てよう」という言葉には注意が必要な雰囲気です。
「石」に「定」められた場所=ペテロの上に建つ教会。
「新世紀福音書」でなにが成就されるのか?僕には実のところよくわからないのですが、「碇」を「ペテロ」にだぶらせることにはムリがないように思えます。ダブルドイメージに耐えうる。「碇」に複数の意味をあずけることができるということを「エヴァ」で発見した人がいる。複数の神話、宗教を繋ぎうる象徴的な名前の発見があったんじゃないか?
まぁ、全部推測なんだけどね。。。乱暴に書けるって楽しい。
作った本人に「いいえ、違います」って言われれば、それで一発撃沈なんだけど、これくらいのことはサラッとやってるんだと思うんですよ。
最大の決め手は、「碇」が「記紀」の記述される「井光」「井氷鹿」(いひか)につながることだと僕は思っています。意識的に使用したとするなら(。。。僕にはそうとしか考えられないのですけど)、古事記につながる回路、神武天皇東征の物語やヤマトタケルの物語へと繋がる意味の抜け穴をちゃんと用意していた、という証拠にもなりそう。「記紀」にもあたっていたというウルトラマンやゴジラからの影響の指摘もありますが、それにしたって古事記そのものにあたらないとそうはならないんじゃないか?っていうことが山ほどあるものですから。ですが、これをまともに追いかけると本居宣長、平田篤胤、矢野玄道に続く国学者の系譜にも言及もしなくちゃいけない。
うわぁ、それってホントかなぁ?
上っ面だけなめるにしても長くなりそうなので、それはまた次回に。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(2)
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(2)