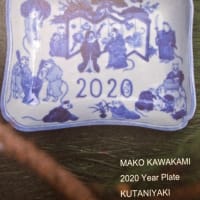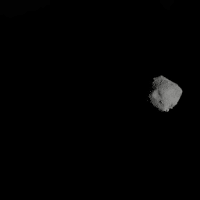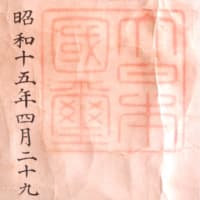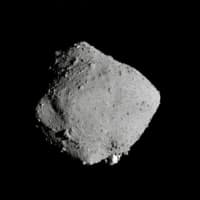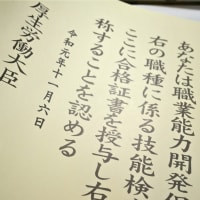御殿場によく行くようになったこともあるけれど、このごろなんで「御殿場」という地名になったのか?ちょこっと気になりはじめたので、調べたりしていました。御殿場の地名は比較的新しいもので、東照大権現、徳川家康に由来しています。それ以前は、伊勢神宮の荘園として「御厨」(みくりや)と呼ばれていたそうです。
ではそれ以前はなんと呼ばれていたのか?
何の気なしに読んでいた本で知ったのですが、御殿場の地名の由来となった御殿の跡に建つ神社あたりは「吾妻原」(あづまはら)とも呼ばれていたのだとか。古事記にならってる?
吾妻は東の語源とも言われます。
「阿豆麻」→「吾妻」→「東」
知っている人には常識かも?だけど、足柄山や箱根、富士山などを眺めて育った僕なんぞには、そこが「古事記」の世界から続く場所だなんてピンと来なかったりします。京都や奈良ほどに、目に見えるわかりやすい手がかりがあれば、それについて何か具体的なことを言えそうなものですが、神話的人物がほんの少し立ち寄った、という記述だけが支えている事実ですから、それ以上に何かをいえるか?というと、どうも。見た目「わかりやすい」っていうわけではないけれど、それでも「ヤマトタケルノミコト」の足跡はここかしこに遺されているようです。
御殿場というのはこちらからすると足柄山の向こう側にあるわけですが、反対側のふもとも足柄山の一面をつくっているという当たり前のことも、東名高速でサァーッと迂回してしまうとあまりよくわからない。僕はだいぶまわり道をして、ここがもう一方の足柄山であったことを知ることになりました。
足柄古道は万葉集にもとりあげられているので、その重要性についてはだいぶ昔から認識されていたことは確かなようです。ヤマトタケルノミコトの東征もそうだし、平安末期にもこの道を重要な情報を持った人が行き来していた。たとえば、源頼朝に挙兵を促したとされる文覚上人などは頻繁にこの道を何度も何度も行き来しています。南北朝の戦いもこの地でひとつの戦局を迎えていたりして、受験勉強の年表では気配さえ出てこないけれど、北朝方がとある山城を2年もの間取り囲んでいたこともあります。
江戸時代に東海道が整備されるようになるまでは、箱根越えをするよりは足柄古道を往くのがあたりまえだったりしたのです。
ところで、「古事記」で「草薙の剣」がヤマトタケルノミコトに手渡され、それが窮地を切り抜けるときに抜かれる場面。そこでの記述は、僕には気になるくらい大雑把なのです。
そしてまもなく相模の国へお着きになりました。
するとそこの国造が、命をお殺し申そうとたくらんで、
「あすこの野中に大きな沼がございます。その沼の中に住んでおります神が、
まことに乱暴なやつで、みんな困っております」と、おだまし申しました。
命はそれをまにお受けになって、その野原の中へはいっておいでになりますと、
国造は、ふいにその野へ火をつけて、どんどん四方から焼きたてました。
命ははじめて、あいつにだまされたかとお気づきになりました。
その間にも火はどんどんま近に迫って来て、お身が危くなりました。
命はおんおば上のおおせを思い出して、急いで、
例の袋のひもをといてご覧になりますと、中には火打がはいっておりました。
命はそれで、急いでお宝物の御剣を抜いて、
あたりの草をどんどんおなぎ払いになり、今の火打でもって、
その草へ向かい火をつけて、あべこべに向こうへ向かってお焼きたてになりました。
命はそれでようやく、その野原からのがれ出ていらっしゃいました。
そしていきなり、その悪い国造と、手下の者どもを、ことごとく切り殺して、
火をつけて焼いておしまいになりました。
それ以来そのところを焼津と呼びました。
それから、命が草をお切りはらいになった御剣を草薙の剣と申しあげるようになりました。
焼津や草薙はいまの静岡県にあって「日本書紀」由来の地名であることも周知のことなのですが、このくだりの最初のところで、「古事記」ははっきりと「そしてまもなく相模の国へお着きになりました」と言っています。
日本書紀ではそこを「駿河の国」としているようですから、同じエピソードが場所を変えて繰り返されていることになります。
未だに得心がいかない部分でもあるのですが、解釈として何通りかのことは自動的に思い浮かびそうなものです。
この火攻めのあとに、上総へと渡ることになるのですが、そこでオトタチバナヒメは荒れ狂う海の神をなだめるために犠牲となります。
橘媛(たちばなひめ)が生前に歌った歌に、
さねさし、 佐泥佐斯
さがむの小野に、 佐賀牟能袁怒邇
もゆる火の、 毛由流肥能
火中に立ちて、 本那迦邇多知弖
問いしきみはも。 斗比斯岐美波母
これは、相模の野原で火攻めにお会いになったときに、
その燃える火の中にお立ちになっていた、あの危急なときにも、
命は私のことをご心配くだすって、いろいろに慰め問うてくだすった、
ほんとに、お情け深い方よと、そのもったいないお心持を忘れない印に歌ったのでした。
どうも前後の記述から察するに、この「相模の野原」(佐賀牟能袁怒)は相模原のことなんじゃないか?って思うのです。
言葉がそのまんま、というだけじゃなくて、地理的にその方が無理がない。確かに「焼津」や「草薙」という地名はないのだけれど市内には「大沼」という地名が残されています。かつては文字通り「大沼」が存在していたそうです。後に埋め立てられて、いまは住宅がびっしり並んでいるのですけど。「相模の野原」にふさわしい場所って、「相模原」くらいしかないのでは?
「古事記」と「日本書紀」の記述の違いについて詳しく知っているわけでもないので、そのうちに調べてみようか?と思っていますが、東征の道をとってみても、ヤマトタケルノミコトが通ったのではないか?とされるルートはいくつかあるようなのです。
芦ノ湖スカイラインの道の脇に「命(ミコト)の泉」という湧き水がでているところがあります。箱根の山の中でも特に眺めのよい芦ノ湖スカイラインですが、「ミコト」がここを通ったということになると、古事記の記述とはだいぶ違うことになります。もっとも、古事記にしても日本書紀にしても、ことこまかに記録されているというものではなくて、どこか「ざっくり」と手がかりを残してあるという雰囲気で書かれている節もある。東征のルートだって往路と復路があるし、ひとところに長く滞在するのが当たり前でもある。また、「日本書紀」ではあからさまに「古事記」とは違うルートが想像されるので、同じ名前の人物が歩いたはずの道筋はそれだけで複数存在する。ルートを簡単単純に直線的に捉えることなんてできないだろうし。。。それにしたって、かなりくまなく、箱根、足柄を歩いていることになるよなぁ~、なんて思ったりします。ほとんどローラー作戦。それが全国各地に及んでいるのですからね~。
倭建命と日本武尊。
どうも一筋縄では解読できない暗号体系が、2系統存在している風なので、もはや選り分けることは困難なのでは?とおもうけれど、専門家の研究は昔とは比べ物にならないくらい細かいところに分け入っているようなので、たくさんの成果がすでに出ているようです。
丹念に読むにはちょっと気がそがれるくらいに研究成果も多い。
いつか決定版と呼ばれうるものが出てきてくれないかなぁ~なんて、こちらはのんびり構えていたりします。
ところで、どちらの記紀に依拠しているかはともかく、神社などでは「日本武尊」という表記で統一されているようですが、これはとりもなおさず、「日本書紀」を正史とする立場が貫かれているようです。
個人的には、僕自身が育った足柄と、今暮らしている相模原を美しく結んでくれる「古事記」を強く推したいのですが。
「古事記」では、「足柄之坂」が西と東の境として捉えられています。足柄之坂をのぼって、走水で入水したオトタチバナヒメを思い出し振返って「阿豆麻波夜」(あずまはや)と三たび口にした。以来、そこより「ひがし」のことを「あづま」と呼ぶようになった。
妻を思い出す、ということが「東」のひとつの語源になっているというエピソードです。
「古事記物語」鈴木三重吉編では「白い鳥 三」のあたりが足柄之坂のくだりです。
ではそれ以前はなんと呼ばれていたのか?
何の気なしに読んでいた本で知ったのですが、御殿場の地名の由来となった御殿の跡に建つ神社あたりは「吾妻原」(あづまはら)とも呼ばれていたのだとか。古事記にならってる?
吾妻は東の語源とも言われます。
「阿豆麻」→「吾妻」→「東」
知っている人には常識かも?だけど、足柄山や箱根、富士山などを眺めて育った僕なんぞには、そこが「古事記」の世界から続く場所だなんてピンと来なかったりします。京都や奈良ほどに、目に見えるわかりやすい手がかりがあれば、それについて何か具体的なことを言えそうなものですが、神話的人物がほんの少し立ち寄った、という記述だけが支えている事実ですから、それ以上に何かをいえるか?というと、どうも。見た目「わかりやすい」っていうわけではないけれど、それでも「ヤマトタケルノミコト」の足跡はここかしこに遺されているようです。
御殿場というのはこちらからすると足柄山の向こう側にあるわけですが、反対側のふもとも足柄山の一面をつくっているという当たり前のことも、東名高速でサァーッと迂回してしまうとあまりよくわからない。僕はだいぶまわり道をして、ここがもう一方の足柄山であったことを知ることになりました。
足柄古道は万葉集にもとりあげられているので、その重要性についてはだいぶ昔から認識されていたことは確かなようです。ヤマトタケルノミコトの東征もそうだし、平安末期にもこの道を重要な情報を持った人が行き来していた。たとえば、源頼朝に挙兵を促したとされる文覚上人などは頻繁にこの道を何度も何度も行き来しています。南北朝の戦いもこの地でひとつの戦局を迎えていたりして、受験勉強の年表では気配さえ出てこないけれど、北朝方がとある山城を2年もの間取り囲んでいたこともあります。
江戸時代に東海道が整備されるようになるまでは、箱根越えをするよりは足柄古道を往くのがあたりまえだったりしたのです。
ところで、「古事記」で「草薙の剣」がヤマトタケルノミコトに手渡され、それが窮地を切り抜けるときに抜かれる場面。そこでの記述は、僕には気になるくらい大雑把なのです。
そしてまもなく相模の国へお着きになりました。
するとそこの国造が、命をお殺し申そうとたくらんで、
「あすこの野中に大きな沼がございます。その沼の中に住んでおります神が、
まことに乱暴なやつで、みんな困っております」と、おだまし申しました。
命はそれをまにお受けになって、その野原の中へはいっておいでになりますと、
国造は、ふいにその野へ火をつけて、どんどん四方から焼きたてました。
命ははじめて、あいつにだまされたかとお気づきになりました。
その間にも火はどんどんま近に迫って来て、お身が危くなりました。
命はおんおば上のおおせを思い出して、急いで、
例の袋のひもをといてご覧になりますと、中には火打がはいっておりました。
命はそれで、急いでお宝物の御剣を抜いて、
あたりの草をどんどんおなぎ払いになり、今の火打でもって、
その草へ向かい火をつけて、あべこべに向こうへ向かってお焼きたてになりました。
命はそれでようやく、その野原からのがれ出ていらっしゃいました。
そしていきなり、その悪い国造と、手下の者どもを、ことごとく切り殺して、
火をつけて焼いておしまいになりました。
それ以来そのところを焼津と呼びました。
それから、命が草をお切りはらいになった御剣を草薙の剣と申しあげるようになりました。
焼津や草薙はいまの静岡県にあって「日本書紀」由来の地名であることも周知のことなのですが、このくだりの最初のところで、「古事記」ははっきりと「そしてまもなく相模の国へお着きになりました」と言っています。
日本書紀ではそこを「駿河の国」としているようですから、同じエピソードが場所を変えて繰り返されていることになります。
未だに得心がいかない部分でもあるのですが、解釈として何通りかのことは自動的に思い浮かびそうなものです。
この火攻めのあとに、上総へと渡ることになるのですが、そこでオトタチバナヒメは荒れ狂う海の神をなだめるために犠牲となります。
橘媛(たちばなひめ)が生前に歌った歌に、
さねさし、 佐泥佐斯
さがむの小野に、 佐賀牟能袁怒邇
もゆる火の、 毛由流肥能
火中に立ちて、 本那迦邇多知弖
問いしきみはも。 斗比斯岐美波母
これは、相模の野原で火攻めにお会いになったときに、
その燃える火の中にお立ちになっていた、あの危急なときにも、
命は私のことをご心配くだすって、いろいろに慰め問うてくだすった、
ほんとに、お情け深い方よと、そのもったいないお心持を忘れない印に歌ったのでした。
どうも前後の記述から察するに、この「相模の野原」(佐賀牟能袁怒)は相模原のことなんじゃないか?って思うのです。
言葉がそのまんま、というだけじゃなくて、地理的にその方が無理がない。確かに「焼津」や「草薙」という地名はないのだけれど市内には「大沼」という地名が残されています。かつては文字通り「大沼」が存在していたそうです。後に埋め立てられて、いまは住宅がびっしり並んでいるのですけど。「相模の野原」にふさわしい場所って、「相模原」くらいしかないのでは?
「古事記」と「日本書紀」の記述の違いについて詳しく知っているわけでもないので、そのうちに調べてみようか?と思っていますが、東征の道をとってみても、ヤマトタケルノミコトが通ったのではないか?とされるルートはいくつかあるようなのです。
芦ノ湖スカイラインの道の脇に「命(ミコト)の泉」という湧き水がでているところがあります。箱根の山の中でも特に眺めのよい芦ノ湖スカイラインですが、「ミコト」がここを通ったということになると、古事記の記述とはだいぶ違うことになります。もっとも、古事記にしても日本書紀にしても、ことこまかに記録されているというものではなくて、どこか「ざっくり」と手がかりを残してあるという雰囲気で書かれている節もある。東征のルートだって往路と復路があるし、ひとところに長く滞在するのが当たり前でもある。また、「日本書紀」ではあからさまに「古事記」とは違うルートが想像されるので、同じ名前の人物が歩いたはずの道筋はそれだけで複数存在する。ルートを簡単単純に直線的に捉えることなんてできないだろうし。。。それにしたって、かなりくまなく、箱根、足柄を歩いていることになるよなぁ~、なんて思ったりします。ほとんどローラー作戦。それが全国各地に及んでいるのですからね~。
倭建命と日本武尊。
どうも一筋縄では解読できない暗号体系が、2系統存在している風なので、もはや選り分けることは困難なのでは?とおもうけれど、専門家の研究は昔とは比べ物にならないくらい細かいところに分け入っているようなので、たくさんの成果がすでに出ているようです。
丹念に読むにはちょっと気がそがれるくらいに研究成果も多い。
いつか決定版と呼ばれうるものが出てきてくれないかなぁ~なんて、こちらはのんびり構えていたりします。
ところで、どちらの記紀に依拠しているかはともかく、神社などでは「日本武尊」という表記で統一されているようですが、これはとりもなおさず、「日本書紀」を正史とする立場が貫かれているようです。
個人的には、僕自身が育った足柄と、今暮らしている相模原を美しく結んでくれる「古事記」を強く推したいのですが。
「古事記」では、「足柄之坂」が西と東の境として捉えられています。足柄之坂をのぼって、走水で入水したオトタチバナヒメを思い出し振返って「阿豆麻波夜」(あずまはや)と三たび口にした。以来、そこより「ひがし」のことを「あづま」と呼ぶようになった。
妻を思い出す、ということが「東」のひとつの語源になっているというエピソードです。
「古事記物語」鈴木三重吉編では「白い鳥 三」のあたりが足柄之坂のくだりです。