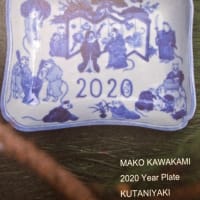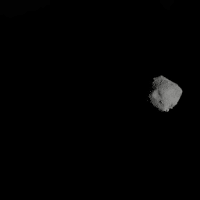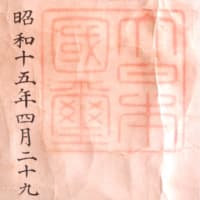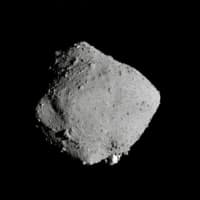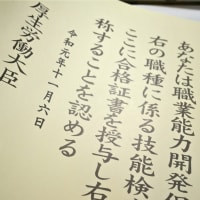足柄峠を実際に歩いてみると、現在の登山道、ハイキングコースとされている道だけを見ても幾筋にも分かれています。地図を見れば、峠を中心にしたネットワークが張られているかのよう。
古事記に見られる「足柄之坂」はそのうちのどれかひとつ。。。ということには、どうもなりそうにありません。箱根から小山まで連なる足柄の山々は人の足にはやはり広大で、「足柄之坂」はそのすべてを総称する呼び名であったことを考えれば、古い道筋を代表的な一本の道に収斂させるという発想そのものにムリがあります。「足柄之坂」はこのネットワークのような道のことを言うべきなのかも。もちろん、後世に開かれた道がこのネットワークを形成しているわけですが、いわゆる「足柄古道」とされている道筋も、奈良、平安、鎌倉時代の長い間に揺れ動いていたに違いなく、現在の「古道」とされているところから少しずれていたりするところも少なからずあるのだと思います。それに、古代の話なら人は道の上だけを進むとは限らない。切り開きながら進んだ道なき道というのもあるはずです。いまとなっては特定できないっていうだけなんじゃないか?って思うと、急にそのあたりの森に人影が見えてくるような。。。

人や物の往来がにぎやかになって道が整備されたのは江戸時代も後期のこと。足柄峠の中でも特に「甲斐路」と呼ばれていた道があって、それが現在の登山道の中でも最も一般的なルートになっているようです。そうしたメジャーな道筋には、道端に大きなものから小さなものまで、「馬頭観世音」が建てられていたりします。また水が流れる沢の近くに道が出るようにもなっている。実際、「水飲沢」なる名前までついている。馬は交通、流通には欠かせない存在です。峠を越えていく途中、冷たい水をたっぷり飲んで、お馬さんにはしっかり休んでもらわないといけません。

小田原など相模湾でとれた海産物を甲斐へと運ぶ「塩の道」。小山側の足柄で「赤坂」と呼ばれているルートがそれです。南足柄側(つまり足柄之坂の東側)から入る道は、地蔵堂のあたりで幾筋かに岐れます。「足柄古道」と呼ばれるルートはこの「赤坂」のルートに自然につながって西側の足柄駅まで下りていきます。また、これらかつての足柄古道のルート沿いに現在の県道78号線は整備されています。
「足柄越え」の記録の中でも「更級日記」の記述は「足柄山」の様子をドラマチックに伝えていています。物語大好き少女、菅原孝標女の筆。1008年生まれといいますから、彼女が生まれたのはいまからざっと千年前ということになります。12歳から13歳のころに上総から京に上ることになるのですが、ルート上には当然のように「足柄山」が待っています。物語大好き少女の眼に、かの「足柄山」がどう映ったか?「更級日記」では以下のように書かれています。
あしがら山といふは、四五日かねて、おそろしげにくらがりわたれり。
やうやういりたつふもとのほどだに、そらのけしき、はかばかしくも見えず。
えもいはずしげりわたりて、いとおそろしげなり。
もともと「足柄小杉」で知られていた足柄の山々。ふもとの方でも「空の景色」がまったく見えないような鬱蒼とした森とされていますが、もしそうなら、1000年前の足柄山は照葉樹が主役の森だったのかもしれません。現在の「足柄」のふもとはいわゆる里山の風景が広がっています。よくよく眺めると、遠目でも植林された杉林が目立ちます。彼女の「足柄越え」を見届けたと思えるような古い照葉樹はさすがに見つかりません。大きな広葉樹ならわりとすぐに見つかるのですけど、それだって1000年にはまったく足りない。森の世代も何世代かは分かりませんけど確実に変わっているはずですが、樹種の交代も相当な規模で進んできたのかもしれません。

菅原孝標一行がどういうルートを越えていったのか?については、はっきりとしたことが分かっているわけではないそうです。かつての地元民としての僕の感覚で読んでみると、東側の南足柄の地蔵堂から登りはじめて、西側の地蔵堂川沿いに抜けていったのではないか?と思わせる節があります。
ふもとにやどりたるに、
月もなくくらき夜の、やみにまどふやうなるにあそび三人、いづくよりともなくいできたり。
五十許なるひとり、二十許なる、十四五なるとあり。いほのまへにからかさをさゝせてすへたり。
をのこども、火をともして見れば、むかし、こはたといひけむがまごといふ。かみいとながく、
ひたひいとよくかゝりて、いろしろくきたなげなくて、さてもありぬべきしもづかへなどにても
ありぬべしなど、人々あはれがるに、こゑすべてにるものなく、そらにすみのぼりて
めでたくうたをうたふ。人々いみじうあはれがりて、けぢかくて人々もてけうずるに、
「にしくにのあそびはえかゝらじ」などいふをききて、「なにはわたりにくらぶれば」
とめでたくうたひたり。見るめのいときたなげなきに、こゑさへにるものなくうたひて、
さばかりおそろしげなる山中にたちてゆくを、人々あかず思てみなゝくを、
おさなき心地には、ましてこのやどりをたたむことさへあかずおぼゆ。
ここでいう「あそび」とは、いわゆる「遊女」「白拍子」。
そういう人たちが夜道をやってきて、旅の一行の前で詠い舞うのですから、「ふもとにやどりたる」場所はそれほど山の奥までは入っていないと思えるのです。だとすると、この宿営は地蔵堂あたりか、それよりもう少し下の方、弘西寺近辺までが該当しそうな雰囲気です。
まだあかつきよりあしがらをこゆ。まいて山のなかのおそろしげなる事いはむ方なし。
雲はあしのしたにふまる。山のなから許の、木のしたのわづかなるに、
あふひのたゞみすぢばかりあるを、世はなれてかゝる山中にしもおいけむよと、
人々あはれがる。水はその山に三所ぞながれたる。
足柄峠の標高は759m。「雲はあしのしたにふまる」というのはやや大げさか?とも思うのですが、それも状況によってはあり得ます。実際、ここは霧もよく出ます。明け方から登りはじめたとするなら、濃い朝霧が追いかけてくるように見えても不思議はありません。でも、菅原孝標女が物語大好き少女であることを思い起こすと、彼女の頭の中では「足柄山」は劇的に脚色されていると考えた方が、なんだかしっくりくるような気もします。上総からの道ならば、右手に丹沢、大山を見ながら遠くの富士山を目指すように進んできたはず。山を越えるとなれば迂回を許さない峠が初めて立ちはだかるのが足柄山。そう考えると、あまりに劇的な描写にも頷けるかも(?)。
「水はその山に三所ぞながれたる」のところ。
この三所ということに意味はない、とするのが古文解釈では普通なのだそうですが、歩けば山の中を流れる川が合流している場所というのがあります。

川の流れは変わりやすいものだけど、山を削り取って形を変えない限り、山あいの川の流れを変えることは難しいのではないか?それ以上に、水飲み場として考えると、そこで休んだことを彼女が記憶していたと考える方が、僕には自然に思えるのです。また、峠の中腹であるこのあたりには湧き水がしみ出している場所もすぐに見つけることができます。足柄峠の西側でこの記述に該当する場所というのは何ヶ所もありません。具体的な名前が出てくるわけではないけれど、そこでは彼女をこわがらせていた「おそろしげなる」「くらがり」はどこか後ろの方に追いやられている風にも読めてくる。「空の景色」が開けた場所と言うなら、やっぱり川なのではないか?と、勝手に想像しています。
からうじて、こえいでて、せき山にとゞまりぬ。これよりは駿河也。
よこはしりの関のかたはらに、いはつぼといふ所あり。えもいはずおほきなるいしのよほうなる中に、
あなのあきたる中よりいづる水の、きよくつめたきことかぎりなし。
足柄峠からの眺めならば富士山のことに触れていてもおかしくないのですが、「雲はあしのしたにふまる」という表現や、峠を越えてからあとに富士山について記述されているところから察するに、さほど視界のよくないお天気の日に足柄越えが敢行された、と見ても良いかもしれません。
山を無事に越えて「せき山」という場所に泊まるとあり、そこでは「よこはしりの関」とか「いはつぼ」などの名前が出てくるのですが、これが具体的にどこを指しているのかはいまでもわからないそうです。名指しされている場所ほどどこにあったのか分からないのですから、1000年という時間が変えてしまったり、消してしまったり、隠してしまうことの容赦ない強さを感じてしまいます。
関の位置もよくは分かっていないけれど、当時のこのあたりは「御厨」と呼ばれていた伊勢神宮の荘園であった、ということは分かっています。「いわつぼ」も、富士山由来の「風穴」のようなところから水が湧きだしていたりしたのかな?と想像するくらいですが、それは足柄山を越えた先の話なので、できたら別の機会に。
古事記に見られる「足柄之坂」はそのうちのどれかひとつ。。。ということには、どうもなりそうにありません。箱根から小山まで連なる足柄の山々は人の足にはやはり広大で、「足柄之坂」はそのすべてを総称する呼び名であったことを考えれば、古い道筋を代表的な一本の道に収斂させるという発想そのものにムリがあります。「足柄之坂」はこのネットワークのような道のことを言うべきなのかも。もちろん、後世に開かれた道がこのネットワークを形成しているわけですが、いわゆる「足柄古道」とされている道筋も、奈良、平安、鎌倉時代の長い間に揺れ動いていたに違いなく、現在の「古道」とされているところから少しずれていたりするところも少なからずあるのだと思います。それに、古代の話なら人は道の上だけを進むとは限らない。切り開きながら進んだ道なき道というのもあるはずです。いまとなっては特定できないっていうだけなんじゃないか?って思うと、急にそのあたりの森に人影が見えてくるような。。。

人や物の往来がにぎやかになって道が整備されたのは江戸時代も後期のこと。足柄峠の中でも特に「甲斐路」と呼ばれていた道があって、それが現在の登山道の中でも最も一般的なルートになっているようです。そうしたメジャーな道筋には、道端に大きなものから小さなものまで、「馬頭観世音」が建てられていたりします。また水が流れる沢の近くに道が出るようにもなっている。実際、「水飲沢」なる名前までついている。馬は交通、流通には欠かせない存在です。峠を越えていく途中、冷たい水をたっぷり飲んで、お馬さんにはしっかり休んでもらわないといけません。

小田原など相模湾でとれた海産物を甲斐へと運ぶ「塩の道」。小山側の足柄で「赤坂」と呼ばれているルートがそれです。南足柄側(つまり足柄之坂の東側)から入る道は、地蔵堂のあたりで幾筋かに岐れます。「足柄古道」と呼ばれるルートはこの「赤坂」のルートに自然につながって西側の足柄駅まで下りていきます。また、これらかつての足柄古道のルート沿いに現在の県道78号線は整備されています。
*
「足柄越え」の記録の中でも「更級日記」の記述は「足柄山」の様子をドラマチックに伝えていています。物語大好き少女、菅原孝標女の筆。1008年生まれといいますから、彼女が生まれたのはいまからざっと千年前ということになります。12歳から13歳のころに上総から京に上ることになるのですが、ルート上には当然のように「足柄山」が待っています。物語大好き少女の眼に、かの「足柄山」がどう映ったか?「更級日記」では以下のように書かれています。
あしがら山といふは、四五日かねて、おそろしげにくらがりわたれり。
やうやういりたつふもとのほどだに、そらのけしき、はかばかしくも見えず。
えもいはずしげりわたりて、いとおそろしげなり。
もともと「足柄小杉」で知られていた足柄の山々。ふもとの方でも「空の景色」がまったく見えないような鬱蒼とした森とされていますが、もしそうなら、1000年前の足柄山は照葉樹が主役の森だったのかもしれません。現在の「足柄」のふもとはいわゆる里山の風景が広がっています。よくよく眺めると、遠目でも植林された杉林が目立ちます。彼女の「足柄越え」を見届けたと思えるような古い照葉樹はさすがに見つかりません。大きな広葉樹ならわりとすぐに見つかるのですけど、それだって1000年にはまったく足りない。森の世代も何世代かは分かりませんけど確実に変わっているはずですが、樹種の交代も相当な規模で進んできたのかもしれません。

菅原孝標一行がどういうルートを越えていったのか?については、はっきりとしたことが分かっているわけではないそうです。かつての地元民としての僕の感覚で読んでみると、東側の南足柄の地蔵堂から登りはじめて、西側の地蔵堂川沿いに抜けていったのではないか?と思わせる節があります。
ふもとにやどりたるに、
月もなくくらき夜の、やみにまどふやうなるにあそび三人、いづくよりともなくいできたり。
五十許なるひとり、二十許なる、十四五なるとあり。いほのまへにからかさをさゝせてすへたり。
をのこども、火をともして見れば、むかし、こはたといひけむがまごといふ。かみいとながく、
ひたひいとよくかゝりて、いろしろくきたなげなくて、さてもありぬべきしもづかへなどにても
ありぬべしなど、人々あはれがるに、こゑすべてにるものなく、そらにすみのぼりて
めでたくうたをうたふ。人々いみじうあはれがりて、けぢかくて人々もてけうずるに、
「にしくにのあそびはえかゝらじ」などいふをききて、「なにはわたりにくらぶれば」
とめでたくうたひたり。見るめのいときたなげなきに、こゑさへにるものなくうたひて、
さばかりおそろしげなる山中にたちてゆくを、人々あかず思てみなゝくを、
おさなき心地には、ましてこのやどりをたたむことさへあかずおぼゆ。
ここでいう「あそび」とは、いわゆる「遊女」「白拍子」。
そういう人たちが夜道をやってきて、旅の一行の前で詠い舞うのですから、「ふもとにやどりたる」場所はそれほど山の奥までは入っていないと思えるのです。だとすると、この宿営は地蔵堂あたりか、それよりもう少し下の方、弘西寺近辺までが該当しそうな雰囲気です。
まだあかつきよりあしがらをこゆ。まいて山のなかのおそろしげなる事いはむ方なし。
雲はあしのしたにふまる。山のなから許の、木のしたのわづかなるに、
あふひのたゞみすぢばかりあるを、世はなれてかゝる山中にしもおいけむよと、
人々あはれがる。水はその山に三所ぞながれたる。
足柄峠の標高は759m。「雲はあしのしたにふまる」というのはやや大げさか?とも思うのですが、それも状況によってはあり得ます。実際、ここは霧もよく出ます。明け方から登りはじめたとするなら、濃い朝霧が追いかけてくるように見えても不思議はありません。でも、菅原孝標女が物語大好き少女であることを思い起こすと、彼女の頭の中では「足柄山」は劇的に脚色されていると考えた方が、なんだかしっくりくるような気もします。上総からの道ならば、右手に丹沢、大山を見ながら遠くの富士山を目指すように進んできたはず。山を越えるとなれば迂回を許さない峠が初めて立ちはだかるのが足柄山。そう考えると、あまりに劇的な描写にも頷けるかも(?)。
「水はその山に三所ぞながれたる」のところ。
この三所ということに意味はない、とするのが古文解釈では普通なのだそうですが、歩けば山の中を流れる川が合流している場所というのがあります。

川の流れは変わりやすいものだけど、山を削り取って形を変えない限り、山あいの川の流れを変えることは難しいのではないか?それ以上に、水飲み場として考えると、そこで休んだことを彼女が記憶していたと考える方が、僕には自然に思えるのです。また、峠の中腹であるこのあたりには湧き水がしみ出している場所もすぐに見つけることができます。足柄峠の西側でこの記述に該当する場所というのは何ヶ所もありません。具体的な名前が出てくるわけではないけれど、そこでは彼女をこわがらせていた「おそろしげなる」「くらがり」はどこか後ろの方に追いやられている風にも読めてくる。「空の景色」が開けた場所と言うなら、やっぱり川なのではないか?と、勝手に想像しています。
からうじて、こえいでて、せき山にとゞまりぬ。これよりは駿河也。
よこはしりの関のかたはらに、いはつぼといふ所あり。えもいはずおほきなるいしのよほうなる中に、
あなのあきたる中よりいづる水の、きよくつめたきことかぎりなし。
足柄峠からの眺めならば富士山のことに触れていてもおかしくないのですが、「雲はあしのしたにふまる」という表現や、峠を越えてからあとに富士山について記述されているところから察するに、さほど視界のよくないお天気の日に足柄越えが敢行された、と見ても良いかもしれません。
山を無事に越えて「せき山」という場所に泊まるとあり、そこでは「よこはしりの関」とか「いはつぼ」などの名前が出てくるのですが、これが具体的にどこを指しているのかはいまでもわからないそうです。名指しされている場所ほどどこにあったのか分からないのですから、1000年という時間が変えてしまったり、消してしまったり、隠してしまうことの容赦ない強さを感じてしまいます。
関の位置もよくは分かっていないけれど、当時のこのあたりは「御厨」と呼ばれていた伊勢神宮の荘園であった、ということは分かっています。「いわつぼ」も、富士山由来の「風穴」のようなところから水が湧きだしていたりしたのかな?と想像するくらいですが、それは足柄山を越えた先の話なので、できたら別の機会に。