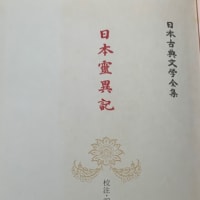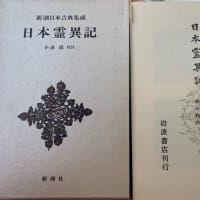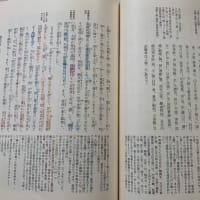古今和歌集を
お稽古のお仲間の皆様と読むことになりました。
どうしてそういうことになったかというと…
月に2回、志野流香道のお稽古をしています。
香道は、茶道や華道などに比べると、
認知度は低いかなと思いますが、
茶道と同じ頃の室町時代に体系化された
芸道です。
なんとなく敷居が高いイメージがあるかも
しれませんが、、、
香木は本当に、本当に、本当に、
いい香りなんです!
香水や、アロマオイル、お線香などとは
また趣きが異なる自然の美しい香りなんです。
香木の香りを聞いたら、どの方もきっと
心からリラックスした心持ちに
なれるんじゃないかと思います。
お近くで体験席などありましたら
ぜひ一度、香りを体験してみて頂きたいです。
ということで、
私は香木の香りを聞きたいので、
お稽古を始めたのですが…
お稽古では組香という形式でお香を聞きます。
香りを聞き当てるゲーム形式です。
その組香は古典文学などを題材に
作られているものがたくさんあります。
もちろん、毎回、先生は組香について
ご説明くださいます。
問題は、その説明を理解するための、
ベースになっている知識が足りないので
組香の意味も、そこに使われている香りの銘や
香りが、どのように響き合っているか、
理解しきれてないなぁと、感じること。
例えば、歌舞伎もお能も、古典絵画でも
知識があって観るのと、無しに観るのとでは、
感じる広がりや深みが違いますよね?
知識がなくても、
目の前にあるものから受け取る
美しさや、素晴らしさは、もちろんあります。
でも、素養があって観える世界もあるのだと思うと、
溢れ落ちてるものの方が多い、
勿体ない観かたをしているんだろうなと、
自分を残念に思います。
そういう感じに
お香のお稽古をしていると、
古典の知識が全然足りない!!と痛感して、
やっぱり勉強しないといけないなぁと思います。
そうは思っていても、
1人で古典の海に乗り出すのはちょっと…
でも、他のお仲間の皆さんも似たような思いを
感じていらっしゃるようで…
では、皆で何か古典の勉強をしましょうか?と。
というお話しになりました。
古典といってもたくさんあります。
何を読んだらいいかと話し合って
とにかく古典のどれも、何も詳しくないのだから
とりあえず、初めからみたいな感じの本に、
勅撰和歌集の初めの古今和歌集からにしましょうか
ということになったわけです。
和歌集…(><)
物語の方が良かったと思ったり…。
歴史は興味もあるし、好きな方ですが
和歌は…う〜
苦手というより、和歌を楽しむとか、
その味わいが今ひとつわからない。
和歌も読んでも、きれいだなぁとか、
いいなぁとか、これは好きだなぁとか、
または、あまりいいと思えないとか、
なんかイマイチ好きじゃないとか
そういう好きも嫌いも、
歌から、あまり感じられないんですよね(><)
私の知識としては
古今和歌集は、勅撰和歌集の初めの書で
紀貫之が仮名で書かいた仮名序と
真名序という漢文の序文がついている。
勅撰とは、天皇が自ら選ぶこと、という意味。
そうはいっても、天皇が自分自身で
いろんな和歌を集めて選んだわけではなく、
専門家を選んで編集させた。
編者は紀貫之他、何人かいた、、、
くらいです。
成立事情と編者選者くらいは
もっと知っておかないとなと思います。
それにしても、そもそも、
どうして勅撰で、和歌集という書を作ることに
なったんでしょうね〜?と思います。
それから、序文が仮名と、漢文と
序文がふたつあるのは
なんででしょうね〜?と思います。
あとは、古今和歌集が序文があって
歌を分類して並べるという書のかたちに
なったのには、手本や見本にした書が
何かあるんじゃないかなと思うのですが…。
あるのかな?
先行書籍の万葉集は参考にしたと思いますが、
和歌の本は古今集以前はないんですから、
参考書の可能性としては、漢詩文集、
日本の書では懐風藻
あとは文選の影響はないかな?
と思いますが…調べてみないとわからないです。
ということを、考えてみるのは
面白そうな感じがします。
少しやる気が出てきました。
でも、それが和歌の内容の理解と
つながるでしょうか?
まぁ読んでみなくてはわからないですね。
ところで
私が家事をしていたり、別の部屋にいたり
今日のように机に向かっていたりしてる時、
くるみはどうしているかというと
寝ています。
ホントに
眠っているか、いないのかわかりませんが
いつもこーんな感じです。

日に何度直しても、敷き物がクチャクチャになります。
お稽古のお仲間の皆様と読むことになりました。
どうしてそういうことになったかというと…
月に2回、志野流香道のお稽古をしています。
香道は、茶道や華道などに比べると、
認知度は低いかなと思いますが、
茶道と同じ頃の室町時代に体系化された
芸道です。
なんとなく敷居が高いイメージがあるかも
しれませんが、、、
香木は本当に、本当に、本当に、
いい香りなんです!
香水や、アロマオイル、お線香などとは
また趣きが異なる自然の美しい香りなんです。
香木の香りを聞いたら、どの方もきっと
心からリラックスした心持ちに
なれるんじゃないかと思います。
お近くで体験席などありましたら
ぜひ一度、香りを体験してみて頂きたいです。
ということで、
私は香木の香りを聞きたいので、
お稽古を始めたのですが…
お稽古では組香という形式でお香を聞きます。
香りを聞き当てるゲーム形式です。
その組香は古典文学などを題材に
作られているものがたくさんあります。
もちろん、毎回、先生は組香について
ご説明くださいます。
問題は、その説明を理解するための、
ベースになっている知識が足りないので
組香の意味も、そこに使われている香りの銘や
香りが、どのように響き合っているか、
理解しきれてないなぁと、感じること。
例えば、歌舞伎もお能も、古典絵画でも
知識があって観るのと、無しに観るのとでは、
感じる広がりや深みが違いますよね?
知識がなくても、
目の前にあるものから受け取る
美しさや、素晴らしさは、もちろんあります。
でも、素養があって観える世界もあるのだと思うと、
溢れ落ちてるものの方が多い、
勿体ない観かたをしているんだろうなと、
自分を残念に思います。
そういう感じに
お香のお稽古をしていると、
古典の知識が全然足りない!!と痛感して、
やっぱり勉強しないといけないなぁと思います。
そうは思っていても、
1人で古典の海に乗り出すのはちょっと…
でも、他のお仲間の皆さんも似たような思いを
感じていらっしゃるようで…
では、皆で何か古典の勉強をしましょうか?と。
というお話しになりました。
古典といってもたくさんあります。
何を読んだらいいかと話し合って
とにかく古典のどれも、何も詳しくないのだから
とりあえず、初めからみたいな感じの本に、
勅撰和歌集の初めの古今和歌集からにしましょうか
ということになったわけです。
和歌集…(><)
物語の方が良かったと思ったり…。
歴史は興味もあるし、好きな方ですが
和歌は…う〜
苦手というより、和歌を楽しむとか、
その味わいが今ひとつわからない。
和歌も読んでも、きれいだなぁとか、
いいなぁとか、これは好きだなぁとか、
または、あまりいいと思えないとか、
なんかイマイチ好きじゃないとか
そういう好きも嫌いも、
歌から、あまり感じられないんですよね(><)
私の知識としては
古今和歌集は、勅撰和歌集の初めの書で
紀貫之が仮名で書かいた仮名序と
真名序という漢文の序文がついている。
勅撰とは、天皇が自ら選ぶこと、という意味。
そうはいっても、天皇が自分自身で
いろんな和歌を集めて選んだわけではなく、
専門家を選んで編集させた。
編者は紀貫之他、何人かいた、、、
くらいです。
成立事情と編者選者くらいは
もっと知っておかないとなと思います。
それにしても、そもそも、
どうして勅撰で、和歌集という書を作ることに
なったんでしょうね〜?と思います。
それから、序文が仮名と、漢文と
序文がふたつあるのは
なんででしょうね〜?と思います。
あとは、古今和歌集が序文があって
歌を分類して並べるという書のかたちに
なったのには、手本や見本にした書が
何かあるんじゃないかなと思うのですが…。
あるのかな?
先行書籍の万葉集は参考にしたと思いますが、
和歌の本は古今集以前はないんですから、
参考書の可能性としては、漢詩文集、
日本の書では懐風藻
あとは文選の影響はないかな?
と思いますが…調べてみないとわからないです。
ということを、考えてみるのは
面白そうな感じがします。
少しやる気が出てきました。
でも、それが和歌の内容の理解と
つながるでしょうか?
まぁ読んでみなくてはわからないですね。
ところで
私が家事をしていたり、別の部屋にいたり
今日のように机に向かっていたりしてる時、
くるみはどうしているかというと
寝ています。
ホントに
眠っているか、いないのかわかりませんが
いつもこーんな感じです。

日に何度直しても、敷き物がクチャクチャになります。