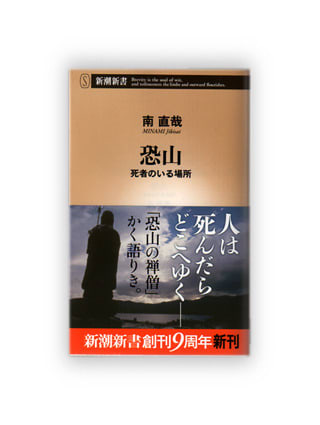新潮新書、2012年発行。
いきなりパワースポットで有名な恐山の本の登場。
といっても、観光の本ではありません。
著者は永平寺で19年間修行し、その後恐山菩提寺の院代(住職代理)という経歴を持ちます。
ま、院代となったのは、偶然(?)恐山山主の娘と結婚したからだそうですが。
僧侶として内側から見つめた「恐山」とその周辺事情を記した書物ということになります。
恐山というとイタコの口寄せ、と言うイメージがありますね。
イタコは民間のシャーマン(霊媒師)で、著者の属する仏教界とは直接の関係ありません。
実は私、今から遡ること30年前の二十歳の時、恐山に行ったことがあります。
当時、大学の「民俗研究部」というマイナーなサークルに所属しており、その仲間で大祭が行われている恐山へ二十歳を迎える夏に向かったのでした。
硫黄臭が立ちこめる荒涼とした土地に到着すると、そこは別世界。
ひときわ人だかりのある一帯があり、そこにはイタコの出店が並んでいました。
祭文を唱える独特のイタコの口調が聞こえる中、シクシク泣く声も混じり、非日常的な異様な空間を感じたことを記憶しています。
そんな私には、恐山を紹介する第一章は、とくに目新しい情報はありませんでした。
第二章以降には著者の経歴と思索遍歴が記されており、興味深く読みました。
著者の印象は“頭でっかちの理論派僧侶”といったところでしょうか。
「死」は生き残った者がいて初めて成立する概念であること、
「死」を受け入れるには時間と器が必要なこと、
「死」を受容する器として仏教や恐山が存在すること、
等々、彼の説が述べられ、一部納得させられました。
しかし「受容」という意味では、仏教より恐山の方が優れているのではないかと私は感じています。
著者も薄々そのことに気づいているようで、恐山に来る人たちを前にして、それまで学んできた仏教教義・禅の知識が役に立たなかったことを告白しています。
「受容」は「カウンセリング」と言い換えることも可能です。
古来、日本には至る所に「カウンセラー」としてのシャーマンが存在してきました。
その一つが、恐山を活動の場にしているイタコさんなのでしょう。
読後感は、永平寺で20年近く修行してもこんなものなのかな、とちょっと肩すかしを食らった気分。
<メモ>
自分自身のための備忘録。
■ 恐山に来る人たちには仏教教義は通用しない。
私が恐山で身にしみて感じたこと、それは実際、これまで蓄えてきた仏教や禅の知識がほとんど通用しない領域だった。それなりに苦心して制作した理屈が、まるで無効な相手だった。
入山当初の正直な感想は「怖かった」というものであった。霊や超常現象を経験したわけではない。何かここにはわけのわからないものがある。それを求めて多くの人がやってくる。しかしそrはこれまで培った知識や経験では、とてもじゃないが捌けるものではない。そんな、わけのわからないものと対峙するときに生じる怖さである。
恐山を「あんなところは日本の土俗信仰に仏教の皮をかぶせたものに過ぎない」となめていたわけではない。今まで考えてきた枠組みの中には、恐山の濃厚なリアリティを収納する器がないことを、早々に痛感させられた。「ただの教義理論や修行経験が通じる次元ではない。一から考え直さないとダメだ」と途方に暮れた。
恐山の信仰というのは、集まってくる人々が作っているもので、上から教義や原理を押しつけてできたものではないことを決して忘れてはいけない。
恐山がパワースポットとして人気を博しているが、これは既存の宗教がすくい取れなかった不安や感情が今を生きる人々に根深く存在することを意味している。
■ イタコと恐山
もとは青森を中心とする北東北地方で霊媒をする女性のことを指す。「口寄せ」と呼ばれる降霊術を行い、死者の魂を呼ぶといわれる。
しかしこれは起源がはっきりしない。目の不自由な女性の生業として始まったのだろうといわれているが、定かではない。
現在のイタコの平均年齢は80歳を超え、後継者は少ない。40歳代の若いイタコは2人しかいない(弟子はいるがすぐにドロップアウトしてしまうらしい)。
世間で誤解していることがある。「恐山のイタコ」は存在しない。
つまり、恐山がイタコを管理しているわけでも、イタコが恐山に所属しているわけでもない。両者の間に一切の契約関係はない。
イタコは個人業者である。本来は自宅に人を招いて行う者である。
それが、北東北地方の神社仏閣で大きな祭礼や法要があると、そこに人が多く集まるので、「出張営業」に来ているのである。縁日の出店みたいな者である。
恐山では、夏の7/20~24にかけて、大祭と呼ばれる地蔵会(じぞうえ)がある。子爵用中心の行事で、全国から参拝や観光客が多く集まる。イタコが一年で一番多く集まるのもこの時期である。大祭の時は、イタコの所に最低3時間待ちの行列ができる。
■ 死後の世界は「あるのか、ないのか」
仏教の公式見解は「答えない」ことであり、それを「無記」と呼ぶ。
なぜ答えないのか。
それは「ある」と答えても、「ない」と答えても、いずれにせよ論理的な矛盾が生じて、世界の体系が閉じてしまうから。
仏教において、この類の話は大して重要ではない。
それよりも、人間が生きていると、うれしくて結構なことよりも、切なくてつらくて苦しいことの方が多い。それについてどう考えるか、この方がよほど大事だとするのが、仏教である。
必ずしも簡単とは言えない人生を、最後まで勇気を持っていき切るにはどうするか。それこそが仏教の一番大事なテーマであって、死んだ後のことは、死ねばわかるだろう、ぐらいに考えればよい。
■ 魂とは何か?
それは人が生きる意味と価値のことである。
魂という者は、一にかかって人との園で育てる者。他者との関係の中で育むものでしかない。
人間は「あなたが何もできなくても、何の価値がなくても、そこにあなたが今いてくれるだけでうれしい」と誰かに受け止めてもらわない限りは、自分という存在が生きる意味や価値、つまり魂を知ることは、絶対にできない。それは自分一人の力では見つけることができないものである。
■ 「取引」でこじれる親子関係
登校拒否、校内暴力、引き込み裏、リストカット、拒食症・過食症、パニック障害などの相談を受けてきた。
そんな苦しみを抱いている人達の話を何度も聞いていると、十のうち八、九割は、親子関係に何らかの歪みがあることに気づいた。残りの一、二割は、小学生か中学生の時に経験した猛烈ないじめだった。
親子関係の歪みとして、共通するのは親子関係の基本が「取引」でできているということ。
・パターンA:母親が愛情という名の圧倒的な支配力で、特に息子を囲い込む。
「あなたのことはお母さんが一番よくわかっているの。お母さんの言うとおりにやればいいのよ」と、母親が先回りしてみんなやってしまうので、息子は楽。それに甘えたままでいるうちに手遅れになり、思春期になってようやく自分の足腰で多糖としても立てない。当然、焦る。そして荒れてくる。荒れることさえできないと引きこもる。
こうした家庭の父親は、判で押したように同じタイプで、存在感が枯れ葉のごとく薄い。子どもに父親のことを聞くと、決まって「あの人」と言う。
・パターンB:家庭内で独裁者のごとく振る舞う父親と、奴隷のように従う母という構図。
父親が子どもの人生の行き先を全て決めてしまう。そんな父親は、子どもが自分の敷いたレールから降りることを絶対に許さない。母親はただ心配して、そのまわりをウロウロするだけ。
この二つのパターンの底にあるのは「取引」である。
「お父さん、お母さんの言うことを聞くならば愛してあげましょう」という取引の関係。しかもそれは親本人には自覚がない。子どものためを思って、よかれと思ってやっているので始末に悪い。
■ 人は死んだらどこへ行く
ある老僧に仕えていた修行僧時代に、老僧から
「おまえは人が死んだらどこへ行くか知っているか。」
と聞かれた。
「知りません。」
と答えると、
「人が死ぬとな、その人が愛したもののところに行くんだ」
「人を愛したなら、その愛した者のところへ行く。仕事を愛したんだったら、その仕事の中に入っていく。だから、人は思い出そうと意識しなくても、死んだ人のことを思い出すだろう。入っていくからだ。」
さらに、
「愛することを知らない人間は気の毒だ。死んでも行く場所がない。」
■ 恐山の由緒と歴史
大昔、そもそも恐山という場所は湯治場として地元に知られていた。由緒には、慈覚大師・円仁(天台宗三代目座主)によって平安時代の貞観4年(861)に開闢された。十五世紀、地元の争いに巻き込まれ、寺は破却、その後百年近く荒廃していた。それが大永2年(1522)、下総にいた曹洞宗の僧侶が、麓の田名部、現在のむつ市に円通寺を開き、続いて享禄3年(1530)、恐山を再興、菩提寺を建立して以来、曹洞宗が管理するようになった。
おそらく最初、恐山は神仏の加護や病気平癒などといった現世利益を祈る場所であり、それが現在のように死者供養の礼状として知られるようになったのは、それより後と考えられる。
恐山というのは、あくまでも器である。それは火口にできた土地である。きれいな湖があって温泉が出る。そこにはこの世とは思えない異様な風景が広がっている。その風景に魅せられて多くの人が集まってきた。それから何か信仰のようなものが芽生えた、と考えるのが自然だろう。
恐山にある信仰というのは、特定の教義では決して割り切れるものではない。極端に言えば、拝む神仏の種類は何でもいい。実際恐山には、地蔵菩薩もいれば、阿弥陀仏も不動明王も観音も薬師もいる。円空仏まであって、仏像のワンダーランド状態。
※ ふだんの恐山の姿:例年、開山すれば、まず沿岸の各漁港の漁師さん達が大量祈願のお参りに来られる。それが済むと、農作業が一段落した6月当たりから、団体や家族で先祖供養の人たちが続々上山してくる。
■ 著者が出家した理由
小さい頃から生きるということより「死とは何か」というテーマが問題の中心にあった。それを抱えたまま大学を出て社会人になったが、世俗にとどまったままではその問題をいかんともしがたく、とうとう出家してしまったのである。
■ 仏教における死者の位置づけと恐山の違い
永平寺の死者供養というのは、オーソドックスな修行体系あるいは教義の体系がまず先にあって、そこに死者供養や先祖供養が持ち込まれている、という構造をしている。つまり、道元禅師の仏法というか正法が軸にあり、死者供養というのはその中の一部分に位置づけられているに過ぎない。
ところが恐山では違う。
死者がまずいる。あるいは死者を想う人がまずいる。
仏教というのは、それを収めるひとつの器に過ぎない。つまり死者の位置づけが、永平寺とは百八十度違うのである。
■ 恐山における「死」の存在
死者から生者に与えられるもの、それは生者にとって決定的に欠けているもの、生きている限りは手に入れることができないもの、つまり「死」である。
恐山というのは、死者を媒介にして、生きている人間にその欠落を気づかさせてしまう場所である。
死は実は使者の側にあるのではない。むしろそれは死者を想う生者の側に張り付いている。
霊魂や死者に対する激しい興味なり欲望の根本には「自分はどこから来てどこに行くのか」という抜きがたい不安がある。この不安こそがまさに人間の抱える欠落であり、生者に見える死の顔であり、「死者」へのやむにやまれぬ欲望なのである。
死者の想い出というのは、それが懐かしさを伴うものだろうが、恨みを伴うものだろうが、死者に背負わせるべきもの。生者が背負うものではなく、死者に預かってもらうしかない。
そして、「死者を思い出すこと」が一番の供養になる。
■ “宗教”という仕掛け
人間には拝むものが必要である。
なぜなら、死や死者に対する懐かしさとおそれが、人間には抜き難くあるから。
なぜそのような感情が生じるかというと、死というわけのわからない何かが自分の内側にもあるから。それを処理するためには、拝む対象がどうしても必要になってくる。
死者を拝むためには、死者の輪郭をはっきりさせて、自分との距離を作ってくれるものが必要になってくる。それが宗教の仕掛けである。
「鎮魂」という行為は、まさに生者と死者の間に距離を作り出すこと。
恐山という所は、死者に近づくことができる場所ではあるが、さらに深く考えていくと、死者と距離を作るための場所でもある。
<追記>
日本100巡礼「
ジュディ・オングが青森県恐山へ死者と向き合う旅」
BS日テレ 2013年8月7日放送
ー番組解説ー
今回の巡礼の舞台は、死者の魂が集まる霊場「恐山」
旅人はジュディ・オング。
比叡山・高野山とともに、日本の三大霊場の一つに数えられている「恐山」。
「人は死ねば、お山(恐山)さ行ぐ。」 と、下北の人々はそう言い、この山に深い祈りを捧げてきた。
「この世」にいながら「あの世」に近づける場所と言われている。
霊界と俗界を隔てる三途の川にかかるのは、朱塗りの太鼓橋。
罪人にはここが針の山に見えて、渡ることが出来ないと言われている。
無事に渡り、境内に足を踏み入れると、今度は荒涼とした岩場と硫黄臭が立ち込める。地の池地獄や無間地獄など、あらゆる名前の付いた地獄や賽の河原をめぐり、やがてたどり着く宇曽利山湖の白い砂浜は、まさに極楽浄土を思わせる景観。
仏の慈悲に救いを求めて訪れる人、亡き人の思いに触れたいと願う人が訪れる
この地で、ジュディ・オングは何を思い、何を得たのか…。
この中で、南氏が出演していました。
長身で痩せた風情でトクトクと語ります。
「頭でっかちの理論派僧侶」という私のイメージがぴったりのお方でした。