
★『1リットルの涙』木藤亜也著【幻冬舎】
難病と闘い続ける少女
亜也の日記
15歳の夏、恐ろしい病魔が少女から青春を奪った。 数々の苦難が襲いかかる中、日記を書き続けることが生きる支えだった。
もう、歩けない、何もできない。
でも、生きていたいのです。
たとえ、どんな小さく弱い力だとしても・・・。
亜也は中学3年生の時、突然、脊髄小脳変性症という難病にかかってしまう。 反射的にバランスをとり、素早い滑らかな運動をするのに必要な小脳・脳幹・脊髄の神経細胞が変化し、ついには消滅してしまう病で、発症の原因が不明のため治すことができない。 それでも亜也は進学校の県立東高校に入学、新しい友達に囲まれて勉学に励んでいた。 しかし病は徐々に進行し、亜也はとうとう自力で歩くことすらできなくなってしまう…。
彼女がかかったのは、現時点では体の筋肉が痩せないよう運動訓練を続け、進行を遅らせる薬を使うしかない難病。 体のふらつきに始まり、歩行困難、手や指の不自由、喋るのも発音があいまいになるなど、それぞれの症状が少しずつ進行し、最後には寝たきりになってしまう。
少し前に映画化され上映されていることは聞いていたが、残念なことに映画を観ることはできなかった。 そこで原作を読んでみることにした。
「脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)」とは、人間の脳には約140億の神経細胞と、その10倍もの神経細胞を支持する細胞があり、それぞれの神経細胞は多くのグループに分けられ、運動する時に働くものもあれば、見たり聞いたり感じたりする時に働くものもあり、およそ人間が生きている間はたくさんのグループの神経細胞が活動していることになる。
脊髄小脳変性症はこれらの神経細胞グループのうち反射的にバランスをとり、素速い、滑らかな運動をするのに必要な小脳・脳幹・脊髄の神経細胞が変化し、ついに消えてしまう病気である。 どうして突然、細胞が消えてしまうのかはわかっていない。 全国的な統計では1,000余の患者さんが集められたが、実際にはこの2~3倍はいるらしい。
(藤田保健衛生大学神経内科助教授 山本子先生)
日々失われていく彼女の体を動かすと言う本来誰しもが持つ、当たり前な人としての能力を、15歳という若さで発症し、闘病生活の中で彼女が感じ、体験したことを、彼女の言葉で書き綴っている。 その病気にかかった人間でしかわからないことなのかもしれないが、言葉の一つ一つが、ずしんと心に響く。 五体満足でのほほんと生きている自分が何て無駄に人生を送っているか改めて問われているような、そんな気持ちにさせられる。
話は少し外れるが、先週の日曜日、JRのホームでアイマスクをして介護者(おそらく親だと思う)の腕に引かれ、目の見えない人の立場を実体験しているのだろうグループに出会った。 普段当たり前のように階段を上る行為、電車に乗る行為、その他様々の健常者が当たり前に生活できている中で、そのひとつの機能が失われたとき、この場合は見ることを奪われたことを想定していたのだろうけど、言葉で言うのは簡単だが疑似体験をするということは貴重な体験かもしれない。
彼女の話に戻るが、身体の機能が奪われ日毎に不自由になっていく中で、少しでも生きるための努力を惜しまない、だけど若い遊びたい盛りの少女が闘病し、葛藤する様を彼女なりの言葉で書き綴っているこの本には生きたいという姿勢が克明に記されている。 読み進むにつれ(この本は通勤電車の中で読んでいた)、熱いものが込み上げてきて、ページを先に送ることをが辛くなることもあった。 涙を堪えることに苦労した。
彼女とともに、彼女の看病をした家族・医師・友人、その他多くの彼女に関わった人たちに支えられ、彼女は25歳10ヶ月で亡くなった。
彼女の人生に接し、彼女の周りの人たちが、また彼女に関わった全ての人たちが、生きる勇気と生きることの大事さを学んだことに違いない。
医師が看護婦が彼女と接することで、医療の現場に居ながら、彼女の“生”に対する強い気持ちを感じ、そして周りの患者たちまでもに、彼女のその気持ちがプラス思考にポジティブにはたらいていたことは、言うまでもない事実だ。
彼女の生きた“証”をこの本を読むことで感じられたこと、何不自由のない生活を送っている自分への戒め、健康で生んでくれ育ててくれた両親に感謝するとともに、残された時間を大事に使っていきたいという想いで一杯である。
この本を読んで、色んなところに感じるものがあった。 そのひとつにこんなくだりがあった。
とうとう言われてしまった。
「○○ちゃんもいい子にしていないと、あんなふうになっちゃうよ」
診察を受けに行った病院のトイレで転びそうになり、母に支えてもらっていた時だった。
必死につかまっているわたしの横で、赤いチェックの服を着た30代くらいのおばさんが、
小さい男の子に、ささやいていた。
悲しくて、惨めだった。
「子どもにあんな言い方をして育てていたら、自分が将来年とって体が不自由になった時、
いいお母さんにしとらんかったからそうなった、と間違った教えが自分にもどってくるんよ」
と母は慰めてくれた。
これからも、こんなことはたびたびあると思う。
幼い子が自分と違う人間に出会った時、珍しくてジロジロ見るのは仕方ないとしても、大人
から子供の躾の材料にされたのは初めてだったので、こたえた。
今更ながら、天国では自由に身体を動かして、今まで出来なかったことをひとつずつ、噛み締めながら遊んでいる、そんな彼女を想いつつ・・・。
ご冥福をお祈りします。




















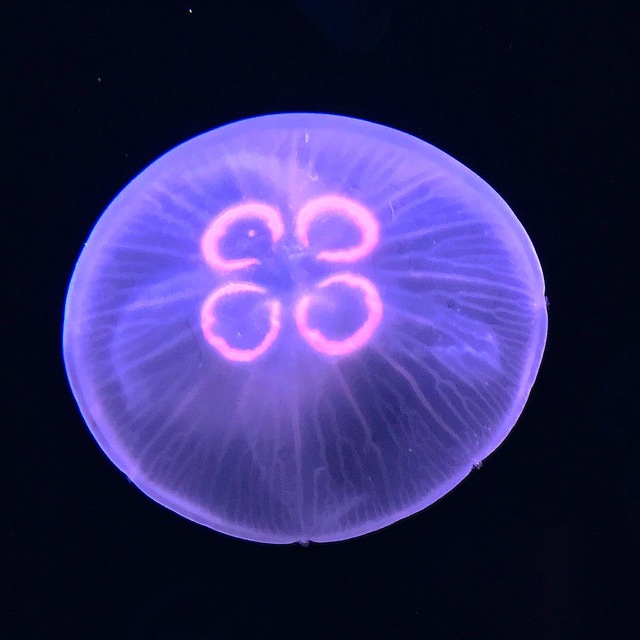





>今 再放送しているけど 亜也ちゃんは 強い人だったんだなぁって 思います
ほう、TVバージョンですね。
>亜也ちゃんとは 4才しか 違わないけど、自分より 大人だったんだなぁって思います
輪をかけて、お母さんはもっと強いですね!
> 亜也ちゃんの兄弟も悲しみを乗り越え 頑張って人の役に立つ仕事をしているらしいので それだけは 救いです。
そうですね^^
学ぶものはたくさん身近にあるということも・・・ですね。
>ドラマも涙なしには観られませんでした。 あそこまで泣いたのは、これまでになかったです。
ドラマは少しだけ観ました。 でも最後まではとても観れなかったです
>原作もそのうち読んでみます。
是非読んでみて下さいね!
原作ではなくドラマのレビューですが、
こちらからもTBさせていただきます。
ドラマも涙なしには観られませんでした。
あそこまで泣いたのは、これまでになかったです。
原作もそのうち読んでみます。
僕も知りませんでした><
今は何で当時この話を知らなかったのかと残念でなりません cyazさんはご存知でしたか?
>同情なんかじゃありません 僕自身も障害者ですし 文章の巧みさ? いえ、魂の叫びだと思います
そうだったんですね。 共感できる部分が多かったのでしょうね? 亜也さんの生き方自体に!
面倒くさいなのに三冊もつずけて読むなんて自分でも
信じられません 何がそんなに僕の心を揺り動かしたんでしょうか? 同情なんかじゃありません 僕自身も障害者ですし 文章の巧みさ? いえ、魂の叫びだと思います
>助言ありがとうございます。 さっそく手紙出してみます
いえいえ、たいした助言ができなくてm(__)m
>お忙しい方なので目にとまるかどうか分かりませんが自分の気持ちを全て書いて待つ事にします。
花を手向けることを断られることはないと思います!
頑張って、気持ちを伝えて下さいね^^
>こんなに感動した事がなかったので、じぶんでも驚いています。 亜也さんのお墓にお参りに行きたいのでご存知の方教えて下さい
ご存知の方がいれば教えてあげてほしいですが、直接お母様にその感動と意思を伝え、手紙でも出されてみてはいかがですか?
でも驚いています。 亜也さんのお墓にお参り
に行きたいのでご存知の方教えて下さい
>ドラマを見て木藤亜也さんの大好きな東高を去り岡養護学校に転校しなければならないそんな時亜也さんはひたむきに生きようとするそんな亜也さんを誇りに思っています。
生きる事の尊さとポジティブな亜也さんの姿勢には感心させられ、また教えられたものを多かったです!
裕美子さんのこれからの長い人生に、亜也さんの生き方が礎となることを期待しています!
抽象的なご質問では良くわかりませんし、ここはこの本に対してのコメントなり意見・感想をコメントいただくものですので、その点をよくご理解ください!
>私は、わざと歩けないまねをして、彼女の気持ちを知ろうとしていました。
それはなかなか難しいことだと思いますね・・・。
>私も彼女と同じ病気です。彼女のようにおおきな人間になりたいです
周りの人を思いやれる人でいて下さいね^^
集約された、凝縮された本ですよね!
死は彼女に取って恐ろしいものであるのに・・・。
最後の最後までまわりに気を使い、ずっと笑顔で接していた。素晴らしい彼女の“時””を過ごせたんだと今は思えます。
いやーーーいろんな意味で考えさせられる本ですよね。涙がとまりませんでしたわ~
こういってみんながいろんなことを感じ取ってくれる本を書いてくれた彼女に感謝ですね。
洞房ブロックという病気自体に何ら知識がないのですみません。
>過去に帰りたいけど帰れないんだから精一杯生きることを決めました
そうですね!ポジティブに生きるということを言うのは簡単ですが、なかなか実行できないのが現実ですね。
でも亜也さんの行き方に後押しされることが幾つかありました。振り向かないで前を向いて歩いていきたいですね^^
一番初めはびっくりしました。でも1リットルの涙を見てから病気の自分を好きにならなければしょうがないのだと思いましたそれで今の自分を精一杯生きようと思いました。過去に帰りたいけど帰れないんだから精一杯生きることを決めました
>思いやりと健康の大切さと「当たり前のものを失ってはじめて気づく人間という生き物の悲しさ」です
確かにそうかもしれません。
大病もなく、入院したこともない僕ですが、風邪ですら2・3日熱を出して寝込むと、健康の大切さを痛感します。でも元気になるとまた元通りの生活・・・。
“人間は考える葦である”
ポジティブに考えたいと思いつつもネガティブな現実があります。
亜也さんの努力の少しだけでも頑張らなければ!
大したことじゃないように聞こえるかもしれませんが以前急性肝炎で入院した際、それは苦しくつらい入院生活に感じ、テレビのどんな番組やCMを観ても「それもこれも健康だからできることだろう」という気持ちにしかなれず、世の中の目に見える広告や雑誌、ストーリー性はほとんど健全者向けのPRだと気づかされました。以前までそれが当たり前だと思わされていたことがそうじゃないと思えた瞬間でした。
しかし、それが完治したあとはそのときの感情や反省をすっかり忘れてまた当たり前の生活に戻りビールを飲んでいる自分がいる。。。
人間というのはそういうところが多かれ少なかれ必ずあるんじゃないかと僕は思います。
少なくとも僕はそんな人間のような気がします。
「自分じゃなくて良かった」とか「自分の大切な人じゃなくてよかった」という感情が恥ずかしながらあるような気がするんです。
前回の自分の病気、今回のドラマの内容、考えさせられるその瞬間瞬間に思うことは思いやりと健康の大切さと「当たり前のものを失ってはじめて気づく人間という生き物の悲しさ」です。
この心に響くような感情を大切に持ち続けることを自分自身に祈り続けるばかりです。
亜也さんありがとう。
僕はドラマは真剣に観ていませんが、エンディングに写される何枚かの彼女のカットは必ず観ています!
それはまさしく彼女の生きた軌跡だと思うからです。
写真は原作で感じた彼女の心を写しだしている様に思えるからなんですよ^^
あたしも泣き虫で毎回、ドラマの最後では、泣いちゃいます。昨日、ラストレター買って来て読みました最後にしたがって文が短くなってくるんです。せつない気持ち
>ついにドラマ化されましたねぇ~
そうですね、チラッと見ましたが最初はホームコメディみたいになってましたね。
>写真の中に残されている闘病中の笑顔などに結構感無量になってしまってます
あそこだけは見てますよ(笑)
このドラマより、あの写真の方が真実が見えて感動しちゃいます^^
TVドラマはさらりと見て、またこの本を読み返してみたいと思います^^
ついにドラマ化されましたねぇ~
時代もインターネットが自由に使える現代にちょっと置き換えたりしてますね(笑)
エンディングの曲が流れる中、当時の亜也さんの写真が何枚か登場します。
写真の中に残されている闘病中の笑顔などに
結構感無量になってしまってます^^;;;
映画とはまた違ったテイストになると思いますけど
やっぱりなんとなく気になって観てしまう今期の連ドラになってしまいました(笑)
最後まで闘い続けた彼女が、幸せだったのかどうかは彼女自身の問題だと思います。
>親より先に死ぬという不幸
突然の不幸でなく、先に子供が死んでいく様を見る親の気持ちは計り知れない悲しみだと思います。
そう考えると優しい家族の中で彼女は幸せな死を迎えることができたと思うのですが。
唯一だれでも一度だけ死ねる権利をあたえてくれる
木藤亜也は過酷な病気と前向きに闘いその
生き様を私たちに残してくれた
彼女の死後には幸な日々が続いているのでしょうか
親より先に死ぬという不幸を背負い難病との闘い
でもこの病気は彼女だけではなく誰にも知られず亡くなっている方もたくさんいるのでしょう
精一杯生きられ、私たちに感動を与えてくれた
彼女は幸せなほうなのでしょうか
私にはわかりません
ただ私は
このもらった人生後悔しないようにまっとうしたい
おひさしぶりですね^^
あやさんすみません、URL違っているようなのですが、確認していただけますか?
別名」は「わたしの子供になりなさい」(98年)
というアルバムに入ってます。調べていたらごめんなさい。あやでした。
大丈夫ですか?
『父と暮らせば』、DVD買いました!
是非レンタルして御覧になって下さいね^^
決して日本人が忘れてはいけないテーマなので・・・。
感想も聞かせて下さいね^^
しばらく、身も心も疲れ果て泣きながら眠るだけの
日々が続いていたので、、、今は回復しつつありますよ♪私と亜也さんの病気は全く違うのに、本を読むたび彼女と私を重ねてしまいます。名前が同じだから?
何故ですかね?私にもわかりません。
「父と暮らせば」の感想を読んだ後、6・24にDVD発売とレンタル開始のニュースを聞きました。
体調の良い時にレンタル屋さんに行って見ようと思います。では。また!
>中島 みゆきの曲名は「いのちの別名」です
了解です。調べてみます~♪
僕は小田和正のオリジナルアルバムが出たばかりなので、
それをずっと聴いています!
心が落ち着きますのであやさんもどうぞ^^
ロック系ですか?例えばどんなものでしょう?
鈴木雅之や高橋真梨子は昔から好きで聴いています~♪
最近はノラ・ジョーンズや綾戸智絵のライブにも行って来ました^^
今月は鈴木雅之、来月は高橋真梨子・綾戸智絵のコンサートに行ってきます^^
>「父と暮らせば」の感想
http://blog.goo.ne.jp/cyaz/m/200408
(テープに無造作に放り込んであるもので)でも、
とても悲しいメロデイですが、いい曲です。昨日
書いた後から気になってこればかり聴いています。
すいません、URL事情でまだ拾得してないんです。
出来たら、アドレスつきで投稿しますね。
ここ、音楽のカテゴリあるんですね。さっき見たら
おお!高橋 真李子(「り」の字を間違ってるかも)
鈴木 雅之!渋いですね。音楽大好きです!どうしてもロック系が多いのですが、、、。最近は年のせいか
民謡や演歌や戦前の歌謡曲なんかも聴いていたりします。
アドレスあったら、「父と暮らせば」の感想を聴くのにと思ってしまいます。まあ、そのうちにですね。
「海を飛ぶ夢」の感想を見てきます。
>ブックマークに登録
ありがとうございます。
ところであやさんのURL入れていただけるとありがたいのですが^^
>あるとすればそれは「自殺」という選択だけです。
う~ん、究極の選択なのでしょうか?
答えが一つだからこそ、そこから脱却し、半ば“悟り”の状態で残された時間を精一杯生きることが出来たのでしょうか?
>中島 みゆきの「いのちの名前」
すみません、この曲はしりません。
>「父と暮らせば」を観たい
是非観て下さい! 僕のレビューにも書きましたが『海を飛ぶ夢』も是非観て下さい!
ブックマークに登録させて頂きました。
亜也さんは、出来てきたことが出来ないと
いう恐怖を感じて生きてこられたと思います。私も、5年前に出来たことが、今出来ない、2年前に生きてきたことが出来ない、
半年前に、、、、ということで絶望する
ことが多々あります。精神障害は「死の恐怖」はありません。あるとすればそれは
「自殺」という選択だけです。亜也さんは
「いつか、自分の死は自然にやってくる」
と感じてましたね。私の恐怖の何倍も辛かったことでしよう。亜也さんにリハビリが必要
だったように、私たちにも「こころとからだ」の両面からのリハビリが課せられています。がんばります。ところで、この本を読んでいると、中島 みゆきの「いのちの名前」(ごめんなさい、タイトル間違っているかも
しれません)が流れてくるのです。
♪ 繰り返すあやまちを 照らす火をかざせ
名もない君にも 名もない僕にも
いのちにつぐ 名前を心と呼ぶ
名もない君にも 名もない僕にも♪
映画は好きですが、1月に「ハウル」を観た
きりです。「真夜中の弥次さん喜多さん」と「父と暮らせば」を観たいと思ってます。
>「私は自分を障害者と認めない」と「受け入れていこう」の2つの中で揺れています
難しいことだと思います。自分がその立場に立って考えることなんてできないと思うので。
でも障害者でなくても、日々色んな場面に遭遇し、葛藤していることは事実ですし、
小さな山を乗り越えながら生きています。
デコボコだらけですから、人生なんて^^
適切な言葉が見つからないですが、あやさんがご自分で選択肢を狭めないように
生きていって欲しいと思います。
貴重なコメントを戴き、ありがとうございました!
映画中心のブログですが、また是非覗いてみて下さい^^
私は、精神障害者です。心療内科を入退院しながら生活しています。亜也さんが高校時代
に「自分の障害を認めて生きていくこと」と
日記に書いていましたね。精神障害は見かけが普通と変わらないから誤解をどうしても
受けがちです。「私は自分を障害者と認めない」と「受け入れていこう」の2つの中で揺れています。亜也さんは、どうして自分の
障害を受け入れていったんだろう。その強さ
が羨ましいです。
いまも時々映画が再上映されないかチェックしていますが、
残念ながら予定はないようです。
DVDまでじっと我慢するしかないですね(笑) ?!
cyazさんは私の所のTB第一号さんでした。
コメント遅くなってしまいすいません。
映画見られなくて残念でしたね。
cyazさんが日記に書かれている印象的なシーンは
やはり映画でも印象に残るシーンでした。
「いい子にしていないと、あんなふうになっちゃうよ」という言葉はあまりに残酷な言葉でした。
ぜひDVDが出たら映画の方も見てみてください。
TBありがとうございました。
彼女の前向きな姿勢は、多分お母さんを見て育ったからでしょう!
この世に生まれ、全てが平等でなければならないのに、
若い年代でハンディを受け止めるには大変なことに違いありません。
それだけで足元を見つめ直してしまいます。
読み始めるのが延び延びになってしまい、
ようやく読了したのでお邪魔しました。
亜也さん、私より少し年上です。病魔に冒されながらもこんなに前向きで、周囲の人に常に感謝の気持ちを持っていられる亜也さん。自分がこの年齢の頃にはとてもできなかっただろうと思いました。
生きておられれば、子供を生み育てている年齢なんですよね。きっといいお母さんになられただろうに、とても残念です。
健常で居られることに感謝しなければいけませんよね^^
結構感動の1作ですよね、これ。
知り合いがちょっと病で倒れたり、親戚をなくしたり、自分も入院したりと色々あって、この作品に出会いましたが、出会えてよかったです
是非観てみたいですねぇ^^
見逃したのは自分のミスでしたが、
何だか映画環境の悪い地方の方の心境が今判るような気がします。
とても残念です。。。
時にふれて読み返してみたいと思っています。
この映画はたまたま原作者が豊橋出身ということで
豊橋での最初の公開時に鑑賞させていただきました。
感想はblogはじめる前なので(笑)猫の映画のDBのほうで公開してますけど
ほんっといろんな意味で大勢の方に観ていただきたい映画です。
人生何がいつ、何が起こるかわからないのですから
やっぱり、時は大事に重ねて生きたいものだと痛感しますね。
なかなか普段日常生活で手助けをと思うのですが、
勇気を持って接することが出来ないのが現実です。
せめてお年寄りには優しく出来るように心がけています。
でも自分ひとりではダメですねぇ・・・
みんながそう思わないと。
“優先席”って意味から理解させないと(怒)?!
読み終わってすぐの感情と少し経ってからの気持ちというのは違いますね。
もう少し、優しくなろうと思いました。
出来るだけ、自分が出来ることは自分でしよう。
助けられることが出来るのであれば、少しでも役に立ったらなぁと思うようになりました。
そういった気持ちの変化も大切ですよね。
これを機会にまた、遊びに来ますね。
ハンディを背負ってもなおかつ諦めないでポジティブに生きる姿勢に感動しました。
この本を読んで彼女は心の中で生き続けています。
また人生に挫けそうになったら読んでみたいと思います!
こちらこそよろしくお願いします。
映画ネタばかりですけど(笑)
私も障害者なので、亜也さんの気持ちが分かる部分(やむなく転校したり、病院での子供と親のやり取りなど)もありますが、辛い状況の中でも自分の人生に絶望せず、光を保って生き続けた姿はとても尊敬しています。
亜也さんの思いはまだ生き続けているんだなと実感できる本ですよね。今後ともよろしくお願いいたします。
彼女の献体は絶対に無駄になっていないはずです。
頑張って下さい!
確かに難しい問題ですね。
この原作の映画版を観なかったことが非常に悔やまれてなりません。
また、東京近郊でこの映画が上映されることを祈ります!
同じようにこの世に生を受け、青春と一番楽しいときに、ハンディを背負ってしまった彼女に罪は無いと思います。
それでも強く生きようと、そして彼女を取り巻く人たちも
彼女と共に強くなったと思うのです。
彼女が献体がこの病気の解明に少しでも役立てばいいと願うばかりです。
心ない大人もいます。幼い子がじろじろ見る、というのも、これは躾とか親やまわりの大人(環境も含めた)の問題のような気もしています。
赤ちゃんだったら、何もわからない、、、とはいえ、「奇異の目」を向けるということは決してないと思うので。
難しいです。自分がそのような立場になったら…という想像がうまくできません。
おかあさんの書かれた「いのちのハードル」もとても感動的でしたよ。
普通の生活ができることのありがたさを普段はつい忘れてしまいますね。読んでいて自分のこと反省させられました。