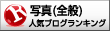現業多忙 な上に、昨日まで母校が夏の甲子園に向けた試合があった関係で、最近は、これまで毎日のようにお邪魔している方のブログウォッチングも、ままならない状況です…
な上に、昨日まで母校が夏の甲子園に向けた試合があった関係で、最近は、これまで毎日のようにお邪魔している方のブログウォッチングも、ままならない状況です…
 。
。
25日の業務進捗報告会が終わるまでは、こんな毎日が続くかもしれません… 。
。
英語との「 格闘
格闘 」も進捗が遅れていて、焦って
」も進捗が遅れていて、焦って いますし…
いますし… 。
。
そんな中、今日、会社に出社し、始業前と昼食休憩中にブログウォッチングをほんの数分していたときに、風屋さんと、nanaponさんが、それぞれ『文化人類学』と、『妻の呼び方』という、大変興味ある記事をエントリーしていました 。
。
もっと申し上げると、nanaponさんは、『研究課題』という記事もエントリーなさっていますが、風屋さんのご指摘どおり、『文化人類学』と相通じるものがあると、小生も感じます 。
。
実は、小生宅でも、本件では随分前に家内と「もめた」こともあるので、そのエピソードも交えて、若干「三番煎じ」と読者の皆さんや、風屋さんとnanaponさんからご批判を受けても致し方ないのですが …ちょっと記事にしてみたいと思います
…ちょっと記事にしてみたいと思います 。
。
山口では、時々風屋さんも同じ表現をなさるときがありますが、男性側から女性の「パートナー」を…
 「おかあちゃん」
「おかあちゃん」
とか…
 「家(うち)の者(もん)」
「家(うち)の者(もん)」
といった表現を用いて呼ぶのが多いようです。
大手総合化学メーカーの、プラント(製品の製造現場=工場)がすぐ近くにある研究所に勤務していると、当然ながら、プラントオペレーターの方とも何らかの接点を持って業務を進めなければなりません。
そんなときは、小生も「山口弁」を駆使しながら、オペレーターの方と業務の話を進めます。
ちなみに最初にお断りをしておきますが、小生は、現在は公の場(この自身のブログも含めて)や、電話での応答などでは、「パートナー」を「家内」と呼ぶように統一しています。
今ではすっかりこの呼び方に慣れましたので、滅多に先程ご紹介したような呼び方は使わないですね 。
。
小生も家族がある身の上で、3歳8ヶ月になった娘が一人いますが、3年程前に、ちょっと家内との関係がギクシャクしていたときに、提案した小生も小生ですが、家内への呼び方を…
「“おかあちゃん”か“おかあさん”にしたいんだけど…」
と提案しました。
ところが、家内からこの呼び方に対し、
「絶対に嫌ですっ
 」
」
と一蹴されたことがあります 。
。
理由は、家内にとっては、小生の「おかあちゃん=母」では決してなく、あくまでも小生は「夫」であり、「パートナー」であるからだそうです。
ですので、もし呼ぶのであれば、“下”の名前に“ちゃん”だの“さん”だのといった「敬称」だけは、略して欲しくはないそうです。
(なんと、「呼び捨て」もダメです。)
これはこれで大変立派な理屈ですので、現在では尊重していますし、実際に「名前の略+“ちゃん”」で小生は呼び止めています。
家内自身も、「名前の略称」で書置きを残したりもしていますね 。
。
(岩根 忍 女流初段が、ご自身を「しぃ」と呼んでいるのと同じ感覚ですね。)
ところが…家内の主張で若干矛盾しているのは、家内は、小生を呼び止めるときに…
 「ねえ」
「ねえ」
とか…
 「君」
「君」
などと呼びます 。
。
(公の場や、お互いの父母の前では、「“下”の名前+君」と呼んでいただけますが… 。)
。)
もう一つお断りしておきますが…実は小生の家内は、将棋界では、渡辺 明 竜王や、片上 大輔 五段や、松尾 歩 六段のように、家内の方が歳が上の、いわゆる「姉さん女房」です。
なので、理屈で抵抗すると、かなり「ボコボコ」にやられます…
 。
。
なので、これも言い返せず、妙に「納得」して、毎日を過ごしています… 。
。
ですが、風屋さんがご自身のエントリー記事でおっしゃっているように、これも『価値観』だと思うのです。
で、よくよく考えますと、小生と家内は、生まれ育った土地が、「埼玉」と「山口」…。
当然全く違う「文化」を持った土地で、お互い成長したわけです。
『価値観』が違って、当然ですよ…ね 。
。
ある部分では似た『価値観』を持っていたから、何かの「ご縁」で、こうして一緒に一つ屋根の下で暮らすことになり、娘も授かったわけです 。
。
(その「ご縁」は、実は「手話」です。蛇足ですが、家内も健聴者です。)
全く『価値観』が一緒なら、ちょっと「怖い」ですよね。
と申し上げるより、人間10人いれば10通りの個性があるわけですから、違っていて当然…ですよね 。
。
そんな中、全く『価値観』が一緒と勘違いして、ある日突然「パートナー」としての関係が崩れたら、実は案外脆いのかもしれません。
それこそ、「坂を転げ落ちる」ように、修復不可能な域に簡単に達してしまうのかも…なんて、ちょっと恐ろしいことを思ったりもします。
でも、その『価値観』の違いを、「新たな発見」と思うと、「パートナー」への見方も凄く変わることに、最近になって気付いてきましたね 。
。
家内とは喧嘩も確かにしますが、ようやく最近になって、お互いに理解できる部分が増えていき、関係は3年前の「ギクシャク感」とは随分変わったと思います 。
。
会話も、実は結婚当初よりは増えましたし、お互いにいい意味での「妥協」なのかもしれませんね… 。
。
(こういうのを、「妥協の産物」と申し上げて宜しいのでしょうかね 。)
。)
ただ1点だけ、「気になっていること」があります… 。
。
それは、こういった「パートナー」同士の呼び方が、娘がこれから大きく育っていく環境にあって、教育上好ましいのかどうか…ということです。
家内の躾がとても良く行き届いているためか 、家内や小生には、娘は、現時点ではちゃんと「おかあさん」「おとうさん」と呼んでくれてはいますが…
、家内や小生には、娘は、現時点ではちゃんと「おかあさん」「おとうさん」と呼んでくれてはいますが… 。
。
でも、そう考えると、非常に微妙…ですよね 。
。
理屈っぽくなりましたが、『価値観』の違いから、どうしても発生する「パートナー」への呼びかけ方…。
案外、アカデミックな事柄ですし、子供を授かっている身の上ですと、余計にその「難しさ」を感じる、今日この頃です 。
。
 な上に、昨日まで母校が夏の甲子園に向けた試合があった関係で、最近は、これまで毎日のようにお邪魔している方のブログウォッチングも、ままならない状況です…
な上に、昨日まで母校が夏の甲子園に向けた試合があった関係で、最近は、これまで毎日のようにお邪魔している方のブログウォッチングも、ままならない状況です…
 。
。25日の業務進捗報告会が終わるまでは、こんな毎日が続くかもしれません…
 。
。英語との「
 格闘
格闘 」も進捗が遅れていて、焦って
」も進捗が遅れていて、焦って いますし…
いますし… 。
。そんな中、今日、会社に出社し、始業前と昼食休憩中にブログウォッチングをほんの数分していたときに、風屋さんと、nanaponさんが、それぞれ『文化人類学』と、『妻の呼び方』という、大変興味ある記事をエントリーしていました
 。
。もっと申し上げると、nanaponさんは、『研究課題』という記事もエントリーなさっていますが、風屋さんのご指摘どおり、『文化人類学』と相通じるものがあると、小生も感じます
 。
。実は、小生宅でも、本件では随分前に家内と「もめた」こともあるので、そのエピソードも交えて、若干「三番煎じ」と読者の皆さんや、風屋さんとnanaponさんからご批判を受けても致し方ないのですが
 …ちょっと記事にしてみたいと思います
…ちょっと記事にしてみたいと思います 。
。山口では、時々風屋さんも同じ表現をなさるときがありますが、男性側から女性の「パートナー」を…
 「おかあちゃん」
「おかあちゃん」とか…
 「家(うち)の者(もん)」
「家(うち)の者(もん)」といった表現を用いて呼ぶのが多いようです。
大手総合化学メーカーの、プラント(製品の製造現場=工場)がすぐ近くにある研究所に勤務していると、当然ながら、プラントオペレーターの方とも何らかの接点を持って業務を進めなければなりません。
そんなときは、小生も「山口弁」を駆使しながら、オペレーターの方と業務の話を進めます。
ちなみに最初にお断りをしておきますが、小生は、現在は公の場(この自身のブログも含めて)や、電話での応答などでは、「パートナー」を「家内」と呼ぶように統一しています。
今ではすっかりこの呼び方に慣れましたので、滅多に先程ご紹介したような呼び方は使わないですね
 。
。小生も家族がある身の上で、3歳8ヶ月になった娘が一人いますが、3年程前に、ちょっと家内との関係がギクシャクしていたときに、提案した小生も小生ですが、家内への呼び方を…
「“おかあちゃん”か“おかあさん”にしたいんだけど…」
と提案しました。
ところが、家内からこの呼び方に対し、
「絶対に嫌ですっ

 」
」と一蹴されたことがあります
 。
。理由は、家内にとっては、小生の「おかあちゃん=母」では決してなく、あくまでも小生は「夫」であり、「パートナー」であるからだそうです。
ですので、もし呼ぶのであれば、“下”の名前に“ちゃん”だの“さん”だのといった「敬称」だけは、略して欲しくはないそうです。
(なんと、「呼び捨て」もダメです。)
これはこれで大変立派な理屈ですので、現在では尊重していますし、実際に「名前の略+“ちゃん”」で小生は呼び止めています。
家内自身も、「名前の略称」で書置きを残したりもしていますね
 。
。(岩根 忍 女流初段が、ご自身を「しぃ」と呼んでいるのと同じ感覚ですね。)
ところが…家内の主張で若干矛盾しているのは、家内は、小生を呼び止めるときに…
 「ねえ」
「ねえ」とか…
 「君」
「君」などと呼びます
 。
。(公の場や、お互いの父母の前では、「“下”の名前+君」と呼んでいただけますが…
 。)
。)もう一つお断りしておきますが…実は小生の家内は、将棋界では、渡辺 明 竜王や、片上 大輔 五段や、松尾 歩 六段のように、家内の方が歳が上の、いわゆる「姉さん女房」です。
なので、理屈で抵抗すると、かなり「ボコボコ」にやられます…

 。
。なので、これも言い返せず、妙に「納得」して、毎日を過ごしています…
 。
。ですが、風屋さんがご自身のエントリー記事でおっしゃっているように、これも『価値観』だと思うのです。
で、よくよく考えますと、小生と家内は、生まれ育った土地が、「埼玉」と「山口」…。
当然全く違う「文化」を持った土地で、お互い成長したわけです。
『価値観』が違って、当然ですよ…ね
 。
。ある部分では似た『価値観』を持っていたから、何かの「ご縁」で、こうして一緒に一つ屋根の下で暮らすことになり、娘も授かったわけです
 。
。(その「ご縁」は、実は「手話」です。蛇足ですが、家内も健聴者です。)
全く『価値観』が一緒なら、ちょっと「怖い」ですよね。
と申し上げるより、人間10人いれば10通りの個性があるわけですから、違っていて当然…ですよね
 。
。そんな中、全く『価値観』が一緒と勘違いして、ある日突然「パートナー」としての関係が崩れたら、実は案外脆いのかもしれません。
それこそ、「坂を転げ落ちる」ように、修復不可能な域に簡単に達してしまうのかも…なんて、ちょっと恐ろしいことを思ったりもします。
でも、その『価値観』の違いを、「新たな発見」と思うと、「パートナー」への見方も凄く変わることに、最近になって気付いてきましたね
 。
。家内とは喧嘩も確かにしますが、ようやく最近になって、お互いに理解できる部分が増えていき、関係は3年前の「ギクシャク感」とは随分変わったと思います
 。
。会話も、実は結婚当初よりは増えましたし、お互いにいい意味での「妥協」なのかもしれませんね…
 。
。(こういうのを、「妥協の産物」と申し上げて宜しいのでしょうかね
 。)
。)ただ1点だけ、「気になっていること」があります…
 。
。それは、こういった「パートナー」同士の呼び方が、娘がこれから大きく育っていく環境にあって、教育上好ましいのかどうか…ということです。
家内の躾がとても良く行き届いているためか
 、家内や小生には、娘は、現時点ではちゃんと「おかあさん」「おとうさん」と呼んでくれてはいますが…
、家内や小生には、娘は、現時点ではちゃんと「おかあさん」「おとうさん」と呼んでくれてはいますが… 。
。でも、そう考えると、非常に微妙…ですよね
 。
。理屈っぽくなりましたが、『価値観』の違いから、どうしても発生する「パートナー」への呼びかけ方…。
案外、アカデミックな事柄ですし、子供を授かっている身の上ですと、余計にその「難しさ」を感じる、今日この頃です
 。
。