前回の設問の解答編です。
ダーウィンの進化理論は複数の主張を含んでおり、例えば以下の5つにまとめられます1,2)。
1)進化すること(進化説)
2)共通祖先と分岐(共通起源説)
3)漸進性(漸進説)
4)集団内の個体変異による進化と種分化
5)自然淘汰説(自然選択説)
この5つの中に現在では必ずしも正しくはない主張が含まれています。それはどれでしょうか? 答えは共通起源説と漸進説です。
まずは3の漸進説です。ダーウィンは進化は地質学的な長時間をかけてゆっくり進むと考えました。それゆえ人の一生くらいの観察時間では進化は目に見えないというわけです。確かに化石等から観察される多くの過去の生物の進化はそうなのですが、目に見えるほど速い進化もあるということは、例えばグラント夫妻によるダーウィンフィンチの研究5,6,7)で明らかになりました。
-------------Ref5,p178
最近、進化学者のフィリップ.シンジャリッチが、数カ月から一年半くらいの速い速度でみられた人為選択の例から、化石標本の例まで進化的変化を五〇〇例以上集め、ダーウィン単位で表わしてみた。その結果、ダーウィンからホールテインにいたる従来の進化学者たちが考えてきたこととはまったく反対の実に単純なパターンを発見した。つまり、生物を近くで見れば見るほど、進化的変化は速く著しいが、時間的に遠く離れれば離れるほど、変化は目につかなくなる。
-------------
ダーウィン理論の漸進説は地質学者のライエルが広めた斉一説から影響を受けたのですが、その地質学でも現在では、堆積や風化などのゆつくりした変化のみならず、例えば火山の噴火、崖崩れ等の急激な変化も、地形を変えることにかなり寄与しているということが知られています。
ただし跳躍説としてまとめられる種の突発的な変化や誕生という説に対する対立仮説という意味での漸進説は揺るがないことは強調しておきます。
次に共通起源説です。そのものずばりの文献をどうぞ。
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0005/roots.html
日経サイエンス 2000年5月号
「生命のルーツはひとつなのか」
つまり、遺伝子の水平移動のために原核生物の段階では系統樹が網の目状になっており、単一の祖先種から多数の種が分岐してきたという図式にはとうてい当てはまらないということです。むしろ全世界にひろがる一塊りの遺伝子プールがゆっくりと組成を変化させてきたという方が当てはまるかも知れません。まるで原子の結合手から電子雲の塊へと見方が変わるようなものですね。もっとも全生物が共通のシステムを持ち遺伝子単位の進化も含めて系統樹思考が有効であることは間違いありません。
しかしその共通システムも、現在のDNA-RNA-タンバク質システムの前にはRNAワールドがあったという仮説もありますし、さらに生命の起源に遡れば鉱物-有機物システムなどという仮説も出ています。ここら辺になると、起源の場所や時が違っても同じ様なものになるという可能性もありますが。
次回は主にマイアの本にしたがって5つの理論の詳しい話をしたいと思います。
-----参考文献-------------
1) エルンスト・マイア(著);養老孟司(訳)『ダーウィン進化論の現在』岩波書店(1994/04)
2) 河田雅圭 "科学(1998/12)[小特集:今を生きるダーウィン]"p943「ダーウィンの進化理論と現代の生物学」
3) Mayr,E. "The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance" Harvard Univ.Press(1982)
4) Futuyma,D.J. "Evolutionary Biology 3rd" Sinaure(1998)
日本語訳は第2版でMayrの文献より前なので5つのまとめはないかも知れない。
フツイマ『進化生物学』蒼樹書房(1997/06), ISBN-10:4789130479
5) ジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴』ハヤカワ文庫(2001/11)
6) http://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textintro/Chapt4.htm
3.自然選択による進化
7) http://meme.biology.tohoku.ac.jp/introevol/finch.html
ダーウィンフィンチの30年間の進化: 自然選択の実証例 (c)河田雅圭
ダーウィンの進化理論は複数の主張を含んでおり、例えば以下の5つにまとめられます1,2)。
1)進化すること(進化説)
2)共通祖先と分岐(共通起源説)
3)漸進性(漸進説)
4)集団内の個体変異による進化と種分化
5)自然淘汰説(自然選択説)
この5つの中に現在では必ずしも正しくはない主張が含まれています。それはどれでしょうか? 答えは共通起源説と漸進説です。
まずは3の漸進説です。ダーウィンは進化は地質学的な長時間をかけてゆっくり進むと考えました。それゆえ人の一生くらいの観察時間では進化は目に見えないというわけです。確かに化石等から観察される多くの過去の生物の進化はそうなのですが、目に見えるほど速い進化もあるということは、例えばグラント夫妻によるダーウィンフィンチの研究5,6,7)で明らかになりました。
-------------Ref5,p178
最近、進化学者のフィリップ.シンジャリッチが、数カ月から一年半くらいの速い速度でみられた人為選択の例から、化石標本の例まで進化的変化を五〇〇例以上集め、ダーウィン単位で表わしてみた。その結果、ダーウィンからホールテインにいたる従来の進化学者たちが考えてきたこととはまったく反対の実に単純なパターンを発見した。つまり、生物を近くで見れば見るほど、進化的変化は速く著しいが、時間的に遠く離れれば離れるほど、変化は目につかなくなる。
-------------
ダーウィン理論の漸進説は地質学者のライエルが広めた斉一説から影響を受けたのですが、その地質学でも現在では、堆積や風化などのゆつくりした変化のみならず、例えば火山の噴火、崖崩れ等の急激な変化も、地形を変えることにかなり寄与しているということが知られています。
ただし跳躍説としてまとめられる種の突発的な変化や誕生という説に対する対立仮説という意味での漸進説は揺るがないことは強調しておきます。
次に共通起源説です。そのものずばりの文献をどうぞ。
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0005/roots.html
日経サイエンス 2000年5月号
「生命のルーツはひとつなのか」
つまり、遺伝子の水平移動のために原核生物の段階では系統樹が網の目状になっており、単一の祖先種から多数の種が分岐してきたという図式にはとうてい当てはまらないということです。むしろ全世界にひろがる一塊りの遺伝子プールがゆっくりと組成を変化させてきたという方が当てはまるかも知れません。まるで原子の結合手から電子雲の塊へと見方が変わるようなものですね。もっとも全生物が共通のシステムを持ち遺伝子単位の進化も含めて系統樹思考が有効であることは間違いありません。
しかしその共通システムも、現在のDNA-RNA-タンバク質システムの前にはRNAワールドがあったという仮説もありますし、さらに生命の起源に遡れば鉱物-有機物システムなどという仮説も出ています。ここら辺になると、起源の場所や時が違っても同じ様なものになるという可能性もありますが。
次回は主にマイアの本にしたがって5つの理論の詳しい話をしたいと思います。
-----参考文献-------------
1) エルンスト・マイア(著);養老孟司(訳)『ダーウィン進化論の現在』岩波書店(1994/04)
2) 河田雅圭 "科学(1998/12)[小特集:今を生きるダーウィン]"p943「ダーウィンの進化理論と現代の生物学」
3) Mayr,E. "The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance" Harvard Univ.Press(1982)
4) Futuyma,D.J. "Evolutionary Biology 3rd" Sinaure(1998)
日本語訳は第2版でMayrの文献より前なので5つのまとめはないかも知れない。
フツイマ『進化生物学』蒼樹書房(1997/06), ISBN-10:4789130479
5) ジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴』ハヤカワ文庫(2001/11)
6) http://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textintro/Chapt4.htm
3.自然選択による進化
7) http://meme.biology.tohoku.ac.jp/introevol/finch.html
ダーウィンフィンチの30年間の進化: 自然選択の実証例 (c)河田雅圭










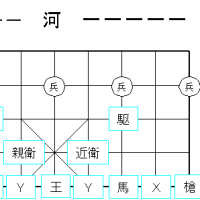
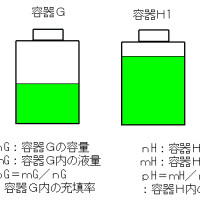
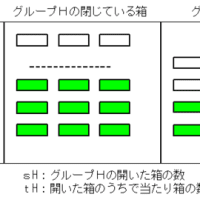
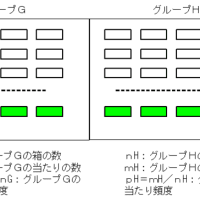
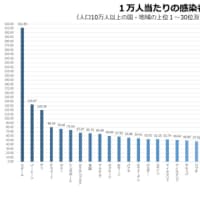
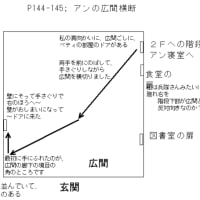
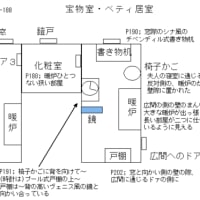
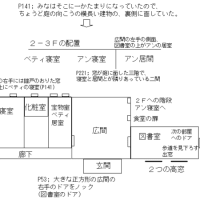
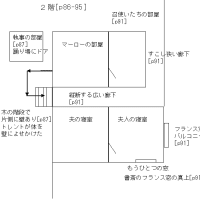
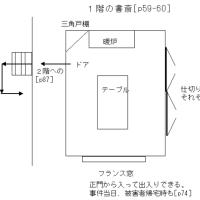






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます