ブルーノ・ラトゥール(Bruno Latour)『科学が作られているとき』という本があります[Ref-1]。実験室(研究室か?)において科学理論が作られているまさにその時の様子を人類学的手法で観察し、その原理を明らかにしたらしいと聞いていました。私の考えではこの手法は、科学技術活動というものを実際に即して知ろうとする、まさに科学的なものです。でもその理論付けがゆきすぎて、科学的知識そのものまで「社会的に構成されたもののみである」と言い切って、トンデモな方向に行ってるらしい、とかそれは誤解だとか色々噂を聞いていました。
ということで読んでみましたが、わかりにくい---。量も多いし、最初から読み進もうとしても無理です。一番困るのは、使われている用語の意味がわかりにくいこと。この手の本では日常的な言葉が実は専門的な意味を持っていて、自分の生半可な知識で読むと誤読することは珍しくありません。自然科学系の本でもそれは同じですが、自然科学系の場合は専門用語の意味は分野内では共通だし辞典にも載っているのが大半です。ところが人文科学系ではへたをすると人によって意味が違ったりする恐れもあります。で、この本の中の何気ない単語が通常の字義通りに受け取ったら誤読しそうなものばかりみたいな気がして困るのです。
そこでまず後ろにある訳者解説と訳者あとがきを読んでから、付録の「方法の規則」と「原理」を読んだうえで、6つの章をとっつきやすそうなものからランダムに読んでみるという方法がよさそうです。
「「原理」という言葉で意味していることは、この領域で一〇年にわたって研究して手に入れた経験的事実の「私の」個人的要約である。したがって、これらの原理が反論され、反証され、他の要約に取って代わられることを期待している。」(序章,p29)とのことなので、つまりは「原理」というのがこの本で言いたい結論と思われます。それは6つあります。
第一原理 事実や機械の命運は後の使用者の手の中にある。したがって、その質は集団的行為の結果であって原因ではない。(第1章)
第二原理 科学者や技術者は、自ら形作り、動員した新たな同盟相手の名で語る。代弁者のなかの代弁者は、力のバランスを自らに有利なように傾けるために、こうした予期せぬリソースを付け加える。(第2章)
第三原理 われわれは、科学や技術や社会と直面することは決してなく、ありとあらゆる弱い連関と強い連関に直面する。したがって、事実や機械が何であるのかを理解することは、人々が誰であるのかを理解することと同じである。(第3章)
第四原理 科学と技術が秘教的内容を持てば持つほど、さらに外側へと拡大する。したがって、「科学と技術」はテクノサイエインスの部分集合でしかない。(第4章)
第五原理 非合理性とは、ネットワークを構築する者が道に立ちふさがる者に対して常に加える告発である。したがって、精神の間の大分割はなく、ただ短いネットワークと長いネットワークがあるだけである。より固い事実は通例ではなく例外である。なぜなら、通常の道から大規模に他の人々を移動させるために少数の例でしか必要でないからである。(第5章)
第六原理 テクノサイエンスの歴史は、その大部分が、遠隔作用を可能にする痕跡の可動性、信頼性、結合、一体性を加速するためにネットワークに沿って分散したリソースの歴史である。(第6章)
えー、意味わかんない。「事実や機械の命運」て何? 「遠隔作用」て、「リソース」て、・・・。
ということで訳者あとがきを読んでみます。それによれば、この本で「打倒すべき科学像と目されている」科学像とは「伝統的な認識論的かつ実在論的な科学像」と「安易に「杜会」というカテゴリーを設定した上で「科学の社会的次元」などを得々と語るような科学論」との2つであり、「いわば二正面作戦」を展開しているとのことです。
前者はわかりますが、後者は具体的に誰のどんな理論かこれだけではわかりません。それを知っておくことが前提知識となるのでしょう。
そして、「われわれ読者は否応なしにラトゥール(や「反対者」や「事実構築者」)とともに「旅人」となってテクノサイエンスの世界を旅していくのだが、その途上で行われていることは、実はたったひとつのことである。それは、連関(associatiion)、関係(relation)、結び付き(connection)、絆(tie)、リンク(link)等と様々な言葉で言い換えられているが(一番多用されるのが「連関」なので、以下「連関」で統一する)、要するに不均質極まりない多種多様な要素とその連関にひたすら注目し、描写していくことにより、従来の科学論で語られていた内容をすべて置換していくという作業である。」
うわー、同じ意味に同一本の中でそんなにたくさんの言葉を当てるなよ。というか、それらの言葉は微妙に使い分けられていて、それが重要かも知れない、と疑心暗鬼にかられるのですが、どうしてくれる。ま、同じだというんだから素直に同じと仮定して読んでみるのが良いでしょう。
結論めいたこととしては、「この過程を通じて、「テクノサイエンス」はネットワークとしての性格を有していることが明らかにされていく、そして、ついには重要なのは互いに結び付いている諸要素よりも、結び付けている連関そのものの方であることを明らかにしていくこと。こうした、いわば「連関一元論」、あるいは「唯物論」ならぬ「唯連関論」とでも呼ぶべきものこそがラトゥールの科学論全体を通底する本質であり、これこそがまさに人類学的発想ないし人類学的思考の産物に他ならない。」
うむ、なんとなくわかります。「テクノサイエンス」という人間の活動をグラフでイメージできるようなネットワークとして表現したということでしょうね。そして結び付けられている具体的な事物(人や物や個別組織などでしょうか、それとも事件(event)等でしょうか)は抽象化してしまう、と。でも、それで何がわかったのか、というのがどうもまだ理解できていません。
他のものごとと同様に「テクノサイエンス」もグラフネットワークとして表現することは可能でしょう。それにより例えばこの本で挙げられているような「テクノサイエンス」の様々な事例について、個々の特種事情によらない共通な性質や共通な原理が見出される可能性は大いにあるでしょう。では何かそのような共通な性質や共通な原理が見出されたのかというと・・・うーん、それが上記の6つの「原理」だということになるのでしょうか? 各用語の(ラトゥールの意図する)意味がわからないということもありますが、どうも観察事実を要約して(かつ抽象化して)述べただけという印象が強くて、この原理から何かが予測できそうというものが感じられません。例えばクーンのパラダイム理論やマルクスの社会発展理論などは何らかの予測をできることがわかりやすく、それゆえに反証可能性があるとも言えるのですが、「科学(活動)の中に連関があるよ」と指摘するだけではねえ。まあ見えることを指摘したこと自体は手柄と見るべきで、その後は具体的な様々な事例で連関構造を調べてゆくのが研究の成り行きとなるでしょうから、つまりはこの本の意義は「テクノサイエンス」研究の新規な方法論を提案したという点にあるのかも知れません。
そして冒頭に述べた噂の真偽ですが、まず「実験室(研究室か?)において科学理論が作られているまさにその時の様子を人類学的手法で観察した報告」はこの本には載っていません。その報告は『実験室の生活ー科学的事実の構成』"Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts" (1979 republished 1986) で邦訳はなさそうです。しかしどのようなものかということは日本での研究である「実験室における社会実践の民族誌学的研究」(2009/10/21と推定)や「科学的事実の産出と研究者の実践について」で雰囲気が感じられそうです。
次に「科学的知識そのものも社会的に構成されたものである」とは書いてありません。むしろ"社会的"という言葉を安易に使うことに反対しているようです。じゃーどう考えているかはよくわかりません。なんだか従来の説明概念を破棄したはいいが、替わりとなる説明概念の提出はできてないという印象です。まあきっと提出されている説明概念が私に理解できていないだけなのでしょう。
科学的知識のどこまでを社会的に構成されたものとみなすかというテーマには、科学論研究者[*1]の間でも多様な見解があるようですから調べるのも大変ですが、Ref-2,3あたりは一連の研究の流れを述べていてひとまず参考になりそうです。
---------------------
参考文献
1) ブルーノ・ラトゥール;川崎勝(訳);高田紀代志(訳)『科学が作られているとき―人類学的考察』産業図書 (1999/03)
2) 書評平英美・中河伸俊編『構築主義の社会学――論争と議論のエスノグラフィー』
3) 書評ジョゼフ・ラウズ(著);成定薫(訳);阿曽沼明裕(訳)『科学のカルチュラル・スタディーズとは何か』
*1) ひとくちに科学論と言っても幅広いし、相対主義、社会構築主義(社会構成主義)と言っても幅広いようだ。
ということで読んでみましたが、わかりにくい---。量も多いし、最初から読み進もうとしても無理です。一番困るのは、使われている用語の意味がわかりにくいこと。この手の本では日常的な言葉が実は専門的な意味を持っていて、自分の生半可な知識で読むと誤読することは珍しくありません。自然科学系の本でもそれは同じですが、自然科学系の場合は専門用語の意味は分野内では共通だし辞典にも載っているのが大半です。ところが人文科学系ではへたをすると人によって意味が違ったりする恐れもあります。で、この本の中の何気ない単語が通常の字義通りに受け取ったら誤読しそうなものばかりみたいな気がして困るのです。
そこでまず後ろにある訳者解説と訳者あとがきを読んでから、付録の「方法の規則」と「原理」を読んだうえで、6つの章をとっつきやすそうなものからランダムに読んでみるという方法がよさそうです。
「「原理」という言葉で意味していることは、この領域で一〇年にわたって研究して手に入れた経験的事実の「私の」個人的要約である。したがって、これらの原理が反論され、反証され、他の要約に取って代わられることを期待している。」(序章,p29)とのことなので、つまりは「原理」というのがこの本で言いたい結論と思われます。それは6つあります。
第一原理 事実や機械の命運は後の使用者の手の中にある。したがって、その質は集団的行為の結果であって原因ではない。(第1章)
第二原理 科学者や技術者は、自ら形作り、動員した新たな同盟相手の名で語る。代弁者のなかの代弁者は、力のバランスを自らに有利なように傾けるために、こうした予期せぬリソースを付け加える。(第2章)
第三原理 われわれは、科学や技術や社会と直面することは決してなく、ありとあらゆる弱い連関と強い連関に直面する。したがって、事実や機械が何であるのかを理解することは、人々が誰であるのかを理解することと同じである。(第3章)
第四原理 科学と技術が秘教的内容を持てば持つほど、さらに外側へと拡大する。したがって、「科学と技術」はテクノサイエインスの部分集合でしかない。(第4章)
第五原理 非合理性とは、ネットワークを構築する者が道に立ちふさがる者に対して常に加える告発である。したがって、精神の間の大分割はなく、ただ短いネットワークと長いネットワークがあるだけである。より固い事実は通例ではなく例外である。なぜなら、通常の道から大規模に他の人々を移動させるために少数の例でしか必要でないからである。(第5章)
第六原理 テクノサイエンスの歴史は、その大部分が、遠隔作用を可能にする痕跡の可動性、信頼性、結合、一体性を加速するためにネットワークに沿って分散したリソースの歴史である。(第6章)
えー、意味わかんない。「事実や機械の命運」て何? 「遠隔作用」て、「リソース」て、・・・。
ということで訳者あとがきを読んでみます。それによれば、この本で「打倒すべき科学像と目されている」科学像とは「伝統的な認識論的かつ実在論的な科学像」と「安易に「杜会」というカテゴリーを設定した上で「科学の社会的次元」などを得々と語るような科学論」との2つであり、「いわば二正面作戦」を展開しているとのことです。
前者はわかりますが、後者は具体的に誰のどんな理論かこれだけではわかりません。それを知っておくことが前提知識となるのでしょう。
そして、「われわれ読者は否応なしにラトゥール(や「反対者」や「事実構築者」)とともに「旅人」となってテクノサイエンスの世界を旅していくのだが、その途上で行われていることは、実はたったひとつのことである。それは、連関(associatiion)、関係(relation)、結び付き(connection)、絆(tie)、リンク(link)等と様々な言葉で言い換えられているが(一番多用されるのが「連関」なので、以下「連関」で統一する)、要するに不均質極まりない多種多様な要素とその連関にひたすら注目し、描写していくことにより、従来の科学論で語られていた内容をすべて置換していくという作業である。」
うわー、同じ意味に同一本の中でそんなにたくさんの言葉を当てるなよ。というか、それらの言葉は微妙に使い分けられていて、それが重要かも知れない、と疑心暗鬼にかられるのですが、どうしてくれる。ま、同じだというんだから素直に同じと仮定して読んでみるのが良いでしょう。
結論めいたこととしては、「この過程を通じて、「テクノサイエンス」はネットワークとしての性格を有していることが明らかにされていく、そして、ついには重要なのは互いに結び付いている諸要素よりも、結び付けている連関そのものの方であることを明らかにしていくこと。こうした、いわば「連関一元論」、あるいは「唯物論」ならぬ「唯連関論」とでも呼ぶべきものこそがラトゥールの科学論全体を通底する本質であり、これこそがまさに人類学的発想ないし人類学的思考の産物に他ならない。」
うむ、なんとなくわかります。「テクノサイエンス」という人間の活動をグラフでイメージできるようなネットワークとして表現したということでしょうね。そして結び付けられている具体的な事物(人や物や個別組織などでしょうか、それとも事件(event)等でしょうか)は抽象化してしまう、と。でも、それで何がわかったのか、というのがどうもまだ理解できていません。
他のものごとと同様に「テクノサイエンス」もグラフネットワークとして表現することは可能でしょう。それにより例えばこの本で挙げられているような「テクノサイエンス」の様々な事例について、個々の特種事情によらない共通な性質や共通な原理が見出される可能性は大いにあるでしょう。では何かそのような共通な性質や共通な原理が見出されたのかというと・・・うーん、それが上記の6つの「原理」だということになるのでしょうか? 各用語の(ラトゥールの意図する)意味がわからないということもありますが、どうも観察事実を要約して(かつ抽象化して)述べただけという印象が強くて、この原理から何かが予測できそうというものが感じられません。例えばクーンのパラダイム理論やマルクスの社会発展理論などは何らかの予測をできることがわかりやすく、それゆえに反証可能性があるとも言えるのですが、「科学(活動)の中に連関があるよ」と指摘するだけではねえ。まあ見えることを指摘したこと自体は手柄と見るべきで、その後は具体的な様々な事例で連関構造を調べてゆくのが研究の成り行きとなるでしょうから、つまりはこの本の意義は「テクノサイエンス」研究の新規な方法論を提案したという点にあるのかも知れません。
そして冒頭に述べた噂の真偽ですが、まず「実験室(研究室か?)において科学理論が作られているまさにその時の様子を人類学的手法で観察した報告」はこの本には載っていません。その報告は『実験室の生活ー科学的事実の構成』"Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts" (1979 republished 1986) で邦訳はなさそうです。しかしどのようなものかということは日本での研究である「実験室における社会実践の民族誌学的研究」(2009/10/21と推定)や「科学的事実の産出と研究者の実践について」で雰囲気が感じられそうです。
次に「科学的知識そのものも社会的に構成されたものである」とは書いてありません。むしろ"社会的"という言葉を安易に使うことに反対しているようです。じゃーどう考えているかはよくわかりません。なんだか従来の説明概念を破棄したはいいが、替わりとなる説明概念の提出はできてないという印象です。まあきっと提出されている説明概念が私に理解できていないだけなのでしょう。
科学的知識のどこまでを社会的に構成されたものとみなすかというテーマには、科学論研究者[*1]の間でも多様な見解があるようですから調べるのも大変ですが、Ref-2,3あたりは一連の研究の流れを述べていてひとまず参考になりそうです。
---------------------
参考文献
1) ブルーノ・ラトゥール;川崎勝(訳);高田紀代志(訳)『科学が作られているとき―人類学的考察』産業図書 (1999/03)
2) 書評平英美・中河伸俊編『構築主義の社会学――論争と議論のエスノグラフィー』
3) 書評ジョゼフ・ラウズ(著);成定薫(訳);阿曽沼明裕(訳)『科学のカルチュラル・スタディーズとは何か』
*1) ひとくちに科学論と言っても幅広いし、相対主義、社会構築主義(社会構成主義)と言っても幅広いようだ。










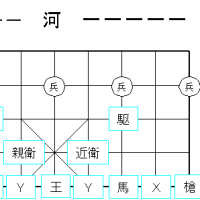
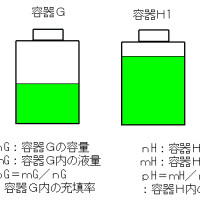
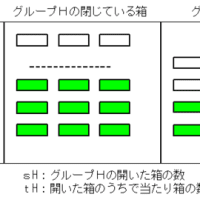
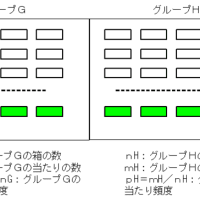
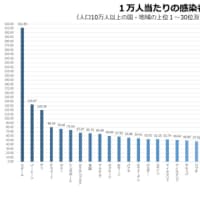
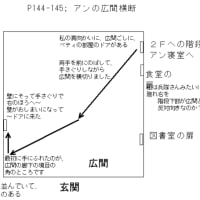
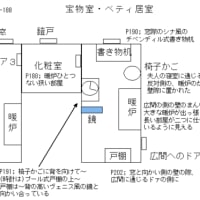

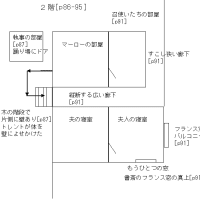
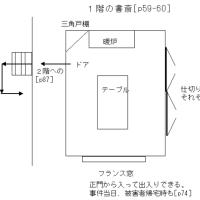






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます