21世紀も既に20年以上が過ぎ科学の進歩も著しいものがあります。人間に替わって肉体労働をしてくれるロボットは前世紀末には普及していましたが、頭脳労働をもしてくれる人工知能AI(Artificial Interigence)も今では珍しくはなくなりました[*1]。そんな時代から見てリアルさに磨きがかかったと思える作品2つを紹介します。
1. マーサ・ウェルズ(Martha Wells)『マーダーボット シリーズ("The Murderbot Diaries")』[Ref-1]
2. デニス・E・テイラー("Dennis E. Taylor")『AI探査機集合体 シリーズ(We are Legion (We are Bob))』[Ref-2]
まず1の主人公の自称"弊機"は、機械部品と有機部品から成る構成機体(a part robot, part human construct )なるもので、警備ユニット(Security Unit)として作られた何者かです。警備ユニットは英語では"SecUnit"と略記するようです。私は後半の『逃亡テレメトリー』から読み始めたこともあり、サイボーグの変形かと思ったのですが、どうも違います。"弊機"が人間そっくりの自意識や感情を持つのは有機部品が原因かとも思えますし、作品の登場者自体がそう考えていることも多いようなのですが、実は機械部品だけから成る多くの"ボット(bot)"達も様々なレベルでの自意識や感情を持っていることが判明してきます。はい、作品世界では多くの自動装置やプログラムが働いていて、それらは総称して"ボット(bot)"と呼ばれています。これも21世紀の言葉ですね。要するに主人公は、"弊機"の心は、一から作られたAIと考えるのが正しそうです。作品中では「コードの塊にすぎない」なんて表現も出てきます。となるとこれは、日本のロボットの原点とも言える鉄腕アトムそのものですね。アトムは天馬博士が死んだ子供に似せて作ったロボットですが、子供の意識を移植したというわけではなく一から機械部品だけで、自意識や感情を持つロボットを作ったのです[*2]。
このような様々な半人半人工物の物語については、『マーダーボット・ダイアリー 下』の巻末解説に詳しいことが書いてあります。
作品2は、現時代のプログラマーにして起業家でありSFオタクのボブが冷凍睡眠に入り、未来で目覚めたらコンピューターに意識を移植されていた、という話です。となると従来の作品であれば、目覚めた人間であるボブの冒険譚となるはずですが、ここにいるのはあくまでも「ボブの記憶と心理傾向を持つAI」であって元の脳に宿るボブではありません。SFにはこのような形でも「不死」を達成したという設定も多いのですが、個人的には自分の複製を残しただけであり「本当の不死」ではないと考えています。実際にこの作品ではボブが増殖したボブ達が主人公になっていて、最初にちょっぴり、「自分は誰なんだ?」という疑問を浮かべるボブも出てきますが、すぐにあっさりと現実を受け入れてお仕事に専念します。原作タイトルの"We are Bob"は主人公が複数だと示していますね。あれ、"Bob"は集合名詞なのか?!
増殖するボブというアイディアでは、ブライアン・W・オールディス「フランクになろう」という短編を思い出しました[Ref-3] 。
というわけで本作品も主人公はAIなんですが、その自意識や感情は人間のものです。でもできることや感覚は人間を遥かに超える超高性能コンピューターシステムのものです。作品1も同じで、その能力や感覚に、さらにはそのような心の描写に21世紀のAI技術のリアルさが込められているところは、本格ハードSFと言えるでしょう。作品2では未だ超光速飛行は実現していないので、宇宙探査機同士の物理的にリアルな戦闘シーンも見られます。主人公達は実質上は寿命のない宇宙探査機集合体なので、超光速飛行がなくても物語が成立します。
自意識を持つ超高性能コンピューターシステムというのも20世紀後半のSFでは定番と言えますが、ロバート・A・ハインライン『月は無慈悲な夜の女王』(1965-66)とか、星新一『声の網』講談社(1970)とかに登場しましたね。
ところで作品1の主人公の自称である"弊機"という言葉は原作では何かというと、単なる"I"です。まさに翻訳者の造語であり、明治時代に多くの専門用語を生み出した翻訳者達を彷彿とさせる素晴らしい翻訳だと思います。この点は『逃亡テレメトリー』の巻末解説でも絶賛されていました。
ひるがえって作品2の日本語タイトルはやや硬すぎるように感じますが、どうなんでしょうね? 「僕らはボブだ」なんて方が主人公の雰囲気を表してるように思えますけれど。俺、私、我、吾、どれもピタッとしません。
----------------------
*1) とはいえ現実のAIなるものは、SF作品のような意識を持つ知能には程遠く、高等動物の脳神経系にも未だ遠いというべきだろう。
*2) 作品を詳細に見直してはいないが、たぶんそう。子供は交通事故で即死みたいだから意識を移植という時間はなかったろうし。
----------------------
Ref-1) これまでの作品と日本語訳の収録巻
1.1 All Systems Red (システムの危殆)(2017/03):『マーダーボット・ダイアリー 上』(2019/12/11)
1.2 Artificial Condition (人工的なあり方)(2018/05):『マーダーボット・ダイアリー 上』(2019/12/11)
1.3 Rogue Protocol (暴走プロトコル)(2018/08):『マーダーボット・ダイアリー 下』(2019/12/11)
1.4 Exit Strategy (出口戦略の無謀)(2018/10):『マーダーボット・ダイアリー 下』(2019/12/11)
1.5 "The Future of Work: Compulsory" (義務)(2018):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
1.6 Network Effect (ネットワーク・エフェクト)(2020/05):『ネットワーク・エフェクト』(2021/10/12)
1.7 "Home: Habitat, Range, Niche, Territory" (ホーム--それは居住施設、有効範囲、生態的地位、あるいは陣地)(2021):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
1.8 Fugitive Telemetry (逃亡テレメトリー)(2021/04):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
Ref-2) デニス・E・テイラー; 金子浩(訳)『われらはレギオン1 AI探査機集合体 (ハヤカワ文庫SF)』 早川書房 (2018/04/04)、以下。
2a) ファンダムが出来ている
2b) こんな感想も。転生したら人工知能にさせられ、有無を言わせず居住可能惑星探査に送り出された件──『われらはレギオン1 AI探査機集合体』(2018/04/07)。
Ref-3)
3a) "ameqlist 翻訳作品集成"より
「フランクになろう」 Let's Be Frank (Science-Fantasy No.23 1957)
translator:荒俣宏(Aramata Hiroshi) S-Fマガジン(S-F Magazine)1969/10 No.125
illustrator:岩淵慶造(Iwabuchi Keizō)
「率直(フランク)にいこう」translator:井上一夫(Inoue Kazuo)
創元推理文庫(Sogen Mystery bunko) editor:ジュディス・メリル(Judith Merril) 『SFベスト・オブ・ザ・ベスト』 SF Best of the Best
3b) SFマガジン 1969年10月(通巻125号):「<新しい波>特集」より。
1. マーサ・ウェルズ(Martha Wells)『マーダーボット シリーズ("The Murderbot Diaries")』[Ref-1]
2. デニス・E・テイラー("Dennis E. Taylor")『AI探査機集合体 シリーズ(We are Legion (We are Bob))』[Ref-2]
まず1の主人公の自称"弊機"は、機械部品と有機部品から成る構成機体(a part robot, part human construct )なるもので、警備ユニット(Security Unit)として作られた何者かです。警備ユニットは英語では"SecUnit"と略記するようです。私は後半の『逃亡テレメトリー』から読み始めたこともあり、サイボーグの変形かと思ったのですが、どうも違います。"弊機"が人間そっくりの自意識や感情を持つのは有機部品が原因かとも思えますし、作品の登場者自体がそう考えていることも多いようなのですが、実は機械部品だけから成る多くの"ボット(bot)"達も様々なレベルでの自意識や感情を持っていることが判明してきます。はい、作品世界では多くの自動装置やプログラムが働いていて、それらは総称して"ボット(bot)"と呼ばれています。これも21世紀の言葉ですね。要するに主人公は、"弊機"の心は、一から作られたAIと考えるのが正しそうです。作品中では「コードの塊にすぎない」なんて表現も出てきます。となるとこれは、日本のロボットの原点とも言える鉄腕アトムそのものですね。アトムは天馬博士が死んだ子供に似せて作ったロボットですが、子供の意識を移植したというわけではなく一から機械部品だけで、自意識や感情を持つロボットを作ったのです[*2]。
このような様々な半人半人工物の物語については、『マーダーボット・ダイアリー 下』の巻末解説に詳しいことが書いてあります。
作品2は、現時代のプログラマーにして起業家でありSFオタクのボブが冷凍睡眠に入り、未来で目覚めたらコンピューターに意識を移植されていた、という話です。となると従来の作品であれば、目覚めた人間であるボブの冒険譚となるはずですが、ここにいるのはあくまでも「ボブの記憶と心理傾向を持つAI」であって元の脳に宿るボブではありません。SFにはこのような形でも「不死」を達成したという設定も多いのですが、個人的には自分の複製を残しただけであり「本当の不死」ではないと考えています。実際にこの作品ではボブが増殖したボブ達が主人公になっていて、最初にちょっぴり、「自分は誰なんだ?」という疑問を浮かべるボブも出てきますが、すぐにあっさりと現実を受け入れてお仕事に専念します。原作タイトルの"We are Bob"は主人公が複数だと示していますね。あれ、"Bob"は集合名詞なのか?!
増殖するボブというアイディアでは、ブライアン・W・オールディス「フランクになろう」という短編を思い出しました[Ref-3] 。
というわけで本作品も主人公はAIなんですが、その自意識や感情は人間のものです。でもできることや感覚は人間を遥かに超える超高性能コンピューターシステムのものです。作品1も同じで、その能力や感覚に、さらにはそのような心の描写に21世紀のAI技術のリアルさが込められているところは、本格ハードSFと言えるでしょう。作品2では未だ超光速飛行は実現していないので、宇宙探査機同士の物理的にリアルな戦闘シーンも見られます。主人公達は実質上は寿命のない宇宙探査機集合体なので、超光速飛行がなくても物語が成立します。
自意識を持つ超高性能コンピューターシステムというのも20世紀後半のSFでは定番と言えますが、ロバート・A・ハインライン『月は無慈悲な夜の女王』(1965-66)とか、星新一『声の網』講談社(1970)とかに登場しましたね。
ところで作品1の主人公の自称である"弊機"という言葉は原作では何かというと、単なる"I"です。まさに翻訳者の造語であり、明治時代に多くの専門用語を生み出した翻訳者達を彷彿とさせる素晴らしい翻訳だと思います。この点は『逃亡テレメトリー』の巻末解説でも絶賛されていました。
ひるがえって作品2の日本語タイトルはやや硬すぎるように感じますが、どうなんでしょうね? 「僕らはボブだ」なんて方が主人公の雰囲気を表してるように思えますけれど。俺、私、我、吾、どれもピタッとしません。
----------------------
*1) とはいえ現実のAIなるものは、SF作品のような意識を持つ知能には程遠く、高等動物の脳神経系にも未だ遠いというべきだろう。
*2) 作品を詳細に見直してはいないが、たぶんそう。子供は交通事故で即死みたいだから意識を移植という時間はなかったろうし。
----------------------
Ref-1) これまでの作品と日本語訳の収録巻
1.1 All Systems Red (システムの危殆)(2017/03):『マーダーボット・ダイアリー 上』(2019/12/11)
1.2 Artificial Condition (人工的なあり方)(2018/05):『マーダーボット・ダイアリー 上』(2019/12/11)
1.3 Rogue Protocol (暴走プロトコル)(2018/08):『マーダーボット・ダイアリー 下』(2019/12/11)
1.4 Exit Strategy (出口戦略の無謀)(2018/10):『マーダーボット・ダイアリー 下』(2019/12/11)
1.5 "The Future of Work: Compulsory" (義務)(2018):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
1.6 Network Effect (ネットワーク・エフェクト)(2020/05):『ネットワーク・エフェクト』(2021/10/12)
1.7 "Home: Habitat, Range, Niche, Territory" (ホーム--それは居住施設、有効範囲、生態的地位、あるいは陣地)(2021):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
1.8 Fugitive Telemetry (逃亡テレメトリー)(2021/04):『逃亡テレメトリー』 (2022/4/11)
Ref-2) デニス・E・テイラー; 金子浩(訳)『われらはレギオン1 AI探査機集合体 (ハヤカワ文庫SF)』 早川書房 (2018/04/04)、以下。
2a) ファンダムが出来ている
2b) こんな感想も。転生したら人工知能にさせられ、有無を言わせず居住可能惑星探査に送り出された件──『われらはレギオン1 AI探査機集合体』(2018/04/07)。
Ref-3)
3a) "ameqlist 翻訳作品集成"より
「フランクになろう」 Let's Be Frank (Science-Fantasy No.23 1957)
translator:荒俣宏(Aramata Hiroshi) S-Fマガジン(S-F Magazine)1969/10 No.125
illustrator:岩淵慶造(Iwabuchi Keizō)
「率直(フランク)にいこう」translator:井上一夫(Inoue Kazuo)
創元推理文庫(Sogen Mystery bunko) editor:ジュディス・メリル(Judith Merril) 『SFベスト・オブ・ザ・ベスト』 SF Best of the Best
3b) SFマガジン 1969年10月(通巻125号):「<新しい波>特集」より。










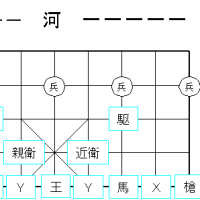
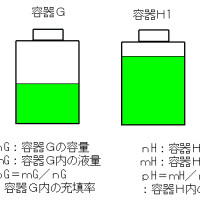
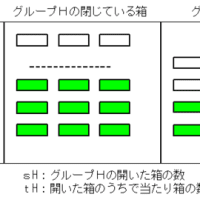
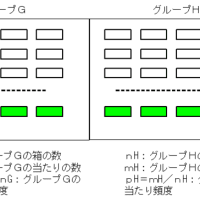
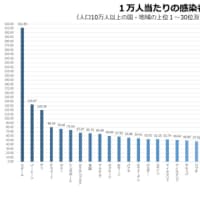
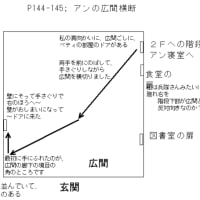
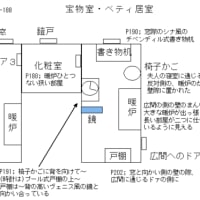

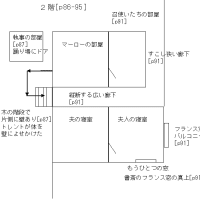
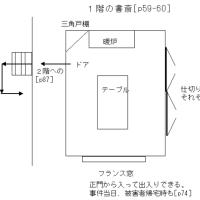






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます