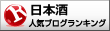「会津」の地名のおこり
崇神天皇の御代、大毘古命(おおひこのみこと)と建沼河別命(たけぬかわわけのみこと)の父子の将軍を東に派遣、その二人が多くの川が集まる所(津)で出会ったので「相津」と名付けた(古事記)。西暦700年頃に今の「会津」になったそうな
磐梯山(1816m)
古くは病悩山(びょうのうざん)(やもうさん、わずらわしやま)とも呼ばれ、後に磐椅山(いわはしやま)、会津嶺(あいづね)とよばれて会津の人々の心のよりどころ、畏れ敬う信仰の山 だったそうな
磐椅神社(いわはしじんじゃ)
磐梯明神が起源 応神天皇の御代(西暦270年頃)、磐梯明神として磐梯山頂に祀られたのが始まりといわれ、天平元年(729)の聖武天皇の御代に現在の見祢山に遷座されたと伝えられる。磐梯明神は磐梯山に「足長・手長」という夫婦の魔物が人々を困らせていたところ、弘法大師が山頂に封じ込めて改心させてなったという民話が伝えられている。
以上 猪苗代の偉人を考える会監修 猪苗代町発行 土津神社と周辺マップより
崇神天皇の御代、大毘古命(おおひこのみこと)と建沼河別命(たけぬかわわけのみこと)の父子の将軍を東に派遣、その二人が多くの川が集まる所(津)で出会ったので「相津」と名付けた(古事記)。西暦700年頃に今の「会津」になったそうな
磐梯山(1816m)
古くは病悩山(びょうのうざん)(やもうさん、わずらわしやま)とも呼ばれ、後に磐椅山(いわはしやま)、会津嶺(あいづね)とよばれて会津の人々の心のよりどころ、畏れ敬う信仰の山 だったそうな
磐椅神社(いわはしじんじゃ)
磐梯明神が起源 応神天皇の御代(西暦270年頃)、磐梯明神として磐梯山頂に祀られたのが始まりといわれ、天平元年(729)の聖武天皇の御代に現在の見祢山に遷座されたと伝えられる。磐梯明神は磐梯山に「足長・手長」という夫婦の魔物が人々を困らせていたところ、弘法大師が山頂に封じ込めて改心させてなったという民話が伝えられている。
以上 猪苗代の偉人を考える会監修 猪苗代町発行 土津神社と周辺マップより