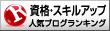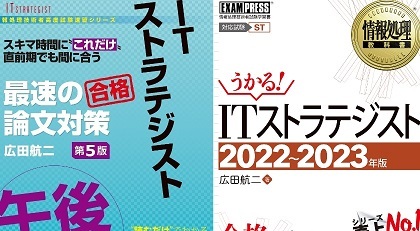昨日は、「PING反映確認テスト」表題で、3回にわたってPINGを投げてしまいました。
あるサイトに対する障害確認テストとして一箇所に絞ってPINGしたつもりでしたが、
うっかり関係の無いサイト様にもPINGしておりました。お騒がせいたしました。
(ここから本文です。前回の記事の終わりのところからです。)
ですから、本書の記録の仕方に従って、ページごとに時間を記録しましょう。
こうすることによって、提出直前に、効率的に点検が出来るようになります。
また、ペースの面からいうと、毎ページごとに所要時間がリアルタイムで把握できるた
め、前のページでは「負けた」が、次のページでは「取り返そう」といったペースメーカ
にもなってくれるのです。
(続く)
![]()
ブログランキングに参加しています。ここをクリックしていただくだけで結構です。アクセス実績が上がります。ブログのランクが上昇すれば、こちらの精神的なモチベーションになります。
(続き)
そこで、各解答用紙のページごとに時刻を記入します。
効果的に時間を把握するためには、時間ではなく、時刻の方が有効です。
記入方法は、本書「ITストラテジスト 午後2最速の論文対策」で解説しています。
使い方のルールがありますので、理解した上で、利点を生かして使いましょう。
私はこの方法で長年、論文を書き続けてきました。
是非この方法で記録することを、お薦めします。
さて、論文記述の際に問題が発生しやすい2つ目のパターンについて述べてみたい
と思います。先ほどの1つ目の問題は、初心者が陥りやすい時間不足になるケースでした。
ここでの問題点はむしろ、早く書き過ぎてしまうパターンです。
論文に慣れてくると、つい夢中になって特定の「節」を必要以上に書きこんでしまったり、
同じ内容の事柄を延々と書き連ねてしまうのがこれです。
私は「暴走書き」と呼んでいます。
「暴走書き」は書いているときは、いたって順調に書いているように感じることもあるため、
本人が気が付かない場合もあります。深刻なのは、この影響で、他の節の記述時間が
無くなったり、節間の記述量のバランスが悪くなったりすることです。
この「暴走書き」に対しても、本書では「防止ノウハウ」を解説しました。論述を開始する
前に、「暴走書き」にならないように、予め、解答用紙にマーキングをするのです。
(続く)
・最速の情報セキュリティスペシャリスト試験の勉強のブログはこちら
具体的な、論文対策は下記の書籍で!
以上