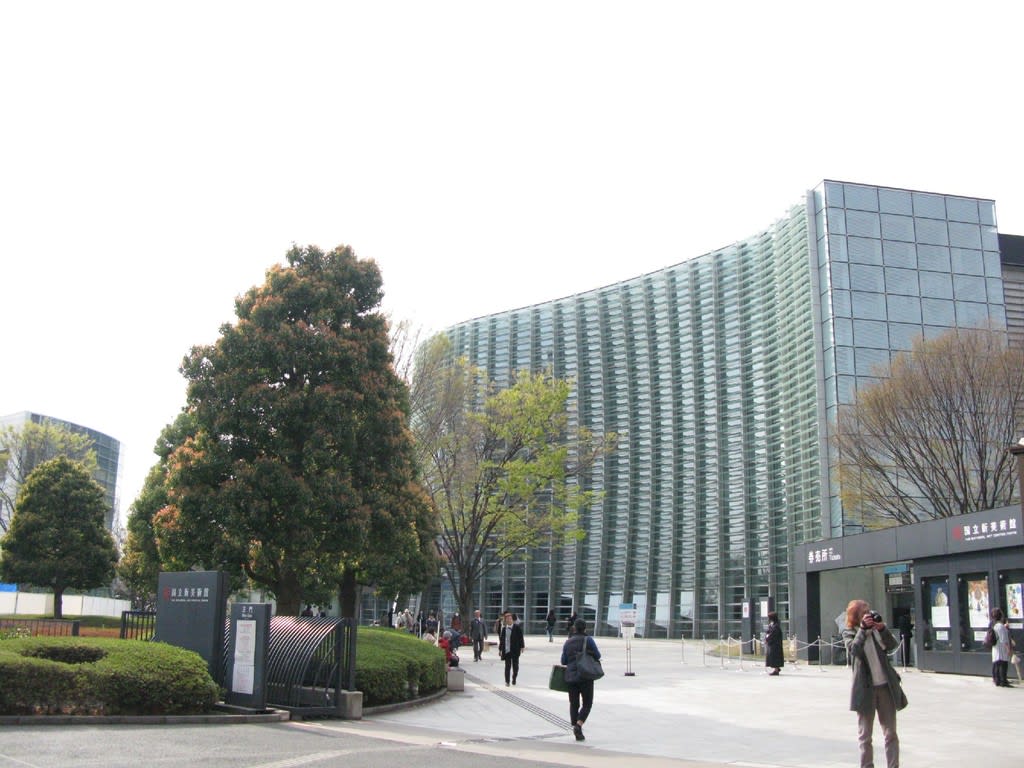震災から約2か月後、8年前の今日は城下南の入り口辺りを通る。
丁切根(仙台で「ちょうぎんね」と呼ぶ)から入り、河原町を古城方面へと進む。
道すがら、めんこいわんこが目に入った。

いるのは、大判焼きやたこ焼きを売っている店先。
昔ながらの店のようだが、店名がない。
「もう焼けた?」と、店の中をうかがっているかのようなわんこ。
おとなしく待っていて、本当にめんこい。
さらに進むと、やがて古城神社が見えてくる。

広瀬川からほど近いこの辺りは、昔、洪水や流域が定まらず難儀していたという。
人々を救おうと、行者が自ら進んで人柱になると願い出た。
生き埋めになった行者は、満願して最期を迎える。
以降、広瀬川は今の流れのように定まり、難儀していた村は肥沃な地となった。
その恩を末永く忘れぬために塚を築き、神々を合わせて祀ったのが、この神社という。
(参考:宮城県神社庁)
わんこの待っていた店は、今は閉めてしまったようだ。
神社は少し修繕したらしいが、今もそこにある。
震災の年、人々を元気づけるかのように多くの商店が踏ん張った。
震災から8年の今は、閉じてしまう店もある。
だが、思い出はこうして、残っている。