未来商店街から、再び高田松原方面へと戻る道すがら、未来商店街から然程離れていない所にも、仮設の商店がある。
「木村屋菓子店」や、酒と和雑貨の「いわ井」、蕎麦の「やぶ屋」が並んでいる。
「いわ井」さんには、風呂敷や酒器などの雑貨の他、地域の製作者の作品や、地場の酒の「酔仙」が置いてある。
その中に、吟味した岩手産の材料で造る「酔仙・オール岩手」があったのでひとつ求めた。
岩手の米、岩手の水、南部杜氏の伝統の技で造られた酒だ。

米の良さ、水の良さを活かし、コクはあるがまろやかで、香りと後味が爽やかな純米酒だった。
隣の「木村屋」さんには、 昔ながらの「がんずき」や「ゆべし」の他に、岩手の小麦と小岩井農場のバターを使った焼き菓子がある。

「夢の樹バウム」と名づけられたその菓子は、かつての高田松原と、今は一つだけ残った松の姿を思い描いて作ったものだという。

部屋の空気が一変するかのように、実に芳しいバターの香りが広がる。
表面に薄くかかった、飴になった砂糖蜜が、さくっと歯切れ良い音を立てる。中はしっとりと、程よい甘さと柔らかさだ。

「夢の樹バウム」が描いた「一本松」は、塩で根を痛めながらも、懸命に生きている。
美しかった松原の浜辺から、爽やかに海風が通る穏やかな町も懐かしい。
あの一本松は、痛みも喜びも知っているだろう。
私らもおんなじ。
時々、ひとりぼっちになったように心細くなることもあるけれど、誰かとどこかで繋がっていて、一緒になって踏ん張っているのだ。
きっと「一本松」は、そんな私らを見守ってくれている。














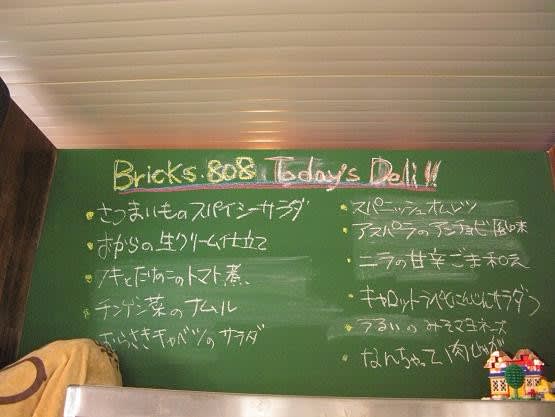


 (2012‐6‐12:道の駅)
(2012‐6‐12:道の駅)










