<①トリアージ=緑:健常者通常生活、黄色:軽傷者隔離避難所、赤色:重病救急搬送=体制無、
②治療薬及び
③予防ワクチン所有せず三無「保健・医療・介護・福祉制度」環境下の2020年武漢離陸肺炎ウイルス及び後続変異ウイルス=家畜人間生物攻撃兵器=空爆被災防禦「密閉・密集・密接」8割減の5分の1「全開・散在・遠隔」オンライン診療システムに
うつ病や認知症診療(注1) を保健・医療・介護・福祉予算要員措置行政制度化か>
(注1)【06月28日放送】ウィークエンド・ケアタイム 「ひだまりハウス」 〜うつ病・認知症について語ろう〜
:::::
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
岸本 泰士郎
慶應義塾大学医大学精神神経科学教室 専任講師
1973年生まれ。2000年、慶應義塾大学医学部卒業、同大学 精神神経科学教室に入局。国家公務員共済組合連合会立川病院神経科を経て、 医療法人財団厚生協会大泉病院にて副医長 ・医長を歴任する。2009年11月より、 The Zucker Hillside Hospital Post Doctoral Research Fellow、
Feinstein Institute for Medical Research, The Zucker Hillside Hospital Assistant Investigator、
Hofstra Nprth Shore-LIJ school of Medicine Assistant Professor of Psychiatryを経験し帰国、現在に至る。
1973年生まれ。2000年、慶應義塾大学医学部卒業、同大学 精神神経科学教室に入局。国家公務員共済組合連合会立川病院神経科を経て、 医療法人財団厚生協会大泉病院にて副医長 ・医長を歴任する。2009年11月より、 The Zucker Hillside Hospital Post Doctoral Research Fellow、
Feinstein Institute for Medical Research, The Zucker Hillside Hospital Assistant Investigator、
Hofstra Nprth Shore-LIJ school of Medicine Assistant Professor of Psychiatryを経験し帰国、現在に至る。
臨床精神薬理の研究に携わっている岸本泰士郎先生。精神科領域の薬の開発がなかなか進んでいないことに課題を感じながら、米国へ留学、遠隔医療に出会いました。これをきっかけに、帰国後、遠隔医療を活用した精神科医領域のさまざまな研究を進めています。遠隔医療の可能性や、今後の展望を伺いました。
―現在、精神科領域での遠隔診療の研究を進められていますね。
精神科では診療の大部分が患者さんとの会話で成り立ちます。いわゆるテレビ電話は、お互いの顔が見え、声が聞こえるため、精神科医療との相性がいいと言われています。


実際に海外では、精神科領域の遠隔医療が保険診療として認められている国もあります。しかし日本では、ごく一部の医療機関で試験的に導入されているにすぎません。そこで私は、日本での遠隔医療をより促進させるためのプロジェクトを展開しています。現在、臨床研究で診ている患者さんは、治療も上手くいっており、全体的には順調に研究を進めることができています。
―遠隔での診療では限界があるという声もあります。一方、研究が順調に進んでいるということは、岸本先生は遠隔診療の限界はあまり感じていないということでしょうか?
そうですね。確かに直接対面で話すほどの情報量がないために、診療として成り立たないのではないか、心理的な距離を感じやすいのではないかなどの意見が聞かれます。しかし実際にやってみると、お互いが遠隔での通信に慣れることによって、そのような問題点は解消されることが分かります。また、諸外国の研究結果を見ても、治療効果や満足度に差はないと報告されています。
効果面よりも、むしろ問題点は、安全性や責任の所在などに関してかもしれません。自傷行為をしたり自殺企図があったりする患者さんを遠隔地で診ていて、万が一そのような行為があった場合、誰がどう対処すべきなのか、万が一の事故の責任を誰がとるのか、あるいは、通信が途切れたときにどう対処したらいいのかなどの議論が、まだ十分になされていないことです。診療を取り巻く制度の整備がされていないことが、遠隔診療推進の障壁になっています
―では、遠隔診療のメリットは、どのような点に感じていますか?
医療過疎地で地理的に通うのが困難な方にとってはもちろんのこと、例えばPTSDや強迫症などの症状によってなかなか医療機関に通えない患者さんにとっても有効だと考えています。
また、遠隔診療はデータの収集が行いやすいという側面があります。仕組みさえ作れば、診療データがデジタルデータとして蓄積されていきます。ビッグデータやそれを用いたAIによる解析の有用性が注目されるようになっていますが、遠隔医療はそういった技術を利用して、より治療効果の高い、効率的な医療を展開していくためのツールになる可能性があります。一つの未来医療の試みとして、私たちが行っているプロジェクトが「機械学習を用いた表情・体動・音声・日常生活活動の解析(PROMPT)」です。
―「機械学習を用いた表情・体動・音声・日常生活活動の解析(PROMPT)」は、具体的にどのように研究を進めているのですか?
一言で表現すると、病気に特徴的な症状を抽出し、重症度を機械がある程度推定できるような解析アルゴリズムをつくるプロジェクトです。精神科の病状は、患者さんの心に生じるものですが、これらは客観的に捉えることが困難でした。それを最新の機械学習を用いて、定量化できないか、と考えています。
―現在の進捗状況はいかがでしょうか?
全体的には順調に進んでいます。現在、750データセット程集まっていて、少なくとも1000まで増やしたいと思っています。ただ、最終的にデータ数がどれくらいあればいいかは、データのばらつきや、精度をどこに設定するかで変わってくるため、明確に集めるべき数が決まっているわけではありません。
ですから、現在は割と満足いく結果が出つつありますが、どこまで完成度を持ち上げるべきか、さらにバラエティに富んだ層の患者さんを集めていくかなどは、今後さらに研究を進めていく中で方向性を決めていくことになります。
―なぜ、今取り組んでいるような研究をするようになったのですか?
もともと私は、薬がどう患者さんに効果をもたらすかという臨床精神薬理に携わっていました。しかし精神科領域の薬の開発は、なかなかうまく進んでいないのが現実です。原因の1つは、病気の根本原因が解明できていないこと。もう1つが、患者さんの重症度を正確に評価できていないことです。
先ほども言った通り、心で起きている現象を客観的に評価することは非常に困難です。そのため、治験のために「このくらいの重症度の人を集めて」と言っても、実際に集まった被験者の重症度はまちまちになってしまいます。そのような状態で治験を行っても、薬がプラセボと区別がつかないような状況がしばしば生じています。
効果があると分かっている薬でも、治験をするとプラセボと区別がつかないということが生じるのです。このように、患者さんの重症度評価がうまくいっていないことが、薬の開発における大きなブレーキになってしまっているのです。
そのような課題を抱えながら8年前、米国に留学しました。たまたまそこで参加した研究では、高度なトレーニングを積み、かつ、患者さんのバックグラウンドをあまり知らないスタッフが、遠隔医療を活用し重症度評価する手法を取り入れていました。つまり直接対面で「この人は薬を飲み始めて2週間が経つから、薬が効き始めているのではないか」などといった先入観なく、テレビ画面越しにインタビューしていました。そして、このほうが正当な評価ができることを体験したのです。これは非常に興味深かったです。
研究や治験といった場面だけでなく、日常臨床でも遠隔医療は取り入れられていました。米国の精神科医の友人が、担当患者さんが引っ越すことになったと聞くと「では、しばらくは遠隔でフォローしましょう」と、日常的に遠隔診療が使われていました。
このような経験から、遠隔医療は日本でも早く取り入れるべきだと感じました。そして帰国後、研究で遠隔医療の活用を始めたのです。














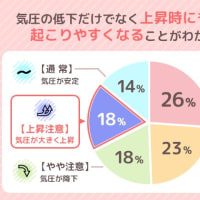



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます