今日は長野県飯田市での実践報告をします。
飯田市ではおひさま進歩エネルギー(以下「おひさま」と略す)という会社を立ち上げています。自然エネルギーと省エネルギーの会社です。
おひさま事業は、環境省のまほろば事業(環境と経済の好循環のまちモデル事業)補助金を受けた事業です。3年間の事業の3年度目で、仕上げのリミットまであと4ヶ月を切ったところです。市民出資を集めた「匿名組合」契約事業は太陽光発電と省エネ(ESCO)事業でした。このほかに木質バイオマス事業というのがあります。
バイオマスペレットへの反応
木質バイオマス事業は、森林の間伐材を活用した木質ペレットによる熱サービス事業です。ときあたかも、「ピークオイル・パニック」がささやかれるこの時期、木質ペレットはさぞかしもてはやされているのだろうとお思いでしょう。灯油の価格も1リットル当たり70円くらいまで上がってきて、ペレットの一般的な流通価格の1kgあたり35円くらいでも、もうちょっとで同等というところまで来ています。
しかし営業状況を率直にお話しますと、これがさっぱりです。世間の人は「ピークオイル」なんてお構いなし、「まずはコスト」という感じです。まあ、まったく商談が成立していないわけではなく、小型のペレットボイラーを入れるという話が進んでいる施設もあります。ここの場合は、責任者が自然エネルギーをできるだけ増やしたいという、いわばコスト度外視の応援団ということです。
飯田市にあるペレット工場、南信バイオマスも設備能力1000トン/年に対して、今年の生産(販売)は20%以下(去年はもっと悪い)で、ペレットは売れていません。長野県も飯田市も、木質ペレットを普及させようと、ペレットストーブ購入補助やペレット価格応援補助などをやっているのですが。正直言って、広がっていないのが現実です。
なぜ木質バイオマスは売れないのか
一番のカギは価格にあると思います。いま石油という船は喫水線すれすれですが、でも浮いています。私たちは小さな船で、乗っている人たちに「おーい、もうすぐ沈むぞ。こっちに乗り移れー」と叫ぶのですが、船上からは「何言ってんだよ。そんな小さい船の方が危ないよ。」と言われる。70円/リットルと35円/kgではなく、80円/リットルと30円/kgになると、ここはドドーッと動きます。水は喫水線を超え、石油という船に入りはじめるからです。逃げ出す人が続出してきます。
私の相場観ですが、この状況は来年には来る・・と思います。でも、今年ではないのです。石油は高くなったり、また下がったり、今年はまだぎりぎりのラインを保っているようです。価格は言うまでもありませんが喫水線を超えないように操作されていると思います。その見えざる力と、木質バイオマスは闘っているのです。
価格が同等になってもまだ障害があります。ペレットボイラーもストーブも、石油のそれより高い。そして何より「かさばる」。バイオマスペレットは同じ木質のチップに比べれば3分の1以下の体積に圧縮されていますが、液体の石油に比べれば、どうやっても大きい。安定して長期に使うには石油タンクの数倍の大きさのペレットサイロを用意しなければならないのです。飯田市のような地方都市ですら、石油ボイラーを使っている施設の中に大きなサイロとペレットボイラーを置けるスペースは、なかなかありません。完全な置き換えならまだしも、既存のボイラーとの併用(出はじめ商品なので、運転管理への不安も持たれる)ともなると、まず難しいのです。
同じことは輸送や流通のシステムでも言えます。お家の建て方から、最後の灰の処理の仕方まで、木質バイオマスに適したスタイルを確立する必要があるのです。違うシステムとスタイルの中で、木質バイオマスを広げようとしていることに無理があるわけです。
ある温泉旅館の問題意識
飯田市内の某有名温泉旅館のご主人は、新しいもの好きです。石油の枯渇や地球温暖化問題にもある程度の意識を持って世界を見ています。だから本当は、ペレットボイラーを入れたくてしょうがない。しかし、このご時勢、観光客も減っていますし、あまり高額の投資はしたくない。そこで、私たちの、初期投資ゼロの「おひさまスタイル」に興味を持ちました。
ペレットボイラーを入れるべく、夏から設計を何度も繰り返し、そのかなり複雑な構造物の中にペレットボイラーを入れられるよう工夫しました。不幸なことに、複雑な構造ゆえに工事費は通常の倍以上かかるものになりました。私たちの熱サービスは、ペレットボイラーを売るわけではなく、設置をさせてもらって「熱」の代金をいただくものです。当然ですが、初期コストの高さは、そのまま提供する「熱」の料金に反映します。料金の内訳は、ペレット価格プラスボイラーの機器工事費プラスおひさまの維持管理費などです。
それでも石油が高騰すれば、その料金の高さはすぐに吸収されるはずです。ところが、このご主人は「リスクは負担しない」という理由で、機器工事費などの費用分は負担しないと言い出したのです。石油価格が高騰するのであれば、ペレット価格との差額分で機器工事費分などはまかなえるはずだから、君たちが負担しなさい。したがって、自分はペレットを石油価格に連動させて、石油と同じ価格で買い取る・・と。
最初は何を無茶苦茶な・・と思いました。私たちは市民出資によって機器費と設置費用をまかなうわけなので、出資者への返還は絶対に確保しなければなりません。しかし石油が確実に高騰するのであれば、この温泉旅館から私たちは大きな利益を得られます。いわば、石油価格とペレット価格の価格差の「先物買い」です。そういうリスクとリターンを明示しての出資募集もありうるのかなと思います。「石油」はいずれ沈没するのですから。
岡山の銘建工業を訪れて
少し前のブログで紹介しましたが、木質バイオマス事業の活路を求めて、このビジネスを成功させている銘建工業を訪ねました。岡山県の中国山地の山懐、銘建工業のある真庭市は飯田市によく似た環境の土地でした。温泉と森林です。バイオマスがビジネスとして成立するだけではなく、森林資源と人々の暮らしと産業がうまく結びつき、人々が資源の活用で山を育てることによって、ますます山のパワーが大きくなる・・という循環が生まれる可能性です。
銘建工業はバイオマスビジネスをやろうとしたわけではなく、もともと建材業なので端材を燃していました。ただ燃すのはもったいないと発電をはじめ、工場のエネルギーは自前でまかなうようになりました。それでも端材が残るので、それを有価物である「ペレット」にしてみました。でも売れない・・というのは、上に私が書いたことと同じです。銘建工業(実際は担当のNさん)が違っていたのは、それならと需要をつくりはじめたこと。
まず地元の温泉にペレットボイラーを入れるため、石油のボイラーメーカーに電話をかけまくり、ペレットボイラーをつくってくれと説得したといいます。その試作には自ら開発費を出し、いま5つか6つの温泉施設にペレットボイラーが入っていると言います。さらに、おひさまの私たちが先だと思っていたビニールハウスへのペレットボイラー導入もすでに実現し、なんと木質バイオマスイチゴが売り出されていました。今後の技術的課題だと思っていた、冷熱共用のペレットボイラーも実現させていました。
その結果、銘建工業のペレット工場はほぼフル稼働で安価に安定的にペレットを生産できるようになりました。こうしてペレットが売れれば、投資は回収できる。ビジネスの基本を教わったような気がします。
GSS(グリーンサービサイジング事業)で開発にチャレンジ
上で書いた、温室農家(ビニールハウス)への木質バイオマスによる熱供給事業が、この夏に経済産業省のグリーンサービサイジング事業補助金に採択されました。事業といっても、これはまだ実証段階で、銘建工業のようにボイラーの開発からはじめています。温室ボイラーと言えばネポン社で、ネポン社自身もビニールハウスのバイオマスによるグリーン化にはとても興味を持っているようですが、その試作品はとてもとても高い。温室農家が、いま使っているボイラーはほとんど50万円程度のものです。そこで地元の鉄工所にお願いして、なんとか100万円を切れる温室用ボイラーをつくってみようとチャレンジしています。
まほろば事業に比べ、はじめは「ままごと」のようなものかなと思っていたのですが、これを指導する委員(この補助金事業には継続して勧め方をチェックする委員がいるのです)の皆さんの厳しい指摘を受けて、まほろば事業の考え方にも影響を与えるほどしっかりしたものに育ってきています。
森林資源と人々の暮らしと産業の循環という考え方、そして冒頭の方で私が書いた、木質バイオマスに適したシステムやスタイルを作り出すことの必要性ということも、このGSSを実践する中で気がついたことです。銘建工業のNさんは、森林はエネルギーだけじゃない、マテリアルでもある・・と語りました。社会のシステムを木質バイオマスに適したものに変えて、木質がどんどん活用されはじめたとき、私たちの未来には石油文化に変わる、木質文化が待っているのかもしれません。

飯田市ではおひさま進歩エネルギー(以下「おひさま」と略す)という会社を立ち上げています。自然エネルギーと省エネルギーの会社です。
おひさま事業は、環境省のまほろば事業(環境と経済の好循環のまちモデル事業)補助金を受けた事業です。3年間の事業の3年度目で、仕上げのリミットまであと4ヶ月を切ったところです。市民出資を集めた「匿名組合」契約事業は太陽光発電と省エネ(ESCO)事業でした。このほかに木質バイオマス事業というのがあります。
バイオマスペレットへの反応
木質バイオマス事業は、森林の間伐材を活用した木質ペレットによる熱サービス事業です。ときあたかも、「ピークオイル・パニック」がささやかれるこの時期、木質ペレットはさぞかしもてはやされているのだろうとお思いでしょう。灯油の価格も1リットル当たり70円くらいまで上がってきて、ペレットの一般的な流通価格の1kgあたり35円くらいでも、もうちょっとで同等というところまで来ています。
しかし営業状況を率直にお話しますと、これがさっぱりです。世間の人は「ピークオイル」なんてお構いなし、「まずはコスト」という感じです。まあ、まったく商談が成立していないわけではなく、小型のペレットボイラーを入れるという話が進んでいる施設もあります。ここの場合は、責任者が自然エネルギーをできるだけ増やしたいという、いわばコスト度外視の応援団ということです。
飯田市にあるペレット工場、南信バイオマスも設備能力1000トン/年に対して、今年の生産(販売)は20%以下(去年はもっと悪い)で、ペレットは売れていません。長野県も飯田市も、木質ペレットを普及させようと、ペレットストーブ購入補助やペレット価格応援補助などをやっているのですが。正直言って、広がっていないのが現実です。
なぜ木質バイオマスは売れないのか
一番のカギは価格にあると思います。いま石油という船は喫水線すれすれですが、でも浮いています。私たちは小さな船で、乗っている人たちに「おーい、もうすぐ沈むぞ。こっちに乗り移れー」と叫ぶのですが、船上からは「何言ってんだよ。そんな小さい船の方が危ないよ。」と言われる。70円/リットルと35円/kgではなく、80円/リットルと30円/kgになると、ここはドドーッと動きます。水は喫水線を超え、石油という船に入りはじめるからです。逃げ出す人が続出してきます。
私の相場観ですが、この状況は来年には来る・・と思います。でも、今年ではないのです。石油は高くなったり、また下がったり、今年はまだぎりぎりのラインを保っているようです。価格は言うまでもありませんが喫水線を超えないように操作されていると思います。その見えざる力と、木質バイオマスは闘っているのです。
価格が同等になってもまだ障害があります。ペレットボイラーもストーブも、石油のそれより高い。そして何より「かさばる」。バイオマスペレットは同じ木質のチップに比べれば3分の1以下の体積に圧縮されていますが、液体の石油に比べれば、どうやっても大きい。安定して長期に使うには石油タンクの数倍の大きさのペレットサイロを用意しなければならないのです。飯田市のような地方都市ですら、石油ボイラーを使っている施設の中に大きなサイロとペレットボイラーを置けるスペースは、なかなかありません。完全な置き換えならまだしも、既存のボイラーとの併用(出はじめ商品なので、運転管理への不安も持たれる)ともなると、まず難しいのです。
同じことは輸送や流通のシステムでも言えます。お家の建て方から、最後の灰の処理の仕方まで、木質バイオマスに適したスタイルを確立する必要があるのです。違うシステムとスタイルの中で、木質バイオマスを広げようとしていることに無理があるわけです。
ある温泉旅館の問題意識
飯田市内の某有名温泉旅館のご主人は、新しいもの好きです。石油の枯渇や地球温暖化問題にもある程度の意識を持って世界を見ています。だから本当は、ペレットボイラーを入れたくてしょうがない。しかし、このご時勢、観光客も減っていますし、あまり高額の投資はしたくない。そこで、私たちの、初期投資ゼロの「おひさまスタイル」に興味を持ちました。
ペレットボイラーを入れるべく、夏から設計を何度も繰り返し、そのかなり複雑な構造物の中にペレットボイラーを入れられるよう工夫しました。不幸なことに、複雑な構造ゆえに工事費は通常の倍以上かかるものになりました。私たちの熱サービスは、ペレットボイラーを売るわけではなく、設置をさせてもらって「熱」の代金をいただくものです。当然ですが、初期コストの高さは、そのまま提供する「熱」の料金に反映します。料金の内訳は、ペレット価格プラスボイラーの機器工事費プラスおひさまの維持管理費などです。
それでも石油が高騰すれば、その料金の高さはすぐに吸収されるはずです。ところが、このご主人は「リスクは負担しない」という理由で、機器工事費などの費用分は負担しないと言い出したのです。石油価格が高騰するのであれば、ペレット価格との差額分で機器工事費分などはまかなえるはずだから、君たちが負担しなさい。したがって、自分はペレットを石油価格に連動させて、石油と同じ価格で買い取る・・と。
最初は何を無茶苦茶な・・と思いました。私たちは市民出資によって機器費と設置費用をまかなうわけなので、出資者への返還は絶対に確保しなければなりません。しかし石油が確実に高騰するのであれば、この温泉旅館から私たちは大きな利益を得られます。いわば、石油価格とペレット価格の価格差の「先物買い」です。そういうリスクとリターンを明示しての出資募集もありうるのかなと思います。「石油」はいずれ沈没するのですから。
岡山の銘建工業を訪れて
少し前のブログで紹介しましたが、木質バイオマス事業の活路を求めて、このビジネスを成功させている銘建工業を訪ねました。岡山県の中国山地の山懐、銘建工業のある真庭市は飯田市によく似た環境の土地でした。温泉と森林です。バイオマスがビジネスとして成立するだけではなく、森林資源と人々の暮らしと産業がうまく結びつき、人々が資源の活用で山を育てることによって、ますます山のパワーが大きくなる・・という循環が生まれる可能性です。
銘建工業はバイオマスビジネスをやろうとしたわけではなく、もともと建材業なので端材を燃していました。ただ燃すのはもったいないと発電をはじめ、工場のエネルギーは自前でまかなうようになりました。それでも端材が残るので、それを有価物である「ペレット」にしてみました。でも売れない・・というのは、上に私が書いたことと同じです。銘建工業(実際は担当のNさん)が違っていたのは、それならと需要をつくりはじめたこと。
まず地元の温泉にペレットボイラーを入れるため、石油のボイラーメーカーに電話をかけまくり、ペレットボイラーをつくってくれと説得したといいます。その試作には自ら開発費を出し、いま5つか6つの温泉施設にペレットボイラーが入っていると言います。さらに、おひさまの私たちが先だと思っていたビニールハウスへのペレットボイラー導入もすでに実現し、なんと木質バイオマスイチゴが売り出されていました。今後の技術的課題だと思っていた、冷熱共用のペレットボイラーも実現させていました。
その結果、銘建工業のペレット工場はほぼフル稼働で安価に安定的にペレットを生産できるようになりました。こうしてペレットが売れれば、投資は回収できる。ビジネスの基本を教わったような気がします。
GSS(グリーンサービサイジング事業)で開発にチャレンジ
上で書いた、温室農家(ビニールハウス)への木質バイオマスによる熱供給事業が、この夏に経済産業省のグリーンサービサイジング事業補助金に採択されました。事業といっても、これはまだ実証段階で、銘建工業のようにボイラーの開発からはじめています。温室ボイラーと言えばネポン社で、ネポン社自身もビニールハウスのバイオマスによるグリーン化にはとても興味を持っているようですが、その試作品はとてもとても高い。温室農家が、いま使っているボイラーはほとんど50万円程度のものです。そこで地元の鉄工所にお願いして、なんとか100万円を切れる温室用ボイラーをつくってみようとチャレンジしています。
まほろば事業に比べ、はじめは「ままごと」のようなものかなと思っていたのですが、これを指導する委員(この補助金事業には継続して勧め方をチェックする委員がいるのです)の皆さんの厳しい指摘を受けて、まほろば事業の考え方にも影響を与えるほどしっかりしたものに育ってきています。
森林資源と人々の暮らしと産業の循環という考え方、そして冒頭の方で私が書いた、木質バイオマスに適したシステムやスタイルを作り出すことの必要性ということも、このGSSを実践する中で気がついたことです。銘建工業のNさんは、森林はエネルギーだけじゃない、マテリアルでもある・・と語りました。社会のシステムを木質バイオマスに適したものに変えて、木質がどんどん活用されはじめたとき、私たちの未来には石油文化に変わる、木質文化が待っているのかもしれません。











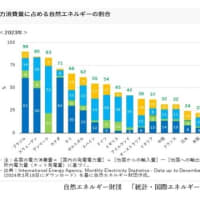


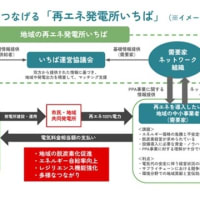






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます