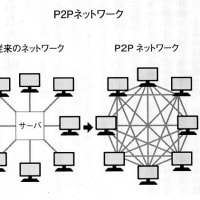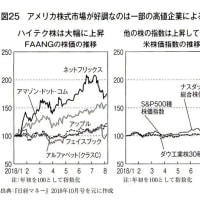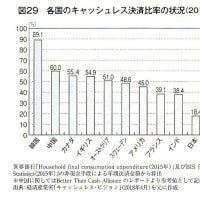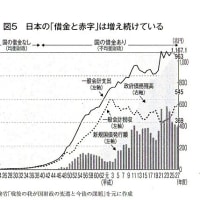禅の立場からすると、単に対話を超脱して人間言語がその作用性を完全に喪失し、言語がまったく働かなくなるようなところに行ってしまい、そしてそれっきりになってしまうということではなくて、かえってそのような無言語の場から言葉が出てきて、普通の意味での対話が成立し得ないようなところで、異次元の対話が成立する、そういう特殊な対話の精神的意義と重要性を指摘し問題にしてみたいというところにあった。
異文化間の対話の可能性
❶コミュニケーション不可能説(フンボルトの言語哲学現代版サピア=ウォーフ仮設)
❷相当程度まで可能(デカルト的な合理主義的言語観)
❶によると、言語とは第一義的には、「現実」(リアリティ)の認識的分節形態の体系ということになります。「現実」それ自体は全く不定、つまり内部になんらの限定もない、従って掴まえどころのないのっぺりした何かであってそれを日本語とか英語とかそれぞれの言語が、それぞれの仕方で、いわば任意に分節し区切りをつける。様々に区切られた「現実」の断面が各々意味的単位として意識され、それが語によって固定される。それらの語、すなわち意味単位、の総体が一つの記号体系としての一々の言語である、と、およそこのように考えるのであります。
ともかくこの派の人々によれば、「現実」とはなんだか得体の知れない、ぬるっとしたようなものであって、この本源的に不確定な「現実」が伝統的にきっちりきまった形に限定され、それが言葉で固定されていて、人間はそれぞれ自分の言語が提供するそのような整理箱の穴から「現実」を見ている、しかも言語ごとに整理箱の構成が違っているというのです。
厳密な意味での翻訳は不可能事です。翻訳は本質的に一種の間に合わせにすぎません。
言語的普遍者=文化的普遍者
こうして対話の可能性――異文化間の対話であれ、同一文化圏内での、あるいは同一言語圏内での対話であれ――は、たんに理論的に興味ある問題であるばかりでなく、いやそれにもまして、今日の世界に生きる我々の存在そのものに関わる重大な問題であることが、ややおわかりいただけたかと存じます。そしてこの問題について、現代の言語理論や言語哲学が決定的な解答をもち合わせていないということも。
世にいわゆる禅的沈黙がそれであります。沈黙とは対話への性向を抑えて、言葉をだんだん少なくしていって最後に行きつく極限の状態であります。
元来、禅の立場から見ますと、人間はどうも喋りすぎる。つまり生まれつきお喋りなのです。
ただし禅の立場からして一番大切なのは、人間がただやたらに喋りたがる性質を持っているという点にあるのではなくて、喋ること、言語を使うことによって知らず知らずのうちに、その言語が意味論的に押しつけてくる特別な「現実」の範疇化の枠に心の動きがはまってしまうということであります。そしてそのことは、禅にとっては、ただちに人間の実存的自由の喪失を意味するのです。
人間は喋っているうちに、意識しないで、習慣の力で、つい自分の喋る言語の意味的枠組に従ってものを見、ものを考えるようになっていく。禅から見れば、人間はこの意味で言葉の奴隷です。
言語によって決定された意味的範疇の枠組から抜け出すことが、禅に言わせれば、まず第一にやらなければならないことであります。言語の区分け形式によって歪められた「現実」の姿を、言語ぬきの、新鮮で溌剌とした直接のヴィジョンで置きかえなければならないのです。
今申しました直接的ヴィジョンにおいて現われてくる「現実」は完全な形而上的無限定者でなければなりません。全然区分けがないのですから当然そうなるはずです。それを禅では「空」とか「無」とか申します。そして「現実」をこのような形而上的無限定者として自覚することが禅の修行の第一段階であります。そのためには当然、人間は先ず喋ることをやめなければなりません。つまりいわゆる言語の圧制から心身を自由にして、言語的範疇化の描く魔法の円を超脱しなければなりません。
つまりもっと平たく言えば、山が山でなくなるためには、それを見る主体の意識も主体の意識であることをやめるほかはありません。
絶対無分節の状態、つまり言葉のもたらす一切の意味的区分けの出てくる以前の状態、ということになります。
禅はこの絶対無限定状態における「現実」が直接端的に実存的体験として味得されることを要求しますが、それは人が言語を超えて、言語の彼方に出なければ実現不可能なのです。なぜなら言語とは、その意味的本性上、本源的に無限定な「現実」を様々に限定し、どこまでも細分して、そうして造り上げた意味的限定形態を内的・外的なものとして措定していくところにはじめて本来の存在形成的ないし認識構成的作用を発揮するものであるからです。
意識内容の伝達と「現実」の分節という人間言語の二つの根本的機能のうち、禅思想において中心的位置を占めるものは後者、すなわち意味的分節機能の方であることが明らかでありましょう。
この点においては、言語にたいして禅の取る――あるいは、取ると想定し得る――立場は、現代のフンボルト学派に属する意味論者たちの立場に非常に近いものであります。
つまりあらかじめ分節された世界の、ヴィジョンを押しつけることにならざるを得ない、と、大体こういうような主張(フンボルト学派)であります。
事実、禅はフンボルト派の意味論と同じく、言語的分節が我々の世界認識に及ぼす強大な影響力をいろいろな形で指摘してきております。ただし、禅がフンボルト流の意味論と違うところは、存在にたいする言語分節の影響力をただ観察したり分析したりするにとどまらず、もつと積極的、建設的な形でこの事実に対処しようとするところにあります。
そして禅は、言うまでもなく、第一に、第一義的に、修道であり、精神鍛錬の道であり、ここで精神鍛錬とは人間の意識構造を根本的に練り直して、今までかくれていた認識能力の扉を開き、それによって今まで見えなかった事物の真相を掴むことができるようにしようというのでありますから、当然のこととして、「現実」の言語的歪曲を払拭し、言語の分節作用の全然働かないところで、ありのままの「現実」を認識させる方法を編み出してきたのであります。
深い観想のうちに、言語分節の蹤跡が消え去り、あらゆる事物の無が体験されるとき、そのときはじめて歪曲されぬ「現実」が顕現するという考えです。
……、体験の巨視的次元が名称あるいは名前の領域だということです。
ところで禅の修行の道の第一歩は、このようにして巨視的次元に生じた意味的凝結体を、観想によって次々に――というより、できることなら、一挙に――溶かしてしまうことにあります。言語的意味分節論の見地から申しますと、座禅とは、意味的に凝結している事物を溶解して、もとの姿に戻すために考案された方法であると申せましょう。
……、座禅で観想状態が深まって参りますと、意識の深層が次第に活発に働き出します。そしてそれと同時に凝結していた世界がだんだん溶けていきます。いわば流動的になっていきます。今まで峻別されていたあらゆる事物の形象はその尖鋭な存在性を失って仄かになり、ついにはいまにも消滅せんばかりのかそけさとなります。いわゆる「本質」なるものによって造り出されていた事物相互の境界線は取り除かれ、いろいろな事物の輪郭はぼやけてきます。そして、今ではほとんど区別し難くなったものたちが相互に浸透し合い、とうとう最後には全く一つに帰してしまいます。それが「一者」の次元です。
だが、観想のより一段の深化とともに、この他者の可能的区別もついに消え去って、万物は絶対の無限定の中に逍溶してしまいます。これこそ真の意味での形而上的「一者」の現成。大乗仏教ではこれを「空」と呼ぶ。
絶対無文節者はいわばどうしても自己自身を分節せずにはおられない。「無名」は「有名」に転じていかずにはおられないのです。そして禅の観想的意識は、本源的形而上的「一者」が次第に自己文節を重ねつつ、ついに具体的事物事象の世界として完全に現象化された形で現われるところまで、「一者」自己分節の全行程をくまなく辿るべく定められているのであります。
ここに「一者」の自己文節の過程とは、「無名」が自らを名付けていく過程にほかなりません。本来なんの名もないものが、いろいろな名称を自己に与えて「有名」となる過程です。この「無名」の名付けが言語を通じてなされることは申すまでもありません。
まだ観想体験を通じて万物の「無」を自覚していない最初の段階では、世界にはいろいろなものがあって――つまり「現実」が意味的に無数の単位に区分けされていて――それらのもののそれぞれがその名前で示される独特の「本質」をそなえた独立の存在者として現われていました。
これに反して、「無」の観想的自覚を経た後の段階では、同じそれらのものが全て絶対無限定者としての「一者」の顕現形態として覚知されるのです。禅の立場から見てここで一番大切なことは、経験的他者界の存在者の一つ一つがどれも「一者」がそっくりそのまま自己を露見した姿として覚知されるという点にあります。
「一者」がたくさんの部分に自らを細分して、それらの部分がそれぞれ独立したものになる、というのでない。そうではなくて、経験界に見られる事物事象の各々が、「一者」そのものの存在的全エネルギーの発露だということです。
分割
全体としての「一者」が四つの部分に分かれて別々のものになるという意味
分節
それぞれが「一者」そのものの、四つの違った現われ方、四つの限定的現象形態
従ってこういう境地において、私が山を見ることは「一者」が「一者」自身を見ることにほかなりません。私が山を見るという一見極めて単純な経験的事実が、実は「一者」がみずからを自らの鏡に映して見るという形而上的事件なのです。
互いに他を排除しつつしかも互いに浸透し合う形而上的事態
それ自体としては本源的に全く無分節である「一者」が存在的に自己を分節していく、この「一者」の自己分節が言語的意味分節として現われるのです。
絶対の沈黙でありながらしかも永遠の言葉であるもの、非言語――私は今この非言語という語を無言語から区別して、例の薬山維儼の「非思量」に合わせて使っているのですが――でありながら、しかもあらゆる言葉、すなわちあらゆる存在形態の本源であるようなコトバです。
禅の言語哲学の中には、インドの「言語的不二論」を代表する哲人バルトリハリ(5世紀ごろの人物)によって提唱された「語・梵」の考えに非常に近いものがあるように私は思います。
経験的世界がこのような異常な様相の下に現成するこの領域において、言語の分節機能そのものもまた普通の場合とは全く違った様相を呈することは当然でなければなりません。
「無」の直接無媒介的自己顕現
いわゆる「転語」というのがそれです。禅は実に厳格に、徹底して、言語が第一次的にはこのような形で使われることを要求します。すなわちすべての語がコトバの直接そのままの顕現としての自覚において話者によって発せられ、またまさにそのようなものとして聴者に受け取られることを要求します。そうでない言葉はすべて本来的な言語行為ではない。だから「一転語を持ち来れ」と言います。
二人の人間の間に成立する普通の対話的関係の地平の彼方の痛烈な実存的状況のうちに演じられる一つの形而上的ドラマとして現成する特殊な対話形式、それを私はBeyond-Dialogueという表現で表してみたのです。このような意味に解されたBeyond-Dialogueを伝統的に禅は「問答」と呼びならわしてきました。
二人の人間、二つの実存、すなわち非言語の自己言語化の互いに平行する二つの実存的機構が相関的展開の過程において、互いに刻々呼び合い応じ合いつつ、瞬間ごとに全く新しい対話的場面を創造していく、それがBeyond-Dialogueとしての禅の問答の本質的構造であります。
当然なことですが、現代の言語理論が問題とする対話とは、要するに常識的な言語観に基づいた対話の概念であります。禅の問題とする対話は、これに反して、非常識な言語観に基づいた非常識に対話です。
対話というものにたいして、またより一般に言語というものにたいして、常識的言語理論とは全く違った見方もある、そしてそれが人間精神の形成にとって、それから人間についての哲学的思索にとって重大な意義をもつものであるということを自覚しておくのは悪いことではないと思うのです。
禅の観点からすれば、現代の言語理論内に生じている言語的コミュニケーションの難問と、それに関連する数々の複雑な問題は、主として言語の伝達機能に不相応な重点が置かれるところに起因します。むしろ言語については、意味分節的機能にこそ第一の重点が於かれなければならない、否定的意味においても肯定的意味においても。これが言語にたいする禅の根本的態度です。
形而上的深みを欠いた水平的言語コミュニケーションは、禅に言わせれば実存的意味のないあだごとであります。
*二〇一六年一〇月二十四日抜粋終了。